artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
範宙遊泳『ディグ・ディグ・フレイミング!〜私はロボットではありません〜』

会期:2022/06/25~2022/07/03
東京芸術劇場シアターイースト[東京都]
『バナナの花は食べられる』で第66回岸田國士戯曲賞を受賞した範宙遊泳/山本卓卓の新作『ディグ・ディグ・フレイミング!〜私はロボットではありません〜』が7月15日(金)18:00から8月14日(日)23:59までオンデマンド配信されている。
炎上を意味する「フレイミング」をタイトルに掲げた本作は、インフルエンサー集団「MenBose−男坊主−」のメンバーである藤壺インセクト(埜本幸良)、キング塚村(小濱昭博)、根津バッハロー根津(福原冠)、そしてエキセントリック与太郎(百瀬朔)が謝罪の準備をしているところからはじまる。いや、正確には、謝罪の準備をしていてふと、何を謝らなければならないのかがわからないということに気づくところからはじまる。謝らなければならないのは与太郎が飼っていたスズメが死んでしまい、それを焼き鳥にして食べてしまったことか。動画のネタで「商店街の看板いくつ蹴って倒せるか大会」を開催したことか。あるいはホームレス美大生のアラレ・ビヨンド(李そじん)をゲストに迎えた企画をバラエティ調に撮ってしまったことか。過去の出来事を舞台上に召喚しながら検証は進むが、どれもこれも違っているようで謝らなければならない理由はなかなか見つからない。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
すると突然「オデのせいだ」と言い出す与太郎。どうやら与太郎には「文字が聞こえる」らしく、その文字は与太郎を責め立て「命をもって謝れ」とまで言っているらしい。「心ない声なんて全部ゴミ」と言い放つアラレに対しディスプレイに映し出される文字は「文字の奥に心がある!」と反論し、二人は「心があるならこんなにひとりの人間を追い詰めない。あなたは人間じゃない」「私は人間だ!!!!!」と激しくやり合う。そしてMenBoseのメンバーは炎上する画面の向こう側から文字の本体を引きずり出すが、そこにあったのはかつて企画でコラボしたインフルエンサー・ロクちゃん(亀上空花)のママ(村岡希美)の姿だった。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
さて、この物語は一体どこに向かうのだろうか。謝らなければならない理由、つまりは「罪」を探し求めることがこの物語を推進するが、ようやく辿り着いたかのように思われた罪もまた、探していたそれではない。ママはMenBoseとの収録の際に起きた出来事がきっかけでロクちゃんが部屋から出てこなくなってしまったと思っているが、そもそもママとMenBoseとでは「起きた出来事」に対する認識が大幅に食い違っている。部屋を訪れ、引きこもりの理由を直接ロクちゃんに尋ねたママとMenBoseは結局、MenBoseには非がなかったことを知るのであった。だがそれでも文字による糾弾は止まらない。それどころかその苛烈さは増し、やがて画面の向こうから「死」が現われ、オレンジ色の浮き輪のようなオブジェとして登場するその巨大な文字にメンバーは捕らわれていく。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
ある時期以降の範宙遊泳は、プロジェクターで舞台上に文字を投影する演出を取り入れ、その文字をときに登場人物のようにも扱ってきた。『ディグ・ディグ・フレイミング!』もその延長線上にあることは確かだが、決定的に異なっているのは、この作品においては文字が単にディスプレイに映し出される文字として扱われているということだろう。範宙遊泳/山本の視線は文字の向こうにいる人間に向けられている。MenBoseはしょうもなくモラルも低い集団かもしれないが、ディスプレイに映る文字の向こうにいる人間を相手にしようとする点においては誠実だ。与太郎が看板を蹴ってしまったスナックで一日バーテンをやってみたらそこのママに気に入られてしまったように、顔を突き合わせることでよい方向に向かうこともあるだろう。匿名の文字を相手にした格闘はほとんど何も生み出さない。そういえば、『バナナの花は食べられる』もまた、マッチングアプリの客とサクラとして画面越しに出会った二人の男がリアルで顔を合わせるところから物語が動き出すのだった。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
スタート地点が間違っているのだから「罪」の追及がどこにも行きつかないのは必然だ。物語はほとんど消化不良のまま唐突な幕切れを迎える。文字によって犯罪歴を含む秘密を暴露され力尽き倒れる登場人物たち。その様子は生配信されていて、舞台上にもその映像が映し出されている。やがて聞こえてくるサイレンの音。どうやら視聴者が通報したらしい。逮捕されると怯える彼らだったがそれはパトカーではなく救急車のサイレンで──。
劇中の言葉の繰り返しにはなるが、最後の最後で罪の追及は傷ついたもののケアへと転じる。そこにあるのは劇作家・山本卓卓が物語に込めたあるべき世界への願いであり、同時に、「そこにいるあなたは物語の結末と世界の行方を委ねるに足る人物のはずだ」という、配信の視聴者=客席の観客に向けられたほとんど攻撃的と言っていいほどの信頼でもあるだろう。世界を、人間を変えるには、まずはそれらを信じるところからはじめなければならない。範宙遊泳はそれを実践してみせたのだ。
範宙遊泳:https://www.hanchuyuei2017.com/
関連レビュー
範宙遊泳『バナナの花』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年09月15日号)
2022/07/03(日)(山﨑健太)
いいへんじ『器』

会期:2022/06/08~2022/06/18
こまばアゴラ劇場[東京都]
「死にたみ」とともに生きるとは、あるいは「死にたみ」とともにある人とともに生きるとはどういうことか。いいへんじ『器』(作・演出:中島梓織)は擬人化された「死にたみ」の存在を通して、「死にたみ」とともにあることになんとか折り合いをつけようとする作品だ。なお、公式のウェブショップでは戯曲も販売されている。以下では作品の結末にも触れているので、興味を持たれた方は先に戯曲を読んでいただく方がいいかもしれない。
冒頭、ピエロのような服(衣装:カワグチコウ)を着た人物が「みんなー! おれっちの声、聞こえるー?」と観客に向かって大声で語りかける。すぐさま「聞こえてないよねー? おっけおっけー!」と言う、もうすぐ生まれるところらしいその人物(?)こそがこの作品に登場する「死にたみ」のひとり・メラン(小澤南穂子)だ。

続く場面では就職し二人での新生活をはじめるカズキ(宮地洸成)とカナ(松浦みる)の引っ越しを友人のショウ(藤家矢麻刀)とその兄・ハル(竹内蓮)が手伝っている。ハルには「死にたみ」・ドンク(箕西祥樹)がついているが、ほかの人間には見えていないようだ。また別の場所ではカズキの高校の同級生・サキ(波多野伶奈)が配信をしていて、その側にも「死にたみ」・クラン(飯尾朋花)がいる。再び場面が転換すると新生活がスタートしていてカナコは出勤していくのだが、どうやらカズキは働いていない様子。夕方になって二度寝から目覚めたカズキは頼まれていた買い物のために訪れたスーパーでメランと出会い──。


アニメやゲームなどメディアミックスで展開する『妖怪ウォッチ』という作品がある。『妖怪ウォッチ』では世の中の困った問題や不思議な現象はすべて「妖怪のしわざ」だとされ、主人公たちは妖怪と友達になることでそれらの問題を解決していく。例えば子供がいたずらをするのもその子が悪いのではなく取り憑いた「妖怪のしわざ」なのだというわけだ。「死にたみ」を感じるのも当人に原因があるのではなく取り憑いた「死にたみ」のせいなのだ、という考えはそれ自体、当人や周囲の人間の気持ちを軽くし「問題解決」への第一歩となり得るものだろう。心理療法でいうところの認知療法の実践に近いところもあるかもしれない。
完治が難しいとされるうつ病では、「普通の」生活ができる程度に症状が改善した状態を寛解と呼ぶ。「持病」としてのうつ病とどう付き合っていくか。ドンクの機嫌の取り方を覚え、何とか日々を過ごしているハル。クランの言葉を聞かないふりでやり過ごそうとするサキ。そして何なのかわからないままに生まれたばかりのクランと暮らしはじめるカズキ。「死にたみ」との距離感は付き合いの長さによって三者三様だ。

「死にたみ」が俳優という生身の人間によって演じられるこの作品では、観客にとって「死にたみ」がそこに存在していること、そしてそれが取り憑いている当人とは別個の存在であることは最初から自明のことだ。だが、登場人物にとってはそうではない。メランがカズキのことをずっと見ていたと言うのに対し、カズキはメランの存在に気づいてなお、「それ」がなんなのかわからずメランの言葉を聞き取ることもできない。メランを「見つけた」カズキはなぜか就職活動に精を出しはじめるのだが、その行動はカズキが自らの抱える感情を見極められていないがゆえのものでもあるだろう(その点では、急に就職活動をはじめたカズキを心配するカナの方がまだカズキの状態に敏感であると言えるかもしれない)。状態が悪化し引きこもり、やがて「死にたい」とつぶやくようになってようやく、カズキはメランの言葉を理解できるようになる。それはつまり自分のなかに「死にたみ」があることを認めることだ。時を同じくしてメランは、自分たちが生まれたのは「このままじゃ死んじゃう」ことに「気づいてもらいたかった」からじゃないかという話を先輩であるところのドンクから聞いていた。当然といえば当然だが、カズキとメランの変化は連動しているのだ。そうしてカズキとメランはともに「生きる」ためのスタート地点に立つ。登場人物の微細な心の揺れを丁寧に掬い上げた俳優陣に拍手を送りたい。


ひとりの女性の脳内会議の様子を描いた『つまり』や自分のなかにある他人のイメージを具現化した『夏眠』『過眠』など、いいへんじには演劇的な仕掛けを巧く使って心の動きを視覚化した作品が多い。一方、作品ごとに描きたいことがあまりに明確であるがゆえか、メイン以外の登場人物に作品内で与えられた役割以上の広がりが感じられず、テーマや物語を描くためだけに存在しているように見えてしまうきらいもある。今回『器』と二本立てで上演された『薬をもらいにいく薬』では演劇的な仕掛けが控えめだったこともあり、特にその点が気になった。どの作品でも中心となるテーマや登場人物へのまなざしとそれを扱う手つきは繊細であるだけに「もっといけるはずだ」と思ってしまうのは高望みだろうか。
いいへんじ:https://ii-hen-ji.amebaownd.com/
関連レビュー
いいへんじ『薬をもらいにいく薬(序章)』(芸劇eyes番外編vol.3.『もしもしこちら弱いい派 ─かそけき声を聴くために─』)|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年08月01日号)
いいへんじ『夏眠』/『過眠』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)
2022/06/16(木)(山﨑健太)
プロトテアトル『レディカンヴァセイション(リライト)』

会期:2022/06/11~2022/06/12
アイホール(伊丹市立演劇ホール)[兵庫県]
関西小劇場シーンの拠点のひとつのアイホールだが、昨年、税金負担や老朽化、市民の利用率の低さなどを理由に、伊丹市の意向で存続の危機に立たされた。演劇界の署名運動や市民からの声を受け、今後3年間は存続が決定したものの、主催・共催事業は縮小される。10年間続いた若手支援企画「break a leg」も今回が最終。同企画にはこれまで、冨士山アネット、劇団子供鉅人、FUKAIPRODUCE羽衣、コトリ会議などが参加してきた。その掉尾を飾るのが、FOペレイラ宏一朗が主宰する「プロトテアトル」。2015年の短編、2019年の長編化を経てリライトした作品が、凹状に一段下げた舞台、むき出しの壁、天井の高さなど劇場の空間性を活かして上演された。
大きな地震で崩れた、山奥の廃墟ビルが舞台。そこに生き埋めになった3つのグループ──2人の警備員、好奇心で訪れたアウトドアサークルの大学生たち、ネットの自殺スレッドに集った自殺志願者たち──計11人による群像劇だ。瓦礫に埋もれて身動きも取れず、携帯は落としたり圏外で助けも呼べず、暗闇のなか、相手と顔も見えないまま「会話」を続けるしかない。そうした極限状況が、身体を硬直させた俳優たちによって演じられる。構成は明快で、①警備員、サークル、自殺スレッドのメンバーという既存のコミュニティ内部での会話、②余震で床が崩落して落下し、それぞれのコミュニティに「外部からの闖入者」が混ざる、③さらに大きな揺れにより、全員が「最下層の地下駐車場」に集合する、という3パートからなる。建物の階層構造が物語レベルとメタ的にリンクする展開である。冒頭と各パート間に起こる「地震の揺れ」を示す、暗闇に響く激しいドラムの音が鮮烈だ。

[写真撮影:河西沙織(劇団壱劇屋)]
人物・設定紹介の①を経て、「部外者」がコミュニティに混ざる②の局面では、「普段言えなかった本音」が口に出されて人間関係の修復や和解が生まれ、自殺願望者も死の恐怖に直面した者たちも、状況は何ひとつ変わらないにもかかわらず、最終的に「生きたい」という希望へ向かい、ラストシーンでは頭上から一筋の光が差し込む。物語はひとまずそのように要約できる。そこにはいくつもの二重性が書き込まれている。「顔の見えない相手とのコミュニケーション」は文字通りの暗闇/ネット空間の匿名性であり、誰かの声が聴こえるたびに反復される「救助隊の人ですか?」という台詞は、自殺スレッドのメンバーにとっては、その名も「ホーリー」と名乗るスレッド主が「死による救済」をもたらしてくれる期待でもある。

[写真撮影:河西沙織(劇団壱劇屋)]
ただ、人物造形やエピソードはステレオタイプで平板に感じた。特に気になるのが、「死から生への転化」の鍵を握る、女性キャラクターの描かれ方の偏向である。「通帳ごと消えた」元彼(=警備員)と再会した自殺志願者の女性は、あっさり彼を許し「もう離さない」と抱きしめる。一方的な思い込みで互いに「相手の理想の恋人」を演じて疲れていた大学生の男女は、本音をぶつけ合い、関係を修復する。いじめが原因で「死にたい」と思っていた女子高校生は、自殺スレッドで知り合い、話を聞いてくれた男性「ホーリー」に「会いたい」気持ちが生きる原動力に転化する。だから彼女は、やっと会えた「ホーリー」が差し出す薬の瓶を、「私が欲しかったのはこんなものじゃない」と床に投げつけるのだ。3人とも、「男性への恋愛感情」のベクトルが、「死から生へと転じる(唯一の)原動力」である。彼女たちは実際には「ただ一人」なのだ。「何が好きで、何に興味があって、どんな人なのか、もっと知りたいから話すんだよ」という台詞が、女子大学生と女子高校生の双方で反復されることが、その証左である。
こうしたステレオタイプ的な描写は過去作品『X X』でも感じたが、ここで、『X X』と本作を空間構造から比較すると、プロトテアトルの志向性がより明確に見えてくるのではないか。『X X』では、四方を座席が囲むフラットな舞台空間上に、両親と娘の家庭、高校生たちが登下校で立ち寄る商店、交番、ホームレスのいる公園などが点在し、架空の田舎町の中で、孤島のように浮かぶコミュニティの生態が描かれる。水平的なコミュニティの住人が次第に交錯することで、人違いの撲殺事件という「悲劇」が最終的に起こる。一方、本作は「垂直性」に貫かれている。リアリズムベースの会話劇に基づくプロトテアトルだが、むしろ描こうとしているものの本質は、構造の方にあるのではないか。
本作では、まず、「既存のコミュニティ」が前提にあり、各成員はその基盤の上に乗っている「安定」状態が示される。廃墟ビル=(すでに綻びを抱えた)社会全体とすると、各階=各コミュニティのメタファーだ。だが、「地震」という外在的要因によって、その基盤が崩壊し、「普段は交わらないコミュニティ」と否応なしに「接触」させられてしまう。従ってここでは、「生き埋めになり救助を待つ人々の心理劇」の背後で、「地震」すなわち社会基盤を揺るがす大事件によって、異質なコミュニティと強制的に「接触・交差」させられる物語が語られているのだ。彼らは、「力を合わせて」脱出しようと奮闘するわけではない。ただ、「話し続ける」だけだ。暗闇のなかで相手を知ろうとするために。終盤、「まずは自己紹介から始めよう」と、各自が「(本当の)名前」を名乗ることは示唆的だ。閉塞感とともに匿名的な集団に飲み込まれていくのではなく、手探りでも「個人」として存在し始めようとすること。その声に傾聴すること。そこに、ラストシーンの「頭上からの光」が照らし出す希望がある。

[写真撮影:河西沙織(劇団壱劇屋)]
2022/06/12(日)(高嶋慈)
康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009):MOTコレクション 光みつる庭/途切れないささやき

会期:2022/03/19~2022/06/19
東京都現代美術館[東京都]
映像のなかでひたすらに雪かきを続ける人物が、康夏奈(1975-2020)である。この作品は康がアーティストインレジデンスでフィンランドに滞在していたときに制作された。康は映像の冒頭ですでに凍った湖の上に立っていて、うすく積もった雪にはグリッド状の線が入っている。その線に沿って、康は除雪用のシャベルで雪を掻いては隣のマス目に雪を載せていく。全編、遠目に康の身振りが見えていて、表情は見て取れない。降り続ける雪に落胆しているのか、淡々とした様子なのかもわからないが、ズボンと靴が黒っぽいから、盛った雪のエッジはこわさないように、雪かきを済ませた箇所から次の作業箇所へと移動するときの慎重な様子はうかがい知ることができる。やっと白と黒のコントラストがはっきりしてきたかと思えば、雪の勢いは増し、掻いても盛っても降り続け、また全体的に白くなる。数分見ていると映像は早回しになり、康がより一層キビキビと氷上を動き回る。
SHAKKIというのはフィンランド語でチェスを意味する。康は何とやりあっていたのだろうか。白と黒、どちらが康かといえば、白い雪に触れないようにしていたからおそらく黒が康だろう。広大な領域に境界線とルールを定めることで、やっと康は白い陣営であろう雪と攻防を繰り広げることができる。でもこれは定められた負け試合。時間もスケールも動かせるエネルギーも枠外の世界。でもそれをもう一度枠内に引き入れることが康にはできた。映像での撮影だ。映像が黒と白の一進一退を、康が雪かきを続ける時間と空間だけに限定することで、無限に循環させる。映像の終盤には、キッチリと雪を掻き分けきった状態がよくわかる、寄り気味の写真が数枚挿入されているが、最後は白くフェードアウトする。少し時間が経つと映像はループされ、また康は戻ってきて、途切れなく白の陣営と格闘を始めることになる。けれども、映像を編集した康はこのチェスの行方に満足しているはずだ。
 康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009)
康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009)
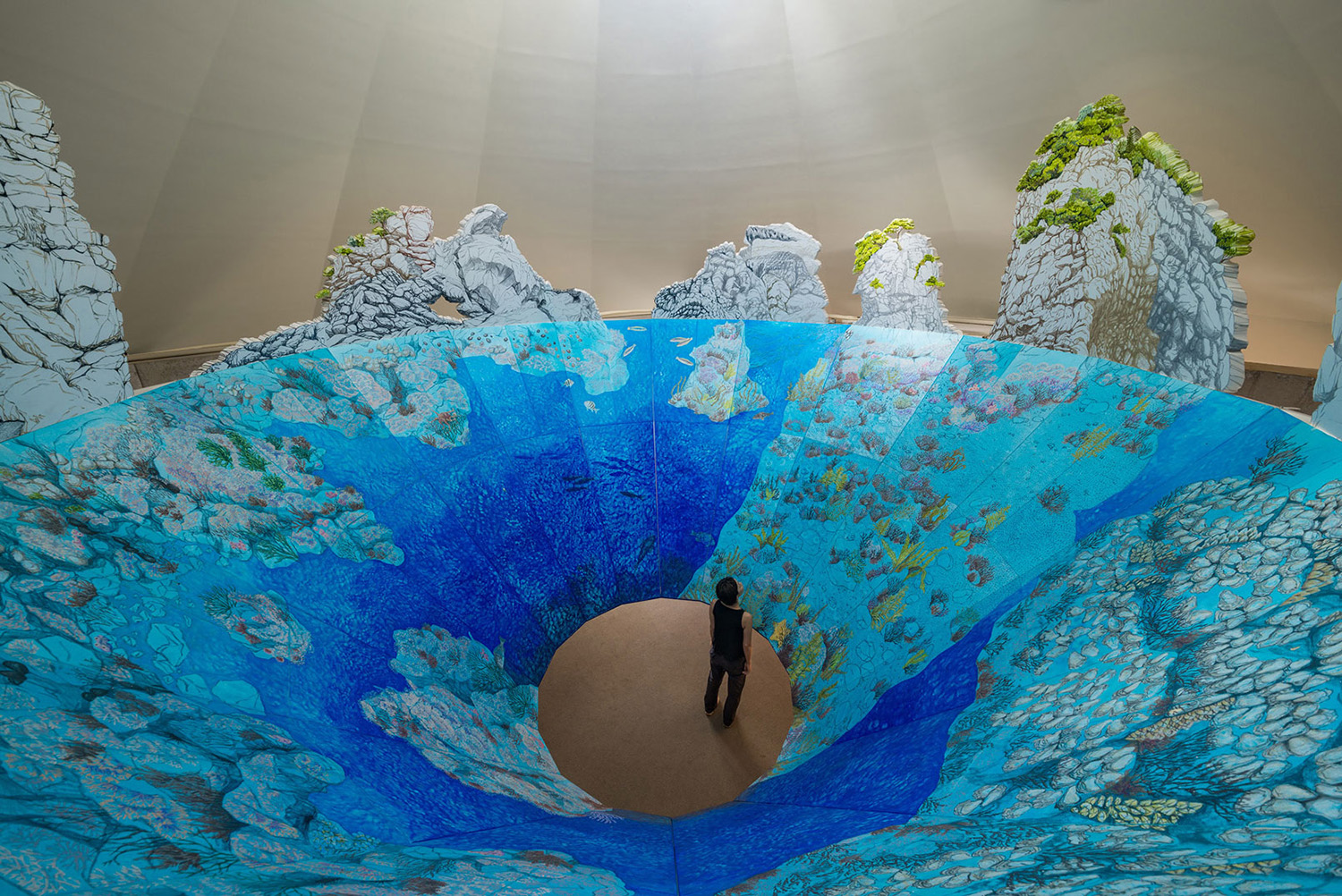 康夏奈(吉田夏奈)《花寿波島の秘密》(2013)個人蔵
康夏奈(吉田夏奈)《花寿波島の秘密》(2013)個人蔵
「瀬戸内国際芸術祭」(香川県小豆島、2013-19)展示風景[Photo: Yasushi Ichikawa]
公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mot-collection-220319/
2022/06/12(日)(きりとりめでる)
音で観るダンスのワークインプログレス

会期:2022/06/11~2022/06/12
京都芸術センター[京都府]
映画や映像配信で普及しつつある、視覚障害者に音声で視覚情報を補助する「音声ガイド」。「音で観るダンスのワークインプログレス」は、「音声ガイド」に着想を得て、視覚に障害のある人もない人にも「ダンスを見る多様な視点の共有」をめざすプロジェクトである。展覧会企画などを通じて、障害当事者とともに鑑賞の多様性を提案している、プロデューサーの田中みゆきが企画した。2017年からの3年間は、捩子ぴじんのソロダンスとともに実施。5年目となる今年は、ダンサーに康本雅子と鈴木美奈子を迎え、デュオ作品を創作した。上演ごとに構成や伝え方を変え、「音声ガイドの完成」自体が目的ではないため、「ワークインプログレス」と称している。
そもそもダンスは、「物語」や「一義的な意味」に還元されず、言葉による捉えがたさを抱えている。また、見えている人(晴眼者)でも「見え方」は多様だ。そうした本質的な困難さを自覚的に引き受けたうえで、「ダンス」のより豊かな射程を掘り起こしていこうとする点に意義がある。
本公演は3部構成で、①康本と鈴木によるデュオ、②そのダンスに触発された言葉の朗読がダンスに重ねられる「テキストバージョン」、③新たな試みである「サウンドバージョン」が上演された。テキスト執筆は文筆家の五所純子、朗読はダンサーの中間アヤカ、サウンドバージョンはサウンドアーティストの荒木優光が手がけ、コラボレーション的側面ももつ。上演後には、観客との対話の時間も設けられた。①のデュオでは、あえて照明を落とし、新聞紙を動かすカサカサという音や身体が床に打ち付けられる硬質な音が「動き」を想像させる余白を残した。

[撮影:松本成人]
特に、さまざまな点で示唆的だったのが、②の「テキストバージョン」である。手から離したティッシュペーパーが空気の抵抗を受けながら落ちる様子を「ハラハラ、ハラリンコ~」と表現するなど、擬音語や擬態語の面白さ。足でくしゃくしゃに踏まれた新聞紙は「足の裏で読んでみます」、ネギを持って振り回す腕は「腕の筋肉組織が伸びてネギの繊維とつながる」など、触覚や体感、想像力を織り交ぜて描写される。ふくらませたビニール袋を蹴るダンサーと、その横で転がるダンサーは、「うさぎが惑星を蹴ると、カメも転がる」と置換される。また、始めは「CとD」として抽象化されていたダンサーは、途中から「キャメロンとディアス」と呼ばれ、「見る人が自分でキャラクターに変換してストーリーを作ってよいのだ」と語りかける。詩のような比喩や視点の自由さ、言葉のリズム感とあいまって、「ダンスの見方がわからない」という人に対して入り口を広げてくれるだろう。
同時に「テキストバージョン」は、「言語」そのものの可能性と限界、力と脆弱さの両極を改めて顕在化させる。言語化の作業は、視点や切り口の多様さを示す一方で、目の前で起こっていることのスピードと同時多発性に追いつけず、出来事は常に言語からこぼれ落ちてしまう過剰さを抱えている。また、身体に貼りついた新聞紙を「文字がどこまでもしみ込んでくる」、ネギを持って激しく回転するダンサーを「ネギに振り回される」と表現するなど、「主語や主導権」を「ダンサー/モノ」のどちらに設定するか(どちらかにしか設定できない)という問題は、言語自体の構造を逆照射してもいる。

[撮影:松本成人]
一方、③の「サウンドバージョン」は異色とも言える試み。まず、舞台奥にカーテンで上半身を隠したダンサーが立ち、モニターの記録映像を見ながら、自分の行なった動きに合わせて、息の音、言葉にならない声、擬音、ハミングのような声を出し続ける。その声は、ノイズを混ぜつつ、舞台中央の2台の巨大なスピーカーから出力される。さらにスピーカーは台車に乗せられ、台車を押す荒木優光ともう一人のスタッフによって、行き交ったり衝突したりと「モノの運動」を繰り広げる。荒木はこれまで、「録音音声を流すスピーカーを俳優の代替物と見立て、音響とその立体的配置による、俳優不在の演劇作品」を演出してきたが、その「ダンスバージョン」とも言えるだろう。ここでは、「ダンスの身体」の不在の反面、ある種の過剰さを目撃することになる。発声に伴う、ダンサーの下半身や腕の微妙な動きや震え。舞台上を動き回るスピーカーの緩慢な運動。それを動かす荒木らの身体。一方、視覚運動と音の関係が興味深いシーンもあった。「スピーカーが定位置で止まったままぐるぐる回転する」シーンは、ダンサーの回転をスピーカーに置換したものだが、スピーカーが正面向きから後ろ向きになると音が遠ざかって感じられたように、音の出力方向の変化が「位置関係の遠近」に変換され、視覚の絶対性への疑いを提起する。

[撮影:松本成人]
このように、「同じものを3回見た」というより、ダンスをベースにどう新たな表現や視点を派生できるかという実験だった本企画。もちろんここには、「単に『動き』を記述することと、『ダンス』を言葉にすることとの違いは何か」という、より大きな問いがある。また、今回は音楽を使用しなかったが、「音楽は、ダンスの世界観をわかりやすく伝えるための補助的手段なのか」という、ダンスと音楽の関係にまつわる問いも派生する。テキストとサウンドを組み合わせたらどうか、ダンサー2人に「1つの声」ではなく「2つの別の声」を割り当てたらどうか、「朗読もダンサー」ではなく、声の質感をより繊細に表現できる俳優などが担ったらどうかなど、さまざまな発展可能性がまだまだある。「正解はどれか」ではなく、実験と対話を重ねながら、ダンスの見方がより豊かになれば、本企画の意義は汲み尽くせないだろう。
関連記事
美術鑑賞における情報保障とは何か|田中みゆき:キュレーターズノート(2018年05月15日号)
死角だらけの視覚──オ・インファン《死角地帯探し》と視覚障害|田中みゆき:キュレーターズノート(2017年11月01日号)
田中みゆき「音で観るダンスのワークインプログレス」上演&トーク|木村覚:artscapeレビュー(2017年10月01日号)
2022/06/11(土)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)