artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
劇団テレワーク:第0回公演 『ZOOM婚活パーティー』と「Zoom演劇」

舞台公演の延期・中止が相次ぐなか、既存のカンパニー/新たな活動形態として立ち上げた新規団体を問わず、「Web会議サービスZoomを活用した演劇」の試みがさまざまに開始・予定されている。本評では、初動の早い一例として、4月5日に第0回公演がYouTube上でライブ配信された劇団テレワークによる『ZOOM婚活パーティー』を取り上げる。
劇団名が示すように、「出演俳優」はそれぞれの自宅からオンライン上の会議室に入室し、分割表示された画面どうしのあいだで会話が交わされる。「司会」役の進行と仕切りのもと、3名の男女ごとに3組に分かれてチャットを始めるが、次第に不穏な展開になり、各セッションごとに「タワマンに住む金持ちに見えたがじつは会社が倒産」「じつは元カレ」「じつはストーカー」が判明するが、最終的には「カップル成立」のハッピーエンドに回収され、エンタメ重視で気楽に見られる。ただし、「会社の倒産という苦労を経験した男性」に共感して惹かれる女性、「自分に経済的に依存していた元カレの感謝の気持ちを受け入れ、よりを戻す」女性、「根暗なストーカーの女性が『運命の女性』に変わった」という「ハッピーエンド」は、いずれも「男性が癒される物語」である偏向が気になる。また、「自室に侵入したストーカー女性に、キスマークを散らされた男性の顔」は、(彼は満面の笑みであるが)もし男女が逆であれば、「レイプ」の比喩的表象として映っただろう。

本評で考えたいのは、内容面よりも、今後増えるであろう「Zoom演劇」の可能性や制約についてである。「舞台公演が打てない」現状の打開策として始まった試みではあるが、(ニコニコ動画と同様)「観客の反応」がリアルタイムでチャットの表示窓に書き込まれる/再生されることで、「舞台/客席」の固定構造を揺るがす潜在性を持つ。「観客の反応」が(身体と切り離して)可視化され、(疑似的な)同期や一体感を得ることで、鑑賞体験は二重化されたものとなる。書き込みがログとして残ることで、(台本とは別の)スクリプトのタイムラインが形成されていく。この仕組みをメタ的に組み込む、「背景をバーチャルで変えられる」仕掛けを使って虚実を攪乱する、「手話や字幕」を入れるなど、さまざまな実験や手法が可能だろう。
また、「Zoomならでは」の特性として、PCやスマホの内蔵カメラで撮影するため、基本的にバストアップで、「顔の表情」が大写しになる。だがこれはメリットであると同時にデメリットでもあり、「表情」以外の身体性は縮減されていく。また、設定がワンシチュエーションに固定され、「オンライン飲み会」「オンライン面接」「オンライン会議」など「Zoomを使用して会話するシチュエーション」に限定されてしまい、「舞台設定」も(「外出の自粛」が解かれない限り)「自室など室内空間」の閉塞性や「ネット接続が可能な場所」の物理的制約を受けるため、今後、似たような試みの量産に陥る可能性も懸念される。
より広い視野で見れば、「Zoom演劇」の試みは、「(ライブ配信であれ録画であれ)生身の俳優が演じる行為を、映像として鑑賞する」という、すでに身近になった鑑賞形態を、より浸透させていくのだろうか。映画のNetflix視聴のように、「演劇=動画配信で見るもの」という消費形態が一般化・加速していくのか。DVDでの鑑賞、「シネマ歌舞伎」、2.5次元ミュージカルの映画館での「ライブビューイング」などのように、流通の経路に乗った「コンテンツ」として、商業的な回路に吸収されていくのだろうか。 「Zoom演劇」に限らず、舞台芸術作品のオンライン配信は次々と始まっており、オンラインチケット、有料配信、投げ銭制やドネーションなど「見ることで支援につながる」取り組みとしても機能している。そして、自粛要請や行動制限が解除され、劇場での公演が再開されるようになった将来(それはいつかきっと来る)、ネット視聴で掴んだ観客をどう「生の劇場空間」に還流させるかが、課題となるだろう。
2020/04/10(金)(高嶋慈)
山下残『インヴィテーション』

会期:2020/03/27~2020/03/29
THEATRE E9 KYOTO[京都府]
飄々としたユーモアとクリティカルな視線で「ダンス」「舞台芸術」を照射してきた山下残。本作では、パフォーマー同士の「~してもいいですか」「どうぞ/ダメです」「~してください」というやり取りによって、許可/禁止/指示される行為が積み重ねられていく。舞台芸術の制作現場やワークショップにおけるコミュニケーションへの自己言及に始まり、パワハラ、セクハラなどさまざまな関係性におけるヒエラルキーや不均衡な権力構造をあぶり出し、「舞台芸術」を成立させている制度内の/外側の社会構造を解体し、再提示してみせた。その先に浮かび上がるのは、コロナ禍における「自粛」の要請と、(あいトリでの文化庁の補助金不交付問題やオリンピック関連の文化事業においてとりわけ顕在化した)「事前に許可と承認を求める」「忖度」という日本の文化芸術を取り巻く現状だ。またここで、「許可/禁止」の判断の根拠の曖昧さや、判断を下す役を絶えず入れ替える流動性は、その判断の咨意性や責任主体の不透明な曖昧さについても鋭く問うていた。
上演会場はオールスタンディングで、舞台の壇も客席のひな壇も取り払われたフラットな空間を40-50人ほどの観客が取り巻く。虫の触覚のような装置を頭につけたパフォーマー(音響担当のおおしまたくろう)が登場し、「ご来場ありがとうございます。只今より山下残振付・演出作品『インヴィテーション』を始めます」とどもりながら告げる。彼が身体を動かすと、触覚状のセンサーが振動を拾い、不穏な音響が響く。だがその「前説」は、「トイレ行っていいですか」という唐突な声によって遮られ、作品の「開始」「輪郭」もまた曖昧にぼかされていく。あるいは、おおしまが何度も登場するたびに繰り返す「前説」によって、「開始」はずるずると遅延させられていく。
「トイレ行っていいですか」「タバコ吸っていいですか」と許可を求める声の積み重なりは、その日常的な行為のたわいのなさゆえに、「わざわざ許可が必要か」という不穏さを次第にまとっていく。許可と指示の言葉は、「左腕を上げてください」「耳を触ってください」「腰を回してください」といった具体的な動作と、「海をつくってください」「橋を架けてください」「入道雲になっていいですか」といった抽象的・詩的な言葉によって、「舞台芸術の制作現場やワークショップにおけるコミュニケーション」の様相を呈し始める。だが、「海をつくる」ために床に唾を垂らし続けるパフォーマーや、「その海に橋を架ける」ためにブリッジの姿勢を取り続けるパフォーマーの姿、そして強い調子で度々発せられる「もっとイマジネーションを使え」という(演出家の? ワークショップ講師の?)声や禁止の命令は、時に理不尽な要求や身体的な過酷さを強いる振付や演出がはらむ権力性や暴力性を浮上させ、舞台芸術の制度への自己批判とともにパワハラへの危うい接近を見せる。また、男性パフォーマーが女性パフォーマーに「身体の部位を触ってもいいですか」と低い声で言うシーンはセクハラを匂わせ、ジェンダーの不均衡に基づく権力関係が追記される。一方的で理不尽な要求のエスカレート、こなしきれない多重のタスクを課された身体は、次第に暴走的な様相を呈していく。

[撮影:中谷利明]
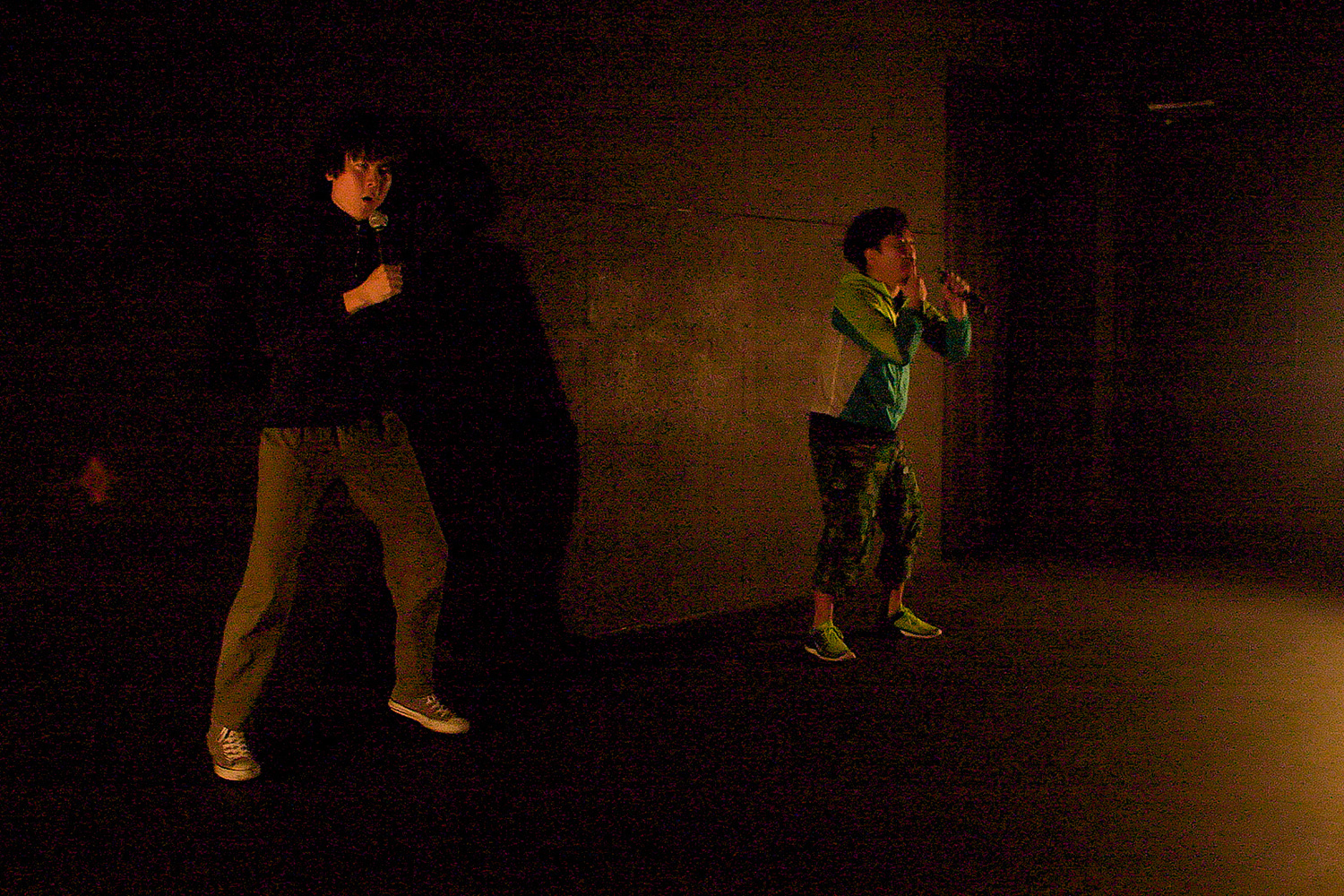
[撮影:中谷利明]
このように本作は、行為遂行的な言葉のやり取りがはらむ、(微温的な/だからこそ不穏な)権力の在りかをさまざまに浮上させつつ、「許可/禁止/要請」を発話する役割はパフォーマー間で絶えず交換される。その流動性は、ヒエラルキーの固定化に抗う一方で、誰が「許可を与える権力の主体」なのか? を曖昧に拡散させ、責任主体の見えにくさについても問いかける。また、反復される「前説」は、劇場に集った観客を迎える「インヴィテーション」の言葉であると同時に、「ここは舞台である」というメタ的な言及の繰り返しは、「人が集まること」という舞台の成立基盤と、それが「禁止」「自粛要請」されていく現状を照射する。「換気」のためと称して何度も解放される「扉」からは新鮮な外気が流れ込み、パフォーマーたちはラストで、開け放たれた扉から「劇場の外」へと歩み去っていく。

[撮影:中谷利明]
「入場料無料」という点も戦略的だ。それは一方では、「舞台作品にお金を払う価値とは」「観客は何を見たいと思って劇場に来るのか」という問いを投げかけ、「見たい」欲望と金銭的価値の交換、劇場・上演批判を繰り出す。だが他方では、スタッフワークの比重を下げ、照明や音響を出演者自身が操作することで、「低資金でも公演が実現可能」「無料で見られる」という、劇場利用者と観客の増加を共に目指す試みの希望的提示でもある。
山下によるこのポジティブな提示は、2019年6月に新しくオープンしたTHEATRE E9 KYOTOという劇場に対する強いメッセージでもある。同劇場は、関西圏のほかの多くの劇場が公演中止や延期を決定するなか、換気やアルコール消毒、客席の間引きなどコロナ対策を講じながら、3月末の本作まで初年度のプログラムをやり切った。もちろんここには、劇場スタッフや各公演団体の尽力があったことは言うまでもない。日々厳しさを増す状況のなか、1年目を最後までやりとげ、そしてこの作品で締めくくったことは、大きな意義があったといえよう。
2020/03/28(土)(高嶋慈)
地点『罪と罰』

会期:2020/03/20~2020/03/22
京都芸術劇場 春秋座[京都府]
原作小説の舞台、ロシアのサンクトペテルブルクにある国立ボリショイ・ドラマ劇場(BDT)から、劇場の所属俳優が上演するレパートリー作品として『罪と罰』の演出依頼を受けた地点の三浦基。2020年6月のロシア公演に先立ち、地点の俳優を中心とした日本人キャスト版が上演された。
長編小説の骨子を約2時間に抽出し、高利貸しの老婆とその妹を斧で殺害した青年ラスコーリニコフを中心に、彼の妹、金で結婚を買おうと言い寄る男、神への信心を説く母親、身代わりに罪を被ろうとする男、刑の軽減と引き換えに自首を勧める予審判事、そしてラスコーリニコフの自白を受け止める娼婦ソーニャらが織りなす人間関係のドラマが、ポリフォニックな発声と運動量によって紡がれていく。(ロシア語公演への引き継ぎということもあり)言葉遊びによるテクストへの介入と意味の脱臼は薄く、ダイジェスト的な要素が強く感じられたが、本作では俳優の身体運動と「階段」の舞台装置が特に目をひいた。俳優たちは台詞を発話しながら、あるいは無言のままで、ひたすら「歩行」に従事し、階段を昇降し続けるのであり、そこでは「ラスコーリニコフ」「ソーニャ」といった固有名詞は都市の匿名的な雑踏のなかにかき消されていく。「尾行」するように相手のあとをつけ、銃口の形をとった指を相手の頭に突きつける仕草や、「見てましたよ」「あなたですよ」という台詞の反復は、19世紀後半のロシアの裏さびれた街角を、匿名性と監視社会という現代に接続させていく。

[撮影:松見拓也]

[撮影:松見拓也]
「シラミを殺したって罪にはならない」と言いながら、ゴキブリを叩くように掌を床に打ち付けて転げ回るラスコーリニコフの姿は、神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」での殺害事件の被告に死刑判決が下されたタイミングと重なったこともあり、独善的な優生思想と肥大したエゴを戯画として突きつける。川への投身自殺を思いとどまった彼が、ソーニャの厳しい弾劾を浴びながら、「自分は特別で、劣った存在とは違うことを証明するために殺害した」ことを認め、のたうちながら自らの頭に「斧を振り下ろす」動作を繰り返すラストの告白は圧巻だ。彼の告白が欺瞞から真実へと近づくにつれ、「背後の街」は彼から切り離されて奥へと遠ざかり、建物に面した「街路」は「川に架かる橋」に変貌し、何もない空虚な空間が出現していく。その空白を埋めるように執拗に鳴り響き続ける鐘の音。そして、強固な存在に見えた「街」は真ん中で二つに割れ、彼の論理と世界の崩壊を告げる。

[撮影:松見拓也]
また、終盤で語られる、彼が見た「夢」の挿話は、コロナ禍とのあまりにも偶然の一致を見せ、預言的ですらある。「アジアの奥地で発生した恐ろしい疫病が、ヨーロッパ全土へと広がってやがて全世界を侵蝕し、大地を浄化する使命を帯びた選ばれた人々だけが生き残る」という夢だ。ラストシーンで彼は、「誰かいませんか!」と虚空に呼びかけるが、応答する者はいない。それは、選別思想によって淘汰が行なわれたあとの死の沈黙なのだろうか。それとも、コロナ禍による「自粛要請」によってもたらされた「文化的な死」の黙示録的な沈黙の光景なのだろうか。
関連レビュー
地点『罪と罰』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年05月15日号)
2020/03/21(土)(高嶋慈)
福井裕孝『インテリア』

会期:2020/03/12~2020/03/15
THEATRE E9 KYOTO[京都府]
「部屋」という空間単位において、ものとそれが置かれた環境と人(俳優)との相互作用として演劇の上演を捉え直す試み「#部屋と演劇」を行なっている、福井裕孝。「#部屋と演劇」には同世代の演出家、中村大地と野村眞人も参加し、1年間コンセプトを共有しながら各自の作品を上演した。
福井裕孝『インテリア』では、観客は自分の部屋にある「インテリア」をひとつ会場に持ち込み、「部屋」に見立てられた上演空間に配置し、上演を「ものと観る」ことができる。会場に入ると、舞台中央にサイドテーブルと円形ラグ、ティッシュボックスなどの小物が置かれ、ここが「リビング」であるらしいことがわかる。だがその手前の床には色鮮やかなパプリカ、マグカップ数個、ポット、ティーバッグが几帳面に一列に並べられ、黄色い靴下が丁寧に広げて3組並べられている。その光景は「何らかの一定の秩序」に従って几帳面に幾何学的な配置を施されていることがわかるが、「普段の生活空間における配置」の完全な再現ではなく、どこかズレている。また、家具や雑貨、日用品たちはいずれも量販店で買えるような没個性的なもので、「持ち主の強い個性や愛着」を声高に主張するわけでもない。この「リビング」の奥には、大きなビーズクッション、収納シェルフ、加湿器、トイレットペーパーのパックなどが置かれ、壁にハンガーと時計の架けられた空間があり、手前/奥で緩やかに二つの空間が境界画定されている。また、上手側には手前と奥に二つのドアがあり(実際に劇場の「外」に出られる)、ドア付近にはアルコール消毒液や傘が置かれていることから、ここが「玄関」であり、「隣接した二つのワンルーム」の設定が見てとれる。

[撮影:中谷利明]
手前のドアが開き、「ただいま」の声とともにビニール袋を下げた男が入ってくる。鍵を玄関脇に置き、靴と上着を脱ぎ、サイドテーブルの上にある(はずの)電球の紐を引っ張り、リモコンでTVをつけ(るフリをし)、手洗いとトイレを同様にマイムで行ない、ポットで湯を沸かし、マグカップを1個取ってティーバッグのお茶を(実際に)淹れる。ビニール袋からペットボトルを出し、丁寧に折りたたんだ袋の上に置き、脱いだ靴下や淹れたあとのティーバッグも丁寧にティッシュペーパーの上に置く。一連の動作は、毎日の帰宅後の彼のルーティンなのだろう。
男性が部屋を出ていくと、奥のドアからリュックを背負った女性が「帰宅」する。上着をハンガーにかけ、加湿器をセットし、ビーズクッションに座ってスチームを顔にあて、ヘッドホンで音楽を聴いてくつろぐ。同様に帰宅後のルーティンが再現されるが、彼女は手前の空間に侵入し、サイドテーブルのガラス天板を外して奥へ運び、ビーズクッションの横に置き直してしまう。彼女が出ていくと、3人目の女性が客席の通路を通って登場する。この女性(美術作家の西原彩香)は、開演前にロビーに展示してあった自身の作品を舞台=部屋に持ち込み、配置のバランスを考えながら壁や床に「展示」していく。彼女にとってここは「生活空間」ではなく「作品の展示空間」であり、「部屋を構成するさまざまな物体」は存在していないかのようだ。彼女が退場すると、再び手前のドアから男が「帰宅」し、同じルーティンを繰り返す。男、女1、女2の順で、「部屋での行動の再現」が3セット繰り返されるのが本作の基本構造である。

[撮影:中谷利明]
本作の面白さは、女1による「サイドテーブルの移動」、すなわち「もの」の再配置が、同じ動作を反復しようとする男の行動に作用を及ぼす点だ。男の動作は「もの」に規定されるため、基準点となる「サイドテーブル」の位置変更に伴い、電球のあるべき場所もTVをつけるリモコン操作の向きもトイレの位置も変化し、鍵は置かれる場所を喪失して床に落下する。一方、脱いだ靴下やペットボトル、ティーバッグを「並べる秩序」もまた「サイドテーブルを起点とする座標的な位置関係」を順守して遂行されるため、「1セット目」で並べて放置された痕跡を残したまま、新たな場所に「同じ空間秩序」がインストールされ、秩序の(再)構築と痕跡の同時進行が、「生活空間の疑似的再現の場」をカオティックに崩壊させていく。

[撮影:中谷利明]
ここで三者の様態を整理すると、男=「秩序の順守」および「もの」の空間配置による動作の規定、女1=「もの」の移動による空間秩序の再配置、女2=外部から新たな「もの」を持ち込み、別レイヤーの重なり合いの形成と規定することができる。また、この「レイヤーの多重化」は空間だけではなく、時間の圧縮と考えることも可能だ。例えば、「ワンルームの2室の壁が取り払われ、ホワイトキューブのギャラリーに改装された」、その「かつての生活空間」と「現在の展示スペース」が交錯する時空を私たちは見ているのだ、というように。
このように、「ルールの読み解き」や生態観察的な面白さとして楽しめる本作だが、それだけにとどまらない。例えばチェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』(2019)など近年の「ものの演劇」の潮流、代理表象の制度、脱人間・俳優中心的な演劇観に位置づけられるとともに、「ものの配置と秩序の(再)構築による、私的領域の主張(と排除)」という政治性についても考えることができる。「手前と奥の2部屋」に分かれていた空間が、「もの」の移動によって境界線が融解し始め、「私的領域」「テリトリー」が流動化し、「もの」が移動した新たな場所に「元の秩序」を持ち込む男は、「もの」を介した空間の私有地化・再領土化を行なう存在でもある。「室内の私的なインテリア」という「穏当な見かけの物体」はそのとき、インフラや制度のインストールによって地図を書き換え、奪取していく植民地的暴力、あるいは新たな移動先に自身の生活秩序を持ち込んで私有地化の権利を主張する移民的生、その双方のメタファーとして屹立するのである。ここに、演劇論的な実験を超えた本作の射程がある。
関連記事
福井裕孝『インテリア』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)
没入するモノたち──チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』|池田剛介:artscapeフォーカス(2019年10月15日号)
2020/03/15(日)(高嶋慈)
小田尚稔の演劇『是でいいのだ』/小田尚稔「是でいいのだ」

会期:2020/03/11~2020/03/15
SCOOL[東京都]
「小田尚稔の演劇」名義で演劇作品を発表してきた劇作家・演出家・俳優の小田尚稔による初小説「是でいいのだ」が『悲劇喜劇』2020年3月号に掲載された。同タイトルの演劇作品を小説化した本作で語られるのは「三月のあの日」に東京にいた5人の男女のそれからの歩みだ。
なにか劇的なことが起きるわけではない。新宿で被災し、震源地に近い実家の両親と犬の安否を気づかいつつ国分寺の自宅へ歩いて帰宅しようとする就活生(小川葉、以下2020年演劇版の配役)。夫に家を追い出された挙句に送りつけられた離婚届に署名しようとしているところで被災した女性(濱野ゆき子)。新宿西口公園で休憩していた彼女に声をかけ、その後もちょくちょく遊ぶようになる大学5年生の男(加賀田玲)。自ら離婚届を送りつけたにもかかわらず、被災後の不安からか「淋しい」と妻に電話をかけてしまう夫(橋本清)。悩んだ末に仕事を辞め、教員採用試験を受けることを決める女(澤田千尋)。彼女たちはそれぞれに自らの体験を淡々と、ときに自虐的なユーモアを交えて語る。
就活生の彼女はエントリーシートを書きながら自分の履歴を「カスみたい」だと思い「他人と比較して自分の越し方を思うと、少しだけ情けなくなる」という。三鷹まで歩いたところで中央線が動き出しているらしいことを彼女は知るが、それでも「今日は歩いて帰りたい」と彼女が思うのは「もし歩いて帰ることが出来たら、自分を自分で褒めてあげよう。失敗だらけの自分の生き方を少しは受け入れてあげよう。『これでいい』って、自分にそう言ってあげよう」と思ったからだった。
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
「是でいいのだ」というタイトルにはいくつかの由来がある。小田作品の多くは哲学者の著作をモチーフとしていて、本作ではイマヌエル・カント『道徳形而上学の基礎づけ』とV・E・フランクル『それでも人生にイエスと言う』がそれにあたる。小説版ではさらに赤塚不二夫の(あるいは『天才バカボン』の)影響が冒頭のエピグラフによって示唆される。
「あなたの考えは全ての出来事存在を、あるがままに前向きに肯定し受け入れることです。それによって人間は、重苦しい意味の世界から解放され、軽やかになり、また時間は前後関係を絶ち放たれて、そのときその場が異様に明るく感じられます。この考えをあなたは見事に一言で言い表しています。すなわち、『これでいいのだ』と。」(樋口毅宏『タモリ論』)
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
ところで、読者にとってこの小説の(ある部分の)語り手が誰であるか、何人の語り手がいるのかを判断することは実はなかなかに難しい。それぞれの語りの質感が似通っていることに加え、小説版では(当たり前だが)俳優もおらず、登場人物の名前も語られないからだ。しかも、語られる固有名詞やエピソードに重なる部分が多くあるため、しばしば彼女ら彼らは同一人物であるかのようにさえ思える。学生か就職しているか、未婚か結婚しているかという属性の違いだけが彼女ら彼らを見分ける手がかりとなるのだが、語りは一貫した時系列の下に進むわけではないため、同じ人物の異なる時間軸の語りが混在している可能性は排除できない。基準点となる「三月のあの日」におけるそれぞれの姿や行動だけが、彼女ら彼らが「別人」であることを示している。
彼女ら彼らに設定された共通点は、共感のための、自分ではない誰かに想像を広げるための糸口として用意されたものなのかもしれない。登場人物がそれぞれにつぶやく「大丈夫かな……」という言葉はその場そのときにいないひとへの想像力の発露にほかならない。本作は再演のたびに橋本以外の俳優を入れ替えてきていて、私の脳裏には「同一人物」を通して「別人」たちの姿も浮かぶ。
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
小説版は演劇版と語りの「感じ」も内容もほとんど同じなのだが、一箇所だけ大きな変更が加えられている。演劇版で重要な場面に登場する「もえあず」が別の人物に置き換わっているのだ。私も友人の指摘で知ったのだが、演劇版では細井くんと呼ばれる大学生の男の「推しメン」である大食いアイドル「もえあず」こともえのあずきが活動を開始したのは2012年3月13日、大食いキャラとして認知される最初のきっかけとなった番組の放送は同年10月のことらしい(Wikipediaによる)。となると、細井くんが被災時にもえあずのファンだったというのは現実的にはあり得ない設定だということになる。小説版の発表のあとに上演された演劇版でも「もえあず」が同じように登場していたことを考えると、これはわざとそのように描かれているのだろう。
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
実は、作中では「三月のあの日」が2011年のことだとは(観客にわかる形では)明言されず、東日本大震災という言葉も登場しない。つまり、「三月のあの日」はいつだってあり得るのだ。それはそのまま「三月のあの日」に私が思い知ったことだ。「その日」がいつ来るかは誰にもわからない。
だからこそ「是でいいのだ」という言葉は重い意味を持つ。それは素朴な現状肯定などではない。起きてしまった、変えられない過去を受け入れ、そこから再び歩みをはじめるための最初の小さな一歩。人生のいつだって、それを踏み出すことはできるはずだ。実は、仕事を辞め教員採用試験を受ける決意する彼女の語りだけは、震災のことに一切触れることがない。「あの日」がいつだってあり得ることの意味は反転する。いや、それはいつだって裏腹なのだ。過去は変えられず、未来はわからない。だから人はその一歩を踏み出す。
2016年10月に新宿眼科画廊スペース地下で初演された演劇版は、その後、三鷹にあるSCOOLに会場を移し、2018年以降、少しずつ改訂を重ねながら毎年3月に上演されている。新宿はこの作品の冒頭で「帰宅困難者」となった就活生が自宅のある国分寺への歩みをはじめた場所であり、三鷹は歩き続けた彼女が作品の最後で立っている「現在地」だ。SCOOLでの観劇を終えた観客は彼女の歩みを引き継ぐようにして帰途への一歩を踏み出す。
公式サイト:http://odanaotoshi.blogspot.com/
2020/03/14(土)(山﨑健太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)