artscapeレビュー
山下残『インヴィテーション』
2020年04月15日号

会期:2020/03/27~2020/03/29
THEATRE E9 KYOTO[京都府]
飄々としたユーモアとクリティカルな視線で「ダンス」「舞台芸術」を照射してきた山下残。本作では、パフォーマー同士の「~してもいいですか」「どうぞ/ダメです」「~してください」というやり取りによって、許可/禁止/指示される行為が積み重ねられていく。舞台芸術の制作現場やワークショップにおけるコミュニケーションへの自己言及に始まり、パワハラ、セクハラなどさまざまな関係性におけるヒエラルキーや不均衡な権力構造をあぶり出し、「舞台芸術」を成立させている制度内の/外側の社会構造を解体し、再提示してみせた。その先に浮かび上がるのは、コロナ禍における「自粛」の要請と、(あいトリでの文化庁の補助金不交付問題やオリンピック関連の文化事業においてとりわけ顕在化した)「事前に許可と承認を求める」「忖度」という日本の文化芸術を取り巻く現状だ。またここで、「許可/禁止」の判断の根拠の曖昧さや、判断を下す役を絶えず入れ替える流動性は、その判断の咨意性や責任主体の不透明な曖昧さについても鋭く問うていた。
上演会場はオールスタンディングで、舞台の壇も客席のひな壇も取り払われたフラットな空間を40-50人ほどの観客が取り巻く。虫の触覚のような装置を頭につけたパフォーマー(音響担当のおおしまたくろう)が登場し、「ご来場ありがとうございます。只今より山下残振付・演出作品『インヴィテーション』を始めます」とどもりながら告げる。彼が身体を動かすと、触覚状のセンサーが振動を拾い、不穏な音響が響く。だがその「前説」は、「トイレ行っていいですか」という唐突な声によって遮られ、作品の「開始」「輪郭」もまた曖昧にぼかされていく。あるいは、おおしまが何度も登場するたびに繰り返す「前説」によって、「開始」はずるずると遅延させられていく。
「トイレ行っていいですか」「タバコ吸っていいですか」と許可を求める声の積み重なりは、その日常的な行為のたわいのなさゆえに、「わざわざ許可が必要か」という不穏さを次第にまとっていく。許可と指示の言葉は、「左腕を上げてください」「耳を触ってください」「腰を回してください」といった具体的な動作と、「海をつくってください」「橋を架けてください」「入道雲になっていいですか」といった抽象的・詩的な言葉によって、「舞台芸術の制作現場やワークショップにおけるコミュニケーション」の様相を呈し始める。だが、「海をつくる」ために床に唾を垂らし続けるパフォーマーや、「その海に橋を架ける」ためにブリッジの姿勢を取り続けるパフォーマーの姿、そして強い調子で度々発せられる「もっとイマジネーションを使え」という(演出家の? ワークショップ講師の?)声や禁止の命令は、時に理不尽な要求や身体的な過酷さを強いる振付や演出がはらむ権力性や暴力性を浮上させ、舞台芸術の制度への自己批判とともにパワハラへの危うい接近を見せる。また、男性パフォーマーが女性パフォーマーに「身体の部位を触ってもいいですか」と低い声で言うシーンはセクハラを匂わせ、ジェンダーの不均衡に基づく権力関係が追記される。一方的で理不尽な要求のエスカレート、こなしきれない多重のタスクを課された身体は、次第に暴走的な様相を呈していく。

[撮影:中谷利明]
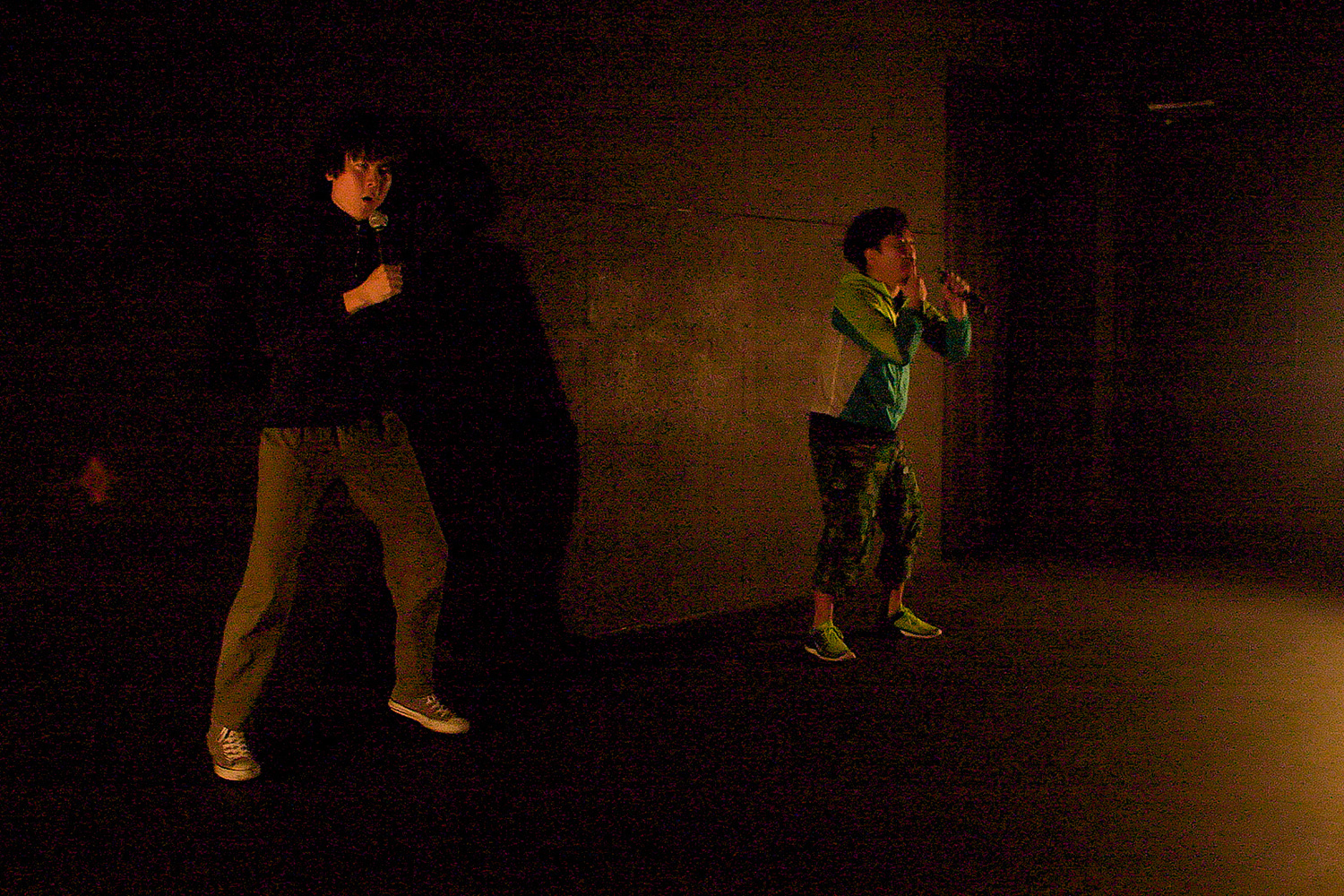
[撮影:中谷利明]
このように本作は、行為遂行的な言葉のやり取りがはらむ、(微温的な/だからこそ不穏な)権力の在りかをさまざまに浮上させつつ、「許可/禁止/要請」を発話する役割はパフォーマー間で絶えず交換される。その流動性は、ヒエラルキーの固定化に抗う一方で、誰が「許可を与える権力の主体」なのか? を曖昧に拡散させ、責任主体の見えにくさについても問いかける。また、反復される「前説」は、劇場に集った観客を迎える「インヴィテーション」の言葉であると同時に、「ここは舞台である」というメタ的な言及の繰り返しは、「人が集まること」という舞台の成立基盤と、それが「禁止」「自粛要請」されていく現状を照射する。「換気」のためと称して何度も解放される「扉」からは新鮮な外気が流れ込み、パフォーマーたちはラストで、開け放たれた扉から「劇場の外」へと歩み去っていく。

[撮影:中谷利明]
「入場料無料」という点も戦略的だ。それは一方では、「舞台作品にお金を払う価値とは」「観客は何を見たいと思って劇場に来るのか」という問いを投げかけ、「見たい」欲望と金銭的価値の交換、劇場・上演批判を繰り出す。だが他方では、スタッフワークの比重を下げ、照明や音響を出演者自身が操作することで、「低資金でも公演が実現可能」「無料で見られる」という、劇場利用者と観客の増加を共に目指す試みの希望的提示でもある。
山下によるこのポジティブな提示は、2019年6月に新しくオープンしたTHEATRE E9 KYOTOという劇場に対する強いメッセージでもある。同劇場は、関西圏のほかの多くの劇場が公演中止や延期を決定するなか、換気やアルコール消毒、客席の間引きなどコロナ対策を講じながら、3月末の本作まで初年度のプログラムをやり切った。もちろんここには、劇場スタッフや各公演団体の尽力があったことは言うまでもない。日々厳しさを増す状況のなか、1年目を最後までやりとげ、そしてこの作品で締めくくったことは、大きな意義があったといえよう。
2020/03/28(土)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)