artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
スペースノットブランク『ウエア』
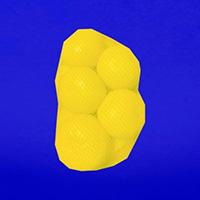
会期:2020/03/13~2020/03/17
新宿眼科画廊 スペース地下[東京都]
前作『ささやかなさ』で岸田賞作家・松原俊太郎の書き下ろし戯曲を上演したスペースノットブランク(以下スペノ)が今回「原作」を依頼したのはいじめや親子関係など自らの実体験を元にした作品で注目を集める「ゆうめい」の池田亮。松原戯曲の饒舌さにはスペノのこれまでの「文体」との共通性が感じられなくもないが、ストレートな「物語」を戯曲として書いてきた池田との組み合わせは正直言って意外だった。だが、スペノもまた、制作のプロセスにおける時間の積み重ねを現在形の舞台として立ち上げる「ドキュメンタリー」を上演してきたアーティストであり、その意味では池田との距離はそう遠くないのかもしれない。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
スペノとゆうめいが共に出演した「どらま館ショーケース2019」では、もうひと組の参加団体であった関田育子も含め、三組が三組とも何らかの意味で「ドキュメンタリー的」な手法を用いていた。あらかじめショーケースのテーマが設定されていたわけではなく、私を含む推薦者3名がそれぞれ一団体を推薦した結果のラインナップだ。演劇の「ドキュメンタリー」としての、つまりは「現実」としての側面に意識的なつくり手が30歳前後の若手には多い。あるいはそれは人的交流による部分もあるだろう。スペノとゆうめいの付き合いは長く、互いの作品にメンバーが出演することもしばしばだ。『ウエア』には音楽担当としてヌトミックの額田大志も参加しているのだが、いわば「バンド」的な連帯による作品/場づくりもまたこの世代の(あるいはここ数年の小劇場シーンの)特徴として指摘できる。
ポストパフォーマンストークでの発言によれば『ウエア』もまた池田の実体験に基づいて書かれたものらしいのだが、上演からそれを読み取ることは不可能だろう。池田による原作は上演台本のかたちに構成し直され、そこにあった(かもしれない)物語は断片となり浮遊している。観客はそれを拾い集めて元のかたちを想像するしかない。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
どうやらそこには何らかの会社の企画会議の参加者とヤクを製造販売するグループとが登場しているらしいのだが、ヤクを吸ってバッド・トリップする登場人物たちはしばしば現実と幻覚、自分と他人の区別がついていない。一方がもう一方の見る幻覚だとも思える場面もある。ナミやニコンロといった漫画『ワンピース』を思い出させる登場人物の名も現実感を乏しくする。4人の俳優(荒木知佳、櫻井麻樹、瀧腰教寛、深澤しほ)は演じる「役」(というものがあるとすればだが)をしきりに入れ替えているようで、「虚構」はやがて決壊し「現実」に流れ込む。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
作中に登場する「メグハギ」というキャラクター(Vtuber?)はさまざまな要素=キャラづけによって成り立っている。キャラクターを構成するのもまた複数のキャラクターなのだ。「メグハギ」と聞いた私が最初に連想したのは「つぎはぎ」という言葉だった。虚構のつぎはぎとしての虚構。ならば現実はどうか。
悪夢的な、とても「意味がわかる」とは言えない上演は緻密なスタッフワークによって支えられている。額田の音楽とstackpicturesの映像は全編がサンプリングによって構成され(ていると思われ)、「メグハギ」のあり方を反復する。俳優の意志によって厳密にコントロールされた身体に櫻内憧海の音響・照明が精確に対応し、観客たる私もまたその世界と合一する。バッド・トリップの手触りは外から眺める虚構としてでなく、まさに私自身が体験するものとしてそこにあった。私の横では非常口のサインまでもが同期し明滅している。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
現実/虚構の分離と一致の運動。原作に書き込まれていたであろう(しかしもちろんそのようにして想像される「原作」も一種の「メグハギ」に過ぎない)その感触をスペノの二人はきわめて高い精度で観客に触知可能なものとして立ち上げてみせた。バッド・トリップめいた「狂った」世界を手渡す演出はどこまでも理性的で巧緻だ。
5月には『ささやかなさ』東京公演が控えている。やはり容易に「わかる」とは言いがたい松原戯曲からスペノは何を引き出し体感させてくれるだろうか。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
公式サイト:https://spacenotblank.com/
関連記事
スペースノットブランク『原風景』 │ artscapeレビュー(2019年03月15日号) | 山﨑健太
ゆうめい 父子の展示・公演『あか』 │ artscapeレビュー(2018年07月01日号) | 山﨑健太
2020/03/14(土)(山﨑健太)
若だんさんと御いんきょさん『鞄』

会期:2020/03/06~2020/03/08
THEATRE E9 KYOTO[京都府]
安部公房の戯曲『棒になった男』(1969)の第1景『鞄』に対して、3人の演出家がそれぞれ演出した3本を一挙上演する企画。演劇ユニット「若だんさんと御いんきょさん」によるシリーズ企画第2弾であり、昨年は第2景『時の崖』が上演されている。演出違いの3バージョンを見比べることで、戯曲に対するアプローチや解釈の振れ幅が浮き彫りになり、ひとつの戯曲の多角的な鑑賞を通して、多様な読みや上演可能性に開かれた創造的な器としての戯曲のあり方が立ち現われる。
『鞄』は、夫が家の中に置いている鍵のかかった不審な旅行鞄をめぐって、気味悪がる「女」(妻)と「客」(女友達)が交わす会話劇。不審な物音や呟き声を立てる鞄の中身について、女は虫かミイラかもしれないと妄想し、「何をしていてもこの音がまとわりつく」と嫌悪する。女友達がヘヤピンで鍵をこじ開けようとするが、生きているかのように奇妙な物音がして二人は飛び退く。行動の決断力も責任も持とうとしない女は、友人の自尊心を刺激して開けさせようとしたり、どこかに捨ててきてほしいと頼み、心理的な駆け引きが展開されるなか、錠前の外れる音がする。「あとは、あなたの心の錠前だけね」と言い残して友人は去るが、女は鞄に鍵をかけ、夫の帰りを待つあいだ、ラーメンの出前を注文する。
リアルな手触りの会話劇から、「鞄」のもつ不条理性を立ち上げるにあたり、「鞄」をどう解釈し、どこまで具現化/抽象化するか。この最大のポイントをめぐり、三者三様のアプローチが分かれたことが興味深い。実物の「旅行鞄」を舞台上に持ち込んだのは、合田団地(努力クラブ)。エスカレートする苛立ちとディスコミュニケーションの閉塞感が出口を求めて暴走していく回路が、「会話劇」だが対話相手と向き合わず、二人の女優それぞれが客席に向けて放つモノローグ的な発話の掛け違いとして提示された。感情を喪失したような平坦な棒読みやひきつった笑いの肥大化は生理的嫌悪感をかき立て、対人的な感情の出力がコントロールできない、非人間的な狂気へ近づいていく。「ほかにも苛立たせる物音はあるのに」と言う友人が列挙する「飛行機や車の轟音、風の音」は効果音として流れるのだが、「食事は毎日あげているの?」「家の中で来る日も来る日もこの音に悩まされている」といった台詞は、「具現化されていない音」、すなわち赤ん坊の泣き声を想起させ、妻に一方的にのしかかる育児の負担を暗示する。二人の女の背後で所在なさげにテーブルに座っていた男は、「ヘヤピン」を腹に刺され、女たちの感情の暴発が乗り移ったかのようにうめき声を発し続け、遂に自壊して「鞄」に変容を遂げる。女たちもまた、座っていた椅子にそれぞれ旅行鞄を置いて立ち去り、「鞄」からはなおも機械的な発声の声が聞こえ続ける(ように見える)。自分自身が「怖れや不安」の対象と同一化し、非人間性の塊と化す戦慄的なラストであると同時に、「本来そうではないもの」が「そうであるフリ」をする齟齬を最大化して提示することで、「演劇」へのメタ的な身振りともとれる。

合田団地演出『鞄』 [撮影:manami tanaka]
一方、「主導権を奪おうと互いに牽制し合う二人の女の駆け引きに、実効的な支配力を及ぼし続ける男」という構図を採用したのが、河井朗(ルサンチカ)。河井演出では、俳優の身体性や動きの抽象化により重きを置き、静かな緊張感のなかに粘着質の生理的な体感の生々しさがじわじわと迫ってくる。対面して左右対称やユニゾンで動く2人の女は、自己の鏡像か分身のようにも見え、「彼女たちにはその存在が見えない」男は、異物として疎外されている/侵入してくる。押さえた発話や身振りの浮遊感のなかに、引力と斥力、磁力のような見えない力の作用や流れを可視化する手つきが洗練されていた。

河井朗演出『鞄』 [撮影:manami tanaka]
田村哲男による演出は、3本の中では最も戯曲に忠実でありつつ、ジェンダー転倒という変化球を投げてきた。だが、その仕掛けによって新たな解釈の端緒を開きつつ、最終的に自ら閉じてしまっていた点が惜しまれる。田村演出では、「妻」役をあえて男優が演じることで、関係性は定位せずにつねに揺らぎ続ける。彼らはゲイカップルなのか? あるいは「私たち、昔はうまくいってたじゃない」と言うシーンでは、バイセクシュアルとして女友達とかつて恋人関係だった可能性が浮上する。さらに、「女言葉でしゃべるが外見は男性」を字義どおり受け取るならば、この「妻」はMale to Femaleのトランスジェンダーという見方も成立する。そこでは、彼/彼女を悩ませ脅かす「鞄から聞こえる異音」は、ホモフォビアあるいはトランスフォビアの謂いとなる。

田村哲男演出『鞄』 [撮影:manami tanaka]
「仕事の帰りが遅い夫」を待ちながら女友達とおしゃべりして抑鬱を晴らそうとする、「家庭内で夫を待つ妻」。それをあえて男優が演じることで、(50年前という時代差に埋め込まれた)ジェンダー描写の偏向が露わとなる。その偏向は、「ゲイカップル」がヘテロセクシュアルのカップルを前提とした性別役割分業を踏襲していることや、トランスジェンダーがどこまでジェンダー規範や性別役割分業を内面化するのかといった問いの喚起によって、より浮き彫りとなる。
だが、ラストシーンでは、背後のスクリーンに「森友・加計学園」「マイクロプラスチック」「CO2排出量」「グレタ・トゥーンベリ」「非正規雇用」「子供の貧困」「原発再稼働」といった単語が次々と投影され、「鞄」の中身が「現代社会の時事問題」に短絡的に限定されてしまう(そこには「LGBTQ」に関する単語は不在である)。関係性の揺らぎ=想像力を投企できる演劇的余白や、セクシュアリティ・ジェンダーをめぐる問題圏、クィアな読解につながる萌芽はあったものの、掘り下げられないまま、「大きな事象」の羅列の中に拡散してしまったことが惜しまれる。

田村哲男演出『鞄』 [撮影:manami tanaka]
関連レビュー
若だんさんと御いんきょさん『時の崖』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)
2020/03/08(日)(高嶋慈)
リーディングパフォーマンス 市原佐都子/ジャコモ・プッチーニ『蝶々夫人』

会期:2020/02/29~2020/03/08
新型コロナウイルス感染症対策を受け、「観客も含めた少人数でのリーディング」という上演形態が、「オンラインによる戯曲配信」と「参加者の自主的なリーディング」に変更となった本作。合わせて公開された動画では、前半で市原佐都子自身が登場し、プッチーニのオペラ『蝶々夫人』(1904)の元となったピエール・ロティの小説『お菊さん』(1887~88)を紹介し、美しいが受動的存在として人形に例えられる「ステレオタイプな日本人女性」について解説したあと、後半では、実際のリーディング風景の抜粋が「お手本」として収録されている。筆者はグループでの自主的なリーディング会に参加する機会が得られなかったため、以下の本評は「戯曲の黙読」に基づくものである。
本作の構成は明快で、プッチーニのオペラ『蝶々夫人』と、市原が書き下ろしたオリジナルの台本が交互に登場する。アメリカから長崎に赴任した軍人ピンカートンの「現地妻」となった15歳の元芸者「蝶々さん」は、3年間夫を信じて帰りを待ち続けるが、彼がアメリカ人の妻を伴って帰還したことを知り、「青い目の息子」を遺して自害する。このメロドラマ『蝶々夫人』のダイジェストの合間に挿入される市原のテクストは、舞台を現代日本に置き換え、オリエンタリズムの眼差しに一方的に晒されてきた「蝶々さん」の側に「私もまた欲望の主体である」という「声」を与えて取り戻しつつ、被抑圧者が「正しい糾弾」を繰り出すのではなく、そうしたPC的な態度に潜む欺瞞に対しても反省的に自覚し、私たちが無意識に抱え込んでいる「差別意識」を突きつける。
市原の書き下ろしは3パートあり、①オペラ『蝶々夫人』をベースにした新作『超蝶々』をドイツの劇場と共同制作中の、女性アーティスト4名から成る劇団「ザ・イエローバタフライズ」の稽古場、②六本木で不倫したビジネスマンのアメリカ人男性による懺悔、③「外人」と結婚した「蝶々ちゃん」の結婚式で祝辞を述べる友人代表、というものだ。このうち、①では、「蝶々さんは、現代では『外人ハンター』(西洋人男性の気を惹くため、ステレオタイプな容姿で六本木に集まる日本人女性)ではないか」という会話に始まり、「容姿を唯一の基準とする女性の優劣化」「見られる対象として相手(西洋人男性/日本人男性)の欲望に容姿を従わせる理不尽さ」に対してルッキズム批判が繰り出されるとともに、「西洋人」への憧れと(コンプレックスの「克服」としての)差別感情があぶり出される。また、ドイツの国際フェスティバルを例に、「非西洋」が文化的植民地として搾取される構造への批判や、「でもフェスから資金が出るから創作できる」=資本主義のマーケットに取り込まれることへの批判が自己言及される。
②では、「不倫を牧師に懺悔するアメリカ人ビジネスマン」の言葉が、「外人」の金とステータスシンボルが目当ての日本人女性を「知性のないサル」と見なす侮蔑と嫌悪に塗り替えられていく。一方、これと対応関係にある③では、「六本木のバーで出会ったピンカートンと結婚した蝶々ちゃん」への祝辞であるはずの言葉が、「外人」(おそらく②のビジネスマンと同一人物)と自身の性行為の赤裸々な描写にすり替わり、「3万円もらった」という言葉が(メロドラマの陰に隠された)「売春」という『蝶々夫人』との共通項を浮かび上がらせる。
形式面を見れば、「牧師への懺悔」「結婚式の祝辞」という形式を借りて、長大なモノローグの「不自然さ」を回避・クリアする手法は、「落語」「歌謡ショー」「セミナー」の形式を借りた『妖精の問題』における問題意識の延長線上に位置づけられる。本作では、この「懺悔」と「祝辞」の双方がお互いへの差別的感情と動物的欲望を赤裸々に吐露するのだが、①の「稽古場シーン」も(市原自身が投影されたと思しき)1人の人物の分裂的な会話にも見える。そのなかで、前作『バッコスの信女―ホルスタインの雌』の海外公演にあたっての経験を自己言及的に引きつつ、「ドイツ人側に対話相手と見られていない」「対等の関係ではない」という台詞が登場する。モノローグの閉塞感の密度をこのまま高めていくのか、あるいはそれを突破してどうダイアローグへと移行するのかが、今後のポイントのひとつになるだろう。
戯曲の段階ではあるが、本作は、これまでの作品との共通項の上に、これからの方向性が見えるものだった。形式的には、オペラすなわち「音楽劇」の要素を含むこと。内容的には、「女性が(見られる・語られる対象ではなく)自身の性や欲望を語ることの肯定」「人種差別」「ハーフ」「ルッキズム批判」に加え、西洋・男性から非西洋・女性に対する「オリエンタリズム」の一方的な眼差しとその反転が加わり、より立体的な拡がりが獲得された。
公式サイト:シアターコモンズ'20 https://theatercommons.tokyo/
関連レビュー
市原佐都子/Q『妖精の問題』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月01日号)
あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)
2020/03/07(土)(高嶋慈)
劇団速度『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』

会期:2020/03/05~2020/03/08
新型コロナウイルス感染症対策として公演の延期・中止が相次ぐ厳しい状況のなか、舞台芸術の存立基盤の危機的状況に対する批評的でしなやかな応答も試みられている。本評ではその一例として、京都を拠点とする劇団速度の試みを取り上げる。
劇団速度は3月5日~8日に京都芸術センターで『舞台の実存とスクリーン、間にいるあなたの眼』の上演を予定していたが、12月に延期となった。この作品は、初期作品の沈黙劇のリクリエーションであり、「言葉と俳優の関係」「沈黙、反復、字幕」について扱うものであったという。彼らはこのコンセプトを引き継いだ映像作品を京都市内の路上で撮影し、集客型の劇場作品からオンラインでの動画配信に切り替え、公演が予定されていた計4日間、映像を1本ずつ公開していった。

と言っても、この映像作品『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』は、「(劇場の代わりに)路上で俳優が行なった演技の記録映像」ではない。副題が示すように、単なる「市街劇の記録映像」との違いは、行為を記述/指定する「字幕の介在」にある。映像は①固定カメラによる定点観測、②キャリーカートを引いて歩く俳優のあとを追うカメラ、の2種類から成るが、いずれもキャリーカートに載せられたディスプレイに「字幕」が投影され、「歩く」に始まり、「横切る」「すれ違う」「カバンを背負って歩く」「通勤する」「挨拶する」「目が合う」「振り向く」といった行為が次々と記述されていく。カメラに気づかず行き交う人々の姿は、あたかも「ト書きに指定された行為」を無言で遂行する俳優であるかのように見えてくる。それは「観察と命名」という一見客観的な行為でありつつ、「路上で起こる出来事のすべてを『演劇化』して取り込もうとする」暴力性をまとってもいる。

一方で、「映像の情報量の圧倒的な多さ」「行為の同時多発性」は、「ト書きによる行為の指定」をすり抜けていこうとするだろう。また、「ラジカセをつける」「音楽」という「字幕」の傍らで俳優が踊ったり、「横になる」「眠る」「リフティングする」という「字幕」どおりの行為を俳優が行なう光景では、確かに「指示どおりの行為」は起こっているのだが、果たしてそれだけで「演劇」が成立するのか? という疑問が浮上する。ここでは、「行為の指定と強制的遂行」に還元された演劇の原理的フレームが強化されつつ、その脆弱性もまた露わとなる。また、(通常の上演においては不可視の)「ト書き」が「字幕」として顕在化することで、「誰がその行為を指定するのか」という権力性や、一方的な関係性がはらむ暴力性も浮上する。
一方で、本来の上演会場であった空間が、「字幕」のディスプレイとともに「無人」で映し出されるシークエンスがたびたび挿入される。俳優も観客もいない薄暗い会場に、ただ「歩く」「すれ違う」「眺めている」「雨が降っている」といった言葉だけが提示されるとき、それは「不在のものの投影、二重化の眼差し」としての演劇を(再び)この場に召喚し、想像力の再起動を促すだろう。また、路上の光景に何度か映る「ビニール傘」「ボール」「ラジカセ」が「無人の劇場空間」に配置されていることは、これらの物体が「小道具」「音響装置」の位置を離脱して「(疑似的な)プレーヤー」の位相へと移行したことを示す点で、「ものの演劇」の潮流、脱人間・俳優中心的な演劇観の更新の試みといえる(劇団速度の主宰、野村眞人は、ものとそれが置かれた環境と人 (俳優)との相互作用として演劇の上演を捉え直す試み「#部屋と演劇」のメンバーでもある)。

このように本作は、「状況による不可避的な要請」を出発点としつつも、単なる代替案を超えて、「演劇」に対するメタ的な思索の試みとして成立している。また、(マスク姿ではあるが)普通に多くの人々が行き交う路上の光景は、その「退屈な日常性」によって、逆説的に「公演延期」に対する密やかな抗議を作品内部に刻印してもいる。こうした経験が12月の上演にどう組み込まれるのか、期待したい。
【劇団速度】『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』①2020年3月5日
関連レビュー
福井裕孝『インテリア』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年4月15日号)
2020/03/07(土)(高嶋慈)
ポスト・コロナとシアターコモンズ’20

会期:2020/02/27~2020/03/08
港区エリア各所[東京都]
新型コロナウィルスの影響により、公演の自粛が増えてゆくなか、幸い、シアターコモンズが企画した、小泉明郎の『縛られたプロメテウス』を体験することができた。実はこれが二度目なのだが、一度目のあいちトリエンナーレ2019では、機器の不具合によって、VRの半分はカラフルな自然ののどかな風景を見ていたという未消化の体験だったため、もう一度完全なかたちで見ておきたかった作品である。やはり、脚本=朗読されるテキストの内容と、後半でその意味が明らかになるコラボレータの選択が傑出している。おそらく、今後もVR技術が日々進化するので、これよりもインパクトのある映像体験は簡単につくられるだろう。いや、すでに存在している。だが、作品がトータルでもたらす世界観の強度は減じないのが、まさにアートの価値だろう。
また同日の夕方、リーブラホールにて、ジルケ・ユイスマンス&ハネス・デレーレ『快適な島』を鑑賞した。壇上の二人が一言もしゃべらず、立ったままスマホを操作するだけなのだが、ドキュメタリー映像をその場で編集・上映するドキュメンタリー演劇だった。鉱石開発によって世界中の資本主義と接続し、翻弄された小さな島のテーマも興味深いが、上演形式そのものが考えさせられる作品である。考えてみるとこの後、筆者は演劇をひとつも見ていない。現時点ではこれが、最後の観劇だった。
改めてこれらの作品を思いだすと、いずれもポスト・コロナの作品としても興味深いように思われた。すなわち、小泉の作品は現存しない世界をVRで体験させており、ゴーグルの機器が一般化すれば、会場に足を運ばなくても成立するかもしれない。しかし(ネタバレになるので、ここでは詳しく書かないが)後半の展開はやはり人が集まることに意味を持たせる演出になっている。
またスマホを操作し、その画面を鑑賞するドキュメンタリー演劇の『快適な島』は、類似した例だと、内容はフィクションだが、父が行方不明の娘を捜索する『search/サーチ』(2018)のように、パソコンの画面だけを用いた映画作品があった。これはリアルタイムで操作しているライヴ感さえ確保できれば、それぞれの自宅で十分に鑑賞ができるかもしれない。自粛ムードの出口がしばらく見えないなか、上演の方法も問われるだろう。
公式サイト:
小泉明郎「縛られたプロメテウス」
https://theatercommons.tokyo/program/meiro_koizumi/
ジルケ・ユイスマンス&ハネス・デレーレ「快適な島」
https://theatercommons.tokyo/program/silke_huysmans_hannes_dereere/
2020/03/06(金)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)