artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング

会期:2022/06/29~2022/11/06
森美術館[東京都]
本展における「ウェルビーイング」は、「心身ともに健やかであること」と暫定的に会場入り口のステイトメントで書かれているが、会場を周れば、それは社会的な生産性への適合を意味しないことがすぐに明らかになる。むしろ、執拗な無為の積み重ねや、自己規範の徹底といった、きわめて内的に練り上げられた倫理による造形の強烈な発露だ。
最初はオノ・ヨーコのインストラクション作品《グレープフルーツ》(1964)で始まる。小さな文字を読み脳内で想像を巡らせ、次はヴォルフガング・ライプによる花粉やミルクによる途方もない作業の集積、だが、それは一面の鮮やかな色面でしかないもの、を目の当たりにする。違う部屋に入る。汲みつくせない細部が描かれたエレン・アルトフェストによる絵画、ひたすらに眼で見て描くことが繰り返された木肌、風景……本展は前後の作品がお互いに緩やかに対比的に配置されることで、それぞれの作品が際立つという、グループ展においてつねに目指されるがなかなかたどり着けない多声性に溢れていた。
例えば、ゾーイ・レナード《アイ・ウォント・ア・プレジデント》(1992)と飯山由貴《影のかたち:親密なパートナーシップ間で起こる力と支配について》(2022)は隣り合うように位置していた。いずれも作者による言葉が記載されたペーパーを持ち帰ることができる展示だ。ゾーイの詩はここにすべて書き写したいくらいなのだが、少し抜粋する。
エアコンを持っていない大統領がいい、クリニックや自動車管理局、福祉局の列に並んでて、失業中で、解雇されて、セクハラを受けて、ゲイバッシングされて、強制送還された人。(……)私たちにとって、なぜ、いつから、大統領はピエロになったのか知りたい。なぜいつも客の方で、決して売春婦ではないのかを知りたい。いつも上司で、決して労働者ではない、いつも嘘つきで、いつも泥棒で、決して捕まらない。
この詩を読んだ後、飯山の作品のある部屋に入る。紫の壁、オレンジのカーペット。ドメスティック・バイオレンスの加害・被害経験者による語り、公的なDV支援の困難な現状、展覧会の観賞者が会場に書き残した言葉がカッティングシートとなり貼られていた。ゾーイの詩から20年。飯山は部屋で配られているハンドアウトで次のように書いている。
日本に「DV防止法」はありますが、被害者に寄り添った法律と支援制度がある、とは決して言えない実態があります。個人の気づきから、それぞれが手探りで自分自身の仲間、支援者を見つけ、そこからの脱出方法や回復の方法、固有の状況に「自助」で問題とつきあっていくしかないのです。この作品は、社会にいるその人の姿からは非常に見えづらい、私的な関係性のなかで起きる出来事をこれから私たちはどのように話し合っていくのか、そして責任を分かち合い、家族やパートナーシップとは異なる別の〈親密圏〉を作り出し、支え合うことを考えていくためにつくられました。
ゾーイの詩が自身の現状に気づく手立てとして鮮烈に観賞者を揺さぶり、現状がなぜこうなのかという問いに形を与える。では、その状況のひとつにどう向き合うかと、飯山は具体的に答えを探す。さらには、どういった情報を集約して、立ち向かうことが可能か示す。国という極大的な公共圏への疑義と、対極的な家という親密圏での暴力。それは為政者と法の下、表裏一体だ。飯山のペーパーには、たくさんのDVに関する相談先とその連絡先が掲載されている。ネットで検索すれば出てくるかもしれない。けど、気づきなしに、検索することが果たしてできることなのか。ゾーイの強烈な世界についての記述が、飯山の作品の情報量を受け止める心構えを与えていた。
公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/earth/
2022/11/05(土)(きりとりめでる)
エバレット・ケネディ・ブラウン『Umui』
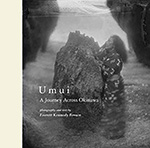
発行所:サローネ フォンタナ
発行日:2022/10/30
1959年、アメリカ・ワシントンD.C.生まれの写真家、日本文化史研究家のエバレット・ケネディ・ブラウンは、このところ初期の写真技法である湿版写真(Wet collodion process)で日本各地の風景、人物、祭事などを撮影している。沖縄県立芸術大学客員研究員(歯科医師、わらべ唄研究家)の高江洲義寛が監修した本作では、沖縄各地を湿版写真で撮影した。
ブラウンが写真撮影を通じて見出そうとしたのは、沖縄人の魂の表出というべき「 UMUI=ウムイ」の在処である。「UMUI」は「思い」と表記されることが多いが、ブラウンによれば「心の中に湧き上がる祈りや感情」であり「生命の叫び」でもある。沖縄の人々、大地、植物、遺跡などに漂う「UMUI」はむろん目に見えたり、手で触ったりできるものではない。だが、あえて露光時間が長くかかり、暗室用のテントで、撮影後すぐに現像・定着をしなければならない湿版写真で撮影することで、被写体をオーラのように取り巻く「UMUI」を捉えようと試みている。そこにはたしかに、沖縄の地霊を思わせる何ものかが、おぼろげに形をとりつつあるように見えてくる。
もう一つ興味深かったのは、そこに写っている沖縄の人たちのたたずまいが、太平洋のより南方の地域に住む人々と共通しているように見えることである。これには理由があって、ガラスのネガを使う湿版写真は、赤に対する感度が低いので、肌や唇の色がやや黒っぽく写ってしまうのだ。だが、そのことによって、沖縄の精神文化がむしろ南方の環太平洋地域に出自をもつものであることが、問わず語りに浮かび上がってくる。日英のテキストと写真とを交互に見せる写真集の構成(デザイン=白谷敏夫)もとてもうまくいっていた。
2022/11/05(土)(飯沢耕太郎)
藤原更『Melting Petals』

発行所:私家版
発行日:2022/10/22
藤原更はユニークな軌跡を描く写真家である。コマーシャル・フォトの世界からアート写真の世界に転じ、2000年代以降は東京・広尾のEmon Photo Gallery(2020年に閉廊)を中心に展覧会を積み重ねていった。ポラロイド写真などによって制作した画像を大きく引き伸し、ギャラリー空間にインスタレーションした作品は、アメリカやヨーロッパ諸国でも評価が高い。今回、町口覚のデザインによって私家版で刊行された『Melting Petals』は、彼女にとっては最初の本格的な写真集となる。
写真集は「Scattered Memories in the Field of Transience(うつろいゆく領域にちりばめられた記憶)」「VOID: Inseparable Domains(空虚:分割できない場所)」「Uncovered Present(見出された現在)」の三部構成であり、それぞれ5~7枚の写真が収められている。ほとんどは色面とフォルムに単純化された抽象的なイメージであり、ポラロイド写真の感光乳剤を剥がしとる「ピーリング」と称する技法を駆使することで、日常の世界からは離脱する幻影のような空間が構築されていた。
とはいえ、主に赤と緑のグラデーションによって織り成された画像は、奇妙に生々しい現実感もまた備えている。それは、これらの写真群の被写体となっているのが、芥子の花(ポピー)であることからもきているのだろう。芥子の花はいうまでもなく阿片の原料でもあり、美しさだけでなく、ある種の魔術性、どこか禍々しい気配を秘めている。藤原はそのあたりを十分に考慮しつつ、ともすれば紋切り型になりがちな「花」の写真に、既存の価値の原理を掻き乱すような要素を付け加えようとした。
たしかに、これまで藤原が発表してきた「花」や植物の写真と比較しても、「Melting Petals」は特別な意味をもつシリーズといえる。とはいえ、藤原の写真家としての可能性は、本写真集におさめられた23枚の写真群だけに収束していくものではないはずだ。むしろその仕事の幅を、さらに広げていくべき時期に来ているのではないだろうか。なお、写真集刊行に合わせて、東京・銀座の森岡書店で出版記念展も開催されている(2022年10月25日〜30日)。
関連レビュー
藤原更「Melting Petals」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年08月01日号)
2022/11/04(金)(飯沢耕太郎)
王露『Frozen are the Wind of Time』

発行所:ふげん社
発行日:2022/10/22
王露(Wang Lu)は1989年、中国山西省出身の写真家。武蔵野美術大学、東京藝術大学で写真を学び、いくつかの賞を受賞している。本作は、2021年にふげん社で開催された同名の個展に出品されたものだが、その時点から写真の数を大幅に増やし、構成も大きく変えて面目を一新し、ハードカバーの写真集として刊行した。同時期に、キヤノンオープンギャラリーで個展も開催している(2022年10月29日~12月1日)。
写真作品の重要なテーマになっているのは、王露自身の父親である。父親は彼女が12歳の時、事故によって脳に損傷を負い、社会生活が難しくなった。記憶が曖昧になり、精神的な障害もある。写真集は事故以前の、若く、幸せそうな父と母の写真の複写から始まり、帰省のたびに二人を撮影した写真が続く。父親が、撮影を拒否するように手で顔を隠す写真が繰り返し出てくるが、不安と諦念を抱え込んだ母親の表情とともに強く印象に残る。撮り続けなら、彼らの生、自分との関係のあり方について、王が自問自答している様が切々と伝わってくる。とはいえ、ネガティブな印象はあまりなく、見つめ続けることで認識が深まり、写真家としての自覚に繋がってくることがよくわかる構成になっていた。
家族の写真に加えて、もう一つ大事なのは、生まれ故郷で、現在も父母が暮らす山西省太原市の環境の変化が丁寧に描写されていることだ。ほかの中国の大都市と同様に、太原市もここ10年余りで都市化が急速に進行し、大きく変貌していった。その移りゆきと、病を抱え込んだ家族の姿とが対比されることで、本作は単純な「私写真」の枠に収まることなく、より大きなスパンを備えた社会的ドキュメンタリーとして成立している。今後の彼女の仕事への期待が高まる作品集だった。
2022/11/04(金)(飯沢耕太郎)
守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』

出版:守屋友樹
発行日:2022/03
アーティストである「守屋友樹」をTwitterで検索するとたくさんの作品写真がヒットする。それらの大部分は、だれかの作品の記録で、その撮影者として守屋の名前がクレジットされているのだ。守屋は京都を中心に関東圏も含め10年近く作品写真を撮影してきた。そして、守屋は自身の作品も同様に記録撮影を行なってきた。
写真を中心としたインスタレーションを展開してきた守屋の特異性は、自身の2015年の個展「gone the mountain / turn up the stone:消えた山、現れた石」(Gallery PARC)以降、自身の展覧会が終わるとほぼ同時に毎回、インスタレーションビューのゼロックスコピーのZINEを制作してきたということにあるだろう。シリーズ名「現れた本」。2022年には、展覧会「すべとしるべ 2021 #02『蛇が歩く音 / walk with serpent:守屋友樹』」のバージョンがつくられた。
 守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)
守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)
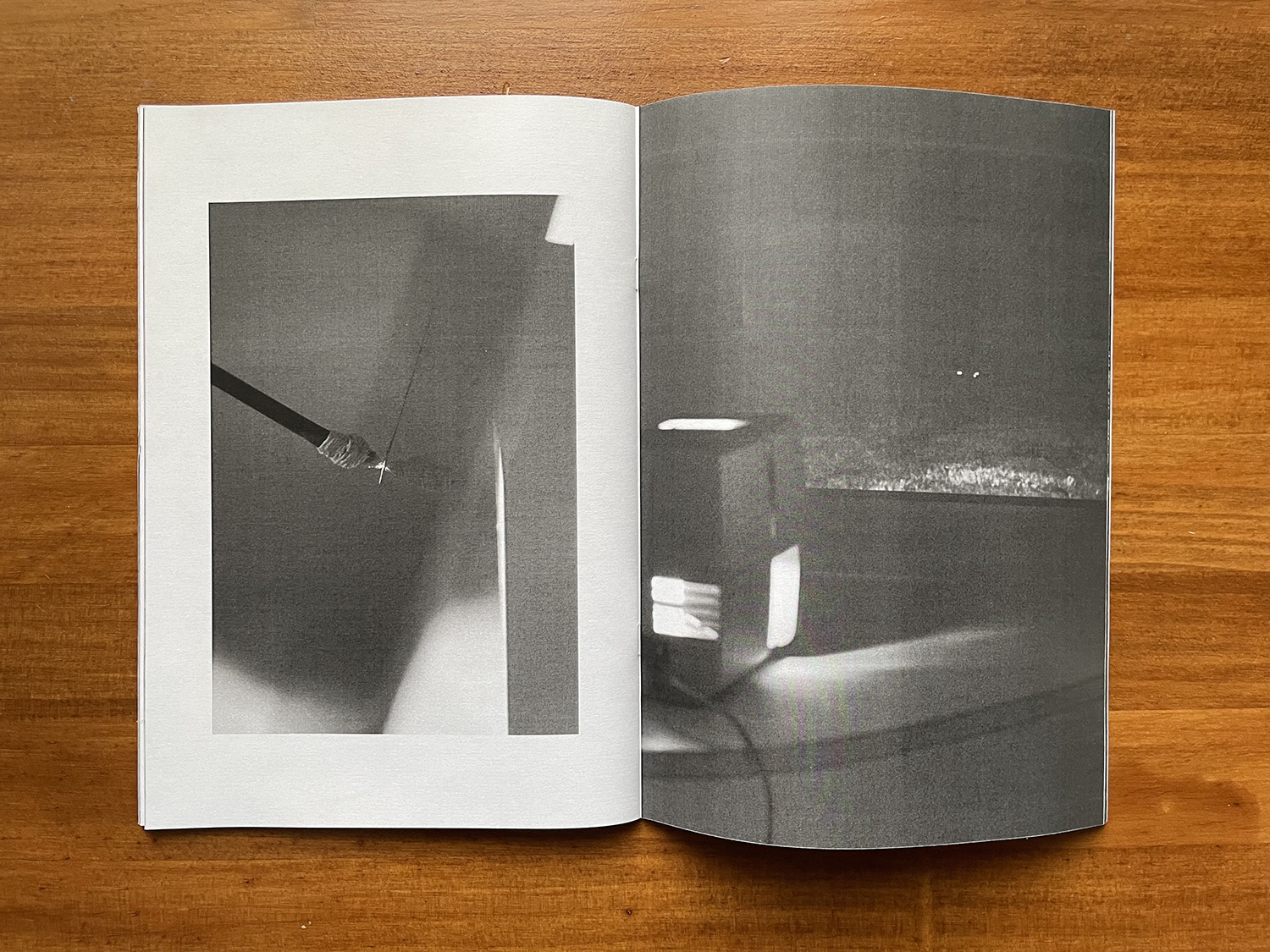 守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)
守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)
 守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)
守屋友樹『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』(現れた本/2022)
山に登ると、視界から山は消え、石が現われる。守屋はつねに境界を指さすことができるようになるものとして写真を示す。わたしは、ベンヤミンが山の稜線や木漏れ日を引き合いに出し写真を論じた理由がわかったような気がした。指示詞を可能にするものとしての写真。「かつてあった」でもなく、「これ」について話し合うことができるようにする力を持つもの。
展覧会に行くと、作品が現われる。ふりかえったらもうなくて。でも、守屋の場合は本が現われる。会場だった場所に数冊だけ預けてあって、それに気付くことができた人やたまたま知った人は、本を手に入れることができる。
2014年の展覧会を見て、守屋から「現れた本」の構想を聞き、そこでわたしは守屋に美術家のアーティ・ヴィアカントが展覧会の記録写真を作品とは別の「イメージ・オブジェクト」として考え、流通させている話を伝えた。ヴィアカントは展覧会を観に来られる人以外に向けた作品として展覧会写真を制作しているわけであり、オブジェクトの正面性から逸脱したイメージオブジェクトを制作することはない。一方で守屋が行なっているのは、インスタレーションにおける複数的な正面を示すことであり、(会場で受け取る、会場で「現れた本」が欲しいと申し出るといった手順が必須であるため)会場がどのようなものであるかという前提を理解した者だけに明かされる、隠しイベントの開示、ボーナストラックとでも言えるだろう。
ヴィアカントが写真の複数性、すなわち、可変的であらゆる媒体に載ることができる、という性質に則り「イメージオブジェクト」を語るなら、守屋は写真の指示性、すなわち、前提とする知識を揃えたうえで初めて「これ」「それ」「あれ」を可能にする、発話的なものとしての写真に向き合う。
 「すべ と しるべ 2021『蛇が歩く音:守屋友樹』」会場写真(オーエヤマ・アートサイト、2021年10月30日〜11月8日)[撮影:守屋友樹]
「すべ と しるべ 2021『蛇が歩く音:守屋友樹』」会場写真(オーエヤマ・アートサイト、2021年10月30日〜11月8日)[撮影:守屋友樹]
 「すべ と しるべ 2021『蛇が歩く音:守屋友樹』」会場写真(オーエヤマ・アートサイト、2021年10月30日〜11月8日)[撮影:守屋友樹]
「すべ と しるべ 2021『蛇が歩く音:守屋友樹』」会場写真(オーエヤマ・アートサイト、2021年10月30日〜11月8日)[撮影:守屋友樹]
 「すべ と しるべ(再)2021-2022 #01『蛇が歩く音 / only the voice remained:守屋友樹』」会場写真(ギャラリー・パルク、2022年6月11日〜7月3日)[撮影:守屋友樹]
「すべ と しるべ(再)2021-2022 #01『蛇が歩く音 / only the voice remained:守屋友樹』」会場写真(ギャラリー・パルク、2022年6月11日〜7月3日)[撮影:守屋友樹]
守屋の作品には、イノシシやヘビやクマといった動物と人間の遭遇がモチーフとして現われる。自然と文化の混交、郊外と山際という曖昧な境目を作品たちは「これ」と示す(ホンマタカシ以降の郊外を考えるうえで重要なアーティストとしても、守屋を位置づけるべきだろう)。しかし、いずれの動物も作中にずばり登場することはない。その被写体の不在性は観者をつねに戸惑わせてきた。写真と対面しても、何が起きているのかがわからないというように。それは、何かが起こる直前の、未然の写真として造形されることもあれば★1、気配の造形であることもあった★2。守屋の写真は、写真を見るものの背後をつくる。それは決して見ることができない。でもそれで終わらせないのが守屋である。見ることができないこともまた指示詞にする。それが「現れた本」だ。このような意味において、守屋の作品造形は特異的である。
★1──個展「守屋友樹 “still untitled & a women S”」(KYOTO ART HOSTEL kumagusuku、2017年4月23日〜5月28日)
★2──展覧会「影を刺す光─三嶽伊紗+守屋友樹」(京都芸術センター、2020年10月10日〜11月29日)
『スポンティニアスリプロダクション #5「蛇が歩く音|walk with serpent」』詳細:https://www.parcstore.com/esp/shop?pid=MY1-03-004
2022/11/01(火)(きりとりめでる)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)