artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
熊谷聖司「RE FORM」
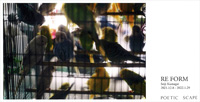
会期:2021/12/08~2022/01/29
POETIC SCAPE[東京都]
熊谷聖司は2013年に『MY HOUSE』(リブロアルテ)という写真集を刊行している。身の回りの光景を、淡々と肩の力を抜いて、だが不思議な哀切さをともなって見えてくる角度から切りとったスナップショットを集めたもので、現在の彼の写真のスタイルの原型となる写真集だった。それから8年余りを経て、まったく同じ判型、レイアウトの『RE FORM』(livers lieu lieu 2021)を刊行した。今回のPOETIC SCAPEでの個展は、そのお披露目の展示である。
写真集のタイトルの付け方に、熊谷の遊び心があらわれている。「本」を「家」と見立てて、「壁の色を変えたり、キッチンに窓を増やしたりするように作品を差し替え」ていったのだという。『RE FORM』というのは、まさにその行為にふさわしいタイトルといえるのではないだろうか。似たような「家」には違いないのだが、その味わいは微妙に違う。写真のテーマ、色合い、画面構成などに配慮して、輻輳するストーリーに沿って写真を並べていく手つきが精妙になった。所々に置かれているピラミッド、コーン、富士山、傘、マスクなど、同じようなフォルムの写真の繰り返しによるリズムの作り方にも、写真家としての奥行きの深さがあらわれている。写真集の掲載作からピックアップした展示も、熊谷の写真の世界に観客を引き込んでいくように、注意深く構成されていた。
なお、今回の熊谷の個展が、POETIC SCAPEの開設10周年にあたる展覧会になるのだという。ギャラリーがある東京・中目黒の住宅街は、あまり行きやすい場所ではないが、熊谷や野村浩、尾仲浩二、渡部敏哉、尾黒久美など、玄人好みのクオリティの高い作品を、コンスタントに展示し続けてきた。写真ギャラリーの運営という点では、厳しい状況が続くが、今後もいい展覧会を開催し続けていってほしい。
2021/12/08(水)(飯沢耕太郎)
大道兄弟『My name is my name is…』

発行所:桜の花本舗
発行日:2021/09/16
毎月、たくさんの写真集が送られてくる。だが、ほとんどが自費出版のそれらの写真集のなかで、何か書いてみたいと思わせるものはそれほど多くない。大道兄弟という未知の二人組が、自分たちの写真をまとめた『My name is my name is…』も、最初はなんとなく見過ごしていたのだが、そのうちじわじわと視界に入ってきて、気になる一冊として浮上していた。
どうやら二人は1994年山梨県生まれ、大阪府堺市育ちの双子の兄弟(YukiとKoki)のようだ。赤々舎などでアルバイトをしながら、写真を撮り続け、Zineを既に40冊余り出している。『My name is my name is…』が最初の本格的な写真集である。モノクロ、カラーが入り混じり、被写体との距離感もバラバラだが、どこか共通の質感を感じさせる写真が並ぶ。特に、人の写真にその眼差しの質がよく表われていて、真っ直ぐに向き合いつつも、暴力的にねじ伏せようとはしていない。共感をベースにしながらも、なかなかそれを伝えることができないもどかしさと、コミュニケーションへの切実な渇望が写真に表われている。と思うと、そっけない、だが体温を感じさせるモノの写真もあり、被写体をあまり厳密に定めてはいないようだ。まだ海のものとも山のものともつかないが、写真を通じて世界と深くかかわっていこうとする、ポジティブな意欲が伝わってくる写真が多かった。
どれがYukiの写真でどれがKokiの写真かは、あえて明確にしていない。「兄弟」というユニットに徹することで、個人作業を超えた共同性が芽生えつつあるのが逆に興味深い。可能性を感じさせる一冊だった。
2021/12/07(火)(飯沢耕太郎)
藤岡亜弥『アヤ子江古田気分/my life as a dog』
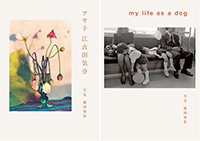
発行所:私家版(発売=ふげん社ほか)
発行日:2021/09/16
藤岡亜弥は1990年から94年にかけて、日本大学芸術学部写真学科の学生として、東京・江古田に住んでいた。今回、彼女が刊行した2冊組の小写真集は、主にその時代に撮影した写真をまとめたものだ。『アヤ子江古田気分』には、「木造の古い一軒家の2階の八畳ひと間」に大学卒業後も含めて8年間住んでいた頃のスナップ写真が、大家の「82歳のおばあさん」との暮らしの記憶を綴った文章とともに収められている。『my life as a dog』は、「大学生のときに夢中になって撮った」という子供たちの写真を集めたものだ。
どちらも彼女の後年の作品、『私は眠らない』(赤々舎、2009)や第43回木村伊兵衛写真賞を受賞した『川はゆく』(赤々舎、2017)と比べれば、「若書き」といえるだろう。とはいえ、奇妙に間を外した写真が並ぶ『アヤ子江古田気分』や、牛腸茂雄の仕事を思わせるところがある『my life as a dog』のページを繰っていると、混沌とした視覚世界が少しずつくっきりと像を結び、まぎれもなく一人の写真家の世界として形をとっていくプロセスが、ありありと浮かび上がってくるように感じる。「若書き」とはいえ、そこにはまぎれもなく藤岡亜弥の写真としかいいようのない「気分」が漂っているのだ。
木村伊兵衛写真賞受賞後、広島県東広島市に移住した藤岡は、いま、次のステップに向けてのもがきの時期を過ごしているようだ。写真学科の学生時代をふりかえることも、その脱皮のプロセスの一環といえるのだろう。だがそれとは別に、2冊の写真集をそのままストレートに楽しむこともできる。笑いと悲哀とが同居し、どこか死の匂いが漂う写真たちが、じわじわと心に食い込んでくる。
2021/12/06(月)(飯沢耕太郎)
土田ヒロミ「ウロボロスのゆくえ」

会期:2021/11/29~2022/01/17
キヤノンギャラリーS[東京都]
土田ヒロミは1939年の生まれだから、今年82歳になるはずだ。普通ならリタイアしてもおかしくない年代であるにもかかわらず、その創作意欲はまったく衰えていない。今回キヤノンギャラリーSで開催した「ウロボロスのゆくえ」展でも、新たな領域にチャレンジする姿勢が全面的に表われていた。
とはいえ、展示されていたのはバブル経済の崩壊の時期だった1990年代前半に撮影された「産業考古学」(1991-2004)と「Fake Scape(消費の風景)」(1995-2000)の2シリーズである。「産業考古学」は「日本の高度経済成長を支えてきた基幹産業の生産現場」を記録するプロジェクトで、工場地帯の光景をその物質性を強調して撮影している。一方「Fake Scape(消費の風景)」では、「大都市郊外の国道線路沿線(主に国道16号)に現われていた消費者が誘導する異様な意匠の店舗の風景」にカメラを向けた。興味深いのは、この2シリーズを合体させることで、1990年代における生産と消費の現場のうごめきが、あたかも合わせ鏡のように出現してくることである。それこそが、土田が今回の写真展のタイトルに「ウロボロス」(自分の尻尾をくわえた蛇、あるいは竜の表象)という名辞を付した理由だろう。同時にその「異様な」眺めが、2020年代の現代の都市風景のプロトタイプであることが、鮮やかに浮かび上がってきていた。
本展では、過去作にあらためてスポットを当てつつ、それらを再解釈、再構築しようとする土田の営みが、実り多い展示として実現していた。彼には、まだ現在も進行中のプロジェクトがいくつもある。現役の写真作家として、さらなる活動の広がりを期待できそうだ。
2021/12/06(月)(飯沢耕太郎)
村越としや「息を止めると言葉はとけるように消えていく」

会期:2021/11/20~2021/12/18
amana TIGP[東京都]
会場に入ると7点の作品が展示されていた。イメージサイズは60×190cm。マットの余白とフレームがあるのでさらに大きく感じる。写っているのは横長の海の景色で、水平線がちょうど画面の中央に来ている。2012年から21年にかけて、福島第一原子力発電所近くの、ほぼ同一の場所から、6×17cmサイズのパノラマカメラで撮影されたものだ。雨、あるいは霧がかかっているのだろう、湿り気を帯びたグレートーンが、画面全体を覆いつくしているものが多い。
この「息を止めると言葉はとけるように消えていく」と題されたシリーズを見て、杉本博司の作品を連想する人は多いだろう。むろん、発想もプロセスもかなり違っているのだが、見かけ上は杉本の「Seascapes」と同工異曲に思える。人によっては、村越がずっと撮り続けてきた、実感のこもった福島の風景とは違った方向に進みつつあるのではないかと感じるかもしれない。彼もそのことを充分に承知の上で、あえてこの隙のない画面構成と、モノクローム・プリントの極致というべき表現スタイルを選択しているのではないかと思う。個人的には、その方向転換をポジティブに捉えたい。村越のなかにもともと強くあったミニマルな美学的アプローチを、むしろ徹底して打ち出そうとしているように思えるからだ。不完全燃焼に終わるよりは、より先に進んだ方がいいのではないだろうか。DMの小さな画像ではよくわからなかった、彼の全身感覚的な被写体の受け止め方が、大判プリントの前に立つことでしっかりと伝わってきた。
関連レビュー
村越としや「沈黙の中身はすべて言葉だった」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年03月15日号)
2021/11/30(火)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)