artscapeレビュー
2021年11月01日号のレビュー/プレビュー
元田敬三「御意見無用」

会期:2021/08/26~2021/10/24
入江泰吉記念奈良市写真美術館[奈良県]
8月に、ここ3年余りの「写真日記」を集成した新作写真集『渚橋からグッドモーニング』(ふげん社)を出したばかりの元田敬三が、入江泰吉記念奈良市写真美術館で意欲的な写真展を開催した。展示の最初のパートに、1996年に『大阪新聞』に連載した「ON THE STREET 出会い」と題する写真入りのコラムを拡大して掲げている。大阪の路上で出会った人物たちに声をかけて撮影した写真とインタビューをまとめたものだが、被写体へのアプローチの仕方、写真そのもののたたずまいが、会場に並ぶ新作(2016〜21年撮影)とほとんど変わっていないことに驚きと嬉しさを感じた。初心を貫き通すというのはそれほど簡単ではないはずだが、元田はそれを見事にやり切っている。
会場構成にも、元田らしいスタイルが貫かれていた。33点の黒白写真(1点のみカラー)をロール紙に大きく引き伸ばし、フレーム入りの1点を除いて壁に直貼りしている。「ON THE STREET, OSAKA」と同様に、写真撮影の前後の状況を細やかに記したテキストを添えていることにも、彼にとっても原点回帰といえる展示だったことが表われている。ロックンローラー、チョッパーのバイクライダー、全身刺青の男、ツッパリの中学生など、街のなかでその存在を全身で主張しているような人物たちに声をかけて撮影しているのだが、その選択の背景に、彼なりの美学と哲学があることが写真からしっかりと伝わってきた。『渚橋からグッドモーニング』は、いわば日常の厚みへの着目というべき写真集だった。その対極というべき今回の展示からは、元田の作品世界の広がりを感じとることができた。写真家として、ひとまわりスケールの大きな世界に出て行きつつあるのではないだろうか。
2021/09/23(木)(飯沢耕太郎)
織作峰子写真展─光韻─
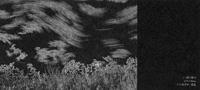
会期:2021/09/18~2021/09/28
和光ホール[東京都]
織作峰子の写真展は和光ホールでは3年ぶり、2回目になる。前回の「織作峰子展─恒久と遷移の美を求めて─」(和光ホール、2018年7月)の時から、デジタルのレーザープリンタと伝統的な箔押しの技法を融合させた「ピクトリアリズム」的な写真作品を発表し始めたのだが、本展ではその手法がより洗練され、内容的にも深みを持つものになってきた。本金箔を手押しした「樹齢」では、画像を反転させたシンメトリカルな画面構成を試み、アルミ箔を大胆かつ豪奢に用いた「夜を流れる桜花の始星」「二胡に舞う」などでは、琳派を思わせる装飾的な表現を追求した。集中して撮影した富士山の連作の集大成というべき「涛。波と富士山」では、四曲の屏風仕立ての大作に挑戦している。ほかに、写真を透明アクリルでサンドイッチする形式の作品も、多数出品されていた。
織作のように、日本の伝統的、工芸的な美意識を写真に取り入れようとしている写真作家が、まったくいないわけではない。だが、それらの多くは中途半端に終わっていることが多く、手法のみが目につくものになりがちだ。技術の完璧さと、内容的な必然性を両立させるのは、かなりむずかしいのではないだろうか。織作の仕事は、デジタル時代における写真と絵画との融合、高度な表現性とポピュラリティの両立という点において、ひとつの到達点となりつつある。次は、伝統美を踏まえつつ、それに依りかかることなく、さらに先に進めていくことが求められている。
2021/09/26(火)(飯沢耕太郎)
奈良原一高「宇宙への郷愁」

会期:2021/09/13~2021/11/20
写大ギャラリー[東京都]
奈良原一高をはじめ、東松照明、川田喜久治、細江英公ら、VIVOの写真家たちには、「宇宙的感覚」とでもいうべきものが共通している。彼らの写真には、むろん現実世界の断片が写り込んでいるのだが、それとともに地上から遥かに離れた遠い場所を希求し、作品に取り込むような志向が見られるのだ。
それはなぜなのかと考えると、あの敗戦の日の、抜けるような青空の体験に行きつく。VIVOの写真家たちは、感受性が最も張り詰めた少年期にその日を迎え、共通体験として記憶に刻みつけた。現実世界のリアリティはその時にいったん失われ、宇宙的な「遠さ」の感覚に置き換えられる。それはVIVOの写真家たちだけではなく、たとえば詩人の谷川俊太郎、作家の大江健三郎、建築家の磯崎新など「戦後世代」の作り手に共通する志向と言ってもよい。
VIVOのメンバーのなかで、「宇宙的感覚」を作品のなかに最も広範囲に、長期にわたって取り入れていったのは、おそらく奈良原一高だろう。今回の写大ギャラリーの個展には、デビュー作である「無国籍地」(1954)から、最後の仕事になった「Double Vision」(2000-2002)まで、代表作50点が出品されていた。それらのほとんどすべてに、遥かに遠い場所への憧れが脈打っているように感じる。
その傾向は、彼が写真家として高く評価され、生涯の締めくくりに向かおうとしていた1990年代以降に、より強まっているように見えるのが興味深い。胸椎腫瘍で入院・手術後に制作された「インナー・フラワー(単純X線像)」(1991)、表参道、神宮前などの光景を近未来的にコラージュした「Vertical Horizon Tokyo(1991-1995)など、地上から浮遊するような感覚がより強まってきている。それらは「消滅した時間」(1970-1974)などのシリーズに、すでにくっきりと表われてきていたのだが、1990年代以降には、より切実なテーマとして意識されるようになったのではないだろうか。
2021/09/29(水)(飯沢耕太郎)
ジャム・セッション 石橋財団コレクション×森村泰昌 M式「海の幸」─森村泰昌 ワタシガタリの神話

会期:2021/10/02~2022/01/10
アーティゾン美術館[東京都]
リニューアル・オープンしたアーティゾン美術館(旧・ブリジストン美術館)での、最初の写真作品を中心とした展覧会は、森村泰昌の大規模展だった。同美術館が所蔵する青木繁の「海の幸」(1904)を起点として、「M式」のジャム・セッションを繰り広げる本展は、まさに森村の面目躍如といえる好企画である。
森村はこのところ、日本の近代美術と自分自身のアーティストとしての軌跡を重ね合わせるような作品を発表してきた。本展も例外ではなく、彼の高校時代の美術部の海辺の合宿の記憶を辿りながら、青木の「海の幸」に描かれた「時間」のなかに分け入っていくという構成をとっている。「『私』を見つめる」「『海の幸』鑑賞」「『海の幸』研究」「M式『海の幸』変奏曲」「ワタシガタリの神話」の5部構成による展示は、緊密に練り上げられており、エンターテインメントとしての要素を取り込みつつも、日本人と日本近代美術史への鋭い批判も含んでいて、見応え充分だった。
注目すべきことは、コロナ禍という事情もあったようだが、いつもは「チーム」を組んで共同制作する森村が、衣装、メーキャップ、撮影、構成までをほぼひとりで行なったということである。だがそのことによって、画面作りの強度が高まり、いくつかのテーマに集中していく制作のプロセスが、より緊張感を孕んで浮かび上がってきた。「海の幸」を元にした10点の連作のスケッチ、資料、記録映像(監視カメラを使用)などをふんだんに提示し、いわば「舞台裏」をも同時に公開することで、観客を森村の作品世界に巻き込んでいくという意図が見事に成功していた。
それにしても、最後のパートで上映されていた、森村が青木繁本人に扮して、大阪弁で語りかける映像作品《ワタシガタリの神話》の完成度の高さは、凄みさえ感じさせる。国立国際美術館で2016年に開催された「森村泰昌:自画像の美術史 『私』と『わたし』が出会うとき」で上映された映像作品《「私」と「わたし」が出会うとき─自画像のシンポシオン─》を見た時にも驚嘆したのだが、森村の脚色、演出、演技のレベルは、とんでもない高さにまで上り詰めようとしている。
関連レビュー
森村泰昌「自画像の美術史 「私」と「わたし」が出会うとき」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年06月15日号)
2021/10/03(日)(飯沢耕太郎)
菅野由美子展

会期:2021/10/04~2021/10/30
ギャルリー東京ユマニテ[東京都]
菅野は15年ほど前から器を並べた静物画を描き続けているが、今回は少し趣を異にする。見た目はこれまでとほとんど変わらないが、違うのは器のヴァリエーションが増えたこと。これまでは自分の収集したお気に入りの器を並べて描いてきたが、今回は友人たちが愛用する器を描いたそうだ。本人いわく、「会いたい人にもなかなか会えない日々が続いたので、友人たちの器を描いてみたくなった」。といっても実物を見て描くのではなく、メールで愛用のカップの画像を送ってもらい、画面上に構成したのだという。
たとえば、案内状にも使われている《MUG_7》。複雑に入り組んだ棚が正方形の画面を大きく十文字に分けている。どこかエッシャーの位相空間を思わせるが、それは重要ではない。その棚の中央2列に計14個のマグカップを置き、右上と左下にティーポットを配する構図だ。これらのマグカップは友人たちから送られた画像を元にしたもの(ぼくの愛用していたマグカップもちゃっかり鎮座している)。実物ではなく画像を見て描くのは安易な気もするが、実はとても難しい。なぜなら、送られてくる画像の大半は斜め上から撮ったものだが、その角度は人それぞれ異なるし、光の方向も右から左から正面からとバラバラに違いない。それらを修正しつつひとつの画面に破綻なくまとめ上げなければならないからだ。
めんどくさそうな作業だし、そもそも他人の選んだ器を描くのだから気が進まないと思いきや、意外にも菅野は楽しかったという。なぜならこれらのカップを描いているとき、それぞれの所有者のことを思い、心のなかで会話したからだそうだ。それはおそらくカップだから可能だったのではないか。言葉を発するのも、カップから飲むのも同じ人の口だから。コロナ禍で人に会えないから友人たちのカップを描いたら、会話が成り立ってしまったという小さな奇跡。静物画が、ただの静物画ではなくなるかもしれない。
2021/10/04(月)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)