artscapeレビュー
2022年07月01日号のレビュー/プレビュー
二人(宇田川直寛、横田大輔)「石が降る」
会期:2022/05/14~2022/06/12
TALION GALLERY[東京都]
本展は、ライトノベルやアニメに見られるフォーマットを踏まえて、「八王子隕石」「錬金術」「新東京ダイヤモンドボウル」という3章立ての物語に基づいて構成される。
(プレスリリースより抜粋)
え? そうだった?
2019年に結成された二人(宇田川直寛、横田大輔)による展覧会。多くの平面や立体作品は、バライタ印画紙で作成されていて、会場の隅には使い古された写真乳剤とシリコンオイルがガラス瓶に入って並ぶ。「フィルム写真の現像についての解釈のバリエーションの模索?」と思いながらも会場を見回す。窯で火にかけられたテラコッタの映像とその出来上がったもの。印画紙に焼き付けられた平面作品の名は「壺」「石」「人」。印画紙を折ってつくられた人形たち。人形は音に反応してカタカタ動く。「人」「不老長寿」を生成せんとする錬金術と、人の「似せ絵」を生成する写真術の目的と技術が重なる可能性が軽やかに示唆されている。動く人形たちは生きているか死んでいるか、魂があるかないか。蘇生や延命というより、新たなものの生成としての写真と錬金術★1。
 二人(宇田川直寛、横田大輔)《パーティータイム(石が降る)》(2022)テラコッタ、接着剤、石膏、映像
二人(宇田川直寛、横田大輔)《パーティータイム(石が降る)》(2022)テラコッタ、接着剤、石膏、映像
[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY
 横田大輔《Untitled(写真)》(2022)ガラス瓶、写真乳剤、シリコンオイル
横田大輔《Untitled(写真)》(2022)ガラス瓶、写真乳剤、シリコンオイル
[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY
 左から
左から
二人(宇田川直寛、横田大輔)《壺(石が降る)》(2022)バライタ印画紙、木パネル 160×92cm
二人(宇田川直寛、横田大輔)《石(石が降る)》(2022)バライタ印画紙、木パネル 160×92cm
二人(宇田川直寛、横田大輔)《人(石が降る)》(2022)バライタ印画紙、木パネル 160×92cm
[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY
会場で入手できたテキスト「石が降る」を読んでみる。
我々は〔…〕物語が始まるのを辛抱強く待っていた。ラノベやアニメの世界では物語は向こうからやってきて主人公を巻き込みながら事件を繰り広げる〔…〕いい写真が撮れない〔…〕我々は主人公ではなく〔…〕中年男性〔…〕八王子市役所のホームページで200年前に落ちた隕石をまだ探している〔…〕「我々は隕石を探しているのです」と人に話しかけ始めた。
「いい写真が撮れない」という苦悩が、ロードムービーの導入のように書かれていた。いい写真。テキストでそれは「事件があるかないか」という暫定的な基準が仄めかされている。中年男性には事件がないという己の幸運さと、それを悲しむ後ろめたさが、突拍子もない問いで動き出す。「我々は隕石を探しているのです」。
立体や平面を一式見てからやっと注意が行ったのだが、会場には声が流れている。二人の写真についての語りが、違う人物によって棒読みされた声。隕石の行方から飛躍して、どこかで聞いたことのあるような怪奇現象について話す人の声。物語が動き出したかと思えば、収集した出来事は類型的なものだった。これも「事件」にはたどり着かない。
ライトノベルの筋書きだったら、ある日、主人公の住む場所に隕石が落ちて、自分だけ助かり、愛する人々を失い、錬金術に没頭して、すべてを元通りにしようとするが、それは叶わず。しかし、驚くべきことに隕石は天災ではなく、実は存在した黒幕を打倒して、新しい場所で喪失を回復する物語になるかもしれない。でも、二人は隕石が落ちてこなくても、写真術=錬金術に平素から取り組んできた。
 二人 (宇田川直寛、横田大輔)《ダイオウイカ》(2022)バライタ印画紙、箱(PET板、ボンド)12×34×77cm
二人 (宇田川直寛、横田大輔)《ダイオウイカ》(2022)バライタ印画紙、箱(PET板、ボンド)12×34×77cm
[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY
過剰な高温現象〔…〕毎日そんな作業を続けているとしまいに肌まで爛れてめくれてきた〔…〕まるでフィルムみたいで〔…〕逆に〔…〕フィルムは自分の身体なのだ〔…〕良い錬金術師は良い性格でなくてはならない。心的内容は物質に投影されるからだ。
爛れた自分の手にフィルムと連続する物質性を見出すと同時に、フィルム現像の環境負荷に思いを馳せた人物は、錬金術師であったら、手が石になるなんてことは「悪い」錬金術師の証明になってしまうと考える。でも、それはどうなのと写真家はつぶやく。「それはそれは失礼な話じゃないの」。こうして錬金術から写真家は袂を分かつ。写真を拡張するため過去に無理に遡及する必要なんかないと。二人が次に向かうのは、ラッセンのポスターが貼られた喫茶店のある、昔ながらのボーリング場、「新東京ダイヤモンドボウル」。
それで物語は始まる。という事で、ここがその場所に違いないと思ったのだ。
このようにして、何にも声をかけず、また二人は待つことにしたようだ。本展はかくして、写真になる瞬間を待つこと自体が造形された、主人公じゃない二人の何も起こらないロードムービーに終着した。
さて、ここで終わってもいいのだが、「声かけと写真」を考えるうえで、例えば、2016年の開催から批判を受けてきた「声かけ写真展」という公募グループ展がある。その応募規約には「こども (学齢期以下の人物) に声をかけて、承諾を得て撮影した、未発表の写真作品。被写体に声をかけ、本人の同意を得て撮影したものにかぎります。親権は同意を意味しません」と書かれ、子どもと撮影者の関係が友達のようにフラットであるなかでの許諾に重きを置くがゆえに、保護者への許諾を主催者は一蹴し続けている。
しかし、ウェブサイトや投稿写真(Twitterのハッシュタグで辿ることができる)の言葉や写真から、子どもというのが「少女」に限定され、撮影者は「おじさん」だと自己規定をし、「おじさん」が未就学者の無知に付け込むという状態自体への快楽、あるいは直接的な性的消費が目的なのではないかと強く批判されてきた。2022年も「声かけ写真展」は作品を募集しているが、①声かけ写真と②リミナルスペースの2部門になっている★2。
「リミナルスペース」とは、英語圏中心の画像投稿サイト「4chan」を中心に起こった写真文化のひとつだ。普段は人で賑わうショッピングモールや駅や街といった場所に誰も人がいないことで引き起こされるサスペンス、異化効果が起きた風景への愛好、またはそれを撮影した写真のことであり、ひいてはゲームキャラクターのいないワールドのキャプチャーも包含する、風景写真のジャンルでもある。近年はCOVID-19で静まり返る都市が撮影された際、多くのものが「リミナルスペース」「#liminalspace」としてSNS上でタグ付けされた。
その一方、「声かけ展」で銘打たれた「リミナルスペース」は、より狭く再定義されている。「声かけ写真がしあわせに行なわれていた(はずと心象に刻まれる)空間」。その写真に人はいないが、幼い子どもの痕跡を辿ろうとするがゆえに、ハッシュタグで紐づけられた写真の多くは、広域な風景写真ではなく、身長が100cm程度の子どもの移動範囲をおさめる、カメラは地平に対して見下ろす角度のきつい、奥行きの浅い写真になっている。多くの「リミナルスペース」は風景の異化効果を増大させようと、より広い領域の人間の不在を求めるため、構図上の消失点はどこまでも深くとるのがセオリーであるから、「リミナルスペース」のSNSタグの海のなかで数点だけアップロードされている、「#声かけ写真展」の「#リミナルスペース」はそういう異質性がある。
本展の写真も人は不在である。だが、リミナルスペース写真と違って、いつも人が閑散としてそうな、うらびれた場所が被写体であったり、走る車の速度のままのブレた写真であるから、撮影されているのはむしろ「移動」で、それを行なっている「二人」の肖像であると言えるだろう。水が入ったグラスも二人のものだろうし、二人の痕跡しかない。地面に対して垂直に視線が向けられた写真も、ノーファインダーで撮影されたような二人の移動する足である。風景写真であるが、それよりも二人の存在へ折り返される写真。「声かけ展」の風景写真はもちろん、子どもの不在を通して子どもの姿を求めているのだが、ゆえに存在を求める撮影者だけが撮影の場に存在する。鑑賞者は痕跡に何も求めるものがないので、撮影者の存在をより強烈に感じる。二つのリミナルスペースも、二人の写真のいずれの風景写真も、そこにいるのは撮影者だけだ。
二人は事件が起きるのを待っている。しかし、二人は、事件は起きちゃいけないし、事件を撮っていいと言えるのかと思いつつ、待つことを考えるのだ。本展はそれを「待つふり」と言ったりはせず、事件を待ち続ける写真家の自写像の展覧会と言えるだろう。
 横田大輔《Untitled (石が降る) 》(2022)ラムダプリント 17.4×25cm
横田大輔《Untitled (石が降る) 》(2022)ラムダプリント 17.4×25cm
宇田川直寛《Untitled (石が降る) 》(2022)ラムダプリント 17.4×26.1cm
左から1、3、7、9、10番目の写真が横田大輔作品、それ以外の5点が宇田川直寛作品
[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY
 二人 (宇田川直寛、横田大輔)《相模原、若葉 (二人のショー) 》(2020)映像 37分40秒(相模原)、37分58秒(若葉)
二人 (宇田川直寛、横田大輔)《相模原、若葉 (二人のショー) 》(2020)映像 37分40秒(相模原)、37分58秒(若葉)
[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY
★1──本展では錬金術師と写真家が対比的だと言えるが、例えば、打林俊は不老不死や物質の変化を求める錬金術師と写真を発明するに至る科学者ニエプスの違いを、硝酸銀と塩が日光で黒化する事象から、画像の定着に向かったか否かにひとつの分水嶺があるのではないかと提起している(打林俊「錬金術と空想科学からみる写真」/『写真の物語──イメージ・メイキングの400年史』森話社、2019、pp.201-206)。
★2──「声かけ写真展」のウェブサイトは以下の通り。https://www.koekakephoto.net/(2022.6.23閲覧)
2022/06/05(日)(きりとりめでる)
景聴園ラジオ 第1回『何故絵を描いているのか?』

会期:2022/06/05〜
チャンチャチャチャーンチャチャ……穏やかなギターの音で始まる「景聴園ラジオ」は「日本画」の勉強会と鑑賞の手引きを行なうポッドキャストだ。
「景聴園」は2012年に発足した日本画のグループ。メンバーは、作家である上坂秀明、合田徹郎、服部しほり、松平莉奈、三橋卓、企画の乃村拓郎、そしてアーカイブとテキストの古田理子。1980年代から90年代生まれの彼らは、京都市立芸術大学での結成当時から、合作を行なうタイプのグループではなく、グループ展を幾度となく開催してきた。かなり雑な言い方で恐縮だが、私から見た「景聴園」は、具象日本画の再考を軸としたグループだ。彼らの企画展に行くと、「日本画」が「物語」を描くとしたら、何を扱うべきか、どう描くべきかが5人ともまったく違うということにいつも驚かされる。でも、私は「日本画」に詳しくないので、そこで思考も眼も立ち止まってしまっていた。そんなときにこのポッドキャスト、渡りに船である。
第1回の冒頭では、「横山大観についての話をしよう」と前振りが来て身構えていたが、初回ということで、まずは「なぜ絵を描いているのか?」という問いからスタートした。「好きだから」という言葉を景聴園はいくつも切り分けていく。どの瞬間によろこびを感じるのか、絵を通して自分の認識が他者にとってどうなのかがわかるよろこび、生きていく手立てとしての絵、絵を描くときの「手癖」をよろこびと捉えるか否か。そこに研究はどう関連するか。
松平が途中で指摘した通り、景聴園の話はすべてが日本画についてのものなのだが、彼らが立ち返るときのエピソードは人間が人間として生きている限りにおいて、誰もが「何か」を「日本画」に代入することが可能という、不思議な体験であった。同時代としての日本画に向き合う彼らだからこそのなせる技だ、と唸ったり笑ったりのポッドキャスト。景聴園の結成10周年特別企画は耳も眼も離せない。
景聴園ラジオ(Anchor):https://anchor.fm/keichoen/
2022/06/05(日)(きりとりめでる)
孤高の高野光正コレクションが語る ただいま やさしき明治

会期:2022/05/21~2022/07/10
府中市美術館[東京都]
つい最近、平塚市美で「リアルのゆくえ」という同じタイトルなのに別内容の展覧会を見たばかり。この「ただいま やさしき明治」も2、3年前に府中市美でやってなかったっけ? と思って調べたら、「おかえり 美しき明治」(2019)という展覧会だった。紛らわしいなあ。でも平塚も府中も以前の展覧会がとてもよかったから、たとえ作品が同じでもまた見にいく気になる。でも逆に同じ展覧会だと思って見に行かない人もいるはず。果たして紛らわしいタイトルは損なのか得なのか。いやそんなことより、この「おかえり」から「ただいま」への変化はなんなんだ? フツーは「ただいま」「おかえり」の順だろう。強いていえば、「ただいま」は作品の側から、「おかえり」はそれを受け止めるわれわれから発せられるあいさつ。だからどっちでもいいといえばどっちでもいいのだが。「美しき」から「やさしき」に変わったのも微妙で、内容を見る限りどっちでもいい。
と、どっちでもいい話をしてる場合ではなく、前回と今回の決定的な違いを述べなければいけない。両展とも水彩画を軸に明治期の珍しい絵画を紹介する点では共通しているが、前回が府中市美をはじめ各地の美術館やプライベート・コレクションからかき集めてきたのに対し、今回は初公開の高野光正コレクションを中心に成り立っていること。高野コレクションは、明治期に訪日した英米の画家と、日本人の画家による水彩画を核とする。英米人の作品は母国に持ち帰られ、日本人の作品は外国人に購入されて海外に流出したもので、高野氏は主に英米の市場でそれらを買い集め、総数700点にも上るという。今回はそのうちの約半数が公開されている。
もう一つ異なっているのは、前回が府中市美独自の企画展だったのに対し、今回は京都からの巡回展を基本に数十点を加えている点だ。だから、前回もっとも驚いた笠木治郎吉の水彩画が今回もたくさん出ているなと思ってカタログを見比べてみたら、大半が異なっていた。笠木の絵は、猟師や花売り娘など明治期の人々を背景や小道具まで丹念に描き出した、ポップでメルヘンチックなイラストにも見紛うような水彩画。きっと外国人に人気があってよく売れたのだろう、似たような作品を繰り返し何点も描いていたのだ。たとえば猟師の絵は前回は3点、今回は5点あるが、重なっているのは府中市美の《帰猟》1点だけで、あとは背景やポーズが異なっている。同じく笠木作品で今回もっともインパクトがあったのは《新聞配達人》で、腰に鈴をつけて新聞の束を抱えた配達人が花咲く道を軽快に走り抜けていく様子を詳細に描いたもの。リアルといえばリアルな描写だが、現実感に乏しく、笠から覗く寄り目には思わず笑ってしまう。
外国人による水彩画も興味深い。幕末に来日し、高橋由一や小林清親に教えたチャールズ・ワーグマンをはじめ、アルフレッド・イースト、ジョン・ヴァーレー・ジュニア、アルフレッド・パーソンズ、ハリー・ハンフリー・ムーアら、想像以上に多くの英米人が来日して作品を残している。彼らに共通しているのは、富士山を別にしていわゆる名所や観光地より、身近な風景や生活風俗を描いていること。自然の風景なら世界中どこも大して代わり映えしないが、生活風俗にこそ彼我の違いが如実に現われるからだ。そして彼らから影響を受けた五姓田義松、五百城文哉、丸山晩霞、吉田博、大下藤次郎らの水彩画を中心とする近代化以前の風景画が並ぶ。
英米人および日本人が描いて海外に流出した水彩画は、おそらくここにある数十倍か数百倍はあるはず。その大半は失われたにしろ、まだまだ発掘される可能性は大きい。これらは忘れられた日本の近代絵画史の穴を埋める貴重なピースというだけでなく、近代化されていく明治時代の生活風俗や文化を知るための資料としても大いに役立つに違いない。
関連レビュー
府中市制施行65周年記念 おかえり 美しき明治|村田真:artscapeレビュー(2018年12月01日号)
2022/06/07(火)(村田真)
αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点
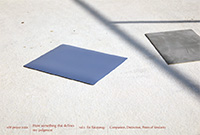
会期:2022/04/16~2022/06/10
gallery αM[東京都]
会場の入り口についた。髙柳恵里の個展だ。大きく開かれた扉の向こうに、コンクリート床にある切断された合板数枚とハンドアウトを見比べている二人がいた。私は検温と消毒と記名を済ませて、ハンドアウトを受付でもらって、二人の仲間入りをした。作品名は《棚板》で、合板は3枚だった。本棚の板って、見えない部分が結構切りっぱなしで、やすりもほどほどだったりする。この木材の毛羽立ち、棚板を切り出したものなのか、そのまま取り出したものなのかどうか。
なんとなく会場を向かって左側に進む。突き当たりにデーンとカーペットが敷かれていた。6畳間カーペットの上にはポリシート、さらにその上には泥のかたまり。カーペットの下にもさらにポリシート。ハンドアウトを確認。これらは下が《敷く(実例)》で、上に乗っているシートと泥の作品は《実例》。振り返るとダイニングテーブルと2脚の椅子、床には床材の仮置き。壁にはハンカチが畳まれ、重心上アンバランスな箇所がクリップで留められて、虫ピンで壁に打たれていた。小部屋の机の上には剪定鋏とそれで刻まれた枝とその欠片。部屋の方々には水のペットボトル。これは《奥行き》で、材質を知ろうとハンドアウトを見ると「ミネラルウォーター」、サイズは「可変」。ハンドアウトには髙柳の言葉も載っていた。冒頭だけだが抜粋する。
合うのか、合わないのか、試してみる。 比べる。選ぶ。 やってみるとどうなのか、やってみる。 「試し」なので、取り返しがつく。極力リスクは回避する。
(会場ハンドアウト、作家ステイトメントより)
 「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」(企画:千葉真智子)展示風景
「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」(企画:千葉真智子)展示風景
gallery αM(2022)[撮影:守屋友樹]
マルティン・ハイデガーにおける「取り返し」は、ゲルマン民族によるドイツの取り戻しというナチズムと結びついた。ハイデガーの前身としてのセーレン・キルケゴールにおける「反覆」とは愛する人の取り戻しだった。国家的なるものと私的なるものの双方で求められてきた「取り返し」。では、この展覧会にとっての「取り返し」が問うものは何だろうと考えてみて、それは「美術展示施設の倫理」だろうと私は考えている。その倫理を個人的に言ってみたら、「次に来るものが不意に損なわれないように」だと思っている。だから、草木は燻蒸し、土は焼成し、水はペットボトルの中に入れて、壁の穴開けは必要最低限、原状復帰が大原則。カビや虫が次に来る作品を損ないませんように。あるいは、目の前の現実へのリスク回避。
国家ないし愛する人とのあるべき歴史を紡ぐための「取り戻し」を求める憧憬と比べると、髙柳の「取り返し」はとてもドライで「リスク」と結びつく。買ったものの使い勝手はどうだろうか、床色を変えるにもまずはサンプルから、作品を制作するのもコスト、作品を抱えることもコスト、再展示ができないのもコスト。これは物をつくり抱え続ける個人サイドの持続可能性への視点だろう。展覧会が終わったら、虫ピンで打ったタオルは使えばいい。ペットボトルの水は飲める。だから次の展示のために、ボトルは「サイズ可変」にしておく。ただしこれは「美術施設に対峙する作家」の尺度でもある以上に、家にこれ以上物を増やせないし、大きな倉庫なんてない「生活の尺度」でもあるだろう。
公式サイト:https://gallery-alpham.com/exhibition/project_2022/vol1/
関連レビュー
αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点|伊村靖子:artscapeレビュー(2022年7月1日号)
2022/06/09(木)(きりとりめでる)
BankART Under35 2022 ナカバヤシアリサ 足立篤史

会期:2022/06/10~2022/06/26
BankART KAIKO[神奈川県]
35歳以下の有望な若手アーティストに発表の場を与える「U35」シリーズ。今回は絵画のナカバヤシアリサ と彫刻の足立篤史の2人展。ナカバヤシはにじみ、ぼかし、ストロークを活かして風景らしきイメージを描いている。その風景は、《The other side》《opposite bank》(2022)というタイトルから察せられるように、水(川?)を挟んで手前と向こう(あるいは右と左)に画面が分割されているものが多い。《ボートピープル》と題する作品もあるので、なにか分断に対する思いがあるのだろうか。筆触に勢いがあり、なにより色彩が美しいのは、キャンバスではなく、紙にアクリルとオイルパステルを使っているせいかもしれない。片隅に飾られていた小サイズの人物画にも惹かれた。
足立は古新聞を素材に、その発行年と同じ時代のモチーフを立体化する。今回のメインである《OHKA》は、第2次大戦の末期に海軍が開発した特攻機「桜花」を、同時代の新聞を使って原寸大で再現し、紙風船状に膨らませたもの。茶色びた古新聞には「皇國民への試煉」とか「いまぞ攻勢の秋」とか勇ましい活字が踊っている。桜花は機首に爆弾を搭載し、母機に吊るされて目標近くで分離され、ロケット噴射で加速させて滑空し、目標に体当たりするという小型の特攻兵器。これに乗り込んだら最後、自力では引き返せないので、目標に当たろうが外れようが、手前で母機ごと墜落しようが、死ぬしかない(大半は目標に達する前に撃ち落とされ、無駄死にしたらしい)。そのため「空飛ぶ棺桶」とも呼ばれたという。機体は全長6メートルに対して幅は5メートルほどと短く、ちょうど爆弾に羽根が生えたような格好で、飛行機としては実に頼りない。それを古新聞をつなぎ合わせてハリボテ状に膨らませただけだから、よけい頼りなさが際立つ。ちなみに桜花を設計した技術者は戦後、新幹線の設計に携わったという。そういえば先端が団子鼻の初期の0系はどこか桜花を思わせないでもない。
ほかにも零戦やロッキード、ノースロップなどの戦闘機をはじめ、戦車、戦艦などを同様の手法で成形した小品を展示。なかでも、1964年と2021年の東京オリンピック開催時に飛んだブルーインパルスをかたどった2点は、それぞれの型の違いだけでなく、新聞報道の扱いの差にも半世紀以上のタイムラグを感じざるをえなかった。

[筆者撮影]
2022/06/10(金)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)