artscapeレビュー
村田真のレビュー/プレビュー
気仙沼と、東日本大震災の記憶

会期:2016/02/13~2016/03/21
目黒区美術館[東京都]
震災から5年、宮城県気仙沼市のリアス・アーク美術館が調査・記録した被災現場写真を中心に、家電やパソコンなどの被災物、過去の震災や津波の資料など約400点を借りてきて展示している。なぜ目黒区美術館でやるのかというと、1996年から続く「目黒のさんま祭」に気仙沼市がサンマを提供してきたからだそうだ。こうした食文化のつながりというのは意外と堅固で納得できる。さて、展示のほうは200点を超す写真が圧巻。といっても写真自体は大きくないし、驚くような光景が写されてるわけでもなく、こういってはなんだがもはや見慣れた被災地の風景ばかり。なのに目を釘づけにしてしまうのは、1点1点に150-200字程度のコメントがつけられ、言葉とイメージのダブルパンチで揺さぶりをかけてくるからだ。撮影者が地元の人であることも説得力があるし、また彼が美術館学芸員であるせいか、被災地や被災物にある種の美しさやおもしろさを見出そうとしているようにも感じられるのだ。例えばJR気仙沼線のレールがめくれ上がり、まるでジェットコースターみたいに裏返っていたり、津波で建物2階に運ばれて息絶えた魚の軌跡が乾いた泥に印されていたり、冠水した路地に建物が映る様子がヴェネツィアの運河を連想させたり。「破壊は美を奪い『醜さ』を生み出す」とコメントにあるが、そこにまた別の「美」を見出してるようにも見える。もちろん言葉とイメージだけですべて伝わるわけでもないだろう。おそらくここに決定的に欠けているのは「匂い」ではないか。大量のサンマが腐ってどす黒い塊と化した写真のコメントには「匂いのレベルが違う」「体が震えだし、身の危険を感じた」と書かれている。そして匂いは記憶のもっとも古層に沈潜し、ふとしたはずみに蘇る。これは美術館では伝わらない。
2016/02/14(日)(村田真)
藤本由紀夫 Broom(Coal)/Tokyo
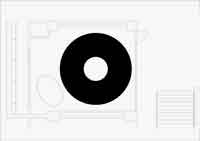
会期:2016/02/06~2016/03/06
シュウゴアーツ ウィークエンドギャラリー[東京都]
ギャラリーいっぱいに黒い石が円環状に敷かれている。石は黒光りしているので石炭とわかる。一瞬リチャード・ロングを想起したが、上を歩いてもいいというのでジャリジャリいわせながら歩いてみる。円環に沿って歩いているうちに、あ、これはレコード盤だと気がつき、自分がレコード針になった気分。「Broom(ほうき)」と題されたこの作品、最初は床に枯れ葉を敷きつめるインスタレーションから始まり(最初に発表した会場が「room B」だったので「Broom」になったとか)、次第に素材や形態を変えながら石炭のレコード盤になったという。考えてみれば石炭はレコード針に使われるダイヤモンドと同じ元素だ。横のテーブル上にはオルゴールを使った小品がいくつかあって、歯が全部そろってる手巻きオルゴールがひとつ、あとは歯が1本しかないもの、ぜんぜんないものなど。さすがに歯が1本だけではなんの音楽かわからない。また、箱のなかにオルゴールが二つ入っていて、ひとつは右から1、3、5……という奇数番目の歯、もうひとつは2、4、6……という偶数番目の歯しかない。同時に鳴らしても同調しないが、なんの曲かはなんとなくわかる。オルゴールひとつでこれだけ遊べるとは。
2016/02/13(土)(村田真)
原田直次郎 展──西洋画は益々奨励すべし

会期:2016/02/11~2016/03/27
埼玉県立近代美術館[埼玉県]
“油絵の先駆者”高橋由一と“近代絵画の立役者”黒田清輝のあいだに、渡欧して油彩技法を身につけた洋画家が何人かいる。五姓田義松、山本芳翠、松岡寿、原田直次郎ら明治美術会の画家たちで、みんな抜群に絵がうまい。由一や清輝よりうまいと思う。なのに由一と清輝の陰に隠れてほとんど日の目を見なかったのは、モダニズムとナショナリズムのせめぎ合いに揺れた明治美術史のいたずらというほかない。とりわけ原田直次郎は36歳で夭逝したこともあって、没後10年の1909年に親友の森鴎外が企画した遺作展以来、本格的に紹介されたことはなく、今回がじつに100余年ぶりの回顧展になるという。ただ活動期間が短かったため作品点数が少なく、松岡寿や大下藤次郎、ドイツで交流のあったガブリエル・フォン・マックスやユリウス・エクステルらの作品も出ているため、キャプションを確かめずに絵だけ見てすべて原田の作品だと勘違いするアホもいるかもしれない。原田の代表作《靴屋の親爺》や《老人》なんか何点も出ているから要注意だ。まあこれだけ作品が模写されるというのは、いかに原田が慕われていたかということの証だろう。この《靴屋の親爺》や《老人》などはよくも悪くも日本人離れした技量を誇るが、帰国後ナショナリズムの吹き荒れる日本では受け入れられず、《騎龍観音》や《素尊斬蛇》といった日本的主題に基づくキッチュな折衷絵画に向かわざるをえなかった(前者は埼玉には出品されず、後者は関東大震災で焼失)。こういう逆境のなかで制作した苦肉の作品というのは、いつの時代にも興味深いものだ。いずれにせよ、歴史のはざまに埋もれて目立たなかった画家の発掘は公立美術館の重要な役割だと思う。
2016/02/11(木)(村田真)
第19回 文化庁メディア芸術祭

会期:2016/02/03~2016/02/14
国立新美術館[東京都]
いつものように漫然と会場を一周してみたが、いい悪いはともかく「おっ!」と引っかかる作品が少ない。まあそれもいつものことだが、今年はとくに少なく感じる。そのなかでひとつだけよくも悪くも引っかかった作品が、アート部門で優秀賞を獲った長谷川愛の《(不)可能な子供、01:朝子とモリガの場合》だ。通常同性カップルでは子供はできないが、ふたりの遺伝情報を調べて掛け合わせればヴァーチャルな子供はできる。ここでは女性同士のカップルがそれぞれの遺伝データを組み合わせ、子供ふたり(つまりふたつの可能性)をつくるという映像。だが、彼女たちによく似たヴァーチャル・チルドレンを見て一瞬気持ち悪くなってしまった。もしこれが「アート」ではなく現実だとしたらおぞましいこと。同性カップルにとって子供がほしいというのは切実な願望かもしれないが、それは自然の摂理に反することであり、生理的に受け入れられない。でもそれを「アート」としてシミュレーションしてみるのは許されるし、むしろどんどんやってみるべきだと思う。つまりアートは、例えば戦争や災害、表現の抑圧といった現実に起きたらマズイ社会的問題を、あらかじめシミュレーションして世に問うことができるメディアなわけだ。たぶんメディア・アートの役割のひとつはそんなところにあるんだろうね。
2016/02/07(日)(村田真)
試写『もしも建物が話せたら』

この奇妙なタイトルの映画は、ヴィム・ヴェンダース監督が総指揮をとり、ヴェンダースを含め6人の監督に建物を主役にした映画を撮ってもらったオムニバス・ドキュメンタリー。ヴェンダースはベルリンのフィルハーモニー、ミハエル・グラウガーはサンクトペテルブルクのロシア国立図書館、マイケル・マドセンはノルウェイのハルデン刑務所、ロバート・レッドフォードはサンディエゴのソーク研究所、マルグレート・オリンはオスロのオペラハウス、カリム・アイノズはパリのポンピドゥー・センターを選択。基本的にそれぞれの建物がみずからについて独白するという趣向だ。どの映像も、というよりどの建築も興味深いが、とくにルイス・カーン設計のソーク研究所は四角い箱を並べた無機的なモダニズム建築に見えるのに、ここで働いた人はだれも辞めたがらないという。なにがそんなに惹きつけるのか、その空間的魅力が画面から十分に伝わってこないけれど、行ってみたいと思わせる映像ではある。逆に18世紀末に建てられたロシア国立図書館は、いかにもヨーロッパの歴史的図書館の趣を残した建築だけど、建築そのものよりおびただしい量の本が織りなす特有のアウラに圧倒される。「薔薇の名前」がそうだったように、図書館を主役にした映画はもうそれだけで引き込まれてしまう。ひとり30分足らずの短編集だが、6本あるので3時間近くになり、ちょっとツライ。単に長いというだけでなく、建物が動かない分カメラが移動するため、見るほうも動いた気分になって疲れるのかもしれない。
映画『もしも建物が話せたら』予告編
2016/02/04(木)(村田真)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)