artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
題府基之 何事もない穏やかな日です。

会期:2016/06/07~2016/06/24
ガーディアン・ガーデン[東京都]
題府基之は、東京ビジュアルアーツ専門学校を卒業した2007年に、第29回「ひとつぼ展」写真部門に入選して写真家デビューを果たした。家族との日常生活の断片を至近距離から撮影した写真群は、たしか同校の卒業制作だったはずだ。その後、彼の仕事は日本よりもむしろ欧米諸国で注目を集めるようになる。『Lovesodey』(Little Big Man Books, 2012)、『Project Family』(Dashwood Books, 2013)などの写真集を刊行し、現代日本写真の有力な作り手の一人とみなされるようになった。今回のガーディアン・ガーデンでの展示は、「ひとつぼ展」のグランプリ受賞を逃した写真家たちをフォローする「The Second Stage at GG」シリーズの第42弾として企画されている。
家族の日常スナップを、B全のペーパーに引き伸ばした26点が壁に連なる展示は圧巻であり、以前より明らかにスケールアップしている。だが、それだけではなく、家族一人一人のポートレート、食卓の上の眺め、近所の住宅の光景などを切り取り、圧縮して、再構築していく精度が格段に上がってきているように感じる。一見ラフな撮影の仕方に思えるが、見かけ以上に操作性の強い作品といえるだろう。とはいえ小綺麗にまとめあげるのではなく、ハイテンションを保ち続け、ノイズを排除することなく取り込んでいく力量を感じる。なんともとぼけた響きのタイトルは、住宅関係らしいポスターのロゴから借用している。テレビの画面に映っているのは、どうやらアメリカの大御所写真家のウィリアム・エグルストンのようだ。社会批評として理に落ちる寸前で、視覚的なエンターテインメントに方向をずらしていく綱渡りが、いまのところはうまくいっているのではないだろうか。
とはいえ、そろそろ「家族」の引力から離脱していく時期が近いのではと思う。どんな風に次の「プロジェクト」を展開していくのかが大きな課題になりつつある。なお、展覧会の会期に合わせるように、食卓の光景だけで構成した新しい写真集『STILL LIFE』(Newfave)が刊行されている。
2016/06/15(水)(飯沢耕太郎)
アート・アーカイヴ資料展XIV「鎌鼬美術館設立記念 KAMAITACHIとTASHIRO」

会期:2016/06/01~2016/07/15
慶應義塾大学アート・スペース[東京都]
細江英公は1965年9月、舞踏家、土方巽をモデルとして秋田県羽後町田代で「鎌鼬」を撮影した。このシリーズは、1968年3月の銀座ニコンサロンでの個展「とてつもなく悲劇的な喜劇」に出品され、69年には田中一光のデザインで現代思潮社から写真集『鎌鼬』として刊行されて、細江の代表作のひとつとなった。それから50年あまりが過ぎたが、撮影の舞台となった田代の住人たちのなかには、わずか2日間あまりの土方との邂逅の記憶が深く刻みつけられているという。東北の農村に、土方はまさに折口信夫のいう「マレビト」として出現したのではないだろうか。
本展は、田代の旧長谷山邸が「里のミュージアム 鎌鼬美術館」として生まれ変わるのを期して、東京・三田の慶應義塾大学アート・スペースで開催された。細江撮影の「鎌鼬」のオリジナルプリントとコンタクトプリントに加えて、桜庭文男が現代の田代を撮影した「稲架(はさ)のある里/四季」、藤原峰のドローン空撮による映像作品、ポスターなどの関連資料が出品され、会場の一角には、細江の写真に印象深く写り込んでいる「稲架」も再現されていた。展示スペースがやや小さいのが残念だが、ひとつの写真シリーズが呼び起こした反響を、時代を超えて検証しようとする興味深い企画である。今後「鎌鼬美術館」の活動が展開していくなかで、さらに多様なコラボレーションが期待できるのではないだろうか。
なお、展覧会を主催した慶應義塾大学アート・センターは、土方巽のほかに、瀧口修造や西脇順三郎の関連資料も多数所蔵している。その一部を見せていただいたのだが、展示企画に結びつきそうな写真資料もかなりたくさんあった。ぜひ展覧会や出版物のかたちで、積極的に公開していってほしいものだ。
2016/06/08(水)(飯沢耕太郎)
笹岡啓子「SHORELINE」
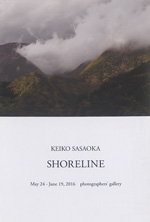
会期:2016/05/24~2016/06/19
photographers’ gallery[東京都]
笹岡啓子が2015年から東京・新宿のphotographers’ galleryで開催している「SHORELINE」展も今回で3回目になる。展覧会にあわせて刊行される同名の小冊子も、もう24号になった。主に川筋を辿りながら、「時制を超えた「地続きの海」を現在の地形から辿り、連ねていく」というシリーズだが、今回は静岡県の大井川沿いの山間部(「奥大井」)と沿岸部(「遠州灘」)を撮影している。
会場に並ぶ13点を見ると、風景の細部に向かう笹岡の眼差しが、少しずつ練り上げられ、厚みを帯びてきているように感じる。かつてルイス・ボルツ、ロバート・アダムズ、ジョー・ディールらが1970年代に試みた、地勢学的な風景の描写(「ニュー・トポグラフィックス」)の現代版といえなくもないが、笹岡のアプローチはそれとも違っている。「ニュー・トポグラフィックス」の厳密で冷ややかなモノクロームの描写と比較すれば、笹岡のカラー写真はもっと柔らかなふくらみがあり、風水的な気の流れが写り込んでいるようでもあるからだ。独特の感触を備えた、日本の風土に即した風景写真が、かたちをとりはじめているのではないだろうか。
なお、隣接する展示スペース、KULA PHOTO GALLERYでは、「飯舘」のシリーズ8点を展示していた。いうまでもなく、福島第一原発の事故による放射能汚染で、いまだに居住制限地域、帰還困難地域が大きな面積を占める土地だ。2014年4月、8月、2016年3月に撮影された笹岡の写真にも、除染された汚染土を袋詰めして、あちこちに放置してある光景が写り込んでいる。数千万年、数億年という単位で「地続きの海」が見えてくる「奥大井」、「遠州灘」と、5年前の震災の記憶がまざまざと甦えってくる「飯舘」を対比的に展示したところに、笹岡の批評的な企みがあるのだろう。
2016/06/07(火)(飯沢耕太郎)
山谷佑介&松川朋奈「at home」+沢渡朔「Rain」

会期:2016/06/04~2016/07/02
YUKA TSURUNO GALLERY[東京都]
不思議な組み合わせの3人展だ。山谷佑介は赤外線カメラでネガ像に転換したボール紙のようなペラペラの感触の「家」の写真を、松川朋奈は同世代の女性たちの日常の痕跡を描いた油絵を「at home」というタイトルで出品している。沢渡朔はここ10年ほど折に触れて撮影してきた「Rain」のシリーズから、夜に撮影された縦位置の写真を展示した。方向性はまったくバラバラだが、そこにはどこか共通の視点も感じられる。山谷が「ホラー感」という言葉で的確に表現していたのだが、どの作品にも何とも不穏な雰囲気、どことなく不安げで危険な匂いが漂っているのだ。
それが一番強く感じられるのは、やはり沢渡の「Rain」だろう。雨に濡れそぼった街、繁茂する植物、その中を軟体動物のようにぬめぬめと漂う車や人間たち──この作品には、あらゆる事物をエロティシズムの原理が支配する世界に封じ込めようとする沢渡の志向がよくあらわれている。じつはこのシリーズは以前、ヌードの女性たちの絡みの写真群とカップリングして発表されたことがあった。国書刊行会から展覧会にあわせて同名の写真集が刊行されているのだが、残念なことにヌードのパートは割愛されている。ぜひ、別ヴァージョンの「Rain」の写真集としてまとめてほしいものだ。
なお、YUKA TSURUNO GALLERYは本展を最後にして東京・東雲から天王洲アイルに移転する。今回の展示の3人中2人が写真家であることでわかるように、これから先も現代写真にスポットを当てた展示が期待できそうだ。
2016/06/04(土)(飯沢耕太郎)
幻の海洋写真家・木滑龍夫の世界

会期:2016/05/23~2016/06/04
表参道画廊[東京都]
表参道画廊ではここ3年ほど、5月~6月のこの時期に、「東京写真月間」にあわせて写真史家の金子隆一の企画による写真展を開催している。一昨年の大西茂、昨年の写真雑誌『白陽』の写真家たちに続いて、今年は北海道・小樽で写真家として活動した木滑龍夫(1897~1941)の作品が展示された。
木滑は東京・東大久保に生まれ、海軍除隊後、函館の汽船会社の社員となって、無線局長として船に乗り組んでいた。そのかたわらアマチュア写真家としても活動する。1939年に『アサヒカメラ』が主催した「海洋写真展覧会」で「激浪」が一等になり、一躍「海洋写真家」として名前が知られるようになった。その後も、写真展や写真雑誌上で作品を発表していたが、1941年に北千島に向かう途中で海難事故のために亡くなった。
残された1930年代のヴィンテージ・プリント20点を見ると、木滑が同時代のモダニズム=「新興写真」の美学に基づいて作品を制作していたことが明確に伝わってくる。船体の一部を斜めのアングルで切り取った作品や、街頭のスナップ写真、岩のクローズアップなどの造形意識は、まさに典型的な「新興写真」的なアプローチといってよいだろう。だが、彼のホームグラウンドというべき、逆巻き、砕ける波を船の甲板から写した数枚には、「新興写真」の枠組みにはおさまりきらない、ダイナミックな現実描写の方向性があらわれている。それらを見ていると、彼がもう少し写真の仕事を続けていけば、どうなったのだろうかと想像してみたくなる。「海洋写真」というユニークなジャンルを、さらに発展させていったのではないだろうか。
2016/06/04(土)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)