artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
堀市郎・前田寅次 作品展

会期:2012/12/04~2013/12/25
JCII PHOTO SALON/ JCIIクラブ25[東京都]
ここ10年ほどの間に、「芸術写真」と称される日本の1910~30年代の写真群についてはかなり多くの新たな知見の積み上げがあり、「芸術写真の精華──日本のピクトリアリズム 珠玉の名品展」(東京都写真美術館、2011)など、いくつかの注目すべき展覧会が開催されてきた。だが、絵画的な美意識(ピクトリアリズム)を基調とする「芸術写真」は、むろん日本だけでなく欧米諸国でも大流行しており、国際的な広がりを持つトレンドだったことを忘れるべきではないだろう。当然、アメリカやヨーロッパ諸国にわたった日本人写真家のなかにも、独自の「芸術写真」を志向する動きが見られた。今回、JCII PHOTO SALONと JCIIクラブ25で開催された「堀市郎・前田寅次作品展」は、アメリカで活動した二人の日本人写真家の作品を展示している。
1901年に渡米した堀市郎は、1912年からニューヨークで肖像写真館を経営し、新渡戸稲造、東郷平八郎などのポートレートも撮影している。ややソフトフォーカス気味の、柔らかな光にモデルの顔が浮かび上がるロマンティックな作風だが、ダンサーを撮影した実験的な作品もある。1929年に帰国後は、肖像画家として活動した。一方、前田寅次は1901年に渡米し、ロサンゼルスで不動産管理の仕事をしながら、アメリカだけでなくカナダ、スペイン、ベルギー、フランスなどの「サロン」(芸術写真家たちの公募展)で入選、入賞を重ねた。前田の作品はほとんどが風景で、さまざまな要素を画面に巧みに配置していく構成力に優れている。そのシャープなピント、抽象的な画面構成は、むしろ日本では1930年代以降に定着する「新興写真」に通じるものがありそうだ。
このような異色の写真家たちの仕事を、日本の「芸術写真」の流れのなかにどのように接続していくかが、次の大きな課題になるだろう。さらなる調査や研究が必要な在外日本人写真家は、堀や前田だけではないのではないだろうか。
2012/12/14(金)(飯沢耕太郎)
この世界とわたしのどこか 日本の新進作家 vol.11

会期:2012/12/08~2013/01/27
東京都写真美術館 2階展示室[東京都]
いつのまにか11回目を迎えていた「日本の新進作家」展。若手の、将来が期待される写真家の選抜展としての役目をしっかり果たすようになった。もうすでに評価の高い写真家だけでなく、今回でいえば大塚千野や菊池智子のように、あまりきちんと紹介されていなかった新しい顔に出会える楽しみがある。
「この世界とわたしのどこか」という曖昧模糊としたタイトルが暗示するように、テーマらしきものはあまりくっきりとは見えてこない。1970年代生まれの女性作家というのが唯一の共通項だが、現代日本の索漠とした状況を映し出す旅のスナップショット(蔵真墨)、ファッション誌の女性像を精密に写しとったドローイングを複写し魔術的な操作を加えた銀塩プリント(田口和奈)、海辺の光景の中に寄る辺なくたたずむ釣り人たちを撮影した作品群(笹岡啓子)、過去のアルバム写真に現在の自分の姿を合成した「ダブル・セルフポートレート」(大塚千野)、中国のトランス・ジェンダーの若者たちを2005年から撮影し続けたプライヴェート・ドキュメンタリー(菊池智子)と、彼らの展示作品は多方向に引き裂かれている。だが、それぞれ「この世界とわたし」との関係のあり方を、真摯に探求していこうとする志向においては重なりあう部分があるのではないかと思う。
大塚の「見ることのできない何か、そこにはない何かを撮ることによって、わたしは新たな表象、新たな記憶を創造する」、あるいは田口の「作品は私の既知をつねに越えていくものだし、私よりずっとさきにいって私にさえ示唆をあたえてくれる」といったコメントに、彼女たちの、未知の「どこか」に写真という杖を差し伸ばし、何ものかを探り当てようという意欲のみなぎりを感じる。個人的には、胸が震えるような切実さをたたえた菊池智子の写真と映像作品(「迷境」2012)に、強い感銘を受けた。
2012/12/14(金)(飯沢耕太郎)
楢橋朝子「in the plural」
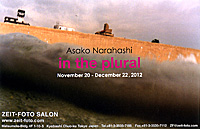
会期:2012/11/20~2013/12/22
ツァイト・フォト・サロン[東京都]
楢橋朝子はこのところ、水の中に半ば没しつつ水中カメラで岸辺の景色を撮影する「half awake and half asleep in the water」のシリーズを中心に発表してきた。このシリーズはたしかに楢橋の写真家としての仕事の到達点というべき作品で、アメリカのNazraeli Pressから写真集が出版されるなど、国際的にも評価が高い。だが、今回のツァイト・フォト・サロンでの個展や、同時期に開催されたphotographers’ galleryでの個展「とおすぎてみえたこと」などを見ると、楢橋が次のステップへ向けて動き出したことが感じられる。
ツァイト・フォト・サロンの「in the plural」は、タイトルが示すように複数形の写真群によって構成されていた。中心になっているのは、さまざまな場所で撮影された「half awake and half asleep in the water」のヴァリエーションだが、そのなかにまったく関係なく見える写真が混じり込んでいる。サンタモニカの草原、湯沢の雪景色、登別のロープウェイなどは、むしろ前作の『フニクリフニクラ』(蒼穹舍、2003)の世界に近い。台北で撮影された鳥の影のようなものが写っているテレビ画面のようなテイストは、これまでの楢橋の作品には見られなかったものだ。実際に撮影期間はかなり長く、ここ10年ほどにまたがっているようだ。
こうしてみると、楢橋が「half awake and half asleep in the water」で打ち出していった、足場がぐらぐら揺れ動くような不安定な画像のあり方は、もともと彼女のなかに体質的に備わっていたものであることがわかる。水中カメラという装置を借りなくても、水の中に浮き沈みするような感覚がすでに身体化されていたということだろう。「half awake and half asleep in the air」とでもいうべき写真群が、次に形をとってきそうな気もする。
2012/12/12(水)(飯沢耕太郎)
MAM PROJECT 018 山城知佳子

会期:2012/11/17~2013/03/31
森美術館 ギャラリ─1[東京都]
沖縄出身の山城知佳子の映像や写真の作品は、以前からずっと気になっていた。沖縄独特の亀甲墓を舞台にした一連のパフォーマンスや、あの海の中を海藻とともに漂う「アーサ女」(2008)など、南島の母系社会の神話的想像力に根ざした注目すべき作品だと思う。今回は森美術館の新進アーティスト紹介企画の一環として、新作の三面スクリーンの映像作品「肉屋の女」が展示されていた。
「肉屋の女」はこれまでの山城の作品とは違って、物語性がかなり強く打ち出され、シナリオのある「映画」として見ても充分なほどの完成度に達している。海の中を漂う肉片を拾い集めて、米軍基地のフェンス近くのバラック小屋で売る女たちの世界と、その肉を争いながら奪い取って食べる男たちの世界とが交錯しつつ、鍾乳洞を舞台に沖縄の精神的な古層との交流を暗示するようなパフォーマンスが展開する映像作品の構造は、そう単純なものではない。それでも、山城自身をはじめとする沖縄在住の若者たちの開かれた身体のあり様が、気持ちよく目に飛び込んできて見応えがあった。それとともに「肉屋」という特異な空間設定が、とてもうまく効いていると思った。映像を見ているうちに、もしかするとこの肉は人肉なのではないかという、奥深いカニバリズム的な恐怖が引き出されてくるのだ。このテーマを深めていけば、さらにめざましい映像世界の展開が期待できそうだ。
2012/12/12(水)(飯沢耕太郎)
北井一夫「いつか見た風景」

会期:2012/11/24~2013/01/27
東京都写真美術館 3階展示室[東京都]
北井一夫の写真家としての位置づけはむずかしい。1976年に「村へ」で第一回木村伊兵衛写真賞を受賞しているのだから、若くしてその業績は高く評価されていたといえるだろう。だが『アサヒカメラ』に1974~77年の足掛け4年にわたって連載された、その「村へ」のシリーズにしても、いま見直してみるとなんとも落着きの悪い写真群だ。高度経済成長の波に洗われて、崩壊しつつあった日本各地の村落共同体のありようを、丹念に写し込んでいった作品といえるだろうが、北井が何を探し求めて辺境の地域を渡り歩いているのか、そのあたりが判然としないのだ。とはいえ、これらの写真を見続けていると、たしかにこのような風景をその時代に見ていたという、動かしようのない既視感に強くとらわれてしまう。それは怒りとも哀しみともつかない、身動きができないような痛切な感情に包み込まれるということでもある。
北井の写真には、いつでもこのような、見る者をうまく制御できない記憶の陥穽に導くような力が備わっていると思う。僕にとって、今回の展覧会でそれを一番強く感じたのは、「過激派・バリケード」(1965~68)のパートに展示されていたバリケード封鎖された日本大学芸術学部内で撮影された一連の「静物写真」だった。闘争が長引くに連れて、「封鎖の校舎内は、ストライキ学生の衣食住の場所になり、非日常空間から日常生活の場へと変化した」という。北井はそこで目にした「靴」「ハンガー」「トイレットペーパー」「傘」「謄写版」「洗面台」などを、135ミリの望遠レンズで接写している。僕自身は彼より一世代若いので、これらの事物をバリケード内で直接目にしたわけではないが、その空気感をぎりぎり実感することはできる。日常を、その厚みごと剥がしとるような北井の眼差しのあり方が、これらの写真には見事に表われている。それぞれの時代の日常性を身体化して体現できる仕掛けを組み込んでいることこそ、北井の写真の動かしようがないリアリティの秘密なのではないだろうか。
2012/12/07(金)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)