artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
瀧本幹也「LAND SPACE」
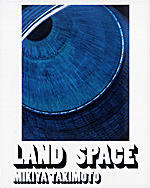
会期:2011/07/16~2011/08/28
MA2 Gallery[東京都]
瀧本幹也の爽やかで意欲的な展示だ。2009年から5回にわたって撮影したというフロリダ・ケネディ宇宙センターのスペースシャトルのシリーズには、「宇宙少年」の夢が結晶している。5キロ以内に近づくのは禁止されているため、音に反応してリモートコントロールでシャッターを切る装置を使って、発射台から500メートルの地点から打ち上げの様子を連続的に撮影しているのだという。スペースシャトル計画が終焉を迎えた今、記念碑的なシリーズになるのではないだろうか。ぜひアメリカでの展示を実現してもらいたいものだ。
ただ、ノイズをすべてカットして、ピカピカのロケットや建築物、発射台の内部などに焦点を絞った作品の選択は微妙なところだろう。もう少し宇宙に挑む人間たちの生々しい営みも見てみたい気がした。完璧な“絵”をめざすあまり、瀧本自身の立ち位置も含めて、宇宙計画を推進する過程につきまとう、どちらかといえば子どもっぽい欲望や衝動の部分が見えにくくなっている。広告を中心として仕事をしてきた写真家にありがちな「小綺麗にまとめてしまう」弱点が出てしまったようにも感じる。
2階のスペースに展示されていた「LAND」のシリーズにも同じようなことを感じた。フレームが凝っていて、左右に内側を照らし出すLED照明が組みこまれている。面白いアイディアなのだが、白っぽい光が強過ぎてむしろ画面が見えにくくなってしまった。そもそも「SPACE」と「LAND」という組み合わせにあまり必然性がないのではないか。スペースシャトルから見た地球の“皮膚”の眺めを、標本のように提示するということなのだろうが、やや理に落ち過ぎた嫌いがある。二つのシリーズは切り離して見せた方がよいのではないかと思った。
なおLOUIS VUITTON六本木ヒルズ店でも、同時期に瀧本の新作展「LOUIS VUITTON FOREST」(7月29日~8月31日)が開催された。やはり「まとめ過ぎ」という感はあるが、こちらも時間をかけた意欲作である。
2011/08/13(土)(飯沢耕太郎)
江成常夫「昭和史のかたち」

会期:2011/07/23~2011/09/25
東京都写真美術館 2階展示室[東京都]
東京都写真美術館の地下1階展示室で鬼海弘雄展を見て、2階にエレベーターで昇り、今度は江成常夫展の会場を回った。重量級の展覧会を二つ続けて見たので、さすがにかなりの疲れを感じた。
江成は1974年に毎日新聞社を退社してフリーランスとなり、その後一貫して「アジア太平洋戦争」の傷跡を辿り、写真を通じて戦後日本人の精神性の「かたち」を問い続けてきた。今回の展示は40年近いその粘り強い営みの集大成である。ハワイ、テニアン、サイパンなど太平洋の島々の戦跡を記録した「鬼哭の島」、旧満州国の成り立ちとそこに取り残された日本人残留孤児を追う「偽満洲国」「シャオハイの満洲」に、近作である「ヒロシマ」「ナガサキ」のシリーズ(被爆者の肖像と遺品)を加えた代表作112点が展示されていた。正統派のドキュメンタリーには違いないが、ロールサイズの大伸ばしの印画紙をアクリルで挟み込んだ展示を積極的に試みるなど、視覚的効果にも気を配って作品を配置している。今年は太平洋戦争開始から70年という節目の年でもあり、記憶の風化が急速に進むなかで「これだけは後世に残しておきたい」という江成の強い思いは充分に伝わってきた。
ただ、鬼海弘雄の展示を見た後なので余計そう感じたのかもしれないが、「シャオハイの満洲」や「ヒロシマ」「ナガサキ」のポートレート作品が、どうも均一に見えてしまう。個々の「顔」の違いが、「日本人残留孤児」「被爆者」といった文脈に強く固定されてしまうことで、あまりうまく立ち上がってこないのだ。やや広角目のレンズによるクローズアップという手法にこだわったためでもあるだろう。無理を承知で言えば、ドキュメンタリーという枠組からこれらの「顔」を解放したならば、それらはどんな風に見えてくるのだろうかとも思った。「顔」は強力な被写体だが、拘束性が強いので扱い方も難しくなる。
2011/08/12(金)(飯沢耕太郎)
鬼海弘雄「東京ポートレイト」

会期:2011/08/13~2011/10/02
東京都写真美術館 地下1階展示室[東京都]
鬼海弘雄の作品を見ていると、語呂合わせではないがいつも「魔」と「間」を感じる。1970年代から撮り続けられている「浅草のポートレイト」のどの一枚でもいい。写真の前に立って、そこに写っている人物の姿をじっと眺めていると、あたかも「魔」に見入られたような気分になってくる。目を離すことができなくなり、ここにいるのは何者なのか、なぜこんな姿でこの場所に出現しているのか、写真家はなぜ彼の前を行き交う無数の通行人からこの人物を選んだのか、この人はどこから来てどこに行こうとしているのか等々、次々に問いが湧き上がり、知らぬうちに長い時間が過ぎてしまうことになる。ふと我に返ってあたりを見回すと、自分の近くでやはり写真に見入っている観客の姿が目に入ってくる。その姿が、どう見ても鬼海が撮影した「浅草のポートレイト」の登場人物そのものなのでびっくりしてしまう。世間からはずれた、異形の人物たちを撮影しているようで、このシリーズはわれわれ一人ひとりのなかに潜む、普遍的とさえ言えそうな「人間」の存在の原型をあぶり出しているのではないだろうか。
今回の「東京ポートレイト」展で発表されたもうひとつのシリーズである「街のポートレイト」の凄みは、6×6判カメラの真四角のフレームの中にひしめく建物や看板の「間」に潜んでいる。シュルレアリスムの美学を思わせる、意表をついた異質な要素の組み合わせの隙間から、どこか不気味であり、笑いを誘うようでもある、なんとも奇妙な気配が立ちのぼってくるのだ。狙いを定めて獲物を撃つような浅草の人物写真と比較すると、鬼海の街の写真には投げやりとは言わないが、被写体の自律性に身をまかせる放心の態度を感じとることができる。それでもやはり、この一見優しげな「街のポートレイト」も相当に怖い。何気なく足を踏み入れると、やはり「魔」の世界に連れ去られて、帰って来られなくなりそうに感じるのだ。
鬼海弘雄は「魔」と「間」を自在に操る術を40年以上にわたって鍛え上げ、他の追随を許さない、そして写真という表現のメディウム以外では絶対に不可能な作品世界を確立してきた。その優れた成果を、今回の展示でしっかりと確認することができた。
2011/08/12(金)(飯沢耕太郎)
田附勝『東北』

発行所:リトルモア
発行日:2011年7月30日
東日本大震災を契機に多くの作品の意味が変わってしまった。田附勝の新しい写真集『東北』もそのひとつだろう。2006年から東北6県の「山の民と海の民」の暮らしぶり、祭りや年中行事、風景やオブジェを6×6判のカメラで丹念に蒐集・記録した写真集である。闇の奥からぐっと前に迫り出してくるような写真群は、魂を直に揺さぶるような迫力がある。こってりと、ディープな色味を強調したカラー写真も、前作『DECOTORA』(リトルモア、2007年)以来の田附のトレードマークとして定着してきた。
だが、「3・11」によって、彼のなかにこのまま写真集を出していいのかという疑いが芽生えたようだ。岩手県釜石市で撮影された「April 1, 2011」の日付がある2枚の写真が、巻末に付け加えられている。だが重要なことは、この写真集に写しとられている風土と人物のたたずまいそのものが、東北の地霊を呼び出すような力を秘めていることだろう。以前、岡本太郎が1950~60年代に撮影した日本各地の祭礼の写真を見ていて、東北と沖縄の写真だけが突出したエネルギーの波動を感じさせるのに驚いたことがある。田附の『東北』からも、この土地に縄文以来のシャーマニズムの伝統がしっかりと根づいていることが伝わってきた。
おそらく震災以後、東北は大きく変貌せざるをえないだろう。何が変わり、何が続いていくのか、できれば田附にはこれ以後も長く撮影を続けていってほしい。
2011/08/12(金)(飯沢耕太郎)
富士幻景 富士に見る日本人の肖像

会期:2011/06/09~2011/09/04
IZU PHOTO MUSEUM[静岡県]
伊豆や箱根に出かけると、富士山が見えるか見えないかというのがとても大事であることに気がつく。晴れ渡った青空に、くっきりと富士の姿が映えていると気分も晴れ晴れしてくるし、逆に雲に隠れているとなんだかがっかりしてしまう。現代の日本人にとっても、富士山は普通の山とはまったく違った思いを込めて仰ぎ見られているわけだ。今回の「富士幻景 富士に見る日本人の肖像」展は、その富士山のシンボル的な意味の変遷を、写真を中心に幕末・明治期から現代まで辿ろうという意欲的な企画である。
『ペリー艦隊日本遠征記』(1856年)の挿図として、E・ブラウン・ジュニアのダゲレオタイプ写真をもとにウィリアム・ハイネが描いた小田原湾から眺めた富士山から、外国人観光客向けのお土産用写真を再プリントした杉本博司の「横浜写真 明治20年代」(2007~2008年)まで、盛り沢山の展示は見応えがある。それを見ていくと、1945年の終戦前後にくっきりとした分水嶺があるのがわかる。幕末・明治期から第二次世界大戦までは、ひたすら富士山を「霊峰」、すなわち「皇国の象徴」として特権化していこうとする動きが目につく。草創期の写真館の書き割りに使われていたような、俗化した富士のイメージが、頭に白い雪を抱き、威風堂々と裾野を左右に伸ばす典型的なシンボリズムへと組織化されていくのだ。ところが、その聖なる富士のイメージ体系は、戦後になって完全に解体していく。濱谷浩『日本列島』(1961年)の地質学的なアプローチ、英伸三「北富士演習場の返還闘争」(1970年)の報道写真の視点、東松照明、藤原新也、森山大道、荒木経惟らの俗化し、日常化した富士等々、その多様に引き裂かれたイメージ群は、まさに激動の戦後の社会状況の反映と言えるだろう。野口里佳の「フジヤマ」(1997年)や松江泰治の「JP」(2006年)になると、もはや「富士山らしさ」のかけらすら見られなくなってしまうのだ。
この展覧会は、これからも続いていく「富士山から見る近代日本」シリーズの第一弾にあたるものだという。まさに富士を仰ぎ見る場所にあるIZU PHOTO MUSEUMにふさわしい企画。次回も楽しみだ。
2011/08/09(火)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)