artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
TOKYO FRONTLINE
会期:2011/02/17~2011/02/20
3331 Arts Chiyoda[東京都]
「ニュー・コンセプトのアートフェア」ということで、今年からスタートしたのが「TOKYO FRONTLINE」。元中学校の校舎をフルに使って、盛り沢山の展示が行なわれていた。若手アーティストたち(うつゆみこ、高木こずえを含む)の作品ショーケースとして設定された「FRONTLINE」(1F)、アート、写真、デザイン、音楽、出版などのプレゼンテーションブースが並ぶ「EXCHANGE」(同)、東京を中心に中国、韓国のギャラリーのブースも加えた「GYM」(2F)がメインの展示である。EMON PHOTO GALLERY(西野壮平)、ときの忘れもの(五味彬)、ユミコ・チバ・アソシエイツ(鷹野隆大)、ZEN FOTO GALLERY(中藤毅彦)、The Third Gallery Aya(垣本泰美、城林希里香)など、写真を中心に展示しているギャラリーも多かった。総花的で焦点が結びにくいのは、このようなアートフェアでは仕方のないことだろう。回を重ねれば、地に足がついたものになってくるのではないだろうか。
同時期に3331 Arts Chiyoda本体の企画で、「ギャラリーに属していないフリーの現代美術アーティスト」を中心とした展覧会も開催されていた。その枠で個展を開催していた西尾美也の「間を縫う」(2月11日~3月14日)がかなり面白かった。西尾は1982年奈良県生まれ。今年東京藝術大学大学院博士課程を修了予定である。衣服とコミュニケーションが彼の主なテーマで、「セルフ・セレクト」シリーズはナイロビやパリで出会った若者たちと自分が着ている服を交換するというプロジェクト。「家族の制服」は、西尾本人の家族が20年前の記念写真とそっくりの服を着て、同じ場所で同じポーズを決めるという作品である。どちらも記念写真の様式をうまく使いこなして、知的な笑いを生み出していた。
2011/02/16(水)(飯沢耕太郎)
星玄人「大阪」

会期:2011/02/11~2011/02/20
サードディストリクトギャラリー[東京都]
星玄人はサードディストリクトギャラリーのメンバーのひとり。これまで同ギャラリーで、新宿界隈を中心に撮影したスナップショットを展示してきたが、今回は大阪という新たなテーマに取り組んだ。2010年11月、12月、11年1月に3回足を運び、集中して撮影した成果だという。
もともと彼のスナップは、撮影する自分を透明化することなく積極的に被写体の前に晒し、火花が散るような視線の交錯を写真に刻みつける力業である。この「大阪」でもそのやり方は貫かれているが、被写体との距離感が微妙に違っているように感じる。やや引き気味に、あらかじめ写真のフレームを舞台として設定し、そこに一癖も二癖もある大阪の人物たちを呼び込むようにして撮影しているのだ。こちらから相手の領域を侵していくような緊張感や不穏な気配は薄らいだものの、逆に人物たちが勝手気ままにポーズを決め、自己主張している面白さが出てきた。大阪人のなかに色濃くある演劇的な資質を、巧みな舞台設定と隅々までシャープに、等価に照らし出すストロボ光の効果で引き出すことに成功しているのだ。会場には西田佐知子の昭和歌謡が流れ、大阪のあの独特の極彩色の空間に、さらに情緒たっぷりの彩りを添えていた。
「大阪」はまだ撮り終えたわけではない。だが、この手法は他の都市でも活かすことができそうだ。星自身も充分に自覚しているようだが、昭和の匂いがする都市空間やエネルギッシュだが哀感が漂う人物たちは、いまやどんどん消えつつある。「まだ間に合ううちに」、その姿を記録に留めておくことが必要になってきている。
2011/02/13(日)(飯沢耕太郎)
川俣正「フィールド・スケッチ」
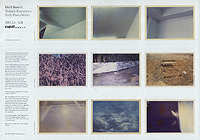
会期:2011/02/04~2011/03/21
NADiff a/p/a/r/t[東京都]
川俣正は東京藝術大学美術学部在学中の1976年から数年にわたって、中古のカメラでスナップを撮影し、L判のサービスサイズにプリントするという試みを続けたことがあった。今回の展示はそのなかから選ばれた630枚の写真を15枚ごとのブロックに分けて、壁にモザイク状に展示している。かなり褪色が進んだり、染みが浮き出したりしているような写真もあり、チープなプリントに時の厚みを感じさせる奇妙な物質性が生じているのが興味深かった。
内容的には、例えば人間の顔のような特別な意味を持つ被写体は注意深く避けられている。これらの「フィールド・スケッチ」の成果は後になって「室内の壁や天井や何の変哲もない一角を写した『宙吊りの部屋』、街中で日常の何気ない物体を写した『ファウンド・オブジェクツ』、光、あるいは境界をモチーフに撮影された『反射と透過』」という3つのセクションに分類された。さらに時間の経過に従って、少しずつアングルを変えながら連続的に被写体を撮影していく、シークエンスの手法が多用されているところにも特徴がある。つまり、20歳代前半のこの時期に、川俣はすでに後年のインスタレーション作品につながる対象のシステム化、多層化、連続性の導入などの要素を作品に取り入れつつあったということだろう。
逆にいえば、彼の写真という表現メディアの使い方は、ロジカルかつ抑制的なもので、あまり揺らぎやふくらみを感じることができない。ただそのなかに一枚だけ、差し伸ばした自分の手を上から撮影した写真があって、その妙に生々しいたたずまいがなぜか強く目に残った。
2011/02/12(土)(飯沢耕太郎)
北川健次「リラダンの消えた鳥籠」

会期:2011/02/09~2011/02/27
tmh.SLEEP[東京都]
北川健次はキャリアのある版画家、オブジェ作家。以前から作品のなかに写真が登場することが多く(例えばマイブリッジの動物の動きの連続写真)、しかもそれがとても的確に使われているのに注目していた。写真にかなり関心があるとは思っていたのだが、すでに何度か個展の形で写真作品を発表しているということを本人からうかがってびっくりした。今回の個展で発表された作品を見ると、たしかに余技の範囲を超えた仕事である。
恵比寿の瀟洒なジュエリー・ショップの壁に並んでいるのは、2年前にヴェネツィアで撮影したというスナップショット。建築物、彫刻、衣裳などの一部を自在に切り取って、光と影のコントラストの強いモノクローム(一部カラー)の画面にまとめている。プリントの段階で画像を重ねている作品もあるが、むしろストレートなプリントの方が多い。版画やオブジェ作品のように、コラージュ的にイメージを繋ぎ合わせたり衝突させたりする効果を狙うよりも、カメラのファインダーに飛び込んでくる被写体を狙い撃ちしているという印象だ。偶発性に身をまかせる方が、スナップとしての強度は上がってくるという逆説をきちんと踏まえているということだろう。「〈写真〉とは、夢と現実とのあわいに揺蕩う、一瞬の光との交接である」。案内状に記された北川のコメントだが、その通りとしかいいようがない。写真家としての構えが最初からきちんとできあがっているということがわかる。イタリアやフランスに題材を求めるのもいいが、むしろもっと日常的な場面に「一瞬の光との交接」を探り当ててほしいとも思う。
なお、会場の隣室にあたるLIBRARIE6でも同時期に北川の「十面体─メデューサの透ける皮膚のために」展を開催している。こちらは手慣れた版画+ドローイング作品だが、写真作品とはまた違った錬金術的なイメージ操作を愉しむことができた。
2011/02/10(木)(飯沢耕太郎)
横田大輔「indication」

会期:2011/02/07~2011/02/24
ガーディアン・ガーデン[東京都]
横田大輔は第2回写真「1_WALL」展(2010年)のグランプリ受賞者。小山泰介、和田裕也、吉田和生ら、僕が「網膜派」と呼んでいる写真家たちに共通する作風の持ち主だ。デジタルカメラを使い、あまり強固な意味を派生しない被写体の触覚的な要素を強調して撮影し、アトランダムに並べていく。結果として、観客は網膜の表層を引きはがしてそのまま提示したような画像の集積を見ることになる。横田の場合、その作業はかなり意識的に為されていて、どうやら動画モードで撮影した画像から選択してプリントしているようだ。ボケ、ブレ、画像の傾き、ストロボ光による極端な明暗のコントラストなどを多用することで、日常的な視点に違和感を生むのも彼らに共通する手法だ。
大小のプリントを虫ピンで壁に止めていく展示構成は、なかなかスタイリッシュで決まっている。悪くはないのだが、ただセンスがいいだけではこれから先が難しくなりそうだ。展覧会に合わせて発行された小冊子に彼が書いていたエピソードが面白かった。電車の中でたまたま見かけた男女を、横田はてっきり兄妹だと思っていたのだが、実はまったくかかわりのない女の子とストーカー的な男の組み合わせだったというちょっと不気味な話だ。こういう日常的なズレの感覚と「網膜派」の手法を、もっと積極的にかかわらせてみるのはどうだろうか。横田にはいい観察力と、言葉を的確に綴る才能も備わっているようなので、逆に画像の意味づけを強めて「物語」を構築していくと、独特の作風に育っていきそうな気もする。
2011/02/09(水)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)