artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
ニュー・スナップショット

会期:2010/12/11~2011/02/06
東京都写真美術館 2F展示室[東京都]
「日本の新進作家展 vol.9」として「スナップショットの魅力」展と併催されているのが「ニュー・スナップショット」展。出品作家は、池田宏彦、小畑雄嗣、白井里美、中村ハルコ、山城知佳子、結城臣雄の6人である。
中村ハルコの作品がこういうかたちで紹介されることが、まずとてもよかったと思う。彼女は2000年に自らの出産体験に題材を得た「海からの贈り物」で写真新世紀のグランプリを受賞し、将来を嘱望されていた。ところが2005年に43歳という若さで膵臓がんのため夭折する。今回展示された「光の音」は、イタリア・トスカーナ地方で農業を営む一家を何度となく足を運んで撮影し続けたシリーズで、生前にはきちんとしたかたちで発表されることがなかったものだ。その心の昂りをそのまま刻みつけた、弾むようなスナップショットを見ていると、もっとこの先を見てみたかったという思いにとらえられる。それはそれとして、土地と人とのかかわりを感情や生命力の流れとして見つめ返す「女性形」のドキュメンタリー写真の可能性を強く示唆する作品といえるだろう。
だが今回の展覧会でいえば、後半のパートに展示されていた山城知佳子、白井里美、池田宏彦の作品の方が「ニュー・スナップショット」という趣旨にふさわしいといえそうだ。彼らの仕事は、それぞれ沖縄、ニューヨーク、イスラエルのネゲヴ砂漠を舞台に、パフォーマンスや演出的な要素を強く打ち出している。土門拳は1950年代に「リアリズム写真」を提唱し、「絶対非演出の絶対スナップ」というテーゼを主張したが、そこから時代は大きく隔たってしまったということだろう。もはやスナップショットとパフォーマンスは相容れないものではなく、時には見分けがつかないほどに入り混じっていることさえある。だが、演出過剰な作品が面白いかといえば、必ずしもそうとは言い切れない。どこか「見えざる神の手」に身を委ねるようなところもあっていいはずで、写真家たちにはそのあたりのバランス感覚が求められているのではないだろうか。
2011/01/06(木)(飯沢耕太郎)
スナップショットの魅力

会期:2010/12/11~2011/02/06
東京都写真美術館 3F展示室[東京都]
2011年の仕事始めということで、まず東京都写真美術館に足を運ぶことにした。スナップショットをテーマにした収蔵作品展(一部に個人蔵を含む)と新進作家展が、「かがやきの瞬間」という共通のコンセプトのもとに開催されている。昨年中に行こうと思っていたが、ゆっくり見る余裕がなかったのでそのまま新年まで持ち越していた展示だ。
マーティン・ムンカッチ、ジャック=アンリ・ラルテーィグ、木村伊兵衛らのクラシックな作品から、鷹野隆大やザ・サートリアリストのような現代写真家の作品まで、「吹き抜ける風」「こどもの心」「正直さ」という3部構成で見せるのが「スナップショットの魅力」展。こうして名作ぞろいの展示をじっくり眺めていると、スナップショットがずっと写真という媒体の持つ表現可能性の中心に位置づけられてきた理由がよくわかる。たしかに、現実世界から思っても見なかった新鮮な眺めを切り出してくるスナップショットには、他にかえ難い「魅力」が備わっているのだ。ウォーカー・エヴァンズが1938~41年にニューヨークの地下鉄の乗客をオーバーコートの内側に隠したカメラで撮影した「サブウェイ・ポートレート」シリーズなどを見ていると、見る者の視線が写真に貼り付き、画像の細部へ細部へと引き込まれていくような気がしてくる。目を捉えて離さないその吸引力には、どこかエクスタシーに誘うような魅惑が備わっているのではないだろうか。
だが、何といっても今回の展示の最大の収穫は、ポール・フスコの「ロバート・F・ケネディの葬送列車」のシリーズ25点を、まとめて見ることができたことだろう。1968年に暗殺された「RFK」の棺を乗せた葬送列車は、1968年6月5日にニューヨークのペン・ステーションからワシントンDCまで8時間かけて走った。『ルック』誌の仕事をしていたフスコは、沿線で列車を見送る人々の姿をその車窓から撮影し続ける。だが2,000カットにも及ぶそれらの写真は結局雑誌には掲載されず、2000年に写真集にまとめられるまでは日の目を見なかった。黒人、白人、修道女、農夫、軍服を身に着けた在郷軍人からヒッピーのような若者まで、そこに写っている人々はそのまま当時のアメリカ社会の縮図であり、その表情や身振りを眺めているだけでさまざまな思いが湧き上がってくる。偶発的な要素が強いスナップショットが、時に雄弁な時代の証言者にもなりうることを、まざまざと示してくれる作品だ。
2011/01/06(木)(飯沢耕太郎)
木村友紀「無題」
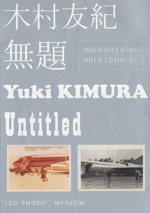
会期:2010/09/05~2011/01/11
IZU PHOTO MUSEUM[静岡県]
2010年の最後に木村友紀の展覧会を見ることができて本当によかった。IZU PHOTO MUSEUMの展示は会期が長いので、逆にうっかりするとまだまだと思っているうちに見過ごしてしまうことになりかねない。この展覧会も危うくそうなりかけていたのだが、年末近くになって何とか間に合った。
木村友紀の作品は、さまざまな写真を蒐集するところからはじまる。自分が撮影したものもあるが、家族のアルバムの中から見つけだしたもの、滞在先の街の「蚤の市」のような場所で買い集めたもの、友人から送られたものなどもある。つまり自分自身の制作物、所有物として徴づけられたものはむしろ少なく、多くは「他者」に帰属するものだ。木村はそれらを大きく引き伸ばし、再配置し、写真同士、また他のオブジェなどと組み合わせてインスタレーションする。その手際がとても洗練されていて、見ていて実に楽しい。
たとえば、どこともしれないオフィスを撮影した写真の前には、鉢植えの観葉植物が写真に触れるように置かれているが、それは写真の中に写っている観葉植物と対応するものだ。黒胡椒の実が写真の上に散乱しているインスタレーションがあるが、それは写真の中の雑然としたモノの状態に呼応している。また、海外で購入したセピア色に変色した飛行機の前半分のカラー写真には、祖父のアルバムに貼られていたというモノクロームの「飛行機型のハリボテの建物」のイメージがつけ合わされている。
つまり、木村の作品は「内と外」「自己と他者」「イメージの内側の世界と外側の現実の世界」との対応関係を、巧みな操作によって浮かび上がらせるところに特徴がある。そのことによって彼女がもくろんでいるのは、写真をある特定の意味や文脈に固定することなく、開放的な場に解き放ち、さまざまな形のイマジネーションを発動する装置として、積極的に「利用」していくことだろう。その作業を目にすることで、鑑賞者もまた、映像を巡ってめまぐるしく飛躍し、変転していく彼女の思考の渦に巻き込まれていく。その巻き込まれ方に、固い殻が破れて液体化していくような妙な快感がある。以前は彼女の作品には、底意地の悪さ、微妙な悪意を感じさせるものが多かった。それが今回はほとんど鳴りを潜めているのがちょっと気になる。木村にはただの趣味のいいインスタレーション作家にはなってほしくない。もちろん、本人もそのあたりは十分に承知しているとは思うのだが。
2010/12/26(日)(飯沢耕太郎)
石川直樹『CORONA』

発行所:青土社
発行日:2010年12月20日
このところ、毎年年末になると石川直樹から立派なハードカバーの写真集が送られてくる。それとともに、「ああ、また木村伊兵衛写真賞の季節だな」と思うことになる。石川がここ数年、木村伊兵衛写真賞の最終候補に残っては落ち続けているのは周知の事実だろう。これまでの経歴、業績とも申し分なく、今後の写真界を担っていく期待の人材であることは誰しもが認めつつ、どういうわけか受賞を逃し続けている。もちろん、こういうことは文芸や美術の世界でもありがちなことで、ある賞に縁が遠いというか、選ばれないでいるうちにますます選びにくくなってしまうというのは珍しいことではない。そうなると本人も意地になってしまうわけで、石川の場合も「今年こそは」という思いが写真集作りのモチベーションを高めているのは間違いないだろう。それにしても、毎年ボルテージを落とさずに、力のこもった写真集を出し続けるエネルギーには脱帽するしかない。
というわけで、今年の『CORONA』はどうかといえば、残念ながら、僕が見る限りは絶対的な決め手は感じることができなかった。「ハワイ、ニュージーランド、イースター島を繋いだ三角圏」、その「ポリネシア・トライアングル」を10年にわたって旅して撮影してきた労作であることは認める。昨年の日本列島の成り立ちを探り直す『ARCHIPELAGO』(集英社)の延長上の仕事として、過不足のない出来栄えといえるだろう。だが、これはいつも感じることだが、写真の配置、構成、レイアウトにもう一つ説得力がない。スケールの大きな神話的なイメージと、旅の途中での日常的なスナップをシャッフルして繋いでいく手法は、これまでの写真集でも試みられたものだが、どうも雑駁でとりとめないように見えてしまうのだ。「これを見た」「これを見せたい」という集中力、緊張感を感じさせる写真の間に、それらを欠いた写真が挟み込まれることで、見る者を遠くへ、別な場所へ連れ去っていく力が決定的に弱まってしまう。
石川は一度立ち止まって、自分の写真、自分が見てきたもの、伝えたい事柄についてじっくりと熟考する時期に来ているのではないだろうか。もっと落ちついて、カメラをしっかりと構え、丁寧に撮影し、無駄な写真はカットし、イメージを精選してほしい。各写真にきちんとつけるべきキャプションが割愛されているのも、おざなりな印象を与えてしまう。既にキャリアのある写真家にこんなことを書くのは失礼だとは思うが、雑な撮り方、見せ方をしている写真が多すぎるのではないか。石川が今回、木村伊兵衛写真賞を受賞できるかどうかは僕にはわからない。だが、もし取れたとしても、取れなかったとしても、彼の行動力と構想力に対する期待感の大きさに変わりはない。納得できる写真集、写真展をぜひ見たいと思っている。
2010/12/25(土)(飯沢耕太郎)
京都写真展

会期:2010/12/21~2011/12/26
ギャラリーマロニエ[京都府]
京都在住の写真家たちを中心に、年末の京都で開催される「京都写真展」。今年は11回目を迎え、「時間論」をテーマに25人の写真家たちが出品している。出品作家はアイウエオ順に浅野裕尚、石原輝雄、市川信也、岩村隆昭、奥野政司、金井杜道、金澤徹、木下憲治、小池貴之、小杉憲之、後藤剛、ササダ貴絵、新治毅、杉浦正和、鈴鹿芳康、須田照子、中島諒、宮本タズ子、村中修、森岡誠、森川潔、安田雅和、矢野隆、薮内晴夫、山崎正文である。
ベテラン作家が多く、表現の水準が安定しているので、毎回安心して見ていられるのだがやや活気に乏しい印象があった。だが今回は意欲作が多く、なかなか充実した展覧会に仕上がっていた。前回までは「風景」がテーマだったのが、今回から「時間論」に変わったのが大きいのかもしれない。いうまでもなく、「時間」は写真の最大の表現要素の一つであり、発想がより多様な形に展開できる。今回の出品作にも、金井杜道や奥野政司のように過去に撮影した旅のスナップを再プリントする者もあれば、森岡誠のブレを活かした表現、鈴鹿芳康の合掌する僧侶の手のクローズアップのような、哲学的な解釈に走る者もいる。マン・レイの研究家としても知られる石原輝雄は、郵便物、絵葉書、書籍、シャンパンのコルク、自分自身の古い肖像写真を組み合わせた、興味深いインスタレーションを試みていた。来年以降も面白い展示が期待できそうだ。
なお、ほぼ同時期に、京都市内のギャラリーカト、ヤマモトギャラリー、同時代ギャラリー、ギャラリーマロニエでは「How are you, PHOTOGRAPHY?」
展が開催された。こちらは15回目、のべ参加人数は1500人を超えるという、年末恒例のグループ展である。出品作家は「京都写真展」とも重なっているが、より幅が広く、写真をはじめたばかりの初心者でも気楽に参加できる。こういうイベントが毎年途切れることなく続いているところに、京都という場所の文化的な懐の深さが感じられる。
2010/12/22(水)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)