artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
村上友重「それらすべてを光の粒子と仮定してみる」

会期:2010/10/29~2010/11/25
CASHI[東京都]
タイトルがとてもいい。「それらすべてを光の粒子と仮定してみる」というのは、写真家のものの見方の基本といってよいだろう。そのことで何が見えてくるかといえば、世界は光の粒子の物質的な集合であり、その疎密によって形成された、あらゆる部分が等価な構造体であるということだ。写真家はその流動的な構造体を、予断のない眼差しで切りとっていく。その結果として、写真家本人にもまるで予想がつかなかったようなイメージが立ち現われてくることがある。その驚きを写真家と観客が共有する時にこそ、写真を「見る」ことの歓びがあふれ出してくるのだろう。
村上友重の今回の個展の作品には、そのような歓ばしい、幸福な気分がしっかりと定着されていた。正直、以前の彼女の作品には、ややひ弱で優等生的なそつのなさを感じてしまうことがあった。だが、どうやらスケールの大きな写真作家への道を、迷うことなく歩き始めたようだ。巨大なロールサイズの印画紙にプリントされた飛行機の光跡のシリーズなど、思いきりよく余分な部分を切り捨てることで、「自分はこのように見た」という確信をさわやかに主張している。逆に「山肌に霧」や「霞む船」といった、霧や水蒸気が画面の全体を覆っているような作品では、「見えそうで見えない」曖昧なイメージを、切り捨てることなく抱え込もうとする。世界に向けられた眼差しが以前より柔軟になり、強靭さをともなってきているのだ。
だが、むしろここからが正念場だろう。村上友重という写真作家が何者なのか、そろそろ、もう少しクリアーに見えてくるような決定的な作品がほしい。
2010/11/12(金)(飯沢耕太郎)
鈴木清 写真展 百の階梯、千の来歴

会期:2010/10/29~2010/12/19
東京国立近代美術館[東京都]
鈴木清が亡くなったのは2000年3月。時の流れの速さに愕然とするのだが、没後10年にあたる今年に回顧展が、しかも東京国立近代美術館というベストの会場で実現したのは本当によかった。「ようやく」という気がしないでもないが、逆に彼の仕事があらためて広く評価されるためには、10年という時間が必要だったともいえる。彼の過剰ともいえる写真集や写真展への執着、果敢な実験精神には、それくらいの期間がないと追いつけなかったということだ。
今回の展示は彼が生涯にわたり、惜しみなく精力を注いで刊行し続けた写真集(1冊を覗いては自費出版)に収録された写真を中心に構成されている。『流れの歌』(1972年)から『デュラスの領土』(1998年)に至る8冊の写真集は、イメージとテキストの混在、写真のくり返し、入れ子構造(写真集の中の小写真集)、折り込み、観音開きなど、ありとあらゆるブック・デザインの手法を駆使した魔術的とさえいえる「書物」である。そのカオス状の構造体を、美術館の展示で再現するのは不可能であり、むしろ見やすくきっちりと写真が並べられていた。だが、大きさを変えてプリントされた同じ写真が何度かあらわれたり、写真集そのものを閲覧するコーナーが設けられたりするなど、鈴木清の作品世界の追体験の場としてとてもうまく機能していたと思う。
だが、今回の展覧会で特別な輝きを放っていたのは、あの伝説的な「ダミー写真集」の展示ではないだろうか。鈴木清は写真集の刊行に向けて、必ず自分の手で「ダミー写真集」をつくっていた。彼は故郷の福島県いわき市で、定時制高校に通いながら印刷所の見習いをしており、写真集のレイアウトや文字組はお手の物だったのだ。これら写真をコピーしてテキストを貼り付けた「ダミー写真集」は、持ち歩いているうちに擦れたり汚れたりして、次第に独特の物質感を備えたオブジェと化していく。その風格や存在感は、完成した印刷物としての写真集をはるかに凌駕しているともいえる。というより、彼の写真集づくりの思考と実践のプロセスが、生々しく刻み込まれた「ダミー写真集」こそ、むしろ彼の作品世界の中心に位置していたようにも思える。
驚かされたのは、1996~98年にコニカプラザ東ギャラリーで開催された連続展「デュラスの領土」のための「個展プラン」である。サインペンや色鉛筆でさっと描かれた、見事としかいいようのないドローイングは、彼の優れたデッサン力をまざまざと示している。頭に思い浮かんだイメージを、さっと形にしていく能力の高さは天性のものがあったのだろう。このデッサン力があったからこそ、一見無頓着に見える彼の写真にも。しっかりとした骨組みを感じとることができるのだ。
この展覧会が、日本における鈴木清評価の第一歩になることを期待している。特に鈴木清の名前すら知らなかった若い世代にぜひ見てほしい。同時に刊行された彼のデビュー写真集『流れの歌』の完全復刻版(白水社刊)も素晴らしい出来栄えである。写真凸版(活版)印刷が、スミとグレーの二色刷りオフセット印刷に置き換えられているのだが、その黒が締まった重厚な印刷は、原本と比べても遜色がない。
2010/11/10(水)(飯沢耕太郎)
澤田知子「Mirrors」
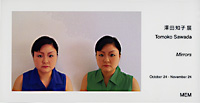
会期:2010/10/24~2010/11/24
MEM[東京都]
現在はニューヨークを拠点に活動している澤田知子。今回も相変わらずの「セルフポートレート」だが、以前の作品とは微妙に印象が違って見える。前はどれだけ違ったタイプの人物に、どれだけ大きな幅で変身できるかが目標のようなところがあったのだが、近作になるにしたがってより微細な差異にこだわり始めた。今回の「Mirrors」は一卵性の双子がテーマで、よく似た二人の人物が並んでこちらを見ているポートレートのシリーズである。いうまでもなく、どちらの人物も澤田自身が演じているのだが、髪型、メーキャップ、衣裳などを微妙にいじって変えている(まったく同じように見える作品もある)。その細かな違いを見比べているうちに、自分と同じ顔の人物がもうひとりいるという、あの双子という存在につきまとう奇妙な違和感=恐怖感がじわじわと形をとってくるのに気がつく。旧作のような派手さはないが、玄人好みのいいシリーズだと思う。
ちょっと思い出したのはザ・ピーナッツのこと。1960~70年代に人気があった双子歌手だが、彼女たちの鼻の横にはホクロがあって、その位置の違いで二人の区別がつくようになっていた。澤田知子も鼻の下にホクロがある。実はそのホクロを目の横に移動させた作品が一点だけある。だが、他の作品ではホクロは元の位置のままだ。それが妙に気になってしまった。ホクロの移動をもっと積極的に試みると、面白い効果を生むのではないだろうか。
2010/11/09(火)(飯沢耕太郎)
松江泰治「suevey of time」

会期:2010/10/23~2010/11/20
TARO NASU[東京都]
写真作品15点と、映像作品7点による展示。初期作品(1987年発表の「TRANSIT」)と新作のビデオ作品(「suevey of time」)という組み合わせは、10月に同じ会場で開催された宮本隆司展とまったく同じである。ギャラリーの企画意図があるのかと思ったのだが、「まったくの偶然」なのだそうだ。だが、このところ強まりつつある、写真を中心に発表してきた作家が映像にも触手を伸ばそうとしているという傾向のあらわれといえるだろう。フル・ハイビジョンカメラの登場とモニターの性能のアップによって、写真家たちも充分に納得できる画像レベルをキープできるようになったことが、その背景にありそうだ。
「TRANSIT」は松江泰治の個展デビュー作で、その頃はまだ東京大学理学部地理学科を卒業したばかりだったはずだ。在学中から撮りためていた35ミリフィルムを使った路上スナップには、当時彼が私淑していた森山大道の影響が色濃い。だが同時に、その後の松江の代名詞となった、大判カメラによる「Landscape」シリーズにつながっていく要素もはっきりと見てとれる。画面全体を、地上に遍在する事物の表層の連なりとして、等価に把握していく視点が見事に一貫しているのだ。彼の作家活動の原点を、あらためて確認できたのがとてもよかった。
新作の「suevey of time」は意欲作である。撮影されている風景は、松江のこれまでの作品でおなじみの場所であり、視点を高くとるカメラ・ポジションも共通している。フルハイビジョンの画像は鮮明で、一見するとスチル・カメラで撮影された作品のようだ。ところが、画面を眺めていると自動車や人物が横切ったり、道端の猫や草原で草を食んでいるリャマがわずかに移動したりして、それが動画であることがわかる。さらに画像がループ状につながっているので、そのつなぎ目の場所にくるとイメージがふっと消えて、わずかに違った場所に再び出現したりする。静止画像と動画との違いを逆手にとって、事物を「見る」という行為を再検証しようとしているのだ。「時間」という体験そのものの映像化の試みという見方も成り立つだろう。宮本隆司もそうなのだが、松江も作品の発想そのものが、よりフレキシブルなものに変わりつつある。
2010/11/09(火)(飯沢耕太郎)
韓超(ハン・チャオ)「私の惨めな小宇宙への狂詩曲」

会期:2010/11/05~2010/11/21
ZEN FOTO GALLERY[東京都]
韓超(ハン・チャオ)とはじめて会ったのは、2010年4月に中国・北京郊外で開催された「草場地春の写真祭」の関連企画として開催されたポートフォリオ・レビューの会場だった。この時は、北京在住の写真家を中心に10人余りの作品を見たのだが、そのなかで最も強い輝きを放っていたのが彼の写真だった。ポートフォリオ・レビューには、ZEN FOTO GALLERYのオーナーのマーク・ピアソンもレビュアーとして参加しており、彼もやはり韓超の仕事に目をつけていたようだ。その縁で、25歳というまだ若い彼の最初の個展を東京で開催することになったのは、とても素晴らしいことだと思う。
韓超のテーマは、ゲイである彼のプライベート・ライフである。もちろん、この種の写真は欧米諸国でも日本でもたくさんあって、とりたてて珍しいものではない。とはいえ、まだ差別や蔑視の感情が強い中国で、ゲイとしてカミングアウトして生きていくのは相当な困難がともなうはずだ。そんな社会との軋轢、厳しい人間関係が、彼の写真に強い緊張感や不安感をともなって写り込んでいる。だが基調となっているのは、そのようなネガティブな感情ではなく、むしろ「愛と写真」の力を信じて、自分と男友達、そして家族などの姿をしっかりと記憶に刻みつけておこうとする彼の強い意志だ。それが彼の写真に、触れれば火傷しそうな熱と、どこか冷ややかな距離感とを同時にもたらしている。ポートレートもいいが、部屋のインテリアや花などをさりげなく撮影したスナップにも実感がこもっていて、じっと見入ってしまうような力がある。
写真家としての才能に恵まれた彼が、それをこのまま順調に伸ばしていくことができるといいのだが。
2010/11/08(月)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)