artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
マン・レイ展 知られざる創作の秘密

会期:2010/07/14~2010/09/13
国立新美術館[東京都]
マン・レイの展覧会はこれまで何度も開催されているが、300点を超えるという今回の展示の規模は最大級といえる。特に興味深かったのは、1930年代までのニューヨーク・パリ時代よりも、1940~51年のロサンゼルス時代や、1951~76年の晩年のパリ時代の方が展示の比重が大きくなっていることだった。これは今回の出品作品の多くが、4,000点以上というニューヨーク州ロングアイランドのマン・レイ財団のコレクションから選ばれているためだろう。ややうがった見方をすれば、マン・レイの最期を看とったジュリエット・ブラウナー夫人の関係者が牛耳るマン・レイ財団が、あえてキキ、リー・ミラー、メレット・オッペンハイムなどの、マン・レイの華麗な女性遍歴に関係する作品の出品を制限したと見えなくもない。
とはいえ、未見の作品が大量に出品されており、この万能のアーティストが、まさに花を摘んでは撒き散らすように、軽やかに、楽しみつつさまざまな分野の作品を制作していった過程がくっきりと浮かび上がってきていた。たとえば1950年代の、カラーポジフィルムの裏面に特殊な溶液を塗って「色彩の輝度を保ちつつ、絵のような質を」生み出す技法で制作されたプリントなどは、今回はじめてきちんと紹介されたものだろう。第二次世界大戦後は、あまり写真に興味を示さなくなったといわれるマン・レイだが、やはり同時期にはポラロイド写真の撮影も試みている。彼が最後まで実験的な写真家としての意識を持ち続けていたというのは嬉しい発見だった。
2010/08/26(木)(飯沢耕太郎)
長島有里枝『SWISS』
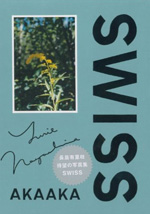
発行所:赤々舎
発行日:2010年7月2日
文章家としての長島有里枝の才能に気づいたのは、2009年に刊行された『背中の記憶』(講談社)を読んだ時だ。『群像』に連載された短編をまとめたもので、幼い頃からの家族、近親者、友人たちの記憶を、糸をたぐるように辿り直した連作である。視覚的記憶を文章として定着していく手つきの、鮮やかさと細やかさにびっくりした。思い出したのは幸田文の『みそっかす』や『おとうと』といった作品群で、はるか昔に起こった出来事に対する生理的反応や感情の起伏を、正確に、くっきりと描写していく才能には、天性のものがあるのではないだろうか。同時に、長島の文章にはどこかスナップショットのような爽快さが備わっており、彼女の写真作品と共通する感触もある。
その長島の新作写真集が赤々舎から刊行された『SWISS』。2007年に5歳の息子とともに、スイスのエスタバイエ・ル・ラックにあるVillage Nomadeという芸術家村に3週間滞在した時の記録だ。日記と写真のページが交互に現われる構成になっており、ここでも日記のパートに彼女の文章力がしっかりと発揮されている。記述そのものは、芸術家村で出会った人びととの交友や、父親と別に暮らすことを選びとったばかりの息子との、3週間の間に微妙に変化していく関係のあり方が淡々と綴られているだけだ。だが、庭に咲き乱れる花々や室内の光景を中心に撮影した写真と、重なり合ったりずれたりしながらページが進むうちに、静かな生活の中に湧き起こる感情のさざ波が、生々しい実感をともなって感じられるようになってくる。そのあたりの呼吸が実に巧みで洗練されている。これまでよりもやや抑え気味に、被写体を凝視するように撮影された写真も、しっとりとした味わいで見応えがある。写真と文章とが、さらにみずみずしい関係を構築していく可能性を感じさせる仕事といえるだろう。
なお、特筆しておきたいのは、寄藤文平による造本・デザインのアイディアの豊かさと新鮮さ。紙質やレイアウトに気を配りつつ、物語を包み込む器をダイナミックに仕上げている。表紙の色が20パターンあり、自由に選べるというのも、あまり聞いたことがない。
2010/08/25(水)(飯沢耕太郎)
尾仲浩二「馬とサボテン」

会期:2010/08/17~2010/09/10
EMON PHOTO GALLERY[東京都]
尾仲浩二のような旅の達人になると、日本全国どこに出かけても、安定した水準で写真を撮影し作品化することができる。それどころか、その揺るぎないポジション取りと巧みな画面構成力は、外国でもまったく変わりがない。写真集『フランスの犬』(蒼穹舎, 2008)は、1992年のフランスへの旅の写真で構成されているし、EMON PHOTO GALLERYでは2007年に続く2回目の作品発表になる今回の「馬とサボテン」は、同年のメキシコへの旅がテーマだ。それでも、それぞれのシリーズに新しい試みを取り入れることで、彼なりに旅の新鮮さを保とうとしているようだ。それが今回は、パノラマカメラを使った写真群ということになるだろう。時には普通は横位置で使うカメラを縦位置にして、前景から後景までをダイナミックにつかみ取るような効果を生み出そうとしている。
その試みはなかなかうまくいっているのだが、基本的には日本でも外国でも被写体との距離の取り方がほぼ同一なので、安心して見ることができる反面、驚きや衝撃には乏しい。もっとも、尾仲のようなキャリアを積んだ写真家に、それを求めても仕方がないだろう。むしろそのカメラワークの名人芸を愉しめば、それでいいのではないだろうか。展示では、これまた名人芸といえるカラープリントのコントロールの巧さも目についた。メキシコには「尾仲カラー」とでもいうべき渋い煉瓦の色味の被写体がたくさんある。まるで闘牛場の牛のように、彼がその赤っぽい色にエキサイトしてシャッターを切っている様子が、微笑ましくも伝わってきた。
2010/08/19(木)(飯沢耕太郎)
トヨダヒトシ スライドショー上映「黒い月」

会期:2010/08/15
ヴァンジ彫刻庭園美術館 展示棟[静岡県]
ニューヨークと東京とを往復しながらスライドショーによる「映像日記」をつくり続けているトヨダヒトシ。彼の新作「黒い月」の上映会が、静岡県長泉町のクレマチスの丘にあるヴァンジ彫刻庭園美術館で開催された。トヨダ自身によるスクリプトによると、その内容は以下の通りである。
「初夏の日本/孤独感、疎外感による事件が矢継ぎ早に起った時期だった/7月の川/いつもの道/争いに勝った者の意見が正しいのか/鎌倉/「私にはなにもない」と/花/午後/丘の上は思ったよりも風が強かった/いくつもの野/どんな風景も完結はせず、ただ光があり、時間があった。闇があった。/暮らし/夜/約束/秋」
いつものように90分近くにわたって、2008年初夏から秋にかけて彼が見た眺めが無音のまま淡々と写し出される。それらをじっと見ながら、これまたいつものようにいろいろなことを考えていた。ひとつはトヨダの作品世界は入り組んだ地層のように連なっているということ。彼自身の日々の暮らし、出会った人びとからなる経験レベルでの映像の層があり、それを包み込むように無差別殺人事件やオバマ大統領の当選などの社会レベルでの映像の層がある。さらにもうひとつその下層(あるいは上層)に宇宙レベルとでも呼ぶべき映像群を抱え込んでいるのが、彼のスライド作品の特異性なのではないだろうか。それらは時に「空」や「月」のようなイメージとして提示されることがあるが、より特徴的なのは昆虫、花、苔などに向けられたミクロコスモス的な視点である。これらの微視的な映像群が挟み込まれることによって、彼の作品世界は個の日常世界から神話的といえそうな領域に越境していくことになる。
もうひとつ考えたのはスライドショーにおいて「言葉」が果たす役割で、これは時に諸刃の剣になりそうな気がした。特に今回の「黒い月」では、最後のパートにかなり長いモノローグが挿入されていて、それが相当に強い引力を発生させている。どうも近作になればなるほど、「言葉」の力が強まっていると感じるのは気のせいだろうか。映像と「言葉」のバランスをとっていくのは、トヨダのスライドショーにおいてつねに綱渡り的なスリリングな作業になる。そのバランスが崩れると、もともと彼の作品世界が孕んでいた開放的な多義性が一定の方向に固着してしまいかねない。その危うい分岐点が、今回のスライドショーで見えてきたように思った。
なお「黒い月」というタイトルは、仏教の暦で満月から新月までの間をさす言葉(黒月)から採られている。「元に戻っていく」という意味を含むこのシリーズは、新月から満月までをさす「白い月」のシリーズと同時並行して制作された。ニューヨークでの日々の映像から構成される「白い月」も既に完成しており、この秋いろいろな場所で上映される予定だ。トヨダの作品は、彼のスライドショーに足を運ばなければ見ることができない。彼のホームページなどの情報を参照して、とにかく一度ライブ上映を体験していただきたい。(http://www.hitoshitoyoda.com/)
2010/08/15(日)(飯沢耕太郎)
126 POLAROID──さよならからの出会い

会期:2010/08/07~2010/08/29
横浜美術館 アートギャラリー1[神奈川県]
2008年のポラロイドフィルムの発売中止の一報に反応して企画された「さよなら、ポラロイド」展。当初は多摩美術大学の萩原朔美の研究室を中心にした50人あまりの参加者だったのだが、東京、京都、大阪と展示が巡回する間に人数が増えて、今回の横浜展では126人に達した。その間に、サミット・グローバルという会社がポラロイドフィルムを再生産することになり、それにともなってタイトルも「126 POLAROID──さよならからの出会い」に変わった。
荒木経惟、石川直樹、石塚元太良、沢渡朔、島尾伸三、杉本博司、津田直、港千尋、森山大道、屋代敏博、若木信吾──出品者の中から目についた写真家の名前を50音順に並べてみただけでも、なんとも多彩で、スリリングな顔ぶれである。ポラロイドという表現手段にもともと備わっていた撮影者を「エキサイトさせる力」が、多くの人たちを動かしているということではないだろうか。実際に展示を見ると、その表現スタイルの多様性、何が出てくるかわからないワクワク感は驚くべきものがある。ポラロイドの魔法の力は、まだまだ衰えていないということだろう。
同時に開催されていた、20×24インチの大判ポラロイド作品の特別展示もかなり面白かった。1983~86年にかけて、重さ90キロ、高さ1・5メートルという巨大カメラを使って、石内都、石元泰博、植田正治、川田喜久治、内藤正敏、奈良原一高、深瀬昌久、藤原新也、森山大道ら17人の写真家たちが取り組んだプロジェクトの成果である。実にひさしぶりに石内都の「同級生」や深瀬昌久の「遊戯」などのシリーズを見ることができたのだが、ここでも写真家たちがポラロイドの表現能力を最大限に活かした「プレイ」を全身で楽しんでいる。もし、この巨大ポラロイドのシステムがまだ使用可能ならば、若手作家が再チャレンジするというのもいいかもしれない。なお、赤々舎から刊行された本展のカタログを兼ねた写真集『126 POLAROID──さよならからの出会い』も盛り沢山の、なかなか充実した出来栄えだ。
2010/08/13(金)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)