artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
林田摂子「箱庭の季節」

会期:2010/09/24~2010/10/03
Place M2 gallery[東京都]
新宿御苑前のPlace Mの階下に、もうひとつ新しいギャラリーが誕生した。名づけてM2 gallery。瀬戸正人が主宰する写真ワークショップ「夜の写真学校」のメンバーを中心に運営していくのだという。瀬戸、坂口トモユキに続く三人目の個展が林田摂子の「箱庭の季節」である。このシリーズは2000年、2009年に続く三回目の展示で、長崎の母方の実家とその周辺を撮影している。先頃ようやく写真集として刊行された『森をさがす』(Rocket)とともに、彼女のライフワークとして成長していってほしいシリーズだが、今回作品を見ながら「これでいいのだろうか」という思いを強くした。
林田はとても力のある写真家で、その撮影ぶりには安定感があり、写真を組み合わせて並べていく能力も高い。この「箱庭の季節」にしても、過去、現在、未来と連綿としてつらなっていく一族の暮らしの細部が的確にとらえられ、ゆったりとした時の流れを感じさせる気持ちのいい作品に仕上がっている。だが、このままだと緊張感を欠いた、穏やかなイメージが淡々と続くだけで終わってしまいそうな気もする。仮に波風が立つにしても、近親者の誕生や死のような予測の範囲内におさまってしまいそうだ。むしろ『森をさがす』のように、「物語」としての大胆で緊密な構築をめざすべきではないだろうか。いまのような「大河小説」ではなく、むしろ「短編」のつらなりのような構成の方が、このシリーズには向いているような気もする。
2010/09/26(日)(飯沢耕太郎)
「榮榮&映里 RongRong & inri」展
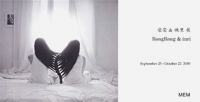
会期:2010/09/25~2010/10/22
MEM[東京都]
大阪の現代美術ギャラリー、MEMが東京に移転してきた。恵比寿のNADiff a/p/a/r/tの2Fというなかなかいいロケーションなので、所属作家の森村泰昌、澤田知子らを含む今後の展示活動が大いに期待できそうだ。
移転第一弾として開催されたのが榮榮(RongRong)と映里(Inri)の二人展。2000年に中国に渡った横浜出身の映里(本名、鈴木映里)は、90年代から身体的なパフォーマンスを作品化していた榮榮とのコラボレーションを開始する。最初の頃は、彼らの愛、歓び、孤独や疎外感などを激しくぶつけあう感情の振幅の大きい作品が多かったのだが、2001年に結婚し、3人の子どもが生まれ、2007年には北京郊外の朝陽区草場地に三影堂攝影芸術中心(Three Shadows Photography Art Centre)を設立といった出来事を経て、彼らの作風も少しずつ変化していった。近作では妊娠中の映里や子どもたちを加えた記念写真的なポートレート、DMにも使われた二人の長い髪の毛を結びあわせ、編み込んだ後ろ姿の作品など、安らぎ、自信、信頼感などが前面に出てきているように見える。今年の5月~7月には深圳のヘーシャンニン美術館で、2000~2010年の代表作170点を展示する大規模な展覧会を実現し、ヨーロッパやアメリカなどでの評価も高まりつつある。
むろん、彼らの写真作家としての意欲が衰えたわけではない。生と表現との深い関わりを、緊密かつヴィヴィッドに投影してきた二人の作品は、これから先も大きく変化しつつ深化していくのだろう。やや意外なことだが、今回が彼らの日本での初個展になる。もう一回りスケールの大きな会場での展示もぜひ実現してもらいたいものだ。
2010/09/26(日)(飯沢耕太郎)
私を見て! ヌードのポートレイト

会期:2010/07/31~2010/10/03
東京都写真美術館 3F展示室[東京都]
東京都写真美術館の所蔵作品を中心としたコレクション展は、今年は「肖像」をテーマとする連続企画展である。その第二弾として「ヌードのポートレイト」展が開催された。ヌード・フォトは多くの場合、「撮る側」(その多くは男性)の視点で語られることが多い。ところがこの展覧会は、タイトルを見てもわかるように「撮られる側」の自己主張=「私を見て!」に注目している。
たしかにヌード撮影には写真家とモデルの共同作業という側面があり、一方的な「撮る─撮られる」という関係が、なし崩しに解体してしまうこともありうる。ただし、展示の流れは「第1章 邂逅」「第2章 表現」「第3章 家族」「第4章 自己(アイデンテティー)」の四部構成で、写真の黎明期からピクトリアリズム、モダニズムの時代を経て、より対人的な関係意識が強い現代写真に至るというきわめてオーソドックス、というより紋切り型のもので、せっかく打ち出した「私を見て!」というモデルの側からの視点が貫かれているとは思えなかった。また、写真に付されたキャプションが、当たり障りのない解説に終始しているのも気になった。ラリー・クラーク、ナン・ゴールディン、ジョエル・ピーター・ウィトキンといった、むしろ丁寧な解説が必要な作品にキャプションがないのはどういうわけだろうか。「問題作」を避けたとしか思えないのが残念だ。
小関庄太郎の、女子学生をモデルにしたという1932年の連作、深瀬昌久の「幸代」シリーズ(1961年)など、あまり展示される機会がない作品をじっくり見ることができたのはよかった。まだまだ眠っている収蔵品がたくさんありそうだが、どうやらコレクション展の限界も見えてきたようだ。
2010/09/24(金)(飯沢耕太郎)
東京フォト2010

会期:2010/09/17~2010/09/20
昨年に続き第二回目の「東京フォト」が開催された。参加ギャラリーが30を超し、写真作品に特化したアートフェアという位置づけも、かなり明確になってきたようだ。観客もかなり入っているし、売り上げも全体としてみれば伸びている。2年目としてはまず成功といえるのではないだろうか。
写真作品をコンスタントに購入するコレクターの絶対数を増やすというのは、アート・ディーラーの永遠の課題のひとつだろう。日本の場合、1970年代からずっとそのことが模索されてきたにもかかわらず、最近までなかなか厳しい状況だった。それでも、今回の「東京フォト」を見ていると、写真作品のマーケットが広く認知されつつあることを感じる。ギャラリーやディーラーの側も、その動きに応えるように、作品をあまり大きくない、壁に掛けるのに適当なサイズに絞り込み、内容的にもあまり過激なものは避けるようになっている。顧客が安心して購入できる、評価の定まったマスター・ピースを中心に出品しているギャラリーも多かった。むろんそれは諸刃の剣で、当たり障りのない穏当な作品が整然と並んでいる様子を見ると、あまり面白味は感じない。昨年と比較しても、出品作品の均質化が急速に進みつつあるのがちょっと気がかりだ。
そんななかで、西野壮平の大画面のコラージュ作品をずらりと並べたエモンフォトギャラリー、イランの女性作家、ラハ・ラスティファードとヌーシャ・タヴァコリアンという新鮮なラインナップを選んだ東京画廊+BTAP、新進作家の春木麻衣子の作品だけで勝負をかけたTARO NASUなどの果敢な展示が目立っていた。「売れる」ことはむろん大事だが、こういうアートフェアはギャラリーの基本姿勢を推しはかる指標になることも否定できない。
2010/09/17(金)(飯沢耕太郎)
田村彰英「AFTERNOON 午後」

会期:2010/09/03~2010/10/30
gallery bauhaus[東京都]
上野修が本展に寄せたメッセージに次のように書いている。「かつて、日本現代写真における天才といえば、たったひとりの写真家を指したものだった。その写真家とは田村彰英である。写真でしかできない表現、写真としての写真が模索された1970年代、情念的にではなく、観念的にでもなく、まったく違ったアプローチで、いきなり直感的にそれを浮かび上がらせたのが田村だった」。
この上野の田村評には全面的に共感する。だが、1990年代以降に写真にかかわりはじめた若い観客にはぴんとこないところがあるのではないだろうか。今回の「AFTERNOON 午後」展には、彼が70年代初頭に『美術手帖』の扉ページに掲載した、6×6判カメラによるモノクローム作品が多数含まれている。これらの作品を同時代的に最初に目にした時の衝撃の大きさを伝えるのは、かなり難しいだろう。つまり彼が提示した、日本的な情感やドキュメンタリ─・フォトの臭みからは完全に一線を画した、光と影とが織り成す無国籍かつ断片的な情景は、その後の日本の写真家たちの作品の定石になってしまったからだ。やや無理な比較をしてしまえば、田村の登場は90年代後半に『生きている』(1997年)でデビューした佐内正史と似ている。佐内もまた「天才」としかいいようのない嗅覚で、バブル崩壊以後の日本社会の希薄な気分を掬いとっていったのだが、田村の写真に写り込んでいるものこそ、70~80年代の空気感そのものなのだ。
それから30年以上が過ぎて、あらためて見ることができた「AFTERNOON 午後」の写真群は、やはり僕にとって充分に魅力的だった。当時よりもさらに生々しさが削ぎ落とされ、まさに「写真でしかできない」世界の眺めが定着されている。それとともに、現像ムラ、画面の端の黒枠、引伸しの時に入り込んできたゴミなどがかなり無頓着に扱われているのが、妙に格好よく決まっている。ロック世代の、汚れたジーンスを颯爽とはきこなすような感覚が、写真にもあらわれている気がするのだ。
2010/09/16(木)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)