artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
寺田真由美「光のモノローグ Vol.II」/「不在の部屋」

- 光のモノローグ Vol. II
- 会期:2010/04/07~2010/04/26
日本橋高島屋 6階美術画廊X[東京都] - 不在の部屋
- 会期:2010/04/21~2010/05/30
練馬区立美術館[東京都]
このところコンスタントに発表の機会が増えている寺田真由美。ニューヨーク在住の彼女の作品は、基本的に紙やガラスなどでミニチュアの「部屋」を作り、それをモノクロームのフィルムで撮影、プリントするという手法をとっている。なぜミニチュアかといえば、寺田が表現しようとしているのは個人的な記憶がまつわりついている特定の場所ではなく、誰もが既視感を感じることができるような「どこにもない部屋」だからだ。窓、扉、カーテン、テーブルなどがある日常的な情景を扱っているにもかかわらず、その背後から浮かび上がってくる物語は、見るもの一人ひとりの記憶や経験によって微妙に異なったニュアンスを帯びる。むしろ、そのような差異を引き出してくる装置として、寺田の「部屋」は注意深く作り上げられているといえるだろう。
だが、日本橋高島屋6階美術画廊Xと練馬区立美術館でほぼ同時期に開催されたふたつの個展(練馬区美術館は企画展「PLATFORM 2010」として画家の若林砂絵子の「平面の空間」展と併催)を見ると、寺田の「部屋」の雰囲気がだいぶ変わりつつあるように感じた。以前は「部屋」の住人の不在が醸し出す喪失感がベースになっていたのだが、近作では主にセントラル・パークで撮影されている「部屋」の外の風景が迫り出してきており、そこを満たしている光や空気も軽やかに弾んでいるように感じられるのだ。哀しみから歓びへの段階的な変化は、当然ながら寺田自身の心境の変化に対応しているはずだ。そのことを、4月24日に練馬美術館でおこなわれた寺田とのトーク・イベントでも確認することができた。作家としての意欲があふれ、自信が芽生えてきている様子がうかがえる。いまは1980~90年代に制作していた立体作品も、作品に取り込んでいきたいと考えているという。次作が楽しみになってきた。
2010/04/24(土)(飯沢耕太郎)
原久路「バルテュス絵画への考察II」

会期:2010/04/06~2010/05/22
gallery bauhaus[東京都]
昨年、四谷のトーテムポールフォトギャラリーで開催されて好評を博した原久路の「バルテュス絵画の考察」のシリーズが、装いも新たにgallery bauhausで展示された。点数が9点から22点に増えるとともに、作品のサイズはかなり小さくなっている。gallery bauhausはメインの会場が地下にあって、やや内向きの雰囲気なので、それにあわせて一回り小さくプリントしたということのようだ。また、最終的にはデジタルプリンターで出力しているのだが、特殊なニスを5回も重ね塗りして画像の厚みと黒の締まりを出しているという。そういう丁寧な気配りと、画面を構築していく時の緻密な作業の進め方こそが、原の真骨頂と言えるだろう。
それにしても、バルテュスの代表作を写真に置き換えるという原の試みは、いろいろな問題を明るみに出すものだと思う。写真が19世紀半ばに発明されて以来、絵画と写真とはまったく別々の道を歩んできた。だが、21世紀になってデジタル化の進行ととともに、両者が融合したり合体したりするような可能性も大きく広がりつつある。原の絵画と写真の「ハイブリッド写真」はその答えのひとつであり、何者かに全身全霊で憑依していくような情熱の傾け方において、森村泰昌の一連の「美術史」シリーズとも通じるものがある。バルテュス作品の構図を日本の空間に置き換える時、セーラー服と学生服を選択したというのも興味深い。そのことによって、東西の衣裳文化が融合・合体するとともに、バルテュスの絵の中にある少年や少女イノセンスへの純粋な希求を、巧みに記号化することに成功しているからだ。次はよりデジタル処理を徹底した作品を作っていきたいとのこと。さらなる展開が大いに期待できそうだ。
2010/04/23(金)(飯沢耕太郎)
大和田良「Log」

会期:2010/04/22~2010/04/28
キヤノンギャラリー銀座[東京都]
大和田良は1978年仙台生まれ。2004年に東京工芸大学大学院を修了して、フリーの写真家として活動しはじめた。このところ急速に力を付けつつある30歳前後の写真家たちの代表格ともいえるだろう。2006年にスイス・ローザンヌのエリゼ美術館で開催された「ReGeneration: 50 Photographers of Tomorrow」展に選出され、2007年には写真集『prism』(青幻舎)を刊行するなど、早くからその仕事が注目されてきた。ただセンスのよさは感じるものの、いまひとつ狙い所がはっきりわからず、評価がむずかしいと感じていた。
だが、今回の個展(大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台のキヤノンギャラリーに巡回)を見て、その知性と感性と技術とが絶妙なバランスを保った作品世界は、もっと大きく展開していく可能性を持っているのではないかと思った。ただし、いまのところ彼が中心的なテーマと考えている日々の「観察と記録」を、日誌(Log)のようにまとめていくシリーズは、より注意深く組織化していかないと、とめどなく拡散していく危険を感じる。個々の作品を結びつけていく「美しさ」という基準が、まだひ弱なものに感じられるのだ。それよりはむしろ、今回は展示されていなかったが、もっとコンセプチュアルな志向性の強い「Type」(数字とアルファベット)、「Banknotes」(紙幣)、「Wine Collection」(ワインの色味のコレクション)といった作品群の方に、彼らしい鋭敏な感覚と細やかな手わざの妙がよく発揮されていると思う。これらをさらに深化させていくか、「Log」シリーズとうまく合体させていくことで、新たな方向性を見出すことができるのではないだろうか。
2010/04/22(木)(飯沢耕太郎)
2010年三影堂攝影奨作品展 交流 Confluence

会期:2010/04/17~2010/06/15
三影堂攝影芸術中心[中国・北京]
2007年に北京郊外の朝陽区草場地に設立された三影堂攝影芸術中心(Three Shadows Photography Art Centre)が主催して、昨年から始まった三影堂攝影奨。今年もおよそ210名(そのうち女性が4分の1)の写真家たちの力作が寄せられ、フランソワ・エベル(フランス)、エヴァ・レスピーニ(アメリカ)、カレン・スミス(イギリス、北京在住)、飯沢耕太郎(日本)、そして三影堂の創始者である榮榮(ロンロン)(中国)の審査によって、1981年生まれの張暁(ジアン・シアン)がグランプリにあたる三影堂攝影賞に選ばれた。柔らかな色調で現代中国の人物群像を描き出したシリーズで、その若者らしい躍動感のある被写体へのアプローチが高く評価された。ほかにもいい作品が多く、全体的には昨年よりもレベルが上がっているように感じた。ただ、作品の応募点数が去年より100点あまりも減っているのが気になる。広報活動がうまくいかなかったようだが、若い意欲的な写真家たちの活動の受け皿として機能させるためには、もう一工夫が必要なのだろう。見る者をワクワクさせるような作品が、もっと増えてきてよいと思う。
その今年の三影堂攝影奨作品展は、フランスのアルル国際写真フェスティバルと提携した「草場地春の写真祭2010」の一環として開催された。南仏のアルルで毎年7~9月に開かれるアルル国際写真フェスティバルは、1970年のスタートという長い歴史を誇る写真祭だが、それが中国の、まだ国際的にはほとんど知られていない写真センターの活動とリンクするというのは、ひとつの事件といえる。三影堂だけではなく、近年ギャラリーやアーティストのアトリエが急増して「芸術区」として注目されている草場地一帯で、30近い写真展が開催され、シンポジウム、ポートフォリオ・レビュー、スライド・ショー、コンサートなどの多彩な企画が展開されている。
ただこの催しが今後もうまく続くのかが心配だ。というのは、水面下できわめて深刻な事態が起こっているからだ。昨年あたりから、草場地一帯を再開発して、マンションやショッピングセンターを建設しようという動きがあり、「草場地春の写真祭2010」のオープニングの前々日に、三影堂にも正式に土地収用の通告が届いたのだ。つい最近も草場地に近い正陽芸術区で同じような問題が持ち上がり、当局が雇ったと思われる暴漢の襲撃で、日本人を含むアーティスト数名が負傷するという事件が起こったばかりだ。もちろん、表現の自由を求めて、時に政治的に過激な方向に走りがちなアーティストたちの存在は、政府や市当局にとって好ましいものとは言えないだろう。だが今回の事態はそのような「思想弾圧」というよりも、単純にここ10年あまりの不動産バブルによって、企業や住人たちのあいだに湧き上がってきている、手っ取り早くお金を儲けたいという気運に乗じたということのようだ。
だが、せっかく三影堂攝影芸術中心を立ち上げ、「草場地春の写真祭」をスタートさせたばかりの写真家たちにとってはまさに一大事だ。この「草場地問題」の推移は、写真に限らず、中国の現代文化、現代美術の将来を占う試金石になるだろう。草場地には三影堂の建物の設計者で、スケールの大きな美術作品でも知られる艾未未(アイ・ウェイウェイ)のアトリエもある。彼を含めて、アーティストたちがどのようにして自分たちの権利を主張し、活動を続けていくのか、注意深く見守るとともに、できる限りの支援をしていきたいと思っている。
2010/04/17(土)(飯沢耕太郎)
太田順一『父の日記』
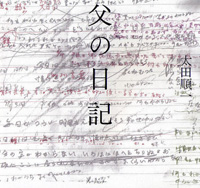
発行所:ブレーンセンター
発行日:2010年3月21日
昨年の銀座ニコンサロンでの個展で、伊奈信男賞を受賞した太田順一の『父の日記』が写真集になった。太田の父が1988年から20年あまりノートに書き続けた「日記」をそのまま複写するように撮影した「父の日記」(モノクローム)46点に、「大阪湾の環境再生実験のため、岸和田の沖合につくられた人工の干潟」に2005年から1年ほど通って撮影した「ひがた記」(カラー)42点を加えて構成されている。
この二つの仕事に直接的なつながりはないのだが、日記の文字を拾い読みし、茫漠と広がる干潟のディテールを眼で撫でるように味わっていくと、生きものの生と死はこんなふうに写真に刻みつけられていくのだという感慨が、静かに広がっていく。これまで太田の仕事は、あくまでもストレートな(正統的な)ドキュメンタリーだったのだが、彼のなかにも表現者としての新たな可能性を模索する気持ちが芽生えてきているのではないだろうか。几帳面な字が次第に乱れて「毎日がつらい」「ボケてしまった」という殴り書きが痛々しい日記にも、海辺の生物や鳥たちの痕跡がくっきりと残る干潟の眺めにも、眼差しに裂け目を入れ、さまざまな連想を引き出す豊かな写真の力が呼び起こされている。たしかにすんなりと受け入れるのがむずかしい写真集かもしれないが、太田が伝えようとする“希望”のかたちは、多くの人が共有できるのではないかと思う。
ブレーンセンターから刊行された太田順一の写真集は、『化外の花』『群衆のまち』に続いて、これで3冊目になった。あまり売行きが期待できそうにない地味な写真集を、しっかりと出し続ける出版社の心意気にも敬意を表したい。
2010/04/14(水)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)