artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
アジアの写真家たち 2010 タイ

会期:2010/05/26~2010/06/11
銀座ニコンサロン(5月26日~6月8日)/リコーフォトギャラリーRING CUBE(5月26日~6月6日)/PLACE M(5月31日~6月11日)[東京都]
日本写真協会が主催する「東京写真月間」の一環として開催されている「アジアの写真家たち」の企画。今年はタイの写真家たちを招聘して、3つのギャラリーで展覧会が開催された。
いつもの年だと、アマチュア写真家のサロン的な作品が並ぶことが多いが、今年は少し様子が違っていた。2007年の東川賞国際賞の受賞作家でもあるマニット・シーワニットプームが「多様性と挑戦」をテーマにセレクトした13人の写真家は、かなりアート志向が強く、刺激的な作品が多かった。マニット自身が銀座ニコンサロンとリコーフォトギャラリーRING CUBEで展示した「Pink Man」のシリーズに、タイ現代写真の特徴がよくあらわれている。「Pink Man」は文字通りショッキング・ピンクのスーツに身を包んだ小太りの中年男(本職は俳優ではなく詩人だそうだ)が、バリ島のような観光地やタイの大衆演劇、リケーの舞台に出現するという演出的な趣向をこらした作品である。当然ながら、その背景には急速な近代化、資本主義化に沸く都市文化と、アジアの伝統社会との間の裂け目や軋みがある。このような批評的、演劇的な視点は、「女の一生」を自ら演じるマイケル・シャオワナーサイや、整形美容の問題を扱うオーム・パンパイロートの「アイデンティティーの危機:性転換シリーズ」にも共通している。日本の写真作家と比較しても、タイの現代写真はポリティカルな志向がかなり強いように感じた。
そんななかでむしろ印象に残ったのは、著名な政治家でもあったスラット・オーサターヌクロの「消えゆくバンコク」のシリーズ(PLACE Mで展示)。モノクロームで、水とともに生きるバンコクの人々の暮らしを細やかに、詩情豊かに描き出す。残念ながら2008年に亡くなって、写真家としての活動は中断してしまうが、記憶に留めておきたい作品だ。
2010/05/27(木)、2010/06/02(水)(飯沢耕太郎)
荒木経惟「古希ノ写真」

会期:2010/05/08~2010/06/05
Taka Ishii Gallery[東京都]
恒例となっているTaka Ishii Galleryでの誕生月写真展。今年70歳(古希)を迎える荒木の現在の状況を確認するには格好の企画といえる。
人気歌手・パフォーマー、レディ・ガガをモデルとした、力のこもったモノクロームのセッションから開始され、「緊縛」「Kaori」「人妻エロス」「クルマド」「空」「バルコニー」などの見慣れたシリーズが並ぶ。目に馴染んでいるだけに、逆にそこに写し出されている光景の荒廃ぶりが胸を突く。バルコニーは錆つき、そこに置かれた恐竜のおもちゃのようなオブジェは地面に打ち伏し、水の染みが黴をともなってそこここに広がっている。タクシーの窓(クルマド)から見られた町の眺めはよろよろとよろめき、そこにも細かなひび割れが少しずつ広がり、通行人は前のめりに傾いていく。人妻の三段腹はたぷたぷと波打ち、厚化粧の下の疲れてたるみきった表情が容赦なくあばき立てられる。その忍び寄る荒廃の影を、最も色濃く背負っているのが「チロの死」のパートだろう。二十二歳という長寿を保って亡くなった愛猫は、ぼろ雑巾のように痩せさらばえて毛布の上に横たわる。その「死者」のイメージの前後に置かれた、誰もいない台所や浴室の写真がぞっとするほど怖い。まるで、チロがふたたび亡霊となってよみがえり、そのあたりを歩きまわっている、「死者」の眼差しで眺められた場面のように見えるのだ。
だが、これらの荒廃や衰弱の気配を、額面通りに受け取る必要はないだろう。今回の「古希の写真」は、「チロの死」の写真を中心に組み上げられることがあらかじめきまっており、荒木はその構成の作業を正確に、熟練の手際で遂行しているのが目に見えているからだ。手品師がハンカチを開けば、次の瞬間、そこにはくるりと幸福とエロスの祝祭的な空間が出現するはずだ。
2010/05/27(木)(飯沢耕太郎)
Wu Chin-Chin「A. face 2 face」
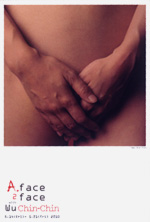
会期:2010/05/14~2010/05/23
ZEN FOTO GALLERY[東京都]
面白そうな展覧会だとは思っていたが、見に行く時間がなかった。ところが、ZEN FOTO GALLERYのオーナーのマーク・ピアソンから突然メールが来て、クロージング・ドリンクをやるというので慌てて出かけてきた。どうやら台湾で印刷していた展覧会のための写真集の輸入に、「風俗を害する物品」ということで税関からストップがかかり、そのことへの緊急アピールという意味もあったようだ。
冗談のような名前のWu Chin-Chin(呉泌泌)は、上海生まれで北京在住の女性アーティスト。原子物理学者だった父の仕事の関係で、14歳でアメリカに渡り、パリで写真を学んだ。今回、日本で初公開された「Vis- -vis」シリーズは、50人あまりの女性モデルの性器をクローズアップでクリアーに写した作品。女性性器を主題にした作品は、クールベの「世界の起原」(1866年)以来、特に珍しいものではないが、本作は作者が女性であること、性器の存在を通じて自らを含めたアイデンティティを問い直すという意図が明確であることが重要だろう。なお、方向性は違うが、荒木経惟のモノクローム作品も同時に展示されていた。
むろん、性器のイメージにはエロティックな意味合いを呼び起こす要素がないわけではない。だが、このような生真面目な作品を杓子定規に「風俗を害する物品」とみなすこと自体、何とも時代遅れで硬直化したものに思える。むしろ、あまりにも生真面目過ぎて、人類学的な記録写真の羅列のように見えてしまうことの方が問題だと思う。もう少し笑いを呼び起こすような、いい意味で不真面目なアプローチもありえたのではないかとも思った。
2010/05/23(日)(飯沢耕太郎)
沈昭良「STAGE」

会期:2010/05/12~2010/05/25
銀座ニコンサロン[東京都]
沈昭良は1968年台湾・台南市生まれの写真家。日本に滞在して日本工学院専門学校で写真を学んだ時期があり、流暢な日本語を話す。この「STAGE」のシリーズは2006~2009年に4×5判の大判カメラで撮影されたものである。
はじめて目にする観客は、いったいこれは何だろうといぶかしむのではないだろうか。きらびやかな電飾が光輝く舞台が、夜空に大きくせり上がっている。これは「台湾綜芸団」(タイワニーズ・キャバレー)と呼ばれる見せ物の舞台として使われるもので、トラックの荷台にセットされ、油圧電動式のモーターによってパタパタと開くようになっているものだ。ステージトラックと呼ばれるこの舞台は台湾全土で600台ほどあり、夜ごといろいろな場所で歌謡ショーや民俗芸能大会などが開催されている。時には「女装の男性によるショー」なども見ることができるという。
沈の撮影の方法はきわめてオーソドックスなドキュメンタリーだが、逆にこのテーマにはそれしかやりようがないのではないだろうか。ドラゴンとディズニー・キャラが共存する華洋折衷というべき舞台のデザインそのものが、もう既に作り物の極みなので、演出的な撮影をする必要がないともいえる。ただ今回の展示では、舞台をあまり大きく扱わず、周囲の状況を取り入れた作品が多くなっていた。亜熱帯の、ねっとりと肌にまつわりついてくるような空気感が丸ごと伝わってくる。華やかだが、どこか悲哀感も漂う、台湾の都市文化のひとつの貌が浮かび上がってきているようにも感じた。
2010/05/21(金)(飯沢耕太郎)
川田喜久治「ワールズ・エンド Worlds’s End 2008-2010」
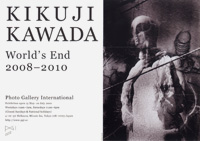
会期:2010/05/13~2010/07/10
フォト・ギャラリー・インターナショナル[東京都]
1933年生まれの川田喜久治は、いまでも週に何日かは「プールで泳いでいる」のだという。70歳代後半だが、気力も体力もまだまだ充実していることが、この新作展からも伝わってきた。
2008年の暮れから2010年3月まで「毎日撮影することを自分に課した」その成果が並んでいる。撮影場所は東京がほとんどだが、あえて今回は、自分が住んでいるこの場所のいまを撮影するというこだわりがあったようだ。前作の「ユリイカ Eureka 全都市」(2005年)、「見えない都市 Invisible City」(2006年)と同様に、デジタルカメラの連写機能やパソコンでの合成や色味の変換を活かした作品が並ぶが、シャドー部の翳りがより強調され、不穏当な気配がさらに大きく迫り出してきているように感じる。全体的に無機的なモノと有機的な生命体とが絡み合うハイブリッドな状況に強く引きつけられるものがあるようだ。その「一瞬のねじれやファルス」を追い求めていくと、どうもフレーム入りの写真が整然と並んでいる、静まりかえった会場の雰囲気とはややそぐわないようにも思えてくる。
これはほんの思いつきだが、逆にノイズがあふれる工事現場のような場所で見たかったような気がする。ノイズ・ミュージックをバックにしたスライドショーのような形も面白いかもしれない。そんなふうに思わせるような、「はみ出していく」エネルギーが、作品に渦巻いているということだろう。
2010/05/21(金)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)