artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
岸幸太「連荘4」

会期:2023/09/26~2023/10/15
岸幸太が2021年からphotographers' galleryで開催している連続展「連荘」も4回目を迎えた。大阪、東京、横浜、京都などの日雇い労働者たちが多く住む地域、いわゆる「ドヤ街」を中心に撮影しているシリーズだが、少しずつ方向性が定まりつつあるように見える。
岸は2005年から2020年にかけて撮影した以前のシリーズ「傷、見た目」でも、同じような場所にカメラを向けている。だが、文字通り「傷」の感触を確かめるような切迫感があった前作と比較すると、カラー写真にシフトしたこともあって、本作にはどこか開放的な、撮影行為そのものに柔らかに没入しているような雰囲気を感じることができる。岸自身は、この連作を通じて「自分の地図を作りたい」と考えているようだ。その意図は、「ドヤ街」の細部を引き剥がして提示するような距離感が近い作品だけでなく、何点か、より客観的な引き気味の写真が含まれていることにもあらわれているのではないだろうか。
おそらくphotographers' galleryの中心メンバーの北島敬三の影響だと思うが、岸だけでなく、笹岡啓子、王子直紀など同ギャラリーに所属する写真家たちは、長期間の連作にこだわることが多い。この「連荘」シリーズも、さらに回を重ねることで、より明確なヴィジョンが見えてくることを期待したいものだ。なお、展覧会にあわせて刊行されるA4サイズの写真集も、今回で4冊目になった。
岸幸太「連荘4」:https://pg-web.net/exhibition/kota-kishi-renchan-4/
関連レビュー
岸幸太『傷、見た目』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年06月01日号)
2023/10/05(木)(飯沢耕太郎)
千葉奈穂子、アンティ・ユロネン、カイサ・ケラター「Dialogue With Land 土地との対話」

会期:2023/10/04~2023/10/15
工房親[東京都]
岩手県出身で、現在は山形県酒田市在住の千葉奈穂子は、2018年にフィンランドに滞在し、ラップランド地方を中心に撮影した。今回の工房親での展示では、そこで知り合った陶芸家、写真家のアンティ・ユロネン、アーティストで生物学者でもあるカイサ・ケラターとのコラボレーションを試みている。
千葉はこれまで、2019年に萬鉄五郎記念美術館八丁土蔵ギャラリーで開催した個展「父の家/Northern Lights」の出品作のように、古典技法のサイアノタイプ(青写真)を用いて、幼い頃の暮らしの記憶を甦らせ、封じ込めるような作品を発表してきた。それがフィンランド滞在を契機として、少しずつ変わり始めているように思う。被写体の細部までしっかりと描写したゼラチン・シルバープリントの黒白写真では、クローズアップや室内の情景を撮影した作品も含めて、より融通無碍なカメラワークを見ることができる。今回の展示には、東日本大震災後に継続して撮影している福島県南相馬市の写真が並んでいた。やはり南相馬市で撮影したアンティ・ユロネンの朽ち果てていく建築物の写真、ラップランドの神話的な記憶を再構築したテキストと写真とを合わせたカイサ・ケラターの作品とも相性がよく、東北とフィンランドという、似通ったところもある風土性が、互いに共振し合う時空間が形成されていた。
1990年代後半から続けてきた千葉の写真の仕事も、かなりの厚みを備えてきている。そろそろ写真集にまとめてほしいものだ。
工房親:https://www.kobochika.com/
2023/10/04(水)(飯沢耕太郎)
片岡利恵「ディスタール」
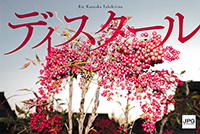
会期:2023/09/19~2023/10/01
Jam Photo Gallery[東京都]
片岡利恵がPlace Mで個展「あわせ鏡」を開催したのは2022年11月だから、まだ1年が経たないうちの展示ということになる。明らかに制作・発表のペースが上がっているだけでなく、今回の写真展を見ると、何をどのように追い求め、どんなかたちに落とし込んでいくかというターゲットがしっかりと見えてきていることがわかる。作品の点数(28点)、大小のカラープリントをアクリルに挟み込んで壁にアトランダムに並べていくやり方、その配列など、前回の展示よりも格段にインスタレーションのクオリティが上がっていた。
夜の場面を中心に、花や植物にカメラを向けるというテーマ自体に変わりはない。ただ、ここでも狙いが絞られてきていて、看護師という職業の実体験に根差した、生と死との境界領域の出来事が、花や植物に託されて説得力を持って語られていた。やや耳慣れないタイトルの「ディスタール」とは、「患者の心臓に一番近いところに向かって点滴を通す」カテーテルの一種なのだという。このタイトルの選び方にも、切実さと必然性を感じる。写真家としての歩みを着実に進めているといえるだろう。
ただ2回続けて同じテーマでの展示を見ると、次の展開を期待してしまう。花へのこだわりは保ち続けながらも、被写体の幅を少し広げてみることはできないだろうか。新たな領域に乗り出していく力は、充分についてきているのではないかと思う。
片岡利恵「ディスタール」:https://www.jamphotogallery.com/exhibitions#comp-llc1ho7y
関連レビュー
片岡利恵「あわせ鏡」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年12月15日号)
2023/09/23(土)(飯沢耕太郎)
山口聡一郎「デッサン」

会期:2023/09/07~2023/10/01
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
1959年、佐賀県生まれ、岡山市在住の山口聡一郎は、同市で写真専門ギャラリー722を主宰しながら作家活動を続けてきた。これまで主に都市風景や車窓からのスナップなど、どちらかといえばオーソドックスなモノクローム写真のシリーズを発表してきたのだが、2023年6月〜7月に奈義町現代美術館ギャラリーで開催した個展「ニュー・ネイチャー」の出品作は、これまでとは一味違っていた。120×90センチのダンボールを支持体として、A4サイズ16枚に分割した画像を感光乳剤に焼き付けた「月の光」「クリアーウォーター」「ビーチ」などの作品群には、彼の前に生起した自然現象が、さまざまな角度から定着されていたのだ。
今回、コミュニケーションギャラリーふげん社で展示した「デッサン」も、その「ニュー・ネイチャー」展で発表した作品である。1999年に、自分自身を被写体として開始したヌードの連作は、その後も続けられ、女性モデルの作品も加えてかなりの厚みに達している。そこにはエロティシズムを強調するよりも、むしろ「裸体という物体」の存在感を突き詰めようとする姿勢が一貫しており、撮影を通じて、写真という表現媒体の原点をあらためて確認しようとしているようにも見える。何かの下絵としての「デッサン」ではなく、むしろ撮り続けるという行為の積み重ねそのものに意味を見出しているのではないだろうか。ただ本作には、「ニュー・ネイチャー」という総体的な営みのひとつのパートという側面がある。その全体像を、東京でも見ることができる機会がほしいものだ。
山口聡一郎「デッサン」:https://fugensha.jp/events/230907yamaguchi/
2023/09/23(土)(飯沢耕太郎)
広川泰士「2023-2011 あれから」

会期:2023/09/22~2023/10/12
フジフイルムスクエア[東京都]
広川泰士は長くファッションや広告の世界で活動してきた写真家だが、同時に高度経済成長期以降の日本の変貌を緻密かつ粘り強く記録していく風景写真を、ライフワークとして撮影し続けている。2015年に赤々舎から刊行した写真集『BABEL ORDINARY LANDSCAPES』には、大地を引き裂き、大規模な工事によって環境そのものを変貌させていく人間の営みを、旧約聖書の、神をも恐れぬバベルの塔の建造と重ね合わせた写真シリーズがおさめられていた。その広川が2011年3月に発生した東日本大震災に強い関心を抱いたのは当然というべきだろう。震災直後に、救援物資を積んだ車で被災地に向かった。だが、その時に撮影した写真群を、すぐに発表する気にはなれなかった。そこには、あまりにも生々しく、凄惨な眺めが広がっていたからだ。
その後、同じ場所を同じアングルで時間を置いて撮影する定点観測写真という方法を見出すことで「撮り続ける」ことが可能となった。広川は、宮城県気仙沼に4ヶ所、岩手県陸前高田に2ヶ所、釜石に3ヶ所、定点観測写真のスポットを設け、2023年まで何度も足を運んで撮影を続けた。今回のフジフイルムスクエアの展覧会では、それらの風景写真に加えて、2011年6月から相馬(福島県)、気仙沼で撮影した被災者の家族たちのポートレートの連作もあわせて展示されていた。
広川の取り組みは、震災後10年以上を経た現時点におけるドキュメンタリー写真のあり方を、あらためて問い直すものと言えるだろう。定点観測という手法に終わりはない。むしろ今後も撮り続けていくことによって、その仕事の意味と重みはより増してくる。そのエンドレスな作業への覚悟が、展示から伝わってくるように感じた。
広川泰士「2023-2011 あれから」:https://fujifilmsquare.jp/exhibition/230922_01.html
関連レビュー
広川泰士「BABEL Ordinary Landscapes」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年03月15日号)
2023/09/22(金)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)