artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
野上眞宏写真集発売記念写真展「METROSCAPE」

会期:2023/08/22~2023/09/03
ギャラリー・ルデコ 4F[東京都]
野上眞宏は1974年に渡米し、1979年からはニューヨークに居を定めた。1983年に8×10インチ判の大判カメラを購入し、マンハッタン島の周縁地域や、クイーンズ、ブルックリン、ブロンクスなどを撮影し始めた。のちに写真集『NEW YORK―Holy City』(美術出版社、1997)にまとまるこのシリーズで、野上は大判カメラとカラーフィルムの取り扱い方を身につけていった。1994年の一時帰国後、野上は2001年から2005年にかけて再びニューヨークに滞在する。この時期に、もう一度ニューヨークの街頭にカメラを向けたのが、今回ギャラリー・ルデコで発表され、オシリスから同名の写真集として刊行された「METROSCAPE: NEW YORK CITY」のシリーズである。
この時期になると、ニューヨークのタイムズスクエアの周辺は、かつてのややいかがわしい雑然とした雰囲気ではなく、小綺麗な、すっきりした外観の都市風景に変わっていた。野上は、19世紀末から20世紀初頭にかけてパリを撮影したウジェーヌ・アジェの仕事を規範として、「マクロとミクロが同時にある写真」をめざすようになる。建物や街路の「マクロ」な構造は、8×10インチ判の緻密な描写力と「アオリ」の機能を活かしてしっかりと浮かび上がらせつつ、風景の「ミクロ」な細部にも目を凝らしていく。さらに、フィルムの感度の問題でどうしてもブレてしまいがちな人物を固定するために、同じカメラアングルで3カット撮影し、特定の人物が止まって写っているスキャンデータを最終的に合成するという、アナログとデジタルを融合させた手法を編み出した。結果的に、本シリーズでは、アジェの100年後の都市風景が、くっきりと浮かびあがってきた。
ギャラリー・ルデコの会場には63×50インチ(160×125センチ)に引き伸ばした3点と、50×45インチ(125×100センチ)に伸ばした14点、計17点の写真が並んでいた、会場がそれほど広くないので仕方がないが、数百点撮影したというこのシリーズには、もう少し大きな(天井の高い)会場が必要だろう。それでも、野上の「未来の人々に2000年代初頭のニューヨークがどんな風だったのか楽しんでいただけるように写真を撮っておこう」という撮影意図は、十分に実現していたのではないかと思う。
公式サイト:https://ledeco.net/?p=19425
関連レビュー
野上眞宏「1978 アメリカーナの探求」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年09月15日号)
2023/08/26(土)(飯沢耕太郎)
篠田優「Long long, ago」
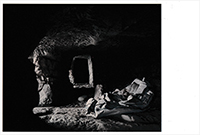
会期:2023/08/21~2023/09/03
三浦半島・小坪の海辺の崖には、第二次世界大戦中にトーチカ(防御陣地)として利用された洞窟が残っている。篠田優は、主にそのうちの二つの洞窟を撮影した。その開口部は、自然の岩肌とコンクリートとが見極めがつかないほどに混じりあっており、「人の手によってつけられたと思しき」、引っ掻き傷のような痕跡を見ることができる。篠田は、開口部だけでなく。カメラを手にその内部まで踏み込み、残留物を含む洞窟のたたずまいを丁寧に描写していった。カラーフィルムを効果的に使っていることで、光と闇の境界のあたりの眺めが、繊細かつヴィヴィッドに浮かびあがってきた。
だが、まだやや物足りない。14点という展示作品の数も中途半端だが、被写体の捉え方にも、もっと工夫の余地があるのではないだろうか。篠田は本作を通じて「地層として形象化した遥かな時間」を捉えようとしている。だが、過去の遺物を愛でるだけでは先がない。出品作の中に1枚だけ、洞窟の中に置き去りにされたビニールボート(?)が写っている面白い写真があった。撮影場所を、三浦半島だけでなく日本各地に広げてほしいし、現代の空気感をもっと積極的に取り入れてもいいだろう。洞窟が戦時に実際にどのように使われていたのか、資料をあたって検証することも必要になりそうだ。篠田は事物を的確に、ポイントを押さえて定着できる能力の持ち主だと思う。さらなる展開を期待したい。
公式サイト:https://pg-web.net/exhibition/yu-shinoda-long-long-ago/
2023/08/24(木)(飯沢耕太郎)
和田悟志「Invisible Border “China”」

会期:2023/08/22~2023/09/03
1980年、福島県生まれで、昨年からTOTEM POLE PHOTO GALLERYのメンバーとなった和田悟志は、台湾と中国東北部(旧満洲)の風景写真を交互に発表している。今回はそのうち、中国東北部の瀋陽やハルビンを「フラットな視点」で撮影した写真群を展示していた。
和田がテーマとして選びとったのは、建物や街路の眺めから見えてくる「Border」である。フェンスや壁のようにわかりやすいものもあるが、その多くは不可視(Invisible)な存在として、風景のなかに埋め込まれている。和田は、6×7判のカメラを使って、重層的に錯綜している「Border」を、繊細な手つきで可視化しようとする。その試みはうまくいく場合もあるが、多くの場合はそれほどくっきりとは見えてこない。だがそのことが逆に、和田の作品に、紋切り型の意味づけに収束しない、魅力的なふくらみを与えているようにも見える。
2012年から開始されたというこのシリーズも、かなりの厚みを備えてきた。もうそろそろ、より大規模な個展、あるいは写真集のような形でまとめるべき時期にきているのではないだろうか。その場合には、台湾と中国東北部という二つの場所の「Border」のあり方の違いを、よりくっきりと明示する指標が必要になるだろう。人工物だけでなく、植生のような要素にも着目すべきだし、人間を集中的に撮影する必要も出てくるかもしれない。個々の「Border」の細部と、それがどんなふうに働いているのかを、もう少し丁寧に描写することも大事になりそうだ。可能性のある仕事なので、ぜひいい着地点を見つけてほしい。
公式サイト:https://tppg.jp/invisible-border-china/
2023/08/24(木)(飯沢耕太郎)
風景論以後

会期:2023/08/11~2023/11/05
東京都写真美術館 地下1階展示室[東京都]
多くの観客にとっては「よくわからない展覧会」なのではないだろうか。東京都写真美術館地下1階の会場に並んでいるのは、何の変哲もないように思える日常の光景の写真、映像、映画のポスターや資料などである。しかも壁面には作品解説はまったくなく、作者名とタイトルだけ。作品についての詳しい情報を得るためには、入り口で手渡されるリーフレット(「展覧会ガイド」)か、カタログに目を通さなければならない。
不親切と言えばその通りだが、逆に昨今の、わかりやすい解説がないと安心できないような展示を見慣れた目には、その素っ気なさが逆に新鮮に思えた。何だか訳のわからない作品を見せられて、拒否反応を起こす観客もいるかもしれないが、そのことに触発され、これは一体何なのかと考え始める契機になるのではないかとも思う。
ただ、1960年代後半以降に松田政男や中平卓馬によって提起され、大島渚、足立正生、若松孝二らの試行を経て、主に実験的な映画のジャンルで展開されていった「風景論」が、その後どのように受け継がれていったのかという本展の最大のテーマが、充分にフォローされているとは思えない。「あらゆる細部に遍在する権力装置としての“風景”」(松田政男)に抗うことを求めていった「風景論」の輪郭は、例えば松田、足立らが関わった『略称・連続射殺魔』(1969)では明確に読みとれるものの、本展の最初のパートに展示された笹岡啓子、遠藤麻衣子のような現代作家の作品では、曖昧かつ拡散しているように見える。むしろかつての「風景論」の枠組みが、現代作家の風景表現において、どのように変質したのかを、もう少しきちんと検証すべきではなかっただろうか。
公式サイト:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4538.html
2023/08/19(土)(飯沢耕太郎)
石川竜一「風土 人間の殻」
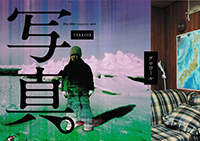
会期:2023/08/03~2023/09/03
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
石川竜一は2015年に第40回木村伊兵衛写真賞を受賞した。その時の受賞対象は、『絶景のポリフォニー』(赤々舎、2014)と『okinawan portraits 2010-2012』(同、2014)だったが、どちらかといえば切れ味の鋭い路上スナップの連作、『絶景のポリフォニー』のほうの印象が強かった。その後、石川は『okinawan portraits 2012-2016』(赤々舎、2016)を、続篇として刊行し、6×6センチ判だけでなく6×4.5センチ判のカメラも使い始める。今回、コミュニケーションギャラリーふげん社で、『写真 vol.4』(特集:テロワール/TERROIR)の刊行記念展として開催された彼の個展はその延長線上で企画されたもので、3階のギャラリースペースで、まさに「テロワール(風土)」というテーマを踏まえたポートレート群が展示されていた。
大判プリントされた12点は沖縄で撮影されており、観光客を含めて、強力な熱を発する風貌の人物をほぼ正面から撮影している。その強度と精度の高さも特筆すべきなのだが、むしろ興味深いのは、小さめにプリントした13点のほうで、こちらは沖縄だけでなく全国各地で撮影した写真を、春夏秋冬の季節を追って並べていた。「okinawan portraits」の連作と比較すると、被写体のたたずまいはやや穏やかなものとなり、複数の人物たちにカメラを向けた作品も増えてきている。また、人物たちの背景となるべき景色が、むしろ前景化してきているようにも見える。これらの変化は、石川の関心が、個としての人間存在だけでなく、彼らを取り巻く風土・環境=「人間の殻」にも向き始めていることを示している。彼のポートレート作品の新たな展開が期待できそうだ。
なお、同ギャラリーの2階スペースでは、同時期に『写真 vol.4』の口絵として掲載された、笹岡啓子、田附勝、中井菜央、山口聡一郎、田代一倫、北井一夫の作品も展示されていた。
公式サイト:https://fugensha.jp/events/230803ishikawa/
関連レビュー
石川竜一写真集『okinawan portraits 2012-2016』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年12月15日号)
石川竜一「絶景のポリフォニー」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年01月15日号)
2023/08/10(木)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)