artscapeレビュー
artscape編集部のレビュー/プレビュー
カタログ&ブックス | 2023年2月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
崇高のリミナリティ
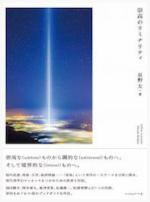
著:星野太
発行:フィルムアート社
発行日:2022年12月24日
サイズ:四六判変形、300ページ
「超越的なもの」から「水平的なもの」へ。 崇高な(sublime)ものから閾的な(subliminal)ものへ、そして境界的な(liminal)ものへ。 現代思想、美術、文学、批評理論……「崇高」という美学の一大テーマを日常に開き、 現代美学のエッセンスをつかむための思索と対話。 池田剛介、岡本源太、塩津青夏、佐藤雄一、松浦寿輝との対話、崇高をめぐるブックガイドを所収。
芸術と共在の中動態──作品をめぐる自他関係とシステムの基層

著:森田亜紀
発行:萌書房
発行日:2022年12月25日
サイズ:四六判、236ページ
能動-受動、主体-客体という図式におさまらない芸術体験(作品の受容と制作)の内実を、「中動態」という言語の範疇を援用することで闡明した前著での議論を踏まえ、そこで残された課題、すなわち芸術という領域における他者との関わり、ひいては芸術制度の社会的成り立ちを考察。
高松次郎 リアリティ/アクチュアリティの美学

著:大澤慶久
発行:水声社
発行日:2023年1月13日
サイズ:A5判、256ページ
高松次郎の多様な作品に内在する、「リアリティ=真実」/「アクチュアリティ=事実」の美学とは何か。この問いを巡って、作家の思考と作品との間に秘められた、未だ見ぬ回路を切り開く。
災間に生かされて
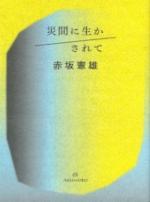
著:赤坂憲雄
発行:亜紀書房
発行日:2023年1月18日
サイズ:四六判、240ページ
〈陸と海、定住と遊動、生と死、虚構と現実、セクシュアリティ…〉
──境界線が溶け合うとき硬直した世界に未来の風景が立ち上がる。
「人は避けがたく、ほんの気まぐれな偶然から、ある者は生き残り、ある者は死んでゆくのです。巨大な災害のあとに、たまたま生き残った人々はどんな思いを抱えて、どのように生きてゆくのか。思えば、それこそが人間たちの歴史を、もっとも深いところから突き動かしてきたものかもしれません」(本文より)
いくつもの不条理なできごとの底知れぬさみしさを抱えて、それでもなお生きるための思考。
原視紀行 地相と浄土と女たち

著:石山修武
写真:中里和人
発行:コトニ社
発行日:2023年1月21日
サイズ:A5判、144ページ
鬼才建築家・石山修武が、日本の深い地相と歴史をたずねながら、知られざる文化や人々の暮らしに迫る! 文化的な遺産や自然の様々な痕跡と出会いながら新たな魅力を再発見するちょっと不思議な「原始旅行のガイドブック」。
ヨコとタテの建築論 モダン・ヒューマンとしての私たちと建築をめぐる10講

著:青井哲人
発行:慶應義塾大学出版会
発行日:2023年1月24日
サイズ:四六判、304ページ
当たり前をじっくり考え直すこと、学び直すこと。 私たち=現生人類の本性に立ち返り、建築の思考をいきいきと語る。 相似の海としての「建物」の広がりから、「建築」はいかに世界と未来の幻視を立ち上げるか──。 東京藝術大学大学院での講義から生まれた出色の入門書。
感性でよむ西洋美術
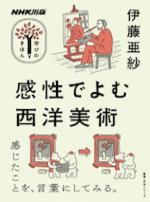
著:伊藤亜紗
発行:NHK出版
発行日:2023年1月26日
サイズ:A5判、144ページ
2500年もの歴史をもつ「西洋美術」。その膨大な歴史や作品を理解するのは至難の業だ。しかし、5つの様式から「大づかみ」で概観すれば、「この時代の作品はこんな感じ」という全体像が見えてくる。キーワードは「感性」。古代から20世紀まで、約40点の名作を鑑賞して、感じたことを言葉にしてみれば、作品理解がぐっと深まる。「ルネサンスはなぜ重要なの?」「マネの何が革新的なの?」「ピカソはなぜ不思議な絵を描くの?」。美術館に行くと、まず解説を読んでしまう鑑賞法から卒業できる、新感覚の美術入門!
レペルトワールⅢ 1968

著:ミシェル・ビュトール
監訳:石橋正孝
訳:三ツ堀広一郎、中野芳彦、堀容子 他
発行:幻戯書房
発行日:2023年1月27日
サイズ:A5判
騙し絵か非゠騙し絵か(ホルバイン、カラヴァッジョ)、小説の地理学(ルソー)とポルノグラフィ(ディドロ)、毒薬/霊薬としての言葉(ユゴー)、連作としての絵画と文学(北斎、バルザック、モネ)、キュビスムの技法(ピカソ、アポリネール)、「正方形とその住人」(モンドリアン)、記憶の多角形(ブルトン)、「宇宙から来た色」(M・ロスコ)、考古学、場所、オペラ等々、文芸×美術を自在に旋回する、アクロバティックな創作゠批評の饗宴。
ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ「柔らかな舞台」

テキスト:菅野優香、ビンナ・チョイ、パブロ・デ・オカンポ、アンドリュー・マークル、崔敬華
デザイン:若林亜希子
発行:torch press
発行日:2023年1月27日
サイズ:200x125mm、272ページ
2022年11月12日(土)〜2023年2月19日(日)まで、東京都現代美術館にて開催されている企画展「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」のカタログ。
場所、それでもなお

著:ジョルジュ・ディディ=ユベルマン
訳:江澤健一郎
発行:月曜社
発行日:2023年1月28日
サイズ:四六判、188ページ
ユダヤ人絶滅収容所の〈場所〉をめぐる表象不可能性に抗して、映画や写真のイメージ(映画『ショアー』『サウルの息子』、アウシュヴィッツ=ビルケナウ国立博物館所蔵の写真群)を分析し、歴史の暗部を透視する試み。『イメージ、それでもなお──アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真』(原著2003年刊)の前後に書かれたユダヤ人大虐殺をめぐるテクスト三篇、「場所、それでもなお」(1998年)、「樹皮」(2011年)、「暗闇から出ること」(2018年)を一冊にまとめた、日本版独自編集の論集。
メディア地質学 ごみ・鉱物・テクノロジーから人新世のメディア環境を考える

著:ユッシ・パリッカ
訳:太田純貴
発行:フィルムアート社
発行日:2023年2月3日
サイズ:四六判、352ページ
物質という視点や長大な時間から現代のメディア状況を捉え直す、気鋭の研究者によるハードでドライなメディア文化論。
共和国の美術 フランス美術史編纂と保守/学芸員の時代
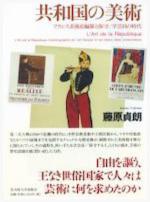
著:藤原貞朗
発行:名古屋大学出版会
発行日:2023年2月10日
サイズ:A5判、454ページ
王なき世俗国家で人々は芸術に何を求めたのか。戦争に向かう危機の時代に、中世宗教美術や王朝芸術から、かつての前衛までを包摂するナショナルな歴史像が、刷新された美術館を舞台に創られていく。その過程を、担い手たる学芸員=「保守する人」とともに描き、芸術の歴史性を問い直す。
文化の力、都市の未来 人のつながりと社会システム
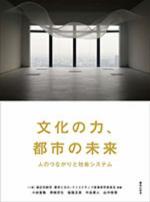
編:(一財)森記念財団 都市と文化・クリエイティブ産業研究委員会
発行:鹿島出版会
発行日:2023年2月13日
サイズ:B5判、220ページ
文化芸術をはぐくみ都市の成長へ。そのための課題やアプローチを、世界の第一線で活躍する有識者へのインタビューより明らかにする。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
2023/02/14(火)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2023年2月1日号[テーマ:手も眼も使って考え、暮らす──現代のデザイナーの思考回路を覗き見る5冊]
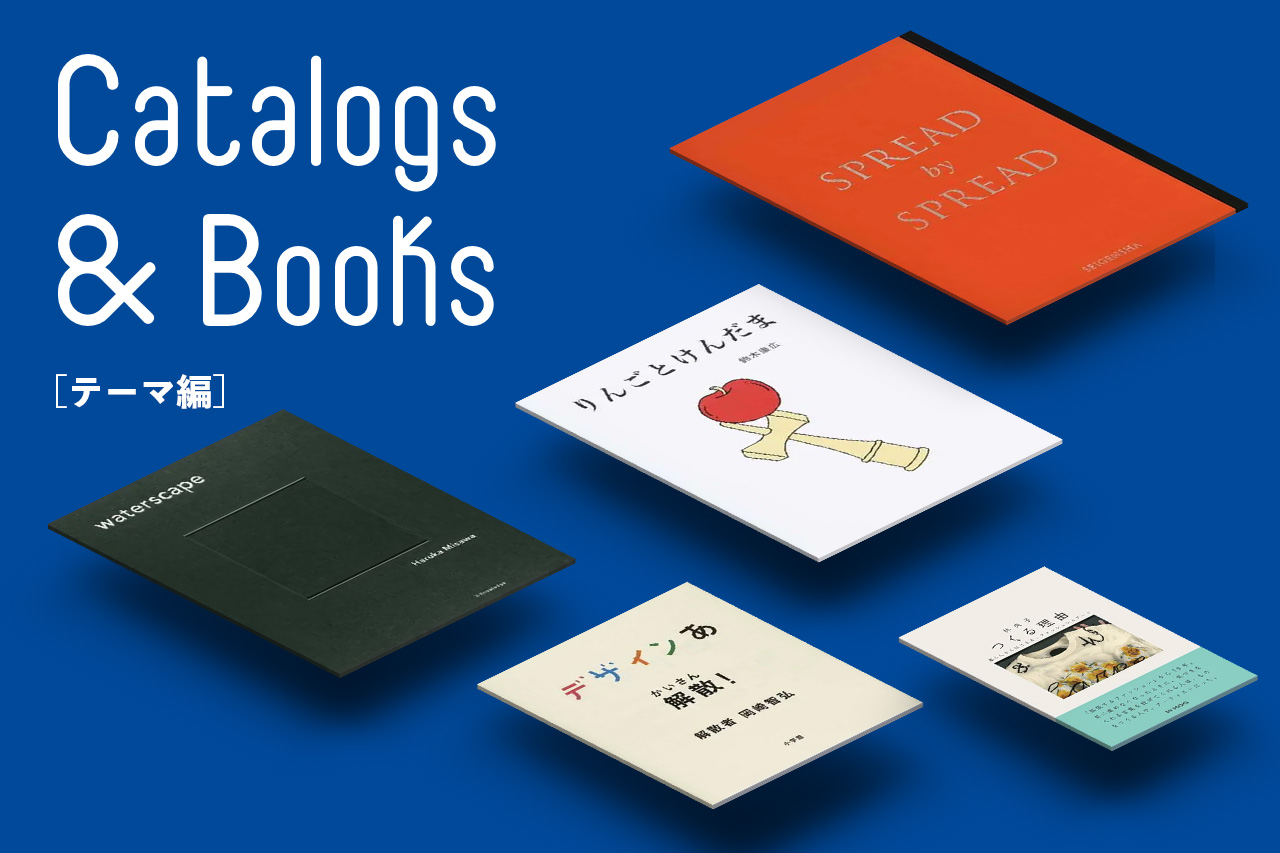
生活のなかでの観察・思考や、アイデアを形にするまでの密かな知的興奮。「デザインスコープ─のぞく ふしぎ きづく ふしぎ」(富山県美術館で2022年12月10日〜2023年3月5日開催)の参加作家が登場したり書いた本を中心に、つくることとその手前にある日常の見方のそれぞれの個性が浮かび上がってくる5冊を選びました。
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
協力:富山県美術館
今月のテーマ:
手も眼も使って考え、暮らす──現代のデザイナーの思考回路を覗き見る5冊
1冊目:デザインあ 解散!
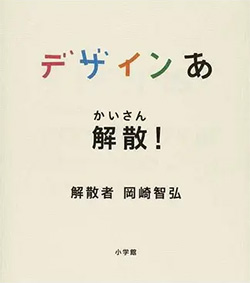
著者:岡崎智弘
発行:小学館
発売日:2013年1月30日
サイズ:21cm
Point
NHK Eテレ『デザインあ』内の人気コーナー「解散!」のビジュアルブック。しめじ、電卓、みかん──身近にあるモノを分解して並べるというシンプルな工程を経て、まったく異なる表情が立ち上がってくるさまは目が離せません。読んだ後しばらくは、視界に入ったあらゆるモノを頭の中でついつい分解してしまいます。
2冊目:りんごとけんだま
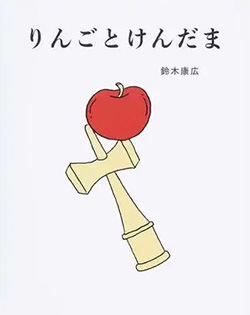
著者:鈴木康広
発行:ブロンズ新社
発売日:2017年10月19日
サイズ:27cm
Point
りんごとけん玉、そしてそれを持つ自分の身体を介在させることで、ニュートンの万有引力、ひいては自分と地球の関わりまで、イメージの力を及ばせることができる──そんな気づきを得られる絵本。鈴木康広氏のスケッチは一見ソフトな印象でありつつも、空想力も地道な鍛錬の積み重ねであることが垣間見えます。
3冊目:waterscape 水の中の風景
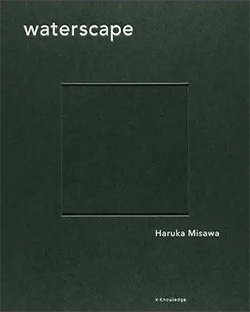
著者:三澤遙
発行:エクスナレッジ
発売日:2018年9月1日
サイズ:26cm、143ページ
Point
身近な素材にある小さなひとひねりを加えると、見たことのない風景が立ち上がる。領域を越え活躍するデザイナー・三澤遥氏が、本書では水中生物の棲む多様な環境を水槽の中に再構築しています。個々の設計図と、それに添えられたアイデアの出発点を明かす解説を読んでから写真に戻ると、より風景が豊かに見えてきます。
4冊目:SPREAD by SPREAD
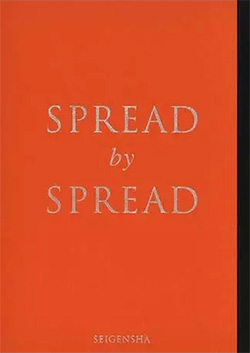
著者:SPREAD
発行:青幻舎
発売日:2021年5月28日
サイズ:30cm、167ページ
Point
ランドスケープとグラフィックを軸に人の記憶と想像力を拡げるクリエイティブユニットSPREADが得意とする、色をコミュニケーション媒介とした制作物。本書は彼らの活動開始からの15年間を記録した作品集で、表紙の鮮やかな朱色は「人類が用いた最初の色」のひとつだそう。質感の豊かさも含めて手元に置きたい一冊。
5冊目:つくる理由 暮らしからはじまる、ファッションとアート
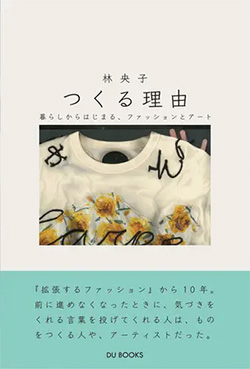
著者:林央子
発行:DU BOOKS
発売日:2021年6月25日
サイズ:19cm、309ページ
Point
つくる理由=生きる理由とも言い換えられるのではないか。著書『拡張するファッション』で知られる編集者の林央子。彼女が美術家やデザイナーなど、多様な分野の「つくる」人々の声を集めた本書の終盤、「デザインスコープ」展参加作家の志村信裕も登場し、不可分である暮らしと制作活動について語っています。
開館5周年記念 デザインスコープ─のぞく ふしぎ きづく ふしぎ
会期:2022年12月10日(土)~2023年3月5日(日)
会場:富山県美術館(富山県富山市木場町3-20)
公式サイト:https://tad-toyama.jp/exhibition-event/16596
[展覧会図録]
「開館5周年記念 デザインスコープ─のぞく ふしぎ きづく ふしぎ」公式図録
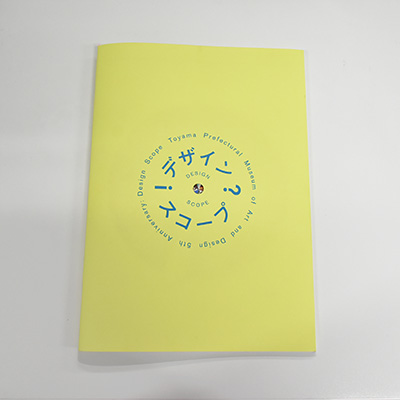
監修・発行:富山県美術館
発行日:2022年12月10日
サイズ:A4判型、28ページ
執筆:桐山登士樹、川上典李子、以倉新(富山県美術館 学芸課主幹)、内藤和音(富山県美術館 普及課学芸員)
アートディレクション/デザイン:永井裕明(N.G.inc.)
デザイン:柏木美月(N.G.inc.)
編集:浦川愛亜
◎富山県美術館ミュージアムショップにて販売中。
2023/02/01(水)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2023年1月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
「すべて未知の世界へ ―GUTAI 分化と統合」カタログ

発行:国立国際美術館、大阪中之島美術館
発行日:2022年10⽉
サイズ:28cm、285ページ
2022年10⽉22⽇(⼟)〜2023年1⽉9⽇(⽉・祝)に国⽴国際美術館、⼤阪中之島美術館にて開催されていた「すべて未知の世界へ ―GUTAI 分化と統合」のカタログ。
「中﨑透 フィクション・トラベラー」カタログ

監修:中﨑透
編集:竹久侑、嘉原妙
写真:加藤健、仲田絵美
発行:水戸芸術館現代美術センター
発行日:2022年11月
サイズ:A5判、288ページ
2022年11月5日(土)〜2023年1月29日(日)まで開催されている展覧会「中﨑透 フィクション・トラベラー」のカタログ。
近代建築における理想の変遷 1750-1950
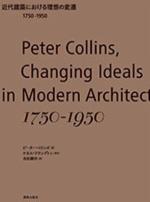
著:ピーター・コリンズ
翻訳:吉田鋼市
発行:鹿島出版会
発行日:2022年12月13日
サイズ:23cm、440ページ
ケネス・フランプトンが再評価した「近代建築の解釈学的古典」。待望の邦訳刊行。
建築と触覚 ─空間と五感をめぐる哲学

著:ユハニ・パッラスマー
解説:スティーヴン・ホール
翻訳:百合田香織
発行:草思社
発行日:2022年12月16日
サイズ:四六判、208ページ
建築における触覚、聴覚、味覚、嗅覚の重要性を視覚偏重の時代に再考し、哲学・美術をも横断しながら「五感を統合する」建築の在り方を問う。
1階革命 ─私設公民館「喫茶ランドリー」とまちづくり
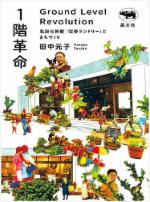
著:田中元子
発行:晶文社
発行日:2022年12月20日
サイズ:四六判、280ページ
1階づくりはまちづくり! 大好評だった『マイパブリックとグランドレベル』から5年、グランドレベル(1階)からはじまる、まちづくり革命の物語、完結編。
田中敦子と具体美術協会

著:加藤瑞穂
発行:大阪大学出版会
発行日:2023年1月20日
サイズ:A5判、400ページ
電気服はいかにして平面になったのか――具体美術協会再考のための初めてのモノグラフ
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
2023/01/13(金)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2022年12月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
SHUZO AZUCHI GULLIVER 「Breath Amorphous:消息の将来」

編集:SAGYO,Tokyo/certo Tokyo
アートディレクション:岡本佳子[ certo Tokyo ]
発行:BankART1929
発行日:2022年10月14日
サイズ:A3、256ページ
2022年10月7日(金)~11月27日(日)まで、BankART KAIKOとBankART Stationにて開催されていた、シュウゾウ・アヅチ・ガリバーの展覧会「Breath Amorphous 消息の将来」のカタログ。
「かげ」の芸術家 ゲルハルト・リヒターの生政治的アート

著:田中純
発行:ワコウ・ワークス・オブ・アート
発行日:2022年10月15日
サイズ:19x13cm、128ページ
思想史学者の田中純(東京大学大学院総合文化研究所教授)によるゲルハルト・リヒターの作品論4編を収録。リヒターの制作史で重要な3つのシリーズ《アトラス》《1977年10月18日》《ビルケナウ》をイメージ論の観点から考察しながら、リヒター作品を生政治的なアートとして紐解いていく。
吉村朗の眼 ─Eyes of Akira Yoshimura─
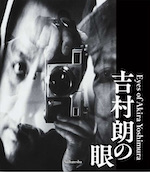
写真:吉村朗/編:深川雅文
発行:さいはて社
発行日:2022年10月20日
サイズ:A4変形判、240ページ
写真表現の革新を目指し、絶えざる前進を続けた吉村朗。馴化されず、媚を売らず、自らの道を突き進んだ、孤高の写真家の眼差しの軌跡と奇跡に刮目せよ!
建築家・石井修―安住への挑戦

編著:倉方俊輔+石井修生誕100年記念展実行委員会
発行:建築資料研究社
発行日:2022年11月10日
サイズ:A4判、176ページ
地形の形状を最大限生かしながら住空間と緑の共生した建築を多く手掛けた住宅作家・石井修。 経年と共に建物は疲弊し、見た目が悪くなってしまうのが一般的だが、年月を掛けることで、自然と建物が一体となることを目指した設計手法は独特である。 今でこそ当たり前の屋上緑化やエコ住宅の考え方も、石井修の自邸「回帰草庵」など初期の作品から取り入れられている。 「建物に外観はいらないのです」という一言に、その建築への考え方が集約されている。 1986年度の建築学会賞を受賞した目神山の一連の住宅作品をはじめ、代表作・天と地の家など、美建・設計事務所を創設以来追い求めてきた建築の理想像-大胆なまでの樹木との調和・合体した住宅作品を収めた「別冊住宅建築No.34」以降、平成期の作品を設計年代順に一挙に収録する。
新宗教と巨大建築 増補新版

著:五十嵐太郎
発行:青土社
発行日:2022年11月14日
サイズ:19cm、445ページ
東大寺や法隆寺だけが美しい宗教建築ではない。著名建築家の作品だけが、先進的な現代建築ではない──。新宗教の巨大で絢爛たる建築が、なぜ信仰の堕落・虚偽の教えの象徴とされるのか。近代国家イデオロギー、天皇制、さらにマスコミが増長させた偏見によって、教団と建築は徹底して弾圧を受け続けた。建築批評の気鋭が読み解く、新宗教建築に投影された「日本近代」の夢と信仰の空間。大幅に増補された決定版。
THE NEW CREATOR ECONOMY[ニュー・クリエイター・エコノミー]

編集:庄野祐輔、hasaqui、廣瀬 剛、田口典子、藤田夏海
発行:ビー・エヌ・エヌ
発行日:2022年11月16日
サイズ:B5判変型、248ページ
本書では、アーティスト、コレクター、キュレーター、リサーチャーなどさまざまな立場の視点を借りて、現在のNFTアートの状況を多面的に解説するとともに、現在へと繋がる歴史にも目を向ける。このグローバルなムーブメントは、連綿と続いてきたコンピュータアートの歴史だけでなく、既成のアートのあり方も書き換えるのか。アーティストはどのような態度で創造に臨むのか。加速するデジタルアートの可能性を追う一冊。
DOMANI・明日展 2022–23 百年まえから、百年あとへ

監修:林洋子(文化庁) 編集:内田伸一、アート・ベンチャー・オフィス ショウ
発行:文化庁
サイズ:A5判、396ページ
2022年11月19日(土)~2023年1月29日(日)まで、国立新美術館にて開催されている展覧会「DOMANI・明日展 2022–23」のカタログ。
飯沢耕太郎「完璧な小さな恋人」

著:飯沢耕太郎
作品掲載作家:野村仁衣那、磯部昭子、下瀬信雄、村上賀子、サイトウマサミツ、ときたま、小林小百合、川田喜久治、小平雅尋、尾仲浩二、飯沢耕太郎
発行:ふげん社
発行日:2022年11月22日
サイズ:B5判、116ページ
写真評論を中心に活動してきた同氏の26年ぶりの詩画集。詩と自作を含むヴィジュアル(写真、ドローイング、コラージュなど)で構成。
合田佐和子 帰る途もつもりもない
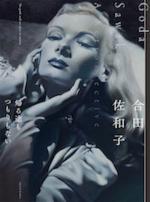
監修:高知県立美術館、三鷹市美術ギャラリー
発行:青幻舎
発行日:2022年11月26日
サイズ:A5判、280ページ
合田佐和子(1940–2016)は高知に生まれ、1965年の個展デビュー以来、オブジェや絵画、写真といったメディアを横断しながら創作を展開しました。唐十郎や寺山修司とのコラボレーション、瀧口修造など美術評論家からの高い評価、またファッションや音楽など領域を超えたものたちとの親和性により、アングラが隆盛した時代の空気を体現するに至ります。しかし一転して90年代以降はその退廃的な作風を脱ぎ捨て、まばゆい光に満たされた、より内省的な世界を深めていきます。
青春20世紀美術講座 激動の世界史が生んだ冒険をめぐる15のレッスン

著:新見隆
発行:東京美術
発行日:2022年11月28日
サイズ:19cm、240ページ
「20世紀美術」は、産業革命ののち、「近代」が定着するとともに露呈したさまざまな問題に直面する中生まれました。芸術家は、「青春」をかけて芸術と社会の問題に取り組み、苦闘の中から前例のない作品を生み出したのです。一方「近代化」の影響は、地球環境問題やコロナ禍などに直面する現代へつながり、人々を苦悩へと引き込みます。解くのが容易ではない山積みの問題を前にした現代の我々は、どうしたらよいのか? 本書では20世紀美術を生み出した芸術家達の苦闘の中にその問いへの答えを探り、現代を生き抜くためのヒントを見出します。
沖縄と琉球の建築|Timeless Landscapes 3

写真:小川重雄
解説:青井哲人
発行:millegraph
発行日:2022年11月29日
サイズ:304×230mm、88ページ
伝統的民家、およそ半世紀前につくられたリゾート建築の金字塔、そしてグスク(城)の遺構、樋川(湧水)、御嶽に見られる密やかな人為の跡、フクギの防風林など、その風土ならではの人工環境を「建築」と捉えた1冊。
潜在景色

編著:アーツ前橋
写真:石塚元太良、片山真理、下道基行、鈴木のぞみ、西野壮平、村越としや
発行:ART DIVER
発行日:2022年11月下旬
サイズ:B5判、144ページ
石塚元太良、片山真理、下道基行、鈴木のぞみ、西野壮平、村越としや これからの写真界を牽引する30歳代から40歳代の実力派作家6名による展覧会の公式カタログ。 撮り下ろし新作を含む、メディア未発表作品を多数掲載。
アートプレイスとパブリック・リレーションズ 芸術支援から何を得るのか

著:川北眞紀子(南山大学教授),薗部靖史(東洋大学教授)
発行:有斐閣
発行日:2022年12月5日
サイズ:A5判、282ページ
デジタル化とコモディティ化が進む現代,アートの「場」から得られる知見や着想,地域や文脈とのつながり,そして真正性は,企業にとって有益なものである。アートプレイスの構築から企業が得られるものとは何か。取材と分析から得られた知見をもとに伝えていく。
金サジ写真集『物語』

デザイン:佐々木暁
発行:赤々舎
発行日:2022年12月中旬(予約販売)
サイズ:B4変形
写真家 金サジの代表作「物語」シリーズの写真集。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
2022/12/14(水)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2022年12月1日号[テーマ:ウォーホルをこの人はどう見ていたか? 個人の記憶と時代が交差する5冊]
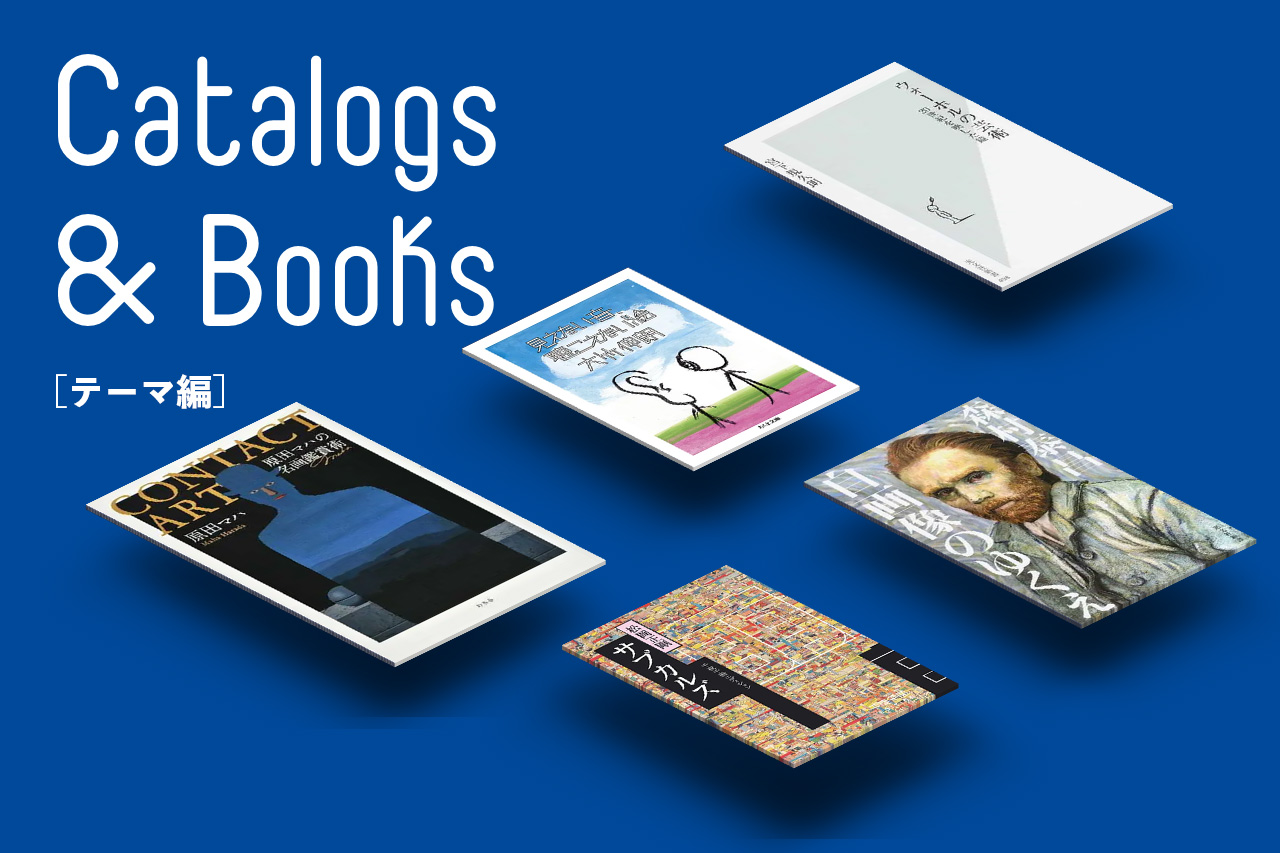
言わずと知れたポップ・アートの旗手ウォーホル。1956年の初来日時の京都と彼の接点にも目を向けた大回顧展「アンディ・ウォーホル・キョウト」(京都市京セラ美術館で2022年9月17日~2023年2月12日開催)に際し、日本の作家や芸術家たちがウォーホルに向けた個人的な眼差しが時代背景とともに垣間見える5冊を選びました。
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
協力:京都市京セラ美術館
今月のテーマ:
ウォーホルをこの人はどう見ていたか? 個人の記憶と時代が交差する5冊
1冊目:見えない音、聴こえない絵(ちくま文庫)
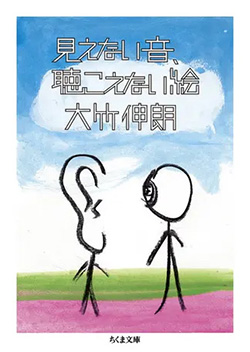
著者:大竹伸朗
発行:筑摩書房
発売日:2022年8月10日
サイズ:15cm、363ページ
Point
アーティスト・大竹伸朗によるエッセイ集。大量消費社会の合わせ鏡としてのウォーホル作品に対する著者の問題意識が綴られる「ウォーホル氏」の章だけでなく、子供時代の雑誌や漫画との衝撃的な出会い、コラージュという手法に目覚めた瞬間など、著者の現在の作家活動にもつながる記憶のディテール描写に気づけば夢中に。
2冊目:ウォーホルの芸術 ~20世紀を映した鏡~(光文社新書)

著者:宮下規久朗
発行:光文社
発売日:2010年4月
サイズ:18cm、294ページ
Point
日本でのウォーホルの回顧展にも関わった美術史家の目線から、メディアを通してセンセーショナルにつくり上げられていった国内でのウォーホルのイメージと、実は多くの人が深くは理解していないであろう美術史上での彼の作品の意義を俯瞰的に解説。ウォーホルという人物を知るうえでの最初の一冊としてもおすすめです。
3冊目:サブカルズ(角川ソフィア文庫 千夜千冊エディション)
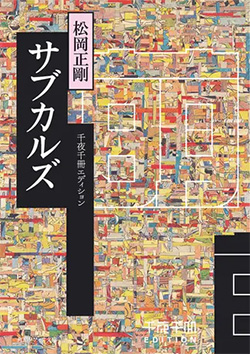
著者:松岡正剛
発行:KADOKAWA
発売日:2021年1月22日
サイズ:15cm、428ページ
Point
現代の知の大家・松岡正剛による「サブカル」に関する書評集。1世紀前のアメリカにサブカルチャーの起源を見出し、日本の漫画・ラノベに至るまで、植草甚一、都築響一、東浩紀などの著書も網羅。ウォーホル『ぼくの哲学』評では「とびきり猜疑心が強くて、ひどく嫉妬心が強い」ウォーホルの人物像を魅力的に描いています。
4冊目:CONTACT ART 原田マハの名画鑑賞術
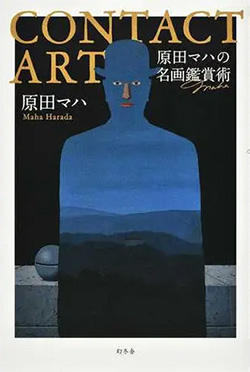
著者:原田マハ
発行:幻冬舎
発売日:2022年10月26日
サイズ:20cm、191ページ
Point
作家・原田マハが日本各地の美術館を訪ね、モネ、ルソー、東山魁夷など名だたる絵画と向き合い語られる、彼女流の作品解説。福岡市美術館で鑑賞するウォーホルのシルクスクリーン作品「エルヴィス」の章も収録。「美術館大国」として日本を少し違った角度から見つめ直すこともできる、アートファンに広く薦めたい一冊です。
5冊目:自画像のゆくえ
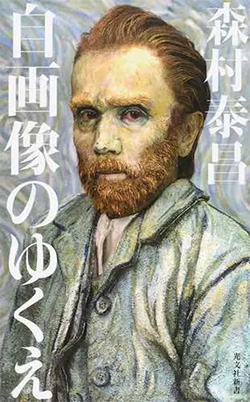
著者:森村泰昌
発行:光文社
発売日:2019年10月17日
サイズ:18cm、615ページ
Point
絵画や作家に扮したセルフポートレイト作品を通してアイデンティティとイメージの関係を問い続ける美術家・森村泰昌が「自画像」という軸で語り直す、世界と日本の美術史。ウォーホル作品を深く読み解く第8章だけでなく、ダ・ヴィンチ、ゴッホから現代日本のコスプレ文化やセルフィーに至るまでの、その射程の広さに驚嘆。
アンディ・ウォーホル・キョウト
会期:2022年9月17日(土)~2023年2月12日(日)
会場:京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」(京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124)
公式サイト:https://www.andywarholkyoto.jp/
[展覧会図録]
「アンディ・ウォーホル・キョウト」公式図録
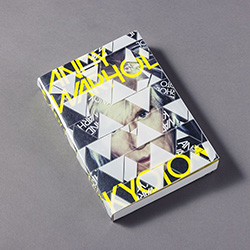
編集:ソニー・ミュージックエンタテインメント、イムラアートギャラリー
発行:ソニー・ミュージックエンタテインメント ©2022-2023
発行日:2022年9月17日
サイズ:A5判型(145×210mm)、340ページ
出品作品のカラー図版と詳細な解説文、本展キュレーターのホセ・ディアズ氏(アンディ・ウォーホル美術館)の「ウォーホルと日本:1956年」と山田隆行氏(京都市京セラ美術館)の「アンディ・ウォーホル・イン・キョウト─ウォーホルの京都滞在(1956年)を振り返る─」論文を収録。1956年のウォーホル来日時の足跡をたどり、ウォーホル芸術に日本が与えた影響を考察します。ニューヨークの「ファクトリー」を二度訪問し、生前のウォーホルと交流のあった美術家・横尾忠則氏によるエッセイも必読! その他にもアンディ・ウォーホル美術館のアーカイブをまとめた『A is for Archive』からファッションをテーマとした「F is for FASHION」を本書のために翻訳。1956年と1974年の二度の日本訪問を記録した貴重な写真を多数収録した永久保存版。
◎展覧会会場にて販売中。
2022/12/01(木)(artscape編集部)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)