artscapeレビュー
artscape編集部のレビュー/プレビュー
カタログ&ブックス | 2022年6月1日号[テーマ:ヨシタケシンスケの視点にシンクロしてしまうかもしれない5冊]
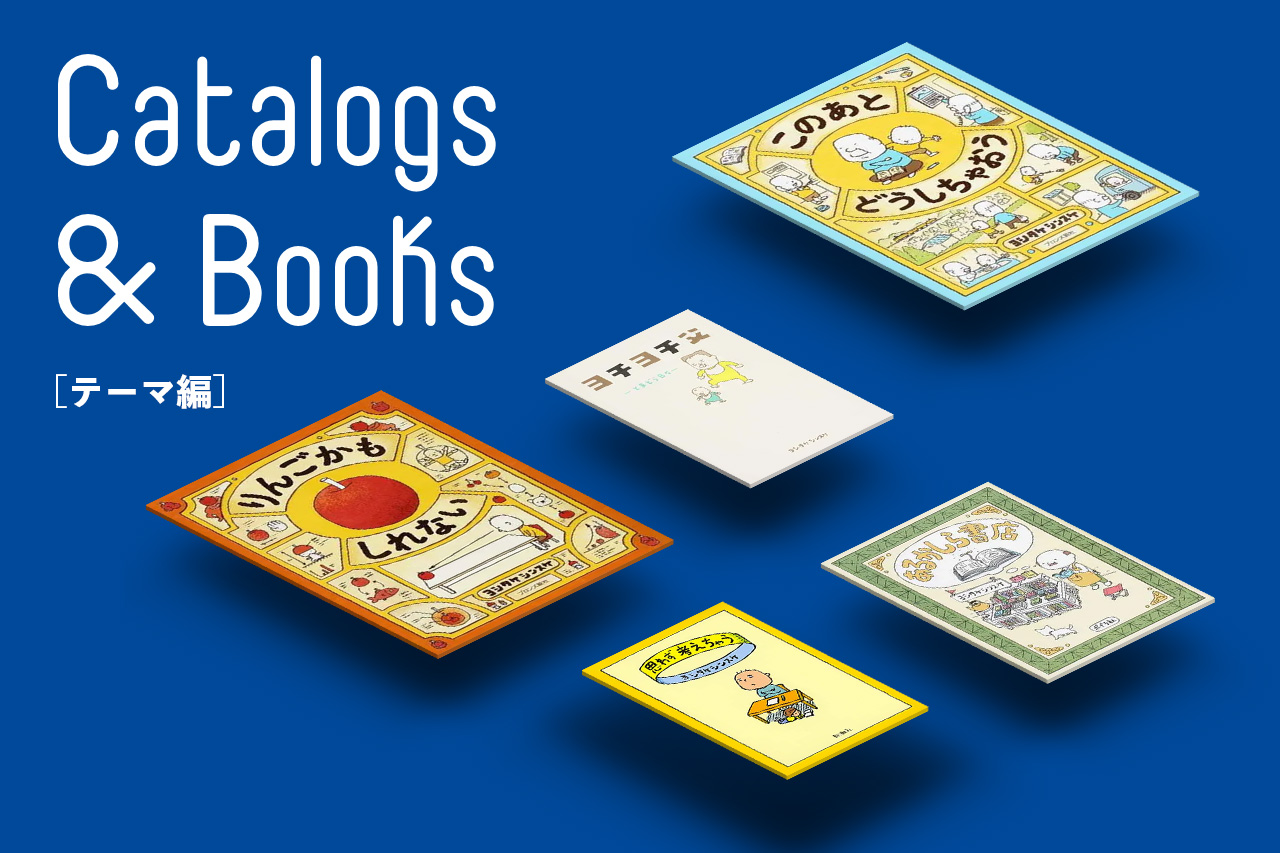
注目の展覧会を訪れる前後にぜひ読みたい、鑑賞体験をより掘り下げ、新たな角度からの示唆を与えてくれる関連書籍やカタログを、artscape編集部が紹介します。
絵本作家として『りんごかもしれない』でデビューして以来、「もしも」の世界の豊かさをさまざまな形で描き続けてきたヨシタケシンスケ氏。世田谷文学館での初の大規模展覧会「ヨシタケシンスケ展かもしれない」(2022年4-7月)の開催も話題のなか、ヨシタケ氏の発想の種が垣間見える、大人も子どもも没入してしまう5冊を選びました。
今月のテーマ:
ヨシタケシンスケの視点にシンクロするかもしれない5冊
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
協力:世田谷文学館
1冊目:りんごかもしれない
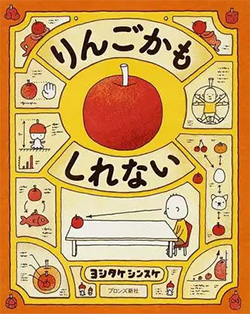
著者:ヨシタケシンスケ
発行:ブロンズ新社
発売日:2013年4月17日
サイズ:27cm
Point
言わずと知れた2013年刊行の絵本デビュー作。目の前の何の変哲もないりんごに、その中身や構造、味、来歴などすべてに「◯◯かもしれない」という仮説を掛け合わせ、想像力を働かせることで見えてくるいくつもの世界をユーモラスに示してみせた本書の構造は、その後のヨシタケ氏の絵本でも一貫しています。
2冊目:このあと どうしちゃおう
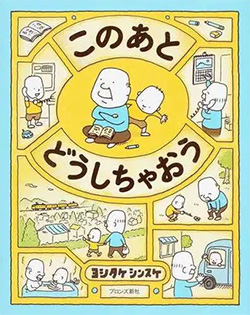
著者:ヨシタケシンスケ
発行:ブロンズ新社
発売日:2016年4月22日
サイズ:27cm
Point
死後の世界はどうなっているの? という問いをタブーにすることなく、むしろワクワクするもうひとつの世界として描いた一冊。自らの両親の他界を経た、日頃から死について気軽に話せた方がいいという想いが本作の出発点だそう。「世の中ふざけながらじゃないと話しあえないこともたくさんある」(付属のリーフレットより)。
3冊目:ヨチヨチ父 とまどう日々
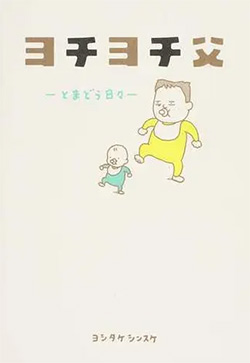
著者:ヨシタケシンスケ
発行:赤ちゃんとママ社
発売日:2017年4月22日
サイズ:19cm、123ページ
Point
父親という立場になって初めて知る感覚を捉えた、ヨシタケ氏自身の視点からのイラストエッセイ。絵に添えられた率直で正直な言葉を押して、きれいごとばかりではない日常、ひいては社会のなかで育児が置かれているどうしようもない現実の姿に共感を抱くお父さんやお母さんはたくさんいるはず。
4冊目:あるかしら書店
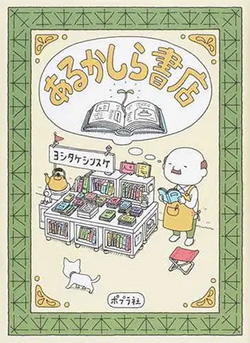
著者:ヨシタケシンスケ
発行:ポプラ社
発売日:2017年6月6日
サイズ:21cm、102ページ
Point
ある町の本屋を舞台に、「こんな本あるかしら?」というお客さんの問いかけから繰り広げられる、「こんな『本にまつわる本』あったらいいな」という妄想のオンパレード。読んでいるうちに何より強く感じられるのは、本や書店への愛とロマン。だんだん本屋に行きたくなってくる、子どもも大人もたっぷり没入できる一冊です。
5冊目:思わず考えちゃう
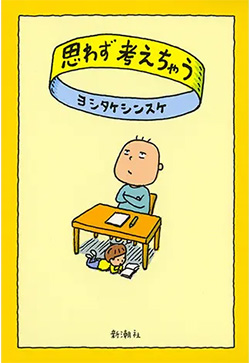
著者:ヨシタケシンスケ
発行:新潮社
発売日:2019年3月29日
サイズ:19cm、143ページ
Point
ヨシタケ氏が日常的に描き留めているスケッチと、それを描いたとき考えていたこと。哲学的な問いにつながりそうな話題もあれば、言語化までは至っていなかった生活の「あるある」もあり、その粒度の幅広さにどんどん読み進めてしまうミニエッセイの集積。この一貫した肩の力の抜け具合、見習いたくなってしまいます。
ヨシタケシンスケ展かもしれない
会期:2022年4月9日(土)~7月3日(日) ※日時指定制
会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1-10-10)
公式サイト:https://yoshitake-ten.exhibit.jp/
『ヨシタケシンスケ展かもしれない公式図録 こっちだったかもしれない』
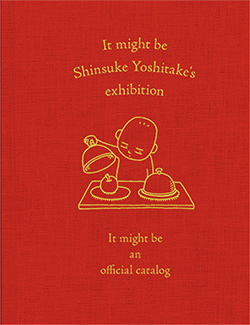
出版社:白泉社
発行日:2022年4月9日
サイズ:B6判変型(W117×H163×D42mm)、496ページ
アートディレクション:大島依提亜
撮影:加藤新作
©Shinsuke Yoshitake
展覧会公式図録は、ヨシタケシンスケ自身が描き下ろしたコンテンツを豊富に収録。絵本のためのラフやアイデア、絵本原画をはじめ、展覧会のために描いた未公開スケッチを1000点以上収録。さらに、展覧会オリジナルグッズを自ら考案したスケッチは170点以上に。展覧会の裏話を含む5500字インタビューや、絵本作家デビューから10年の軌跡をたどる専門家による絵本論も必読です。
◎展示会場で販売中。
2022/06/01(水)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2022年5月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
ポスター芸術論 十九〜二〇世紀フランスの広告、絵画、ポピュラー・イメージ

著:吉田紀子
発行:三元社
発行日:2022年2月25日
サイズ:A5判、306ページ
シェレ、ロートレック、ミュシャ、……街に氾濫する大型の広告ポスター。大量に流通し始めたポピュラー・イメージの衝撃に画家やデザイナーはいかに対峙し、美術批評家、文化政策、産業界はどう関わったのか。フランス美術史への新しい視点。
『丸亀での現在』展カタログ

企画・編集:旅するリサーチ・ラボラトリー
執筆:旅するリサーチ・ラボラトリー、石川卓磨、竹崎瑞季
発行:丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 公益財団法人ミモカ美術振興財団
発行日:2022年3月
サイズ:B5判、152ページ
2021年12月18日〜2022年3月21日に開催された展覧会「丸亀での現在」のカタログ。
国を越えてアジアの芸術

編著:高橋宏幸 ほか
発行:彩流社
発行日:2022年3月16日
サイズ:四六判、335ページ
アジア・アートの国を越える可能性を問うて、各界、第一線で活躍する人達へ取材。西洋規範に則られがちな我々の価値観・芸術観を相対化し、現代演劇や舞台芸術の最前線で「いま・なに」が行われているかを探求する。
文化政策の論理と芸術支援の実際

著者:枝川明敬
発行:晃洋書房
発行日:2022年3月20日
サイズ:A5判、272ページ
文化芸術支援のロジックを欧米と比較しつつ,日本では議論が遅れている芸術の倫理性についても考察。明治期以降の国と地方の行政統治機構の関係を明らかにし,政策決定における会議の内実に踏み込み検討する。
COMPOST vol.03

編集:COMPOST編集委員会
著者:井上明彦、建畠晢、高嶋慈、山本和弘、津崎実、川上央、佐藤直哉、青木敬士、岡田加津子、砂原悟、黒川岳、中村典子、王杰、高林弘実、竹浪遠、棚橋映水、前﨑信也、白石晃一、石原友明、遠藤水城、田口かおり、加治屋健司、中井康之、相澤邦彦、山本毅
装丁・組版:松本久木+納谷衣美(松本工房)
表紙アートワーク:建畠晳
木版画制作:桐月沙樹
発行:京都市立芸術大学芸術資源研究センター
発行日:2022年3月31日
サイズ:261ページ
京都市立芸術大学芸術資源研究センターの研究紀要。
『Chim↑Pom:ハッピースプリング』展カタログ第1巻(LPレコード版)

編集:綾女欣伸/近藤健一
発行:森美術館
発行日:2022年3月31日
サイズ:37.5×37.5cm、47ページ
2022年2月18日(金)~ 5月29日(日)まで森美術館にて開催されている展覧会『Chim↑Pom』のカタログ。
絵の中に入る
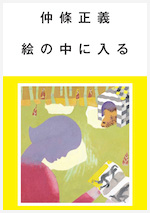
著者:仲條正義
発行:リトルモア
発行日:2022年4月25日
サイズ:A5判、160ページ
グラフィック・デザインで大きな足跡を残した巨星、仲條正義氏が12年にわたり「暮しの手帖」の表紙として描き続けた75枚の絵が一冊に。
蓮の暗号 〈法華〉から眺める日本文化

著者:東晋平
発行:ART DIVER
発行日:2022年4月28日
サイズ:四六判、352ページ
「侘び・寂び」でも「アニミズム」でも「武士道」でもない日本。
その流れは、あからさまな水音を立てない。
むしろ地中深くを潤し、あらゆる草木の根から茎へと巡って森を育んできた。
ありありと描かれているのに、私たちがそうとは気づかないもの。気づかせないもの。
それについて、あえて想像力を豊かに解読の妄想に耽ってみたい。(帯文より)
建築家の基点 「1本の線」から「映画」まで、13人に聞く建築のはじまり

編著:坂牛卓
発行:彰国社
発行日:2022年5月6日
サイズ:四六判、304ページ
建築家の作品は、創造の「基点」が人生の初期に現れ、現在まで継続的に展開している。 本書は、建築家・坂牛卓氏による、建築家13人のインタビュー集。
画文でわかるモダニズム建築とは何か

文:藤森照信
画:宮沢洋
発行:彰国社
発行日:2022年5月6日
サイズ:A5変形、128ページ
藤森照信によるモダニズム建築論を宮沢洋が描くイラストとともに楽しく学ぶ入門書。
世界中の都市に鉄とガラスとコンクリートでつくられた四角い箱が立ち並んでいるのはなぜか?
歴史主義建築が席巻していた19世紀から一転、インターナショナル・スタイルがどのように生まれ世界に広がったのか、その謎に迫る。
ミュージアムグッズのチカラ2

著:大澤夏美
発行:国書刊行会
発行日:2022年5月20日
サイズ:A5判、144ページ
待望の続編‼ ミュージアムグッズの持つ「チカラ」を紐解こう。美術館、歴史博物館、自然史博物館、動物園、水族館……日本全国、あらゆるジャンルのミュージアムを訪ね歩き、その活動とミュージアムグッズを紹介。豊富なインタビューと愛らしいグッズが、あなたをミュージアムの世界へ誘います。
新しいエコロジーとアート──「まごつき期」としての人新世

編:長谷川祐子
発行:以文社
発行日:2022年5月9日
サイズ:A5判、336ページ
本書は、「人新世」「資本新世」とよばれる新しい環境下で生じてきた自然、 政治、社会、情報、精神面での変化に対する現代美術の応答と変容、そして、これらを伝えるキュラトリアル実践に関して、キュレーター、哲学者、人類学者らによる領域横断的なアンソロジーである。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2022/05/13(金)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2022年4月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
語りの複数性

企画・執筆・編集:田中みゆき
発行:公益財団法人 東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 東京都渋谷公園通りギャラリー
発行日:2022年2月
サイズ:A5判、119ページ
2021年10月9日(土)~12月26日(日)に東京都渋谷公園通りギャラリーにて開催された展覧会「語りの複数性」のカタログ。
DOMANI・明日2021-22

監修:林洋子(文化庁)
編集:内田伸一/アート・ベンチャー・オフィス ショウ
発行:文化庁
発行日:2022年3月
サイズ:B5判変形、151ページ
2021年度、全国5会場(京都・水戸・広島・愛知・石巻)で開催した展覧会『DOMANI・明日2021-22 』展のカタログ。
塩田千春 いのちのかたち
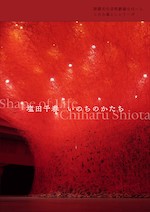
著者:那覇文化芸術劇場なはーと
発行:那覇市文化振興課
発行日:2022年3月、104ページ
2021年12月4日~2022年3月6日に那覇文化芸術劇場なはーとにて開催された塩田千春「いのちのかたち」のコンセプトブック。
都市デザイン横浜 個性と魅力あるまちをつくる

企画・編集:横浜都市デザイン50周年事業実行委員会/横浜市都市整備局
発行:BankART1929
発行日:2022年3月5日
サイズ:A4判、352ページ
横浜の都市デザイン活動の50周年を記念した展覧会に合わせて作成された、これまでの横浜の都市デザインを振り返るカタログ。
新・建築入門 思想と歴史 (ちくま学芸文庫)
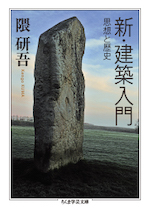
著者:隈研吾
発行:筑摩書房
発行日:2022年3月10日
サイズ:文庫判、240ページ
「建築とは何か」という困難な問いに立ち向かい、建築様式の変遷と背景にある思想の流れをたどりつつ、思考を積み重ねる。書下ろし自著解説を付す。
デザイン保護法
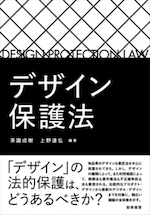
編著:茶園成樹/上野達弘
発行:勁草書房
発行日:2022年3月11日
サイズ:A5判、304ページ
「デザイン」の法的保護は、どうあるべきなのか? 意匠法、著作権法、商標法、不正競争防止法による保護を多角的に検討する。
現代思想入門 (講談社現代新書)

著者:千葉雅也
発行:講談社
発行日:2022年3月16日
サイズ:新書判、248ページ
人生を変える哲学が、ここにある――。現代思想の真髄をかつてない仕方で書き尽くした、「入門書」の決定版。
彫刻2:彫刻、死語/新しい彫刻

編集・装幀:小田原のどか
発行:書肆九十九
発行日:2022年3月18日
サイズ:菊判、608ページ
1940年代後半の、イタリアとアメリカ。〈死語としての彫刻〉と、〈新しい彫刻〉。彫刻の言説はなぜ二分したのか──。「彫刻」をめぐる叢書、最新巻刊行。
おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる 地域×デザインの実践

編著:新山直広/坂本大祐
著者:小林新也/迫一成/古庄悠泰/稲波伸行/福田まや/吉田勝信/佐藤哲也/長谷川和俊/羽田純/吉野敏充/佐藤かつあき/今尾真也/小板橋基希/安田陽子/土屋誠/堀内康広/タケムラナオヤ/森脇碌/中西拓郎
発行:学芸出版社
発行日:2022年3月20日
サイズ:四六判、192ページ
わずかな予算、想定外の作業、地域の付き合い。そんな状況をおもしろがり、顔の見える関係で仕事したり、自ら店に立ったり、販路を見つめ直したり。ディレクションも手仕事も行き来しながら現場を動かし、その土地だからできるデザインを生む。きっかけ、仕事への姿勢、生活の実際、これからの期待を本人たちが書き下ろす。
デザインと障害が出会うとき

著者:Graham Pullin
監訳:小林茂、訳:水原文
発行:オライリー・ジャパン
発行日:2022年3月22日
サイズ:21x15x2.5cm、408ページ
本書は、長年にわたって障害者向けのプロダクトの開発・教育に携わってきた著者による「障害に向き合うデザイン」のための書籍です。ファッション性と目立たないこと、問題解決的アプローチとオープンエンドな探求など、一見対立するように見える要素の健全な緊張関係から生まれる新しいデザインの可能性を考えます。
現代建築 社会を映し出す建築の100年史 (クリティカル・ワード)

編著:山崎泰寛/本橋仁
著者:勝原基貴/熊谷亮平/吉江俊
発行:フィルムアート社
発行日:2022年3月23日
サイズ:四六判、328ページ
都市、技術、政治、文化、メディア。5つの切り口で建築の現代(いま)に迫る。基本用語から、時事、サブカル、最新テクノロジーまで、建築を取り巻く幅広いトピックを一冊で学べる“クリティカル”なキーワード集。
地球的思考 グローバル・スタディーズの課題

編:國分功一郎/清水光明
発行:水声社
発行日:2022年3月25日
サイズ:四六判、492ページ
グローバルな俯瞰力と世界諸地域の文化や社会の多様性はどのようにして思考できるのか? 様々な分野で最先端を走る研究者たちの実践を垣間見る。東大駒場「グローバル・スタディーズ・イニシアティヴ」構想の成果。
原郷の森

著者:横尾忠則
発行:文藝春秋
発行日:2022年3月24日
サイズ:四六判、520ページ
ダ・ビンチ、ピカソ、デュシャン、葛飾北斎、三島由紀夫、黒澤明……横尾アトリエの隣には、芸術家たちが時空を超えて語り合う「原郷の森」がある。さらにはそこに宇宙人たちまで現れて――。横尾版『饗宴』とも呼べる壮大な芸術論が展開される。
黒川紀章のカプセル建築
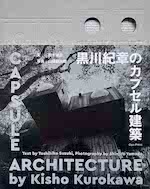
文:鈴木敏彦
写真:山田新治郎
発行:Opa Press
発行日:2022年4月5日
サイズ:B5判変型、254ページ
本書は80年代後半に黒川紀章都市建築設計事務所に所属した著者が、70年代にカプセル建築を担当した元所員にインタビューを行い、1970年の大阪万博のパビリオンや、1973年の別荘カプセルハウスK、1979年に発明した世界初のカプセルホテルを時系列に解説しました。新たに撮り下ろしたカラー写真を豊富に紹介する豪華愛蔵本です。
待ってたぞ!美術館 大阪中之島美術館開館に寄せて

編:中之島芸術文化協議会
発行:澪標
発行日:2022年4月6日
サイズ:四六判、214ページ
もともと大阪には市民の力で作られた文化施設が数多くあるのですが、今まではそれぞれの連携が少なく今一つ存在感を発揮できていなかったように思います。この新美術館が発火点となり核となって大阪が文化都市としてスポットライトが当たるようになればと願っています。(大林 剛郎)
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2022/04/14(木)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2022年4月1日号[テーマ:Chim↑Pomが「時代に呼応」し続けてきた記録としての5冊]
注目の展覧会を訪れる前後にぜひ読みたい、鑑賞体験をより掘り下げ、新たな角度からの示唆を与えてくれる関連書籍やカタログを、artscape編集部が紹介します。
震災、都市、原発などさまざまな社会問題に呼応しては介入を試みるアーティストコレクティブ・Chim↑Pomの過去最大規模の回顧展「ハッピースプリング」(森美術館にて2022年2-5月開催)。2005年から活動を続ける彼らの問題意識と、発想を定着させる瞬発力・行動力にひたすら圧倒される本展。その秘密に迫る5冊を選びました。
今月のテーマ:
Chim↑Pomが「時代に呼応」し続けてきた記録としての5冊
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
協力:森美術館
1冊目:We Don't Know God: Chim↑Pom 2005–2019
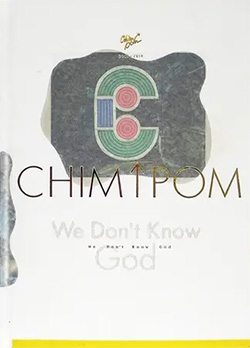
著者:Chim↑Pom
発行:ユナイテッドヴァガボンズ
発売日:2019年6月4日
サイズ:292ページ
Point
それまでのChim↑Pom作品を一挙にまとめた、2019年の刊行時点での決定版的作品集。その後に続くコロナ禍や東京五輪の開催など、この数年間の社会の激動ぶりと、それに呼応して新たな作品を続々と発表しているChim↑Pomの活動の旺盛さに目が回るような思い。会田誠、椹木野衣などによる論考も豊富に掲載。
2冊目:都市は人なり SukurappuandoBirudoプロジェクト全記録
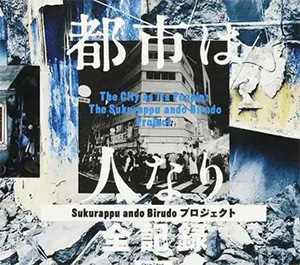
著者:Chim↑Pom
発行:LIXIL出版
発売日:2017年8月18日
サイズ:20×23cm、227ページ
Point
五輪の開催が2013年に決定して以降、都市開発の名の下に急速な変貌を遂げてきた東京。本書は、取り壊しを控えた歌舞伎町のビルでの展覧会「また明日も観てくれるかな?」を中心としたプロジェクトの克明な記録集。初期より路上からの視点を一貫して持ち続けてきたChim↑Pomの《ビルバーガー》はやはり圧巻。
3冊目:はい、こんにちは ─Chim↑Pomエリイの生活と意見─

著者:エリイ
発行:新潮社
発売日:2022年1月31日
サイズ:20cm、174ページ
Point
「ハッピースプリング」展の後半に彼女に焦点を当てたパートがあることからもわかる通り、Chim↑Pomのパフォーマンスに不可欠なのがエリイの存在。そんな彼女が人工授精からの出産を経て上梓したドキュメント。いわゆる出産エッセイとは一線を画する、エッセイと小説の中間のような独自の文体が脳裏に焼き付くよう。
4冊目:公の時代──官民による巨大プロジェクトが相次ぎ、炎上やポリコレが広がる新時代。社会にアートが拡大するにつれ埋没してゆく「アーティスト」と、その先に消えゆく「個」の居場所を、二人の美術家がラディカルに語り合う。
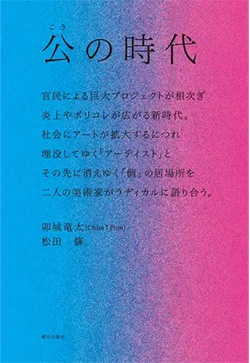
著者:卯城竜太、松田修
発行:朝日出版社
発売日:2019年9月30日
サイズ:19cm、322ページ
Point
Chim↑Pomのメンバー卯城竜太と美術家の松田修による二人の対話で淡々と綴られていくのは、地域芸術祭などを通して公共に「配置」される存在となりかけているアーティストや、現代日本における個人の感覚の変化に対する問題。近年頻繁に起こる、表現活動と炎上の関係性などを考えたい人にも勧めたい一冊です。
5冊目:乙女の絵画案内 「かわいい」を見つけると名画がもっとわかる(PHP新書)
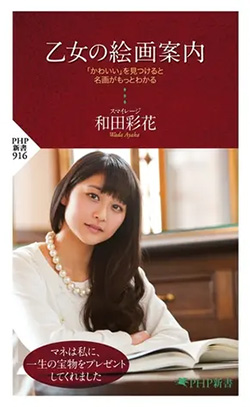
著者:和田彩花
発行:PHP研究所
発売日:2014年6月20日
Point
大学院でも美術史を専攻した和田彩花(元アンジュルム)が古今東西の名画の見どころを綴った、アート鑑賞入門としても読みやすく自由な視点がもらえる一冊。彼女が現代美術の面白さに開眼したのは、3.11に関連したChim↑Pomの展示「Don’t Follow The Wind」(2015)がきっかけだそう。
Chim↑Pom展:ハッピースプリング
会期:2022年2月18日(金)~5月29日(日)
会場:森美術館(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53F)
公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/chimpom/index.html
「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」展覧会図録

出版社:カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、美術出版社書籍編集部
発行:森美術館
発行日:2022年3月31日
サイズ:37.5×37.5cm、48ページ+大型ポスター
言語:日英バイリンガル
展覧会カタログ + 大型ポスター + LPレコード
本展を企画した森美術館キュレーター(近藤健一)による論考や、セクション解説、作品解説、作品図版、作家によるイラストなどを掲載。LPレコードには、展覧会会場用オーディオガイド音声の抜粋とアーティスト涌井智仁によるリミックスを収録。
※LPレコードの音源はパソコンのみでダウンロードできます(期間限定回数制限あり)。詳細は商品に同封される説明書をご確認ください。
◎展示会場、森美術館オンラインショップで販売中。
2022/04/01(金)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2022年3月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
TOKYO POPから始まる 日本現代美術1996‐2021

著者:小松崎拓男
発行:平凡社
発行日:2022年2月18日
サイズ:四六判、304ページ
現代美術の現場を並走してきた著者が語る、日本のアート・シーンの四半世紀。村上隆から奈良美智まで、日本現代美術の貴重な記録。
建築から世界史を読む方法(KAWADE夢新書)
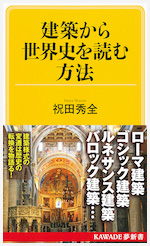
著者:祝田秀全
発行:河出書房新社
発行日:2022年2月21日
サイズ:新書判、240ページ
ギリシャ、ロマネスク、ゴシックなど建築様式の変遷と世界史は連動している。著名な建築物が「なぜそこに」「なぜその意匠で」造られたのかを追究すると、歴史の意外な事実が見えてくる!
日本文学大全集 1901-1925

著者:指田菜穂子
解説:ロバート キャンベル
発行:ART DIVER
発行日:2022年2月22日
サイズ:B5判、152ページ
「絵で百科事典をつくる」という発想のもと、言葉から連想されるあらゆる事象を一枚の画面に緻密に描き込む芸術家・指田菜穂子。その1冊目となる作品集です。
ゴッホを考えるヒント 小林秀雄『ゴッホの手紙』にならって

著者:佐藤公一
発行:アーツアンドクラフツ
発行日:2022年2月24日
サイズ:四六判、112ページ
印象派を超えようとした絵画制作と、いわば「文豪の手紙」とも見まがう書簡文学を表わしたゴッホ。その太陽のように輝く存在であるゴッホの真実を、一枚の《自画像》をからめつつ、ゴッホの全生涯の歩みをたどる。
アート&デザイン表現史 1800s-2000s
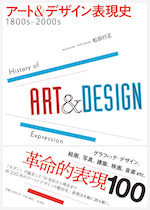
著者:松田行正
発行:左右社
発行日:2022年2月25日
サイズ:A5判、440ページ
グラフィック・デザイン、絵画、写真、建築、映画、音楽etc. 1807年〜2019年までに生まれた革新的な表現法。 その中心となる作品と、そこから派生、影響を受けた作品や似た作品をビジュアルとともに解説する。アートとデザインの歴史が概観できる「デザインの歴史探偵」松田行正による渾身の一冊!
春はまた巡る デイヴィッド・ホックニー 芸術と人生とこれからを語る
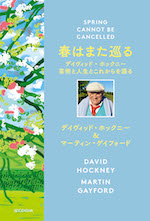
著者:デイヴィッド・ホックニー/マーティン・ゲイフォード
翻訳者:藤村奈緒美
発行:青幻舎
発行日:2022年2月25日
サイズ:B5判変型、280ページ
デイヴィッド・ホックニー×マーティン・ゲイフォード ロングセラー『絵画の歴史』コンビによる コロナ禍、ノルマンディーからの最新エッセイ!
中銀カプセルタワービル 最後の記録
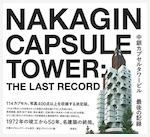
編:中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト
発行:草思社
発行日:2022年3月1日
サイズ:A4判変型、204ページ
1972年の竣工から50年のときを経て解体される、日本屈指の名建築の最後の姿を記録する決定版。114カプセル、写真400以上に、実測図面と論考を収録。
和辻哲郎 建築と風土(ちくま新書)

著者:三嶋輝夫
発行:筑摩書房
発行日:2022年3月8日
サイズ:新書判、256ページ
唐招提寺、薬師寺、法隆寺から、世界の名建築を経めぐり、そして桂離宮へ――。知られざる和辻倫理学のもうひとつの思想的源泉!
新・今日の作家展2021 日常の輪郭

対談:田代一倫×百瀬文、百瀬文×清水知子、田代一倫×倉石信乃
編集:大塚真弓(横浜市民ギャラリー学芸員)
デザイン:川村格夫(ten pieces)
撮影:加藤健
発行:横浜市民ギャラリー
サイズ:B5判、34ページ
2021年9月18日(土) ~ 10月10日(日)に行われた「新・今日の作家展2021 日常の輪郭」の展示風景と、関連イベントの文字起こしを収めた記録集。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2022/03/14(月)(artscape編集部)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)