artscapeレビュー
SYNKのレビュー/プレビュー
釜池光夫『自動車デザイン──歴史・理論・実務』

著者:釜池光夫
発行日:2010/10
発行:三樹書房
価格:2,940円(税込)
サイズ:258×184×20mm
製品のなかでデザインがはたしている役割が重要であるにもかかわらず、デザイン史においてほとんど取り上げられることがない分野がいくつかある。自動車のデザインもそのひとつだと思う。本書で著者も述べているとおり、自動車の歴史の本や写真集は多数出版されているものの、デザインを主体とする本はほとんどないのである。著者は三菱自動車で長らくデザイン開発に従事し、千葉大学を経て現在は芝浦工業大学で教鞭をとっている。本書は大学における自動車デザインのテキストとして書かれ、理論と実務に重きがおかれているが、タイトルにもあるとおりデザインの歴史的考察にも一章を割いているので、ここではその点に触れたい。
自動車デザインの変化をどのようにとらえ、その理由をどのように示すのか。著者は、多数ある自動車メーカーのなかからフォードを選び、そのなかでも年代毎にもっとも売れたモデルを考察し、スタイルの変化を年表にプロットする。その結果、自動車が誕生してから約100年の間に9つの基本スタイル(アイコン)があったとする。各時代における社会環境や生活スタイルの変化を背景に、人々の自動車に対する要求は変化する。その要求を実現する技術進歩があると、スタイルが大きく変化すると著者は指摘する。歴史叙述においてデザイナーの仕事を中心に据えると、特異な外観やデザイン思想を持つプロダクトに目が奪われがちであるが、もっとも売れたモデルに対象を絞ることで、著者は自動車のデザインが社会との関わりのなかで生まれ変化してきた姿を示す。
ところで、そのようなスタイルを規定する社会とは、じつはデザインがなされる時点での社会ではない。自動車のデザインは常に5年から10年先の社会をターゲットとして開発されている。「10年先のユーザーは何を欲し、その時の経済やインフラ市場はどのように変化し、そして周辺技術がどのように進歩しているかなど、ひと・もの(自動車技術)・環境の予測の上に自動車デザインが行われる」。そのためには、「自動車の歴史すなわち、現在と過去の会話を通して将来の予測が不可欠」なのだ。「デザインの方法論の基本は歴史学と言ってよいのです」と著者は書く。
著者はこれまでデザイン学会のジャーナル『デザイン学研究』に自動車デザインの歴史に関する論考をいくつも発表しており、本書第1章はそのエッセンスといえる。このような視点が実践的なテキストに盛り込まれていることはとてもすばらしいことだと思う。[新川徳彦]
2011/02/10(木)(SYNK)
GRAPHIC WEST 3:phono/graph──音・文字・グラフィック

会期:2011/01/18~2011/03/09
dddギャラリー[大阪府]
1877年、エジソンによって発明された蓄音機はphonographと名付けられた。音の(phono)記録(graph)であるphonographは、先行して世に出た、光の(photo)記録(graph)であるphotographyとともに、20世紀の情報世界を形成する重要な役割を担うことになった(藤本由紀夫・広報資料より)。
日常生活のなかで、人が視覚を通して物事を認識する割合は80%にのぼると言われている。もちろん、「物事を認識する」というのが具体的にどのようなことなのかを明確にする必要はあるが、人間のおもな情報源が眼であることは確かだ。だが、皮肉なことに人間のもつ五感のなかでもっとも騙されやすいものもまた、視覚、眼なのかもしれない。たとえば、トリックアートや映像と音声・音楽との関係、色彩心理学などを思い出してみれば容易にわかる。「騙されやすい」とは否定的な意味だが、その裏を返せば、視覚とはそれだけダイナミックな感覚であるという意味にもなる。文字や画像がそのまま音となり、音は文字や画像をもり立て、時には別のものに変える。本企画展は、テクノロジーの発展によって急激な変貌を遂げつつある音と文字との関係、そしてグラフィックデザインのいまを、5組のクリエイターたちを通して紹介している。監修を担当した、アーティストの藤本由紀夫をはじめ、八木良太、ニュール・シュミット(Nicole Schmid)、京都を中心に活動するアート/デザインユニットsoftpad(ソフトパッド)、デザイナーグループintext(インテクスト)が参加。[金相美]
2011/02/08(火)(SYNK)
「倉俣史朗とエットレ・ソットサス展」(オープニングトークと特別シンポジウム)
会期:2011/02/02~2011/05/08
オープニングトーク:21_21 DESIGN SITE、特別シンポジウム:東京ミッドタウンホール[東京都]
東京の「21_21 DESIGN SITE」で開催中の「倉俣史朗とエットレ・ソットサス展」の関連企画として、ふたつのトーク・イベントが実施された。筆者は本展図録に関わった者としてトークを聴講したため、その一端をレポートしておきたい。
第1回目として、2月5日にバルバラ・ラディーチェ・ソットサス氏(以下、ラディーチェ氏とする)と佐藤和子氏によるトークが行なわれた。ラディーチェ氏は30年以上にわたりエットレ・ソットサス(1917-2007)のパートナーであったライターであり、佐藤氏は1960年代からミラノを拠点として活動するジャーナリストである。
トークは、ラディーチェ氏による講演「ソットサスの生きた時代とデザイン」を中心に構成され、ソットサスの仕事がスライドで多数紹介されたが、なかでも印象深かったのは、1970年代以降のラディカルなプロジェクトだ。彼は、1976年にハンス・ホラインがキュレイターを務めた「変容する人類」展(ニューヨーク、クーパー=ヒューイット美術館)に、「人間の権利のためのデザイン」などの写真連作を出品した。これは、山や海辺などの野外に家具などを置いた光景をモノクロ写真で撮り、それを「あなたは芝生の上で寝たいか、それともベッドの上で?」といった警句とともに展示した作品である。その後、1970年代末にはアレッサンドロ・メンディーニらと「アルキミア」に参加。しかし、すぐに袂をわかち、1981年に「メンフィス」を結成する。理由のひとつはソットサスが、プロトタイプを志向したメンディーニとは異なり、デザインとは製造可能なもの、肯定的・楽観的なものであるべきと考えたためだという。1980年代末には広範なテーマを扱った雑誌『Terrazzo』を刊行した。ラディーチェ氏によれば、ソットサスは「デザインのフォルムは機能だけでなく、感情でもある」と語り、「感覚作用はコミュニケーションの手段」「デザインは幸運をもたらすものであるべき」と述べていた。筆者にとってソットサスの作品はモダニズムに対する過激かつ知的な攻撃という印象があったのだが、講演を聞いて、そのような表層的理解では遠く及ばない、人間に対する愛のようなものが彼の作品の底流にあることを知った思いがした。
第2回目は、2月11日に建築家・磯崎新氏を招いて特別シンポジウムが催された。初めに磯崎氏による「post festum──エットレ/シローの1975年」と題された講演が行なわれ、次に公募で選ばれた30代のデザイナーやプロデューサーら5名と磯崎氏によるシンポジウムが短時間ながら行なわれた。
「post festum」とは元来、精神病理学の用語で「祭りの後に」生じる気分を意味し、ここでは1960年代のラディカルな動きの後、日本でいえば、1970年の万博後の喪失感に例えられる。講演ではこの観点からソットサスと倉俣の仕事が分析され、磯崎氏が採り上げたのもまた、1976年のホライン企画の展覧会にソットサスが出品した写真連作だった。氏によれば、同連作は人間が自然においてどこからデザインし始めるかという、デザインに対する疑いを表現しており、新たなデザインの背後にあるものを詩的に表わしたものだという。倉俣史朗(1934-1991)の仕事でクローズアップされたのは、磯崎氏が企画し、1978年に開催された「間」展(パリ、装飾美術館)の出品作《橋》である。板ガラスを重ねたのみの同作品は、氏の解釈では、「橋」や「端」と読み替えられる「はし」、すなわち、世界の境目や繋ぎ目という、空間で線が発生するものの意味をぎりぎりのところで表現している。つまり、お祭り騒ぎの後にソットサスや倉俣が向かったのは、デザインをこれ以上削ぎ落せない状態にまで追い詰めることだった。だが、シンポジウムで磯崎氏が若者たちに語ったのは、単に先人の教えに学べということではない。氏が温かな口調で語ったのは、技術も社会も以前と異なる現代においては、70年代とは問いややり方も異なるのであり、新世代に託された課題とは、自ら新しい問いややり方を開発することなのである。それは難題極まりないが、少なくとも新しい世代が、例えば思いつきでデザインする前に、ソットサスや倉俣、磯崎氏と同様の真摯な態度を今一度デザインに対して持とうとすることは必要だろう。バルバラ氏も磯崎氏もそれを心からの言葉を以て示してくれたのである。[橋本啓子]
2011/02/05(土)(SYNK)
マイセン磁器の300年──壮大なる創造と進化

会期:2011/01/08~2011/03/06
サントリー美術館[東京都]
2010年に開窯300周年を迎えたドイツのマイセン磁器製作所の歴史を約160点の作品により辿る展覧会。時代順に5つの章にわけられて作品が展示されており、各章に時代背景についての解説があるため、たとえ陶器に関心がなくとも文化史として十分に楽しめる。その点で興味深かったのは、やはり西洋磁器の最高峰としてのマイセンの地位を不動のものにした第1、2章の時代の展示だろうか。
第1章では、まず17世紀から続くヨーロッパの王侯貴族の東洋磁器収集の背景が語られる。熱狂的な収集家であったザクセン選帝侯アウグスト強王(1670-1733)が、錬金術師ベトガー(1682-1719)を幽閉してまで硬質磁器の解明を渇望したという史実は、のちの西洋近代主義の精神を予見するものだろう。実際、ヨーロッパ初の硬質磁器の誕生には、哲学者・数学者・科学者チルンハウス(1651-1708)の貢献もあった。展示作品は、赤い「ベトガー 器」に始まり、ドレスデン近郊で発見されたカオリンを用いた白磁の作品がそれに続く。この白磁は東洋の青味がかった磁器よりも白く、この白さは西洋磁器を特徴づける要素となる。続いて絵付師ヘロルト(1696-1775)によるシノワズリ(中国風)などの華麗な作品が登場する。愛らしい絵付けは今日のマイセン磁器にも受け継がれている。
第2章では、バロックとロココの時代に特有な文化であった「メナージュリ(宮廷動物園)」の発想を中心とした展示内容となる。アウグスト強王は、東洋の品やマイセン磁器で埋め尽くした「日本宮」の造営を計画し、その大広間に磁器の動物によるメナージュリをつくることを夢みた。計画は王の死により挫折したが、この時期、彫刻家ケンドラー(1706-1775)の原型になる動物彫刻が多数製作された。本章ではケンドラーの原型に基づき製造された代表作《コンゴウィンコ》(原型1732、製造1924-1932頃)や、やはりケンドラーが得意としたフィギュリン(小立像)が出品されており、磁器による精緻な彫刻を可能にした当時のマイセンの抜きん出た技法は無論のこと、他国に比べて自然主義的傾向が強かったドイツ・ロココの特徴も伝えてくれる。
第3章から第5章までは、19世紀の万国博覧会時代以降、アール・ヌーヴォー、アール・デコの時代を経て、現代のアーティスティックな作品に至るまでの作品が展示されており、おのおの当時のヨーロッパの流行を映し出している。もっとも、1960年に製作所内でアーティストたちにより結成された「芸術の発展をめざすグループ」の幻想的な作品群は、当時のポップの流行とは異質であるかもしれない。シュトラング(1936-)が1969年に原型・装飾を手がけた《真夏の夜の夢》とツェプナー(1931-)の1974年の原型による《アラビアン・ナイト花瓶》が放つ奇妙なエキゾチックさは、社会主義体制という状況があってこそ生まれたものなのか、あるいはそれとはまったく無関係なのか。もし解説パネルにそのような背景との関わりが記してあれば、不勉強の身にはありがたかった。同時にまた、東西の壁が崩壊して20年を過ぎたいま、19世紀以降のマイセンの展開に関してはさらなる研究が求められる時期に来ているのだろうと思った。[橋本啓子]
図版キャプション=真夏の夜の夢《ティタニアとロバ頭のボトム》と《オベロン》原型・装飾ペーター・シュトラング、原型・製造1969年、国立マイセン磁器美術館所蔵
2011/02/04(金)(SYNK)
エイドリアン・フォーティ『欲望のオブジェ─デザインと社会1750年以後』
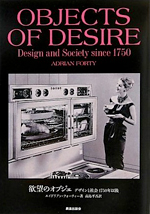
著者:エイドリアン・フォーティ
訳:高島平語
発行日:2010/08
発行:鹿島出版会
価格:3,465円(税込)
サイズ:208×148×22mm
長らく版元切れとなっていたエイドリアン・フォーティの『欲望のオブジェ』がソフトカバーの新装版になって復刊した。単なるリプリントではない。1)新たにフォーティによるまえがきが附された(2005年版の原著に加えられたもの)。2)翻訳が一部手直しされた。3)写真図版がきれいになった。4)著者名のカナ表記が変わり、また副題も英文にあわせて変更された。5)価格が安くなり入手しやすくなった。
内容についてはいまさら語るまでもないかも知れない。原著は1986年、邦訳は1992年に刊行された。デザインの歴史を語るにあたって、フォーティは二つの対象からアプローチを試みる。ひとつは、モノをつくる企業あるいは流通・市場。もうひとつは、消費者である。陶磁器、ナイフ、家具、家電製品等々、彼は多様な商品のデザインを事例として、モノがつくられ、売られ、買われるプロセスを描き出す。中心にあるのは消費である。そこには、デザイン史で主流であったデザイナーの思想やデザイン運動の歴史はない。本書はデザイン史の名著あるいは必読書とも言われるが、刊行当時デザイン誌の大半から敵対的な反応があったという。批判の中心はまさにデザイナーの貢献を排除している点にあった。もちろん、こうした批判をフォーティは想定していたであろう。「序論」を読めば、本書がペヴスナーの系譜に連なるデザイン史の方法を批判していることは明らかだからだ。
ではなぜ彼はこのようなアプローチを試みるに至ったのか。新装版のまえがきは「私がこの本を書きはじめたときには、まだ『グッド・デザイン』というようなものがあった」ということばから始まる。フォーティが本書を書きはじめたころ、すでにデザインに対する多様な価値観が現われつつあったはずだが、歴史叙述においてはいまだモダニズムの価値観が幅をきかせており、その価値観によって選別された「優れたデザイナー」「優れたデザイン」の歴史を描くことが正しいデザイン史の方法であると考えられていたのだ。はたして「グッド・デザイン論」に依らずにモノの出現と変化の歴史的プロセスを描くことはできないのか。この問題に対する答えが本書だとフォーティはいう。
フォーティが試みた二つのアプローチ対象のうち、消費に関してはその後社会学やカルチュラル・スタディーズとの関連において発展してきたが、企業や市場とデザインとの関係はあまり人々の関心を惹かないようである。どのようなデザインが社会に現われるかという点において、企業のはたしてきた役割はデザイナーの貢献に劣らず重要だと思うのだが。[新川徳彦]
2011/02/03(木)(SYNK)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)