artscapeレビュー
建築に関するレビュー/プレビュー
コープ・ヒンメルブラウ 回帰する未来
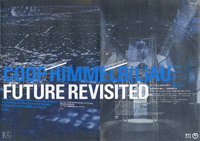
会期:2009/09/19~2009/12/23
NTTインターコミュニケーション・センター(ICC)[東京都]
コープ・ヒンメルブラウは、ヴォルフ・プリックスを中心人物として1968年に設立されたオーストリアの建築設計事務所。《アストロバルーン 1969 リヴィジテッド──フィードバック・スペース》と《ブレイン・シティ・ラボ》という二つの作品を展示。前者は、皮膜を装着することで心拍を光や音に変換する1969年の《ハート・スペース──アストロバルーン》の発展形で、2008年のヴェネツィア・ビエンナーレに出展されたもの。装着することで身体が拡張するという意味では、同じオーストリアの建築家・彫刻家であるワルター・ピッヒラーの透視ヘルメット(《TV-Helmet (Portable living room)》、1967年)のコンセプトと似ているし、彼らが知らなかったはずがない。しかしピッヒラーが彫刻的に拡張現実を表現したことに対し、コープ・ヒンメルブラウは、光や音といった形なき形態として表現する。バルーンも、形はあるが、透明である。後者は、パリ郊外の都市計画プロジェクトから発展し、神経科学と都市計画の接点を見つけようとするもの。観客の位置に従って、都市模型に光の道が生まれては消えていく。コープ・ヒンメルブラウの建築が、形態的な特徴をもつことと対照的に、本展示では形にならない、光や音や軌跡といったものが表現されている。しかし、むしろこの展示から彼らの建築形態の目指す本質が見えてきたような気がした。ヒンメルブラウはドイツ語で「青い空」を意味し、彼らは雲のような変幻自在な建築を目指すのだという。過去にザハ・ハディドらとともにデコンの建築家として扱われたことから、形態へのこだわりを感じていたのであるが、むしろ形態なき形態こそが彼らの建築の本質にあるのだろう。
展覧会URL:http://www.ntticc.or.jp/Exhibition/2009/CoopHimmelblau/index_j.html
2009/10/18(日)(松田達)
近藤哲雄《するところ》

[東京都]
竣工:2009年
SANAA出身の建築家近藤哲雄による、200平米程度の築40年の古い工場の改修。一階が印刷所、二階が地域の人たちがワークショップ等を通じて交流するためのスタジオ兼事務所。紙や印刷を活かしたワークショップが行なわれるという。外壁は白く塗られ、3カ所に大きな開口部が開けられた。工場という閉じた空間を、街に開いていく意図が込められているという。また二階の床の一部が大きく切り取られ、上下階がつながり、一階の印刷機の様子を見ることができる。特に、開口部の開き方が興味深い。道路に面した長辺側面の開口部は、建物全体のプロポーションを異化させるくらい巨大であり、まるで外壁が「紙」でできているかのような印象もある。この開口部の大きさとリズムからは、ル・コルビュジエのオザンファンの住宅の開口部も想起された。サッシ枠の見付けがかなり細く、そのことが開口部の大きさを余計に引き立てていたといえよう。40年の間に開けられた複数のタイプの開口部が同居していることも面白い。抽象的な空間を獲得すると同時に、歴史を内包し、下町の空間にもなじんでいた。
写真提供:近藤哲雄
2009/10/17(土)(松田達)
隈研吾 展「Kengo Kuma Studies in Organic」

会期:2009/10/15~2009/12/19
ギャラリー間[東京都]
ギャラリー間で開かれている隈研吾の展覧会。下階には多くのスタディ模型やサンプルの展示、中庭には水を入れたポリタンクでできた《ウォーターブランチ》が原寸大で設置、上階には《グラナダ・パフォーミング・アーツ・センター》や《ブザンソン芸術文化センター》の1/25の大型模型等が展示。大きなテーマは、抽象的なるものから抜け出した先にある有機的なるものだという。
有機的?建築を消す、溶かす、砕く、といっていた隈が、その方向性を180度変えたようなキーワードではないか。晩年のコルビュジエのロンシャンの礼拝堂にはじまる見かけ上の大きな転向も想起されよう。あるいはフランク・ロイド・ライトか。しかしこれは転向ではないはずだ。過去に、一度も隈は転向していない。今回は、建築的遺伝子が、環境に負けながらある全体を生成していくプロセスによって、有機体にたどり着こうとする試みだという。展示のポイントは、まさにタイトルにあるように「Studies」と「Organic」にあるだろう。「Organic」を実現するために、その生成をシミュレートしたかのような「Studies」が、下階にて展示されているのだ。この生成の過程が興味深い。OMA/AMOの「Contents」展やHerzog & de Meuronの「NO.250 An Exhibition」展を見たときの印象に近く、膨大なスタディ模型がところ狭しと並べられていた。おそらく、状況は近い。数年前にOMAとH&dMが近づいてきたと感じたのと同じような状況を感じた。グローバルな状況下においては、設計事務所のスタッフの流動化も起こり、情報や考え方も似通ってきてもおかしくはない。
にもかかわらず、それらの展覧会とは何かが違う印象も受けた。OMAやH&dMの展示は、多くのスタディ案を「進化」させていくことにより、従来なかった建築に到達するという方法論による最良の展示であった。これは、建築においてはいわば一般的な方法論であるともいえよう。多くの案をつくるうちに、突然変異と自然淘汰によって、結果的に進化が起こる。選択は暗黙には建築家が行なうといえるので、ダーウィンの自然選択説になぞらえて建築家選択説といってもよいだろう。一方、隈の展示から感じたのは、そのような「進化」ではないという印象だった。それに変わる言葉として「エピジェネティクス」が最も適切であるように思われる。「エピジェネティクス」とは、個体におけるDNA配列の変化によらない後天的な作用が、遺伝子発現を制御する仕組みの総称のことである。「進化」が世代を超えることによって生まれる変異であるのに対し、「エピジェネティクス」は同一個体における環境の違いによって生じる変異である。隈は、細胞が環境に応じてさまざまな紆余曲折を経て有機体にたどり着くイメージについて語っていた。これは、「建築家」が複数の変異体の中から、もっとも適した案を「選択」することを、他世代にわたって繰り返しつつ案を「進化」させていくというモデルとは明確に異なり、個体としての「建築」がそれを取り囲むさまざまな条件といった「環境」的な要因に影響を受けながら、後天的にある「形質を獲得」するというモデルである。このモデルは「獲得形質の遺伝」を主張したラマルク説に近いものである。ラマルク進化論は、歴史上批判され続けてきたが、エピジェネティック機構の発見により、完全に否定はできなくなった。
つまり、隈の考える建築の生成のイメージは、ダーウィン的な進化モデルより、ラマルク的な進化モデルにむしろ近いものである。ある建築が、環境に応じて、自分自身を発見していくというプロセスは、従来のダーウィン進化論的な建築生成モデルに対して、オルタナティブをつきつけるものとなるのではないだろうか。今回見た隈のいくつかのプロジェクトから感じたのは、多世代に渡り行き当たりばったりな突然変異を繰り返すうちに、一定の段階に到達したような建築ではなく、ある環境に応じて変化を繰り返しているうちに確実に解にいきつくような、生命として連続的同一性を持ったような建築であった。
2009/10/14(水)(松田達)
菊地宏 展「FOTOTEST」

会期:2009/10/03~2009/11/01
radlab.(京都市中京区恵比須町531-13-3F)[京都府]
京都で開かれた菊地宏の展覧会。場所はRAD(川勝真一+榊原充大)の活動拠点、京都河原町三条にあるradlab.内。写真で展示するという条件の使い方がうまい。建築の展示では模型と大判の写真が分かりやすいはずであるが、ギャラリーの大きさや効果を加味して、ほとんどアートの展示のように写真が配置されていた。パースにあわせて微妙に折り曲げられた写真、包み張りキャンパスの布地のように木枠の裏側で写真の印刷面を留めることにより枠の側面にも回り込んだ写真、展示の原則をあえて外し奥行き方向にやや傾けられた写真など、ヴァリエーション溢れる「建築写真」の展示がされていた。おそらく展示に使える予算的な条件もあったのだろうが、むしろ写真という条件を逆手に取り、建築と写真の関係を思考させるという方向に展開させた点が秀逸な展覧会だった。
2009/10/12(月)(松田達)
水都大阪2009

会期:2009/08/22~2009/10/12
中之島公園・水辺会場、八軒家浜会場、水の回廊・まちなか会場[大阪府]
大阪・中之島エリアを中心に、約7週間にわたって多数のワークショップ、展覧会、各種イベントが開催された「水都大阪2009」。しかし、終了後に改めて思ったのは、果たしてこの催しにアートは必須だったのかという疑問だ。もちろん、ヤノベケンジは奮闘したし、今村源が適塾で行なった展示は見応えがあった。ワークショップのなかにもきっと素晴らしいものがあったのだろう。でも、私が何度か会場を訪れて感じたのは、アートと言うよりも文化祭的な狂騒ばかりだ。いや、最初からアートは脇役で、私が勘違いしていただけなのかもしれない。結局、最後まで意図を理解できないまま「水都大阪」は終わってしまった。
2009/10/12(月)(小吹隆文)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)