artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
ルーシー・リー展

会期:2010/12/11~2011/02/13
大阪市立東洋陶磁美術館[大阪府]
一気に春が来たようで、心が躍った。陶芸家ルーシー・リー没後初めての本格的な回顧展。ウィーン時代の初期から、ロンドンに渡って以後──形成期・円熟期──の作品まで、約200点の作品が展示され、見応え充分。柔らかく明るいピンクにレモン・イエロー、爽やかなブルーがとりわけ目を引く。フリーハンドによる温かみのある線、ストライプや格子柄の文様はどれもすがすがしい。その端正なうつわの佇まいには、しかし、歪みのあるフォルムや釉薬の滲み・変調など、どこか揺らぎの要素があって、それが私たちの諸感覚をいっせいに刺激する。傾いだ部分や熔岩釉のようなでこぼこした表面には、つい触れてみたくなるし、彼女のうつわにはなにを盛ったら美味しそうか、とまで想像してしまう。初期から後年にかけての作品を順に見続けていくと、彼女の造形の根底にある宇宙観のようなものを、うつわの総体に感じた。それはひとつには、轆轤を使って彼女の手が「つくる」反復的行為から生まれる、永遠的なるものの表出であるかもしれない。だがもうひとつ、図録の出川哲朗氏の論文「ルーシー・リーの現代性」が、その謎を解く鍵を与えてくれる。リーと物理学との関係性がそれだ。なお、本展の図録はその内容に加えて、とても素敵な製本になっているのでお薦めしたい。見返しのうつわの色とリンクする、花布・栞のピンク色を見たとき、「やられた!」。[竹内有子]
2011/01/13(木)(SYNK)
白石綾子 展

会期:2011/01/07~2011/01/22
Gallery Q[東京都]
顔を伏せたまましゃがみこむ女性の身体。洋服の模様が身体の皮膚にまで及んでいるので、まるで刺青のようにも見えるが、これは模様を描いたのではなく、その模様の生地の上に絵を描いたのだという。昨年、ギャラリー・ショウ・コンテンポラリー・アートで松山賢が同じような絵を発表していたが、白石とはじつに対照的だ。松山が確信犯的に皮膚に背景の模様を描き込み、だからそこには主体としての身体と客体としての背景という関係が一貫していたのに対し、白石の絵には背景の方に身体が溶け込むかのような透明感がある。主体はむしろ背景の模様であり、身体はそこに隷属しているわけだ。この図柄に侵犯される身体という主題が、服飾や美容に翻弄される現代女性の身体観を明示しているのは疑いないが、同時に色やかたちを反復する「芸術的なもの」が顔に象徴される個性を抹消するほどのさばっている現代社会も暗示しているように思えた。
2011/01/13(木)(福住廉)
青木千絵 展 URUSHI BODY

会期:2011/01/07~2011/01/28
INAXギャラリー2[東京都]
漆とはかくもエロティックなものだったのか。青木千絵が制作した女性像を目の当たりにすると、伝統工芸としての漆という既成概念がみごとに覆される。漆で制作された女性像は、黒光りした表面と屈折した身体のかたちが女性の滑らかな皮膚感を再現しているようで、艶かしいエロティシズムを感じてならない。かといってすべてを具象的に表現しているわけではなく、上半身を丸く抽象化したり、他の下半身と連結させるなどして、下半身の造形に眼を巧みに誘導するところも、そうしたエロスに拍車をかけていたようだ。内実を欠いた表面の円滑性。スーパーフラットが目指していた理想は、じつは伝統工芸のなかですでに実践されていたのではなかったか。青木千絵の漆は、次の時代を切り開く鍵が、必ずしも新たな表現様式だけに隠されているわけではなく、伝統的な工芸のなかにもひそんでいることを予感させた。
2011/01/13(木)(福住廉)
mariane個展 um beijinho!

会期:2011/01/08~2011/01/16
iTohen[大阪府]
和紙にアクリル絵具で描かれたmarianeの作品。植物と海の軟体生物が融合したような不思議な生命を、細かな線と鮮やかな色彩で表現しており、濃密なエロティシズムを内包しているのが特徴だ。和紙を用い、背景を描かない画風は日本画を思わせるが、実はアクリル絵具でほとんど下書きなしに描かれているのも興味深い。また新作では、ひとつのモチーフを異なる角度から描き分けたり、誕生から朽ちるまでの経過を表現するなど、新たな展開も見られた。以前の個展と比べて伸びが感じられ、作家が充実期に入ったとの思いを強く感じた。
2011/01/12(水)(小吹隆文)
圓井義典「光をあつめる」
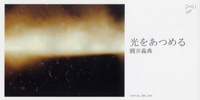
会期:2011/01/11~2011/02/26
フォト・ギャラリー・インターナショナル[東京都]
柴田敏雄、畠山直哉、松江泰治、鈴木理策など、それぞれスタイルは違っていても、中判~大判カメラを使って「風景」を緻密に描写する写真家たちの系譜が1980年代以来途絶えることなく続いている。それは明らかに日本の現代写真の重要な流れを形成しているのだが、圓井義典もそこに連なる作家といえるだろう。彼は2000年代以降「自分の暮らす世界、とりわけこの日本という国を自分の目で見て回りたい」という意欲的なプロジェクトを展開している。その成果は「地図」(2000~05年)、「海岸線を歩く──喜屋武から摩文仁まで」(2005~08年)といったシリーズにまとまり、個展やグループ展で発表されてきた。
今回展示された新作「光をあつめる」は、これまでの作品とは一線を画する意欲作である。ちょうど「海岸線を歩く──喜屋武から摩文仁まで」を制作するため沖縄の旅を続けていた途中で、カメラのピントグラスに光が突然飛び込んできたのだという。それを「何ものをも名指しえない、原初の光」であると感じとった彼は、光そのものを定着することに取り組んでいった。ピントをわざとはずした画面に捕獲された光は、点、塊、渦巻きとさまざまな形に変容し、手応えのある物質感を感じさせる。このチャーミングな作品群が、これから先どんな風に展開していくかが楽しみだ。なお、展覧会にあわせて写真集『圓井義典 2000-2010』(私家版)が刊行された。3つのシリーズを分冊で木箱におさめた、すっきりとした造本(アートディレクション=中新)の写真集である。
2011/01/11(火)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)