artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
グザヴィエ・ヴェイヤン展「FREE FALL」
会期:2011/01/15~2011/05/08
エスパス ルイ・ヴィトン東京[東京都]
以前は、一般に非公開だったルイヴィトン表参道の7階スペースが、アートの空間として開放された。その下の外壁とは違い、ガラスに囲まれた空間は、まわりの都市を眺めるのに絶好の場所だ。ヴェイヤンは、コンストラクティヴィズム、モビールなどを踏まえ、青木淳が設計した白く塗られた鉄骨の部屋とばっちり似合うインスタレーションを展開している。つまり、建築的な作品であると同時に、建築とも調和するのだ。もっとも、床にベニヤ板を敷き詰め、工事現場のような雰囲気に変えるなど、ラグジュアリーな建築にも介入している。彼はヴェルサイユ宮殿で「建築家」展(2009)を開催しているが、村上隆のヴェルサイユ展も空間と作品の相性が抜群だった。ヴェイヤンの自由落下をテーマにした作品群でも、自らの落下のイメージを表現した「FREE FALL」(2011)はとくに興味深い。ただの画像に見えて、実はピンによって多数の紙片をとめており、個別のサイズよりも重さのバランスによって、必要なピンの数が決まっている。
2011/01/22(土)(五十嵐太郎)
荒川智則 個展

会期:2011/01/13~2011/02/13
トーキョーワンダーサイト渋谷[東京都]
渋谷のTWSにて、カオス*ラウンジによる荒川智則展を見る。なんでロゴがメタリカ風なのだろうと思いつつ、会場のオタク的な空間とゆるい雰囲気に現代らしさを痛烈に感じた。即座に秋葉原的なオタクショップ、あるいはメイドカフェや猫カフェなどのラウンジなどを連想させる空間だろう。「?」をつきつける意味では「アート」なのだが、筆者は技術や審美にもとづく作品の方が好みだと痛感した。一見、ゆるくて汚い感じは、泉太郎の展覧会とも似ているのだが、彼は空間の使い方が巧く(神奈川県民ホールギャラリーの「こねる」展)、古典的な意味でもアートになりえている。ダメならもっと徹底する道もあると思うが、それも狙いではないのだろう。また本展は、集合知の別名である荒川智則とは誰かをめぐって、ネット時代の言説と批評を喚起する。確かに、語りたくなる展覧会ではある。
2011/01/22(土)(五十嵐太郎)
森村泰昌 なにものかへのレクイエム─戦場の頂上の芸術
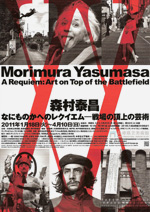
会期:2011/01/18~2011/04/10
兵庫県立美術館[兵庫県]
東京、愛知、広島を巡回し美術ファンの注目を集めてきた本展が、遂に(やっと)関西で開催。待たされた分だけ期待は膨らんだが、森村の作品はこちらが勝手に上げたハードルを楽々と超えてきた。「時代」という得体の知れないものに真正面から向き合って、堂々たる見解を示したその手腕に感服! また、映像作品の比重が高まっていることから、今後の森村の展開へも思いを馳せることができた。全43点の作品のうち、私が特に注目したのは、《烈火の季節/なにものかへのレクイエム(MISHIMA)》と、《海の幸・戦場の頂上の旗》の2作品。共に映像で、これまでの森村では考えられないほどメッセージ性の強い作品だ。この2点を見られただけでも、本展は価値があると思う。
2011/01/22(土)(小吹隆文)
トランスフォーメーション
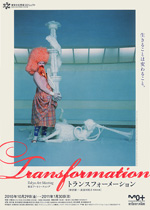
会期:2010/10/29~2011/01/30
東京都現代美術館[東京都]
明治以来の西洋コンプレックスはいったいいつまで続くのだろうか? 長谷川祐子がキュレーションを手がけた展覧会を見ると、つねにやるせない倦怠感を覚えてならない。西洋の芸術を翻訳しながら輸入することで前進してきた美術史がもはや隠しようがないほど行き詰まり、それに代わる新たな歴史観を模索することが、少なくとも80年代後半のポストモダニズム以後の共通認識だったはずだ。「日本」固有の歴史をでっちあげるにせよ、東アジアの連帯を目指すにせよ、日本社会の隅々で地域の再生に取り組むにせよ、あるいはもっと別のかたちを考えるにせよ、この数十年はその糸口を求めた試行錯誤の連続だったといってよい。けれども、いずれの立場にも通底していたのは、西洋の芸術を一方的に受容する歴史のモデルからの意識的な切断だった。にもかかわらず、何かといえばマシュー・バーニーを召還し、白い空間に審美的な作品を並べ立てる(だけの)展示は、もうこれまで何度も見てきたし、はっきり言って、そうとう古い。今回の展覧会では、その古さを覆い隠す装置として「人類学との出会い」が演出されたのだろうが、それにしてもいかにも取ってつけたような中途半端な扱いで、古さを塗り変えるほど新しいわけではない。いや、これまでの輸入史観を批判的に相対化する視座をもたらした90年代のポストコロニアリズム理論やポストモダン人類学の成果がまるで考慮されていなかったことを考えると、むしろ退行というべきである。こうした果てしない悪循環を許してしまう、私たち自身の精神構造に蔓延る奴隷根性こそ、もっとも厄介な問題なのだろう。
2011/01/21(金)(福住廉)
はろー、言ってみる/ミシシッピ展 hello it's me.

会期:2011/01/18~2011/01/28
ギャラリーH2O[京都府]
2009年から複数のアーティストとともにコミック誌『KYOCO(キョーコ)』を発行するなど、コミック作家としても活動しているmississippiの個展。印刷された小さな誌面やグループ展でその作品を見ることはあったが、これまで彼の大きなペインティングを目にする機会はほとんどなかった。2010年の12月に東京で開催された個展で出品されたドローイングに加え、新作のペインティングが発表された今展、展示数は少なかったが、それまでとは異なる面で、その作品世界の魅力がうかがえるものだった。やや暗いグレーのトーンで描かれた情景の夢のような浮遊感が物語を誘発し、場面への想像をかき立てる。カラスや人物など、かわいいのかそうでないのか微妙なモチーフやそれらの表情も、つかみどころのないイメージでかえって記憶に残る。《1月16日》という 小さな作品が壁面の隅の低い位置にぽつんと展示されていた。聞くとこれは会期が始まってから展示されたもので、搬入日、降り止まない雪のなかを歩く自らの足下を描いたものだという。 さらっと描いたように見えるし、これだけが他とは雰囲気も異なる。しかし、いずれ融ける地面の雪を見つめながら、作品をしっかりと抱き指先に力を入れて会場へ向かう作家の姿や、冷たい空気に触れるリアルな感覚が想像できて、もっともこの作家の情緒を見ることができる一点に感じた。今後の活動展開も楽しみだ。
2011/01/21(金)(酒井千穂)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)