artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
楊哲一「山水─あるいはフロンティアの消滅」

会期:2023/05/16~2023/05/28
楊哲一は1981年、台湾宣蘭県出身の写真家。中国・河北省出身で、東京在住の田凱の企画で開催された本展は、彼の日本での初個展となる。
楊は台湾、中国、東南アジアの石灰岩採掘現場を、4×5インチの大判カメラを使って、モノクロームで撮影する仕事を続けてきた。今回は同シリーズから8点、さらに、中国奥地のオルドスの廃棄されたコンクリートの住宅群をカラー写真で撮影した1点、およびその映像作品も展示していた。
楊の関心が、現代社会における産業化(工業化)の最前線の状況を浮かび上がらせることにあるのは明らかだろう。興味深いのは、その画面構成に中国・宋時代の山水画の様式を取り入れようとしていることである。そのもくろみはかなり成功していて、どちらかといえば即物的で、殺風景とさえいえる鉱山の眺めが、ピトレスクな山水画として再構築され、奇妙な味わいの「風景画」が成立していた。同じような試みは、1980年代以降に畠山直哉によっても試みられているのだが、畠山が微妙に変化していく大気や光の描写に向かったのに対して、楊はハードエッジな輪郭線を強調している。力のある作家なので、彼のほかのシリーズもぜひ見てみたい。
公式サイト:https://tppg.jp/trans-regional-landscape/
2023/05/19(金)(飯沢耕太郎)
菅野純『Planet Fukushima』
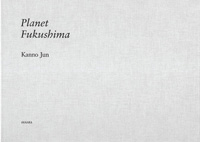
発行所:赤々舎
発行日:2023/03/21
福島県伊達市出身の菅野純は、2011年3月11日の東日本大震災によって姿を変えていった、故郷の人と風景を撮影し続けてきた。ニコンサロンでの個展(2017年12月)などを経て、それらの写真群を2部構成でまとめたのが、本書『Planet Fukushima』である。
第1部の「Fat Fish」には魚の鱗のように山肌に増殖していくフレコンバッグ(汚染土を詰めた袋)の眺めを、俯瞰して撮影した写真群と、身近な人物を含む福島県各地の日常の光景が、対比的に提示されている。第2部の「Little Fish」には、放射線量を測る線量計(小さい魚を思わせる)を、手を伸ばして被写体に向けている様を自ら撮影した写真が並ぶ。菅野は撮影を続けるうちに、福島の光景が遠景(「遠くの山」)、中景(「放射能という異物」)、近景(「手前の人」)の3層に分離しているように見えてきたのだという。本書はその3層だけではなく、さらにその間に介在するさまざまなレイヤーを丁寧に検証していった、厚みのある視覚的経験の集積といえるだろう。
尾仲俊介による、「Fat Fish」と「Little Fish」のパートをそれぞれ分離させてから、くるみ込んだ造本・デザインに説得力がある。糸綴の背中をそのまま見せて製本した、コデックス装の強みがうまく活かされていた。
2023/05/19(金)(飯沢耕太郎)
中井奈央「雪の刻(とき)」

会期:2023/04/20~2023/06/18
砂丘館[新潟県]
中井奈央は2006年に日本写真芸術専門学校卒業後、写真作家としての活動を積み上げてきた。2018年に写真集『繍』(赤々舎)を出版するなど、既に注目を集めていたが、昨年刊行した写真集『雪の刻』(赤々舎)を目にしたとき、ひとつ抜け出したという印象を強く抱いた。そこにさし示された写真の世界が、揺るぎなく、しかもみずみずしく、見る者に語りかけてくる力を備えていたからだ。同年度の日本写真協会賞新人賞、さがみはら写真新人奨励賞を受賞したのも、当然というべきだろう。
『雪の刻』は、豪雪地帯である新潟県津南町を中心に、2015~2021年に長期にわたって通い詰めて撮影した写真群をまとめた連作である。中井のカメラワークは、柔らかく伸び縮みしながら、津南町の人々、風景を絡めとっていく。特に強い印象を残すのは、画面の中心に被写体となる人物を置いた正面向きのポートレートで、説明的な要素を削ぎ落として、その人の全存在(過去・現在・未来)と向き合おうという意思が明確にあらわされている。それだけではなく、多くの写真に、この人、ここにあるものとの出会いが、置き換えのできない1回限りの経験であることが示されており、見ていて静かな感動の波紋が広がっていくように感じた。
新潟の砂丘館の古い建物の蔵、2階での展示も素晴らしいものだった(キュレーションは同館館長の大倉宏)。天然木の台座に、和紙のプリントを1枚ずつ置いた2階の展示など、37点の作品が展覧会場と溶け合って、得がたい視覚的な経験を与えてくれる。展示空間の力によって、写真が新たな生命力を獲得しているようにも見えた。
公式サイト:https://www.sakyukan.jp/2023/04/9773
2023/05/13(土)(飯沢耕太郎)
フィルムフォトのアクチュアリティー

会期:2023/04/01~2023/06/25
東京アートミュージアム[東京都]
デジタル化の急速な進行により、いまは写真のほとんどすべてがデジタルカメラで撮影されている。そんななかで、あえて「フィルムフォト」にこだわり続ける写真家たちもいる。東京・仙川の東京アートミュージアムで開催された本展では、そんな少数者たちの自己主張が、くっきりと表明されていた。
出品者は小平雅尋(企画者も兼ねる)、船木菜穂子、由良環の3人。それぞれ、なぜ写真を撮り続けるのかと自らに問いかけつつ、じっくりと作品制作に取り組んできた写真家たちの展示は、見応え充分だった。小平の「videre videor」は、風景から身近な事物まで、写真を撮る「われ」のあり方を深く考察しつつシャッターを切ったモノクロームの作品群、船木は「くらやみに目が慣れる」で、6×6判のカメラで撮影した女性ポートレートと断片的な光景(カラー)を2枚セットで提示し、「撮った時に感じた喜び」を追体験させようとする。由良はモノクローム作品の「けそめき」で、残雪が残る景色の細部に目を凝らしつつ、その土地から立ち上がる気配を定着しようとしている。どの作品も魅力的だが、特に被写体に向ける眼差しを、研ぎ澄ませて彫り込んでいくような船木の写真が、印象深く目に残った。
展覧会と同時に刊行された、小平と船木、由良との対話集『Dialogue』を読むと、彼らは異口同音に「フィルムフォト」の必然性について、「デジカメのように、撮った途端に結果が見れるとわかっていると、やっぱりうまくいかない」と語っている。たしかに、「撮る」という行為が画像を「見る」ことによって中断されると、被写体に純粋に向き合い続けることがむずかしくなるのだろう。小平の言う「自分が思い描くものとは別な答えが導かれる」ということは、いまなお、写真という表現媒体の根幹であり続けているではないだろうか。「フィルムフォトのアクチュアリティー」について、説得力のある理由を提示しようとするいい展覧会だった。
公式サイト:http://www.tokyoartmuseum.com/exhibition.html
2023/05/11(木)(飯沢耕太郎)
芦屋の美術、もうひとつの起点 伊藤継郎

会期:2023/04/15~2023/07/02
芦屋市立美術博物館[兵庫県]
伊藤継郎って名前にかすかに覚えがあったので、ひょっとしてと思って経歴を見たら、やっぱりそうだった。ぼくが確か中学生のときに初めて買った油彩画の入門書『油絵入門』の著者。保育社から出ていた「カラーブックス」シリーズの1冊で、初版が1967年となっている。当時は手軽な技法書がほかに見当たらなかったので繰り返し読んだ覚えがある。でも見本として載っていた伊藤の作品は、昭和の洋画に典型的に見られるデフォルメされた具象にゴテゴテ厚塗りした油絵で、あまり好きになれなかったなあ。とはいえ曲がりなりにも最初の油彩画の師ではあるし、直前に横浜で偶然お会いした原久子さんも推していたので、ちょっと離れているけど見に行った。
展示は「学び──大阪の洋画会を背景に」「研鑽──美術団体での活躍」「開花──新制作派協会」「再出発──芦屋の地で」「伊藤絵画の内実」の5章立て。時代別に見れば、主に1、2章が戦前、3章が戦中、4、5章が戦後だが、必ずしも制作順に並んでいるわけではない。あれ? と思ったのは、第4章まで伊藤作品は38点中13点しかなく、師匠や同僚や教え子の作品のほうが多いこと。伊藤が最初に入門した天彩画塾を主宰していた松原三五郎をはじめ、赤松麟作、小出楢重、小磯良平、猪熊弦一郎、そして戦後の具体美術協会の吉原治良、村上三郎、白髪一雄まで、伊藤を取り巻く画家たちの作品のなかに伊藤作品を点在させているのだ。しかも重要なのは、それらが19世紀の洋画から阪神間モダニズム絵画、戦後の現代美術まで実に多彩なことだ。
肝腎の伊藤作品は第5章に油彩、水彩、パステルなど61点がまとめて並べられている。これらを見ると、戦前こそスタイルが定まらなかったものの、戦後は一貫してデフォルメされた形象に褐色系を中心とした絵具をこってりと塗り重ねていくスタイルを固持してきたことがわかる。なるほど、伊藤作品だけ見せられたら、昭和の洋画によくある厚塗りの画家で終わってしまいかねないが、彼を含めて周辺にいた画家たちは激動の美術史に身を置いていたことが理解できるのだ。
たとえば、先輩の小磯良平や猪熊弦一郎は多くの戦争画の「傑作」を生み出したが、伊藤は年齢的にも少し若かったし、デフォルメの激しかったスタイルも戦争画には合わなかったせいか、従軍画家ではなく兵士として戦地に赴いている。また戦後、同世代の吉原治良や教え子の白髪一雄らは具体美術協会で前衛芸術を牽引したが、伊藤はそれらに合流することなく我が道を歩み続けた。『油絵入門』にはそんなこと一言も書いてなかったけど、幸か不幸か伊藤は美術史の激流に巻き込まれることなく、ブレずに画業をまっとうしたといっていい。だからといって伊藤の絵画が好きになったかというと、そんなことはないけれど、でも最初に油絵を教えてくれた画家が怒涛の20世紀をすり抜け、人間的な広がりをもっていたことを知っただけでもなんだか救われた気分になった。
公式サイト:https://ashiya-museum.jp/exhibition/17446.html
2023/05/10(水)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)