artscapeレビュー
その他のジャンルに関するレビュー/プレビュー
あいちトリエンナーレ2013 プロデュースオペラ プッチーニ作曲「蝶々夫人」
愛知芸術劇場 大ホール[愛知県]
あいちトリエンナーレ2013のプロデュースオペラ「蝶々夫人」を観劇した。一言でいうと、(最も)美しい「蝶々夫人」である。音楽布陣が最高とされるポネル演出の「蝶々夫人」の映像を何度も見ていたので、この演目の日本だからこそできる優位性を使い、特に視覚的な面においてはこれをはるかに凌駕していた。卒論で古今東西の「蝶々夫人」の舞台美術を研究した建築出身の演出家・田尾下哲ならではの空間表現である。登場人物が日本家屋の特性を説明する冒頭のシーンでは、見ている前で可動の建具=障子が次々と入り込み、柱が設置される。そして劇中は、物語の展開に合わせて、次々とシフトを変えていく。多層のレイヤーは、日本的な奥行き表現である。が、オペラの舞台の比例に合わせ、垂直に引き伸ばされた巨大な建具、段々になった床面、そしてはっきりした中心軸と奥に向けて傾斜する床は、西洋の透視図法的な空間も想起させるだろう。和洋が出会う演目におけるハイブリッドな空間である。以上で建築的なフレームは完成するが、ここに命を吹き込むのが、女方の歌舞伎俳優・市川笑三郎が振付を担当したことによる、オペラの歌手とは思えない、「日本的」というべき優雅な所作だった。とりわけ、最初の蝶々さんの登場から友人たちが歌うシーンは別格。ほかにも動く絵のような美しいシーンが幾つかあった。第一幕フィナーレの星空に包まれた二重唱。第二幕第一部の黒い床の全域に降り積もる花。そして第一部から第二部への切り替えで、海を眺めて立ち尽くす蝶々さんと夜から朝への時間の変化(この演出なので、ここに休憩を入れないのもいうなづける)。蝶々さん=安藤赴美子も素晴らしい。田尾下の「蝶々夫人」は。この演目に内在するオリエンタリズムへの批判やひねった解釈とも違う。むしろ、日本人も忘れている「日本的」な美はこれだと、ストレートに提示したものだ(たぶん海外はもっと驚く)。舞台の美しさを通じて、物語に没入させ、音楽の美しさを改めて感じさせる演出。通常の音楽ファンのみならず、美術ファンにも建築ファンにも楽しめるような総合芸術としてのオペラは、当初の目的どおり、まさにあいちトリエンナーレにふさわしいものだった。なお、世界には数えきれないほど、トリエンナーレはあるが、オペラも含まれるのはあいちだけである。
2013/09/16(月)(五十嵐太郎)
アンリアレイジ展 A REAL UN REAL AGE
会期:2013/08/30~2013/09/16
パルコギャラリー 名古屋パルコ西館8F[愛知県]
名古屋PARCO GALLERYで開催されたアンリアレイジ展がよかった。球、正四面体、立方体を包む服(が、人も着用可)、極細や極太の人体用の衣服、光をあてると分子構造が変わり、色が変わる服など、次世代のファッションの前衛を感じることができる。アンリアレイジは、形や比例など、規範となる身体の前提をズラしたところから、ファッションの可能性を切り開く。その概念的操作とデザインの対応は、建築的にも興味深い。
2013/09/15(日)(五十嵐太郎)
あいちトリエンナーレ2013 パブリック・プログラム スポットライト「青木淳×杉戸洋(スパイダース)」
名古屋市美術館 2階講堂[愛知県]
名古屋市美術館にて、青木淳と杉戸洋のトークが行なわれた。青木は、モダニズムおける軸線の手法とポストモダンの断片化を、ミケランジェロとピラネージに対応させつつ説明し、今回のプロジェクトで名古屋市美術館の断片化された軸線を縫いなおすような試みを説明する。また初期案から最終案までの変遷も詳しく紹介した。2人の間で濃密なビジュアル・コミュニケーションを通じて、さまざまなツッコミと修正がなされ、単独名義ではなく、スパイダースという共同名義に至った理由がよくわかる。論理的で分析的な青木に対し、感覚的で天才的な杉戸。2階のカラフルな空間インスタレーションは、最後に現場でライブ的に決定したらしい。トークの後、オープンアーキテクチャーのチームに対し、2人が名古屋市美のガイドツアーを行なう。1階に3.11のメモリアル・スペースを制作したアルフレッド・ジャーは、吹き抜けに挿入された仮設の階段を「天国への階段」だねと言ったらしい。また市美の2つの軸線を延長すると、杉戸のアトリエや材料を購入したホームセンターを通るという興味深いエピソードなどもうかがうことができた。
2013/09/14(土)(五十嵐太郎)
人生の民俗─誕生・結婚・葬送─

会期:2013/07/20~2013/09/16
松戸市立博物館[千葉県]
人が生まれ、成人に育ちゆき、やがて結婚し、しばらくすると老いて死を迎え、先祖となってまつられる。人生のライフサイクルを民俗学の知見から振り返った展覧会だ。
お宮参り、お食い初め、雛祭り、鯉のぼり、そして祝言や葬列。現在の都市社会では馴染みの薄い儀式や行事の数々が、同館が属する松戸の農村をケーススタディとして紹介された。文字資料が中心だったとはいえ、なかなか見応えがあった。
特に印象深かったのは、個々のライフサイクルが地域の共同体と密接不可分であり、その接点に人生の節目が刻まれていたという事実だ。共同体はおろか家族という紐帯すら分解しつつある今日の都市社会から見ると、その共同体による分節がやけに新鮮に見える。個人主義の享楽を謳歌しつつも、同時に人工的な共同体を希求する現代人が多く存在していることを考えれば、こうした人生の民俗を改めてつくりなおすことが求められているのではないか。
放射能の時代にあって、人はいま、どう生きるべきか、幸福とは何かを考えあぐねている。人生の民俗がその答えのひとつになりうるとすれば、そのときアーティストは何ができるのか。何かできるはずだ。
2013/09/13(金)(福住廉)
肥やしの底チカラ
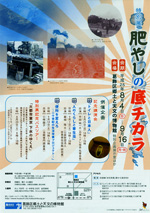
会期:2013/08/04~2013/09/16
葛飾区郷土と天文の博物館[東京都]
文字どおり人糞尿についての展覧会。2004年に同館で催された「肥やしのチカラ」展をグレードアップした内容で、ひじょうに見応えがあった。展示されたのは、このたび新たに発見された綾瀬作業所の資料をはじめ、古文書や写真、器物など。関係者にインタビューしたにもかかわらず、その映像資料が含まれていなかった点が惜しまれるにせよ、それでも緻密な研究成果を反映した良質の展覧会だった。
展示を見て理解できたのは、かつての江戸が極めて合理的な循環型社会だったこと。近郊の農村で生産された野菜を江戸の人びとが消費し、そこから排出された糞尿を農村に運搬し、肥料として活用する。運ぶのは長船で、下げ潮に乗って江戸まで行き、上げ潮に乗って帰ってきた。とりわけネギやレンコン、クワイ、ナスには効果てきめんだったようで、下肥として盛んに利用されていたようだ。水洗式便所がデフォルトになった現在では考えにくいことだが、当時の人糞尿はかなり重宝されていたのである。事実、外国人が使う水洗便所の糞尿は、水で薄められていたため肥料としては価値が低かった。
明治以後の近代化に伴い、こうした循環型社会は次第に影を潜めていく。下水道の整備や、安価で有効な化学肥料の登場、そして衛生概念の普及により、人糞尿を肥料として再利用する発想が制度的に退けられていくのである。とはいえ、鉄道による屎尿輸送は昭和20年代後半まで行なわれていたし、下水道が到達していない地方の農村で、この循環システムがいまも機能していることは言うまでもない。しかも屎尿の海洋投棄にいたっては、東京都の場合、じつは平成9年まで続いていた。現在の都市社会は人糞尿を不浄のものとして不可視の領域に囲い込んでいるが、じつはそれは、部分的とはいえ、現在の社会にもなお通底する合理的なシステムなのだ。
近代という価値観に重心を置いた社会のありようが、いたるところで綻びを見せ始め、それに代わる新たな価値観が模索されているいま、この糞尿を循環させるシステムは、近代的合理性とは異なる、もうひとつの合理性として見直すことができるのではないだろうか。何しろ、それらは1日もやむことなく、果てしなく生産されるのだから、これらを無駄にする手はない。
あまり知られていないことだが、美術評論家の中原佑介は、かつて「科学的糞尿譚 東京の排泄物」(『総合』1957年7月号、pp.174-179)というルポルタージュを書いた。東京の砂町処理場を取材した中原は、当時の東京で1日に排出される糞尿が約45,000千石であり、そのうち30%は下水道、65%は汲み取り、残る5%は自己処理されるというデータを明らかにしている。さらにその65%の汲み取りのうち、下水処理場に回収されるのは30%だけで、残りはすべて農村還元ないしは海中投棄されていたという。中原によれば、ゴルフ場の芝生の育成には、それらを加工した「発酵乾粉」という肥料が使用されていたらしい。
興味深いのは、このルポルタージュの末尾で中原が糞尿と放射能を併せて記述していることだ。当時の原水爆実験を受けてのことだろう、中原は次のような危機を暗示している。「糞尿の処理にまごまごしているうちに、糞尿が放射能をおびるようになるかもしれない」(同、p.179)。中原の予見が半ば現実化してしまっていることを、今日の私たちは知っている。人糞は循環しうるが、放射性物質は蓄積する。資本の蓄積が資本主義を内側から蝕む恐れがあるように、放射性物質の蓄積は人類を内側から滅ぼしかねない。私たちはいま、来るべき社会をどのように想像することができるだろうか。
2013/09/13(金)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)