artscapeレビュー
肥やしの底チカラ
2013年10月01日号
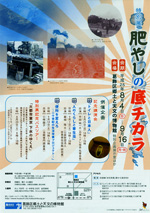
会期:2013/08/04~2013/09/16
葛飾区郷土と天文の博物館[東京都]
文字どおり人糞尿についての展覧会。2004年に同館で催された「肥やしのチカラ」展をグレードアップした内容で、ひじょうに見応えがあった。展示されたのは、このたび新たに発見された綾瀬作業所の資料をはじめ、古文書や写真、器物など。関係者にインタビューしたにもかかわらず、その映像資料が含まれていなかった点が惜しまれるにせよ、それでも緻密な研究成果を反映した良質の展覧会だった。
展示を見て理解できたのは、かつての江戸が極めて合理的な循環型社会だったこと。近郊の農村で生産された野菜を江戸の人びとが消費し、そこから排出された糞尿を農村に運搬し、肥料として活用する。運ぶのは長船で、下げ潮に乗って江戸まで行き、上げ潮に乗って帰ってきた。とりわけネギやレンコン、クワイ、ナスには効果てきめんだったようで、下肥として盛んに利用されていたようだ。水洗式便所がデフォルトになった現在では考えにくいことだが、当時の人糞尿はかなり重宝されていたのである。事実、外国人が使う水洗便所の糞尿は、水で薄められていたため肥料としては価値が低かった。
明治以後の近代化に伴い、こうした循環型社会は次第に影を潜めていく。下水道の整備や、安価で有効な化学肥料の登場、そして衛生概念の普及により、人糞尿を肥料として再利用する発想が制度的に退けられていくのである。とはいえ、鉄道による屎尿輸送は昭和20年代後半まで行なわれていたし、下水道が到達していない地方の農村で、この循環システムがいまも機能していることは言うまでもない。しかも屎尿の海洋投棄にいたっては、東京都の場合、じつは平成9年まで続いていた。現在の都市社会は人糞尿を不浄のものとして不可視の領域に囲い込んでいるが、じつはそれは、部分的とはいえ、現在の社会にもなお通底する合理的なシステムなのだ。
近代という価値観に重心を置いた社会のありようが、いたるところで綻びを見せ始め、それに代わる新たな価値観が模索されているいま、この糞尿を循環させるシステムは、近代的合理性とは異なる、もうひとつの合理性として見直すことができるのではないだろうか。何しろ、それらは1日もやむことなく、果てしなく生産されるのだから、これらを無駄にする手はない。
あまり知られていないことだが、美術評論家の中原佑介は、かつて「科学的糞尿譚 東京の排泄物」(『総合』1957年7月号、pp.174-179)というルポルタージュを書いた。東京の砂町処理場を取材した中原は、当時の東京で1日に排出される糞尿が約45,000千石であり、そのうち30%は下水道、65%は汲み取り、残る5%は自己処理されるというデータを明らかにしている。さらにその65%の汲み取りのうち、下水処理場に回収されるのは30%だけで、残りはすべて農村還元ないしは海中投棄されていたという。中原によれば、ゴルフ場の芝生の育成には、それらを加工した「発酵乾粉」という肥料が使用されていたらしい。
興味深いのは、このルポルタージュの末尾で中原が糞尿と放射能を併せて記述していることだ。当時の原水爆実験を受けてのことだろう、中原は次のような危機を暗示している。「糞尿の処理にまごまごしているうちに、糞尿が放射能をおびるようになるかもしれない」(同、p.179)。中原の予見が半ば現実化してしまっていることを、今日の私たちは知っている。人糞は循環しうるが、放射性物質は蓄積する。資本の蓄積が資本主義を内側から蝕む恐れがあるように、放射性物質の蓄積は人類を内側から滅ぼしかねない。私たちはいま、来るべき社会をどのように想像することができるだろうか。
2013/09/13(金)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)