artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
円盤に乗る派『流刑地エウロパ』
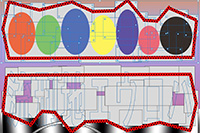
会期:2021/02/06~2021/02/08
BUoY[東京都]
『流刑地エウロパ』は円盤に乗る派の前身にあたるsons wo:が「最後の公演」として2018年に上演した作品。今回は初演のキャストから山村麻由美が小山薫子へと変わり、それ以外はキャスト(キヨスヨネスク、佐藤駿、田上碧、畠山峻、日和下駄)も戯曲も会場(BUoY)も変わらず、しかし3年の時を経ての再演となった。
戯曲には「正気を保つ」、「全ては明るい、全ては清潔だ」、そしてTLC“Waterfalls”と、円盤に乗る派として上演することになる作品のタイトル(『正気を保つために』『清潔でとても明るい場所を』『ウォーターフォールを追いかけて』)を示唆し、あるいは「僕は目の前に、空飛ぶ円盤があったら迷わず乗りたい」と団体名を予告するようなキーワードも散りばめられている。その意味で「sons wo: 最後の公演」にはすでに「未来」としての円盤に乗る派の可能性が埋め込まれていた。2018年の私にとって知るはずのない未来であったそれは2021年の私にとっては既知の過去となった。しかしもちろんまだ見ぬ未来も埋め込まれているかもしれない。
「演劇をやっていていつも思うんだけど、本番がいちばん演劇ではない、通り過ぎてしまった記憶、まだ見ない何かの方が演劇みたいに見える」。『流刑地エウロパ』で唯一明確な名前を与えられた登場人物であるハレヤマ天文台は言う。私にとって『流刑地エウロパ』の再演は初演の記憶とともにあり、目の前で上演されつつある演劇へのまなざしは同時に過去へも向かう。舞台の三方を囲む配置の客席で、私はちょうど初演のときに座った席と向かい合う位置に座ることになった。記憶のなかで『流刑地エウロパ』を観る過去の私は未来=現在の私に視線を向けている。再演を観ることで思い出される初演の記憶は捏造され、過去と未来に挟まれるようにして立ち上がる上演が演劇としてそこにある。
 [撮影:濱田晋]
[撮影:濱田晋]
ハレヤマ天文台という、明らかに作・演出を担当するカゲヤマ気象台のもじりである登場人物名が示唆するように、『流刑地エウロパ』はある種のパラレルワールドを扱っている。冒頭、オという記号めいた名前を与えられた登場人物のひとりは「地球を平面だと本気で思っている人たち」の集う「地球平面協会」の存在に触れ「なんというか本気になれば何でも信じられるんだなと思いました」と言う。どこからか聞こえてくる声(それは舞台上に登場する俳優たちの声のようだ)の語りによれば、木星の衛星エウロパに流刑された大犯罪者ケニー・G(ゴジマ)の生死を確認するため、探査隊タイタニックゴウが地球から木星へと旅立ってから2年が経つらしい。作品の中盤でまず明らかになるのは、その世界では「人間が二つの場所に同時に存在できる」テクノロジーが開発されており、登場人物たちは「あるいはエウロパへ向かい、あるいはこうして地球に残っている」ということ。だが、ピクニックに出かけた登場人物たちは土中からエウロパに流刑されたはずのケニー・G(ゴジマ)の日記を掘り出してしまう。そこには「俺はいくつもの森を抜け、沼を渡り、星の見えない暗い空間を何年間も進んで、(上演の日付)まで到達して戻ってきた」と記されていた。
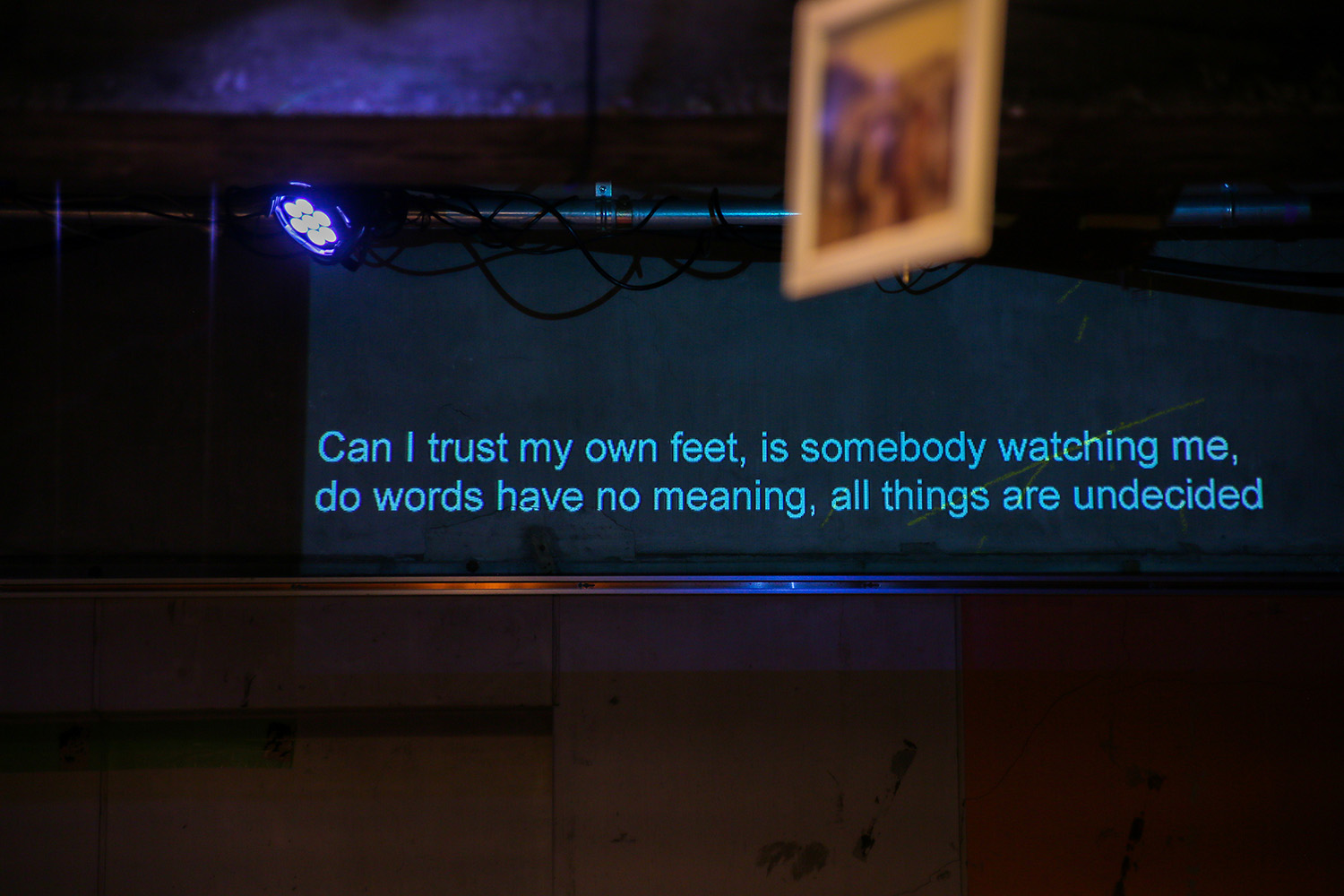 [撮影:濱田晋]
[撮影:濱田晋]
 [撮影:濱田晋]
[撮影:濱田晋]
結末に至り、冒頭で地球平面協会のことを話していたオは、ケニー・G(ゴジマ)と思しき男と邂逅したときのことを語る。ケニーによれば「やつら」によって1993年の9月にエウロパに地球がインストールされ、「その日にこの世界は始まった」のだという。「ここはずっとエウロパだった」。「真実」が露わになり、二つの世界が重なり合う。だがもちろん、ここがエウロパならば「本当の地球」がどこかにあるということになる。「きっと今ごろ、もう一人の私たちは、地球に帰り着いて、家族か、友達かに会って、ゆっくりお茶でも飲んでいるのかもしれない」。
「あの世界」「この世界」と分かたれた世界の足元は案外脆く、科学に裏打ちされた「たしからしい」世界も暫定的なものでしかない。科学とはその定義からしてそういうものだ。土中から見つかった日記のように、新たな発見は世界の「真実」を書き換える。
ハレヤマ天文台は言う。「だからと言って何かが変わるわけじゃなくって、僕たちは僕たちで、なんとか家に帰って、僕はちょうど演劇をやりたくなっているので、またみんなを集めて、まず話し合いからやろうと思います」。
既知となり過ぎ去った過去と未知としてこれから来る未来。テクノロジーの進歩をまたずとも人間はすでに二つの世界を生きていて、二つの世界を生きるしかない。
 [撮影:濱田晋]
[撮影:濱田晋]
公式サイト:https://noruha.net/
関連レビュー
円盤に乗る派『ウォーターフォールを追いかけて』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年11月15日号)
円盤に乗る派『正気を保つために』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年08月01日号)
KAC Performing Arts Program『シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年02月01日号)
2021/02/08(月)(山﨑健太)
プレビュー:東日本大震災と向き合う舞台作品4本──『福島三部作』『消しゴム山』『光のない。─エピローグ?』『是でいいのだ』

会期:2021/02~2021/03
[神奈川県/東京都]
東日本大震災から10年。関連する舞台作品が相次いで上演される。
TPAM2021でTPAMディレクションとして上演されるDULL-COLORED POP『福島三部作』(作・演出:谷賢一)は2018年に第一部が先行上演され、2019年に三部作として初演、2020年には第二部が第23回鶴屋南北戯曲賞を、三部作として第64回岸田國士戯曲賞を受賞した作品。福島県双葉町を舞台に住民たちが原発誘致を決定するまでを描く第一部『1961年:夜に昇る太陽』、かつて原発反対派だった男が賛成派として町長となり、そしてチェルノブイリの原発事故に直面する第二部『1986年:メビウスの輪』、被災者への取材で語られる無数の言葉とテレビスタッフの葛藤が観客をも揺さぶる第三部『2011年:語られたがる言葉たち』。三つの時代、半世紀にわたる物語はひとつの視点からの断罪を許さない。科学技術への期待と人間の欲望、職業倫理とひとりの人間としての意志、積み上げてきた時間と来るべき未来。善悪では割り切れない人間の葛藤がそこにはある。
『福島三部作』は2月12日から14日、KAAT神奈川芸術劇場で上演。劇場上演に先がけて9日から12日にはオンライン配信も予定されている。膨大な注釈が付された『戯曲 福島三部作』(而立書房)も併せて読みたい。
同じTPAMのフリンジプログラムではチェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』が上演される。『消しゴム山』は、作・演出の岡田利規が岩手県陸前高田市で津波被害を防ぐための高台の造成工事によって人工的に造りかえられていく風景を目撃したことをきっかけに構想されたのだという。津波という自然災害で壊滅した街並みと、人間の都合で書き換えられる風景。岡田は『現在地』(2012年初演)、『地面と床』(2013年初演)、『部屋に流れる時間の旅』(2016年初演)と東日本大震災をきっかけに顕在化した価値観の相違や対立を描いてきた。『消しゴム山』はさらに、人間中心の世界観の外側へと目を向けようとする。瓦礫の山にも似た舞台美術は美術家・金氏徹平の手によるもの。モノに埋もれ、なかばそれらと一体になりながらそこに立つ俳優の姿は、不可解なこの世界に生きるしかない私の似姿かもしれない。あうるすぽっとで2月11日から14日まで。ライブ配信とアーカイブ配信も予定されている。
シアターコモンズ'21では高山明/Port B『光のない。─エピローグ?』が上演される。今回の上演はフェスティバル/トーキョー12でPort B『光のないⅡ』として上演された作品のリクリエーション。高山はオーストリアのノーベル賞作家エルフリーデ・イェリネクが東日本大震災と福島第一原発事故への応答として発表した『光のない。』の続編として執筆した戯曲(白水社から刊行されている戯曲集『光のない。』[林立騎訳]には「エピローグ?[光のないⅡ]」として収録)を、東京電力本社ビルの立つ新橋駅周辺を舞台とするツアーパフォーマンスとして構成した。スタート地点は福島第一原子力発電所と同じ1971年に開業したニュー新橋ビル。12枚のポストカードとラジオを手に新橋駅周辺を巡る観客は、新橋と福島との距離に対峙することになる。今回のリクリエーションは10年という「距離」とも否応なく向き合うものになるだろう。
「距離」というテーマはVR作品や鍼を用いたセラピーパフォーマンスなど、シアターコモンズ'21のほかのプログラムとも共振する。フェスティバル/トーキョー12当時の、そして現在はシアターコモンズのディレクターである相馬千秋によるキュレーション・コンセプト「孵化/潜伏するからだ」は観客に個々のプログラムを超えた更なる思考を促すものだ。シアターコモンズ'21は2月11日から3月11日まで開催。高山明/Port B『光のない。—エピローグ?』 は3月4日から3月11日まで。すでに満席となっているようだが増席の可能性も検討されているとのこと。
3月11日から15日にかけては三鷹SCOOLで小田尚稔の演劇『是でいいのだ』が上演される。『是でいいのだ』は2016年初演、2018年以降は毎年3月に再演されている小田の代表作。東京で被災したと思われる5人の登場人物が自らの体験をときに自虐的なユーモアを交えながら淡々と語る。劇的なことは起こらない。「自らの人生の境遇や環境を受け入れて前に進むこと」を描いたというこの作品はしかし、等身大であるからこそ観客に10年前の自身の体験を思い出させ、現在の自らを省みる契機となり得る。
それぞれに異なるやり方で東日本大震災や福島第一原発事故と向き合う四つの作品。いずれも再演だが、そこに舞台芸術のひとつの意義がある。作品に刻印された初演当時の記憶。時を経て作品と向き合う自分の、社会の変化。あるいは作品自体の変化。繰り返し上演される舞台芸術は、そのたびにつくり手と観客の現在地を問い続ける。
DULL-COLORED POP『福島三部作』:https://www.tpam.or.jp/program/2021/?filter=.tag--fukushima-trilogy
チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』:https://www.tpam.or.jp/program/2021/?program=53
高山明/Port B『光のない。─エピローグ?』:https://theatercommons.tokyo/program/akira_takayama/
小田尚稔の演劇『是でいいのだ』:http://odanaotoshi.blogspot.com/2021/01/20213.html
関連レビュー
小田尚稔の演劇『是でいいのだ』/小田尚稔「是でいいのだ」|山﨑健太:フォーカス(2020年04月15日号)
没入するモノたち──チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』|池田剛介:フォーカス(2019年10月15日号)
2021/02/01(月)(山﨑健太)
ほろびて『コンとロール』

会期:2021/01/19~2021/01/21
下北沢OFF・OFFシアター[東京都]
ほろびては劇作家・演出家・俳優の細川洋平が主宰するカンパニー。2020年2月・3月に上演された『ぼうだあ』は大きな注目を集め、その後、期間限定で同作の映像と戯曲も公開されていた。4月には俳優の三浦俊輔がメンバーに加入。本作は細川のソロ・カンパニーから体制変更後、初の公演となる。
テレビゲームをしているうるい(藤井千帆)と永端(三浦俊輔)。うまくプレイできないうるいに永端は横からああしろこうしろと口を出すが、うるいは聞く耳を持たず気ままにゲームを楽しんでいる。プレイヤー交代。今度は永端が(腕前を自画自賛するような蘊蓄を垂れながら)プレイするが、うるいは退屈そうだ。しかしある瞬間、永端が握るコントローラーによって操作されるキャラクターの動きに連動し、うるいの体が彼女の意思とは無関係に動き出してしまう。どうやらそのコントローラーには近くにいる人間の体を自在に操作する力があるらしい──。
 [撮影:渡邊綾人]
[撮影:渡邊綾人]
 [撮影:渡邊綾人]
[撮影:渡邊綾人]
一方、カフェにいる男女。スーパーの店長であるイマミチ(松浦祐也)はアルバイトのしすく(鈴政ゲン)に契約の打ち切りを告げる。どうやら経営が思わしくないらしい。笑顔で話を聞いていたしすくだったが、突然泣き崩れてしまう。「生きていけない」「アンタが私と妹を路頭に迷わせるんだ」と責め立てるしすくに「いつも楽しそうだから、ほんとはお小遣い稼ぎくらいに思ってた」「うっかり」「知らなかったから」と言うことしかできないイマミチ。やがて「うちに来るのがいいと思う」としすくを抱きしめ──。
 [撮影:渡邊綾人]
[撮影:渡邊綾人]
男たちが他人の生殺与奪の権利を図らずも得てしまうところからはじまる二つの物語はある日、イマミチとその弟カワハギ(細井じゅん)、しすくとその妹カコ(宮城茉帆)が同居するマンションの一室に、隣室に住む永端がコントローラーを持って闖入してきたことによって陰惨な監禁暴行事件へと展開していく。コントローラーを使ってイマミチたちを操り、自分自身やお互いを傷つけ合わせる永端。爪を剥がれ、腱を切られ、電気ショックを与えられ、指を折られ。痛みは抵抗する気力を削ぎ、イマミチたちはやがてコントローラーなしでも永端の指令に従うようになっていく。カワハギは片手片足が動かなくなり、カコは4本の指を折られ、しすくは永端に弄ばれ、そしてイマミチは息を引き取る。いつまでも続くかと思われた暴力の時間は、隣の部屋で同じように監禁されていたらしいうるいが外の世界へと出て行く決意をすることでようやく終わりを迎えるのだった。
 [撮影:渡邊綾人]
[撮影:渡邊綾人]
 [撮影:渡邊綾人]
[撮影:渡邊綾人]
陰惨な事件を起こした「犯人」は間違いなく永端だが、彼は自らの手を一度も汚していない。暴力を振るったのは監禁されていたイマミチたち自身であり、その意味では被害者は残らず加害者でもある。目を背けたくなるような暴力は事件を特別な、私とは無関係なもののようにも見せる。しかし、強者は自ら手を汚さず、立場の弱いもの同士が互いを攻撃し合う構図は、程度の差こそあれ、現代日本を含め古今東西あらゆるところで見られるものだ。
ところで、「犯人」たる永端さえいなければこのような事件は起きなかったのだろうか。永端の言葉はそれを否定する。「他でもないコントローラーに操られていただけなんだからなにひとつ俺に責任はない」。イマミチたちに対する絶対的な支配を可能としたコントローラーの存在は、それを使う側であるはずの永端をも操っていたというのだ。もちろんこれは卑劣な言い逃れだが、同時に、力というものの本質を表わしている。そう言えば、永端はコントローラーの力に気づいた当初、自らの体を進んでうるいの操作に委ね、「楽しかった」「すごい充実感」と言っていたのだった。それがどちらの側であれ、力に身を委ねることの快楽というものはたしかに存在する。
この行動は自らの意思によるものではない、という言い訳が人間を残虐にすることは心理学的実験によっても歴史的な事実によっても証明されている。大義名分を掲げることにも同じような効果があるだろう。あなたのため、国のため、あるいは作品のため、芸術のため。支配をめぐる構造は演劇という形式とも不可分に結びついている。演出家と俳優、俳優と役、俳優の意思と体。苛烈な暴力を舞台上に出現させているのは誰の意志か。
 [撮影:渡邊綾人]
[撮影:渡邊綾人]
永端と暮らす部屋から逃げ出したうるいは裸足で走り続ける。透明なロープ状のものがうるいの体に絡みつき、その場に縛りつけようとするが、彼女はそれを振りほどき、やがて舞台と客席とを仕切る枠組みを越える(美術:西廣奏)。自分を縛る環境から逃れ出ることは容易ではなく、そもそも自分が環境に縛られていること自体を認識できない場合も多い。客席を正面から見据える彼女の目はこう問うているようだ。暴力を許していたのはほかならぬお前ではなかったかと。
本作は春ごろに配信が予定されている。
公式サイト:https://horobite.com/
2021/01/20(水)(山﨑健太)
akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』

会期:2021/01/08~2021/01/09
THEATRE E9 KYOTO[京都府]
舞台芸術の「再演」において、「初演以降に流れた時間」はどのように作品内部に刻印されるのか。とりわけ、(プロの俳優やダンサーではない人々の)「個人としての生」を扱うドキュメンタリー性の強い作品の場合、この問いは分かち難く絡んでくる。akakilikeが薬物依存症回復支援施設「京都ダルク」の利用者とともにつくり上げた本作は、作品の基本構造を保持しつつ、彼ら自身が語る「ダルクに来る以前(依存症の背景)」と「2019年の初演から経過した時間」を対比的に構成し直すことで、家族との関係や彼ら自身の変化を浮かび上がらせ、「いま」をポジティブに肯定する力に満ちていた。
冒頭、akakilike主宰の倉田翠とともに登場したダルク利用者たちは、無言で客席に対峙したあと、頭上から落下した普段着の私服に着替え、「料理の共同作業」と「グループセラピーのミーティング」というダルクの日常を淡々と再現していく。一方、倉田はその傍らで独り言のように身体を動かし続ける。これが本作の基本的な構造である。

[撮影:前谷開]

[撮影:前谷開]
初演との違いは、まず、出演者が13名から6名に半減し、うち初演経験者は4名で、新たに2名が参加したことだ。コロナの影響もあるだろうが、「利用期間2年」の制限のため、利用者の入れ替わりが激しいことも一因だ。そのため、ミーティングの再現として語られる生い立ち、家族事情、薬物との関わり、日々の経験などのエピソードの多くが入れ替わり、「初演後に起こった出来事」が追加された。また演出上の変更として、冒頭のシーン構成と「衣装」の変化がある。初演では、全員がYシャツに黒いスラックスという事務的な服装で「住民説明会」を再現したが、再演では、ダブルのダークスーツ、派手な柄シャツに金のチェーンネックレスといった「ヤクザやホスト」を思わせる衣装で登場したあと、普段着に着替えて料理の共同作業に向かうことで、ダルク以前の過去/ダルクにいる「現在」への移行を視覚的に印象づけた。
また、語られるエピソードも一人ひとりの比重が増し、家族関係の変化や「いまの自分」を肯定する前向きな印象を強く感じた。絶縁状態だった父親の七回忌に出席した際、ロウソクの火が揺れるのを見た家族が「父親が喜んでいる」と語り、「自分はここにいていいんだ」と思えたこと。初演で「留置所での首吊り」を再現した出演者は、「あんたは死んだも同然」と家族に拒絶されていたが、勉強中のイラストで生計を立てたいという夢を伝えると、「生きがいを見つけたんだね」という言葉をかけてくれたことを語る。別の出演者は、年末の埼玉公演の際、見に来てくれた地元の家族の姿を客席に探した経験を語る。一方、依存症の背景には、複雑な家庭環境や児童虐待といった問題があることも語られる。
カラオケの熱唱や(最前列の観客をモデルに描く)似顔絵イラストの披露など、歓待的なサービス精神に開かれつつ、「出演者のキャラや個性」に頼る側面は否定できない。だが、本作をそれでも「ダンス作品」であると言いうるなら、この場に「ダンス」はどのように存在できるのか? 「ダンス」の居場所はどこにあるのか? と倉田自身が問いながら立ち続けている点にある。一見、即興的に自由に踊っているように見える倉田だが、「振付提供:筒井潤」のクレジットが示すように、演出家の筒井が振付けた過去作品の再現に従事しているにすぎない。「私は(他人に振付られる)ダンサーである」という態度表明とともに、倉田自身もまた、「過去の記憶」を身体的に反芻しているのだ。
「ダルクの日常」の再現の中に「過去からの移行」を語りつないでいく利用者たちと、その輪には入れない「ダンサーの私」。交わらないはずの両者だが、例えば「クスリをやってない」と嘘の否定を家族に繰り返した告白が語られる傍らで、四つん這いの倉田が激しく頭を振り続けるとき、ふと交差し共振し合うようにも見える。その両者が交わるのが、ともに食卓を囲むラストシーンだ。「LINEを無視する妻と、それでも社交ダンスを踊りたい」という叶わぬ願望を語る出演者に応えるように、倉田は「不在の誰か」と手を繋いで楽しそうに踊る。だが、そのダンスは次第に失速し、表情は逆光の闇に暗く沈み、もどかしい手探り状態に陥っていく。それは、「ここは本当に私の居場所なのか」「ダンスはそこに存在できるのか」という逡巡の自問自答であると同時に、再び「ダンス」を手探りし始める胚胎の瞬間でもある。
「作品」を固定化してしまうことは、「徐々に、あるいは目まぐるしく変わっていく彼らの生」の否定につながってしまう。状況的な要請もあるが、「再演」とは固定化でも単なる反復でもなく、「二度と繰り返せない差異を通して、過去との隔たりを計測することにこそ、作品の本質が新たに照射される」という「再演」の持つ意義を提示した好例であった。

[撮影:前谷開]

[撮影:前谷開]
公式サイト:https://akakilike.jimdofree.com/
関連レビュー
akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年10月15日号)
2021/01/09(土)(高嶋慈)
ベートーヴェン「第九」と『音楽の危機』

会期:2020/12/26
横浜みなとみらいホール[神奈川県]
年末になって、ようやく生のドラムが入った音楽をライブで聴くことができた。コロナ禍において執筆されたすぐれた芸術論である岡田暁生『音楽の危機—《第九》が歌えなくなった日』(中公新書)が指摘したように、「録楽」と違い、聞こえない音も含むような、リアルな空気の振動こそ、ライブの醍醐味である。そして同書が問題にしていた三密の極地というべき近代の市民文化の音楽とホールの象徴が、年末の風物詩となっているベートーヴェンの交響曲「第九」だった。壇上の先頭中央に指揮者と4人のソリスト、これを囲むようにオーケストラのメンバーがところ狭しと密集し、さらにその背後にひな段を組んで、合唱団がずらりと並ぶ。すなわち、大人数を前提としたスペクタクル的な作品である。無言の演奏だけならともかく、ハイライトの「歓喜の歌」では、一斉に飛沫が発生するだろう。果たしてコロナ禍において「第九」は可能か、というのが、『音楽の危機』の問いかけだった。また同書は、音楽の時間構造のほか、それが演奏される空間=ホールの刷新も提唱した芸術論でもある。筆者は2020年の暮れ、横浜みなとみらいホールにおいて、読売日本交響楽団の演奏による「第九」をついに聴くことができた。
当然、通常の演奏形態ではない。パイプオルガン前の高所の座席に観客の姿はなく、代わりにソーシャル・ディスタンスをとりながら、通常の半数に厳選された合唱隊を分散配置する。また独唱の4名も最前線ではなく、小編成になったオーケストラの後に並ぶ異例のパターンだった。それゆえ、正面の席は、いつもより遠くから声が聴こえ、人数も少ないことから、音圧の迫力は足りなかったかもしれない。が、逆に筆者が座っていた、指揮者がよく見えるオーケストラ真横の二階席は、思いがけず、最高の特等席と化した。なぜなら、第四楽章で合唱隊が起立し、全員が一斉に黒マスクを外して歌いだすと、すぐ斜め前から同じ高さでダイレクトに声が突き刺さる。しかも正面の真下からはオーケストラの音が湧き上がるのだ。まるで「第九」の音空間の只中にいるような、忘れられない貴重な体験となった。平常時であれば、絶対にこんな聴こえ方はしない。また読響としても年末の最後の公演であり、この一年は音楽が抑圧されていたことを踏まえると、それが解放されたかのような喜びが爆発した演奏だった。
2020/12/26(土)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)