artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
百々武「草葉の陰で眠る獣」

会期:2015/03/11~2015/03/24
銀座ニコンサロン[東京都]
百々武は1977年大阪生まれ。1999年にビジュアルアーツ専門学校・大阪を卒業後、しばらく東京で暮らしていたが、奈良の実家に帰ってから、2009年から奈良県南部の山村を撮影しはじめた。百々の前作『島の力』(ブレーンセンター、2009年)は、日本全国、北から南までの島に足を運んで撮影したモノクロームの連作だったが、今回の「草葉の陰で眠る獣」は、カラーで撮影している。そのためもあるのだろうか。開放的な気分がシリーズ全体にあらわれていて、どこか明るい雰囲気に包み込まれていた。
冒頭の5点の写真は、菜の花畑にやってきた蜜蜂を撮影しているのだが、その導入部がとてもよかった。蜜蜂に導かれるように村の空間に入り込み、そこに住む人たちと出会い、さまざまな行事に参加し、猪狩りなども経験する。彼のカメラの前に姿をあらわすさまざまな風物を、昆虫や小動物などを含めて、気負うことなく、すっと画面におさめていく、その手つきの柔らかさ、しなやかさに、彼のカメラワークの特質があらわれているように感じた。結果的に、古い歴史を背負った奈良の風土が四季を通じて細やかに浮かび上がってくる、いいドキュメンタリーになったと思う。父親の写真家、百々俊二の重厚な力業とも、兄の木村伊兵衛写真賞受賞作家、百々新の軽やかなフットワークともひと味違った、百々武の写真のあり方が、はっきりと見えてきつつあるのではないだろうか。
展覧会にあわせて、赤々舎から同名のハードカバー写真集が刊行された。なお、本展は4月2日~8日に大阪ニコンサロンに巡回する。
2015/03/11(水)(飯沢耕太郎)
石川直樹+奈良美智「ここより北へ」

会期:2015/01/25~2015/05/10
ワタリウム美術館[東京都]
石川直樹と奈良美智という組み合わせは案外悪くないかもしれない。世界の辺境を旅してきた写真家と、イノセントな作風で知られる画家は、偶然の機会から2014年夏に青森(下北半島、津軽半島)、北海道(函館、札幌、知床半島、斜里、ウトロ)、サハリン(ユジノサハリンスク、ノグリキ、ポロナイスク、ドリンスク、コルサコフなど)を一緒に旅することになった。今回の展示の中心になっているのは、その時に両者によって撮影された写真群である。石川の眼差しののびやかさ(見方によってはゆるさ)、奈良の写真の端正な画面構成の取り合わせが絶妙なのだが、それ以上に、旅の副産物というべき彼らの備品、地図、蔵書、奈良がコレクションしたレコード類などが展示されている、3Fの「二人の原点」のスペースがなかなかよかった。
もともと石川も奈良も、その作品は無菌状態で頭のなかから湧き出てきたのではなく、彼らの実生活やこれまで過ごしてきた環境のなかから育っていったものなのではないかと思う。むしろ、そういうバックグラウンドの部分に伸び広がっていくような展示のあり方が、面白い効果を生んでいた。ワタリウム美術館のそれほど大きくない空間(しかも2F、3F、4Fに分割されている)だと、まだ物足りなさが残るが、二人とも、こういう展示形態の方がのびのびと自分の作品世界を展開できそうな気がする。展覧会にあわせて制作された、タブロイド判の新聞のような形態のカタログも、500円(+税)という破格の値段も含めて、親しみやすいいい味わいを出していた。
2015/03/08(日)(飯沢耕太郎)
猪瀬光「COMPLETE WORKS」

会期:2015/03/06~2015/04/19
森山大道は、展覧会にあわせて出版された『猪瀬光全作品』(月曜社)に寄せた「猪瀬光という名のミステリー」というテキストで、写真家をウーヴェ・ヨーンゾンの小説「三冊目のアヒム伝」に登場するアヒムになぞらえている。伝記作者が依頼を受けてアヒムという男に紹介されるのだが、ついにその正体をつかむことができず、伝記も未刊に終わるという筋書きだという。
たしかに、極端な寡作で知られる猪瀬にもアヒムめいた所があって、その正体をなかなかあらわそうとしない。というより、前回の個展(Space Kobo & Tomo、2001年)から14年が過ぎ、写真集の刊行(『VISIONS of JAPAN INOSE Kou』光琳社出版、1998年)からはもう既に17年も過ぎているということを考えると、正体をつかみようがないというのが正しいだろう。だが、その間にも「伝説」が一人歩きしていって、虚像のみが膨らんできていた。その意味では、関係者の方たちには大変な苦労があったとは思うが、今回の「COMPLETE WORKS」の展覧会、及び2冊のポートフォリオ(『DOGURA MAGURA』、『PHANTASMAGORIA』各30部限定)と全作品集の刊行は、画期的な企画なのではないかと思う。
あらためて、「DOGURA MAGURA」の写真群を見て感じるのは、彼が大阪芸術大学在学中の1982年から開始されたこのシリーズが、初期の代表作というだけに留まらず、ライフワーク的な意味を持ちはじめているということだ。2000年代以降に撮影された作品3点も加わることで、総点数は75点に達するとともに、旧作にも追加や見直しがおこなわれている。サーカスや解剖学教室などの特異な被写体に目を奪われがちだが、「DOGURA MAGURA」は、彼自身の生の起伏とともに伸び縮みし、成長していくシリーズであり、「私写真」的な要素がより強まってきている印象を受けた。
もう一つは、その湿り気がじっとりと滲み出てくるような白黒のコントラストの強いプリントワーク、偶発的で、常に変容していく被写体のフォルムに鋭敏に反応していく撮影のスタイルとも、「日本写真」の典型に思えることだ。日本の写真家たちが写真を通じて練り上げてきた現実把握のあり方を、極端に肥大化させ、純化したのが、まさに「DOGURA MAGURA」だったのではないだろうか。猪瀬の写真を孤立した営為としてではなく、むしろ「日本写真」の流れの中で捉え直してみることが必要になりそうだ。
第1期「DOGURA MAGURA」2015年3月6日~29日
第2期「PHANTASMAGORIA」2015年4月1日~19日
2015/03/07(土)(飯沢耕太郎)
PARASOPHIA:京都国際現代芸術祭2015
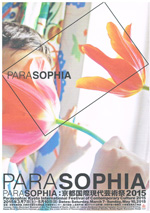
会期:2015/03/07~2015/05/10
京都市美術館、京都府京都文化博物館 別館、京都芸術センター、大垣書店烏丸三条店ショーウインドー、堀川団地、鴨川デルタ(出町柳)、河原町塩小路周辺[京都府]
今年春の関西美術界で最注目の国際現代芸術祭。京都市美術館、京都文化博物館など、京都市内中心部の8カ所を舞台に国内外約40組のアーティストが展示を行なっている。芸術監督の河本信治は、あえて統一的なテーマを設定せず、現場から自律的に生成されるクリエイティビティを優先した。これは、昨今流行している地域アートやアートフェア、ほかの国際展に対するアンチテーゼの一種とみなすことができるだろう。それはイベント名が「para(別の、逆の、対抗的な)」+「sophia(叡智)」であることからも明らかだ。一方、統一テーマがないことでイベントの全体像が把握しにくいこともまた事実である。展示は全体の約8割方が主会場の京都市美術館に集中しており、そのうち約半数は映像もしくは映像を用いたインスタレーションである。ほかの会場は1~3名程度が出品しており、サイトスペシフィックな展示が行なわれた。筆者が注目したのは、鴨川デルタ(出町柳)でサウンドアート作品を披露したスーザン・フィリップス、堀川団地の一室で美しい映像インスタレーションを構築したピピロッティ・リスト、河原町塩小路周辺のフェンスに囲まれた空き地で、廃物を利用したブリコラージュの立体作品を発表したヘフナー/ザックス、京都市美術館でのワークショップと館の歴史を重層的に組み合わせた田中功起、一人の女性の生涯を複数の映像とオブジェ、迷路のような会場構成でエンタテインメント性豊かに表現した石橋義正、自身のDIY精神あふれる行動をドキュメント風に映像化したヨースト・コナイン、音楽のジャムセッションの様子を約6時間にわたり捉えたスタン・ダグラスといったところであろうか。ほかの国際展に比べて規模は大きくない「PARASOPHIA」だが、映像系が多いこともあって、鑑賞には時間がかかる。まず、会場で配布されているガイドブックを入手して、作品概要やコース取りなどを事前にチェックすることをおすすめする。
2015/03/06(金)(小吹隆文)
北島敬三「ヘンリー・ダーガーの部屋」

会期:2015/02/20~2015/03/12
ヘンリー・ダーガー(Henry Darger 1892-1973)は、いうまでもなくシカゴの伝説的なアウトサイダー・アーティスト。病院の掃除夫の仕事を続けながら、『非現実の王国として知られる地における、ヴィヴィアン・ガールズの物語、子供奴隷の反乱に起因するグランデコ─アンジェリニアン戦争の嵐の物語』と題する、史上最大級の長大な挿絵入りの物語を制作し続けた。そのダーガーが生前暮らしていた部屋が、2000年4月に取り壊されることになり、急遽北島敬三が撮影したのが今回発表された「ヘンリー・ダーガーの部屋」である。なお、このシリーズは、2007年4月~7月に原美術館で開催された「ヘンリー・ダーガー─少女たちの戦いの物語 夢の楽園」展に際して刊行された小冊子『ヘンリー・ダーガーの部屋』(インペリアルプレス)にその一部が発表されたことがある。
むろん、このシリーズの見所は、いまは失われてしまったダーガーの部屋の細部を観客に追体験させるところにある。積み上げられた水彩絵具や色鉛筆、筆、タイプライター、コラージュやドローイングの材料として使われた絵本、広告、古写真などを、北島はライカと4×5判のリンホフテヒニカで丁寧に押さえていく。窓や照明器具からの光線に気を配り、そこに漂っている光の粒子をそっと拾い集めていくような撮影のやり方によって、観客はまさに時を超えて「ヘンリー・ダーガーの部屋」に連れていかれるのだ。北島がもともと備えている、被写体をリスペクトしつつ、本質的な部分を引き出していく能力が、充分に発揮されたいい仕事だと思う。点数を10点に絞り、会場を暗くしてスポットライトで作品を照らし出す会場構成もうまく決まっていた。
2015/03/05(木)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)