artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
岸幸太「連荘4」

会期:2023/09/26~2023/10/15
岸幸太が2021年からphotographers' galleryで開催している連続展「連荘」も4回目を迎えた。大阪、東京、横浜、京都などの日雇い労働者たちが多く住む地域、いわゆる「ドヤ街」を中心に撮影しているシリーズだが、少しずつ方向性が定まりつつあるように見える。
岸は2005年から2020年にかけて撮影した以前のシリーズ「傷、見た目」でも、同じような場所にカメラを向けている。だが、文字通り「傷」の感触を確かめるような切迫感があった前作と比較すると、カラー写真にシフトしたこともあって、本作にはどこか開放的な、撮影行為そのものに柔らかに没入しているような雰囲気を感じることができる。岸自身は、この連作を通じて「自分の地図を作りたい」と考えているようだ。その意図は、「ドヤ街」の細部を引き剥がして提示するような距離感が近い作品だけでなく、何点か、より客観的な引き気味の写真が含まれていることにもあらわれているのではないだろうか。
おそらくphotographers' galleryの中心メンバーの北島敬三の影響だと思うが、岸だけでなく、笹岡啓子、王子直紀など同ギャラリーに所属する写真家たちは、長期間の連作にこだわることが多い。この「連荘」シリーズも、さらに回を重ねることで、より明確なヴィジョンが見えてくることを期待したいものだ。なお、展覧会にあわせて刊行されるA4サイズの写真集も、今回で4冊目になった。
岸幸太「連荘4」:https://pg-web.net/exhibition/kota-kishi-renchan-4/
関連レビュー
岸幸太『傷、見た目』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年06月01日号)
2023/10/05(木)(飯沢耕太郎)
ジェシカ・ワイン『数学者たちの黒板』

翻訳:徳田功
発行所:草思社
発行日:2023/07/20
先日、仕事で中国・北京に滞在したおりに、クリストファー・ノーランの新作『オッペンハイマー』(2023)を観る機会があった。原爆の父ロバート・オッペンハイマー(1904-1967)を主人公とするこの伝記映画は、2023年9月末日現在、いまだ日本公開の目処が立っていないことで知られる。あくまで憶測の域を出ないとはいえ、その理由は、日本が世界で唯一の被爆国──というより、この映画で開発される原子爆弾の投下された国──であるという事実と無関係ではないだろう。さらに、SNS上で物議を醸した「バーベンハイマー」現象の余波もあり、同作は映画としての内容以前に、公開前から──良くも悪くも──高い注目を集めている。
ここでその『オッペンハイマー』について詳しく語るつもりはないが、個人的にこの映画で印象的だった要素のひとつが、物語中つねに大きな存在感を示す「黒板」の存在だった。知られるように、理論物理学者であったオッペンハイマーが「原爆の父」と言われるのは、かれが原爆開発を目的とするマンハッタン計画で主導的な役割を担った人物だからである。そんな科学者を主人公とする映画とあらば自然なことだが、本作には前途有望な若きオッペンハイマー博士が黒板を背に講義する場面が頻繁に登場する。そして、やがて始まるマンハッタン計画のために集った科学者たちの議論もまた、いつも複雑な式をともなった黒板を背になされるのだ。科学者たちが集まるところ、つねに黒板がある──。この事実は、やはり本作品の主要な部分を占める政治的な弁論(公聴会)の場面が口頭でのやりとりに終始するのと、どこか対照的である。
そんな特異な媒体としての黒板に着目したのが、写真家ジェシカ・ワイン(1972-)による「Do Not Erase」というプロジェクトだ。本書『数学者たちの黒板』は、このプロジェクトをもとにした作家初のモノグラフであり、原著は2021年にプリンストン大学出版局から上梓されている。
本書に収められた109枚の写真は、いずれも数学者たちの黒板を写しとったものだ。教室や研究室のものと思しき黒板には、個性豊かな図や数式が描かれており、どれひとつとして同じものはない。これを書いているわたしも含め、その内容を十全に理解できる者はほとんどいないだろうから、大多数の読者はこれを、ひとつのタブローとして把握することになるだろう。
その黒板の写真には、それぞれのタブローの「作者」である数学者たちの短いエセーが添えられている。これらもまた、写真に劣らず興味深いものばかりだ。とはいえ、その内容は人によってさまざまで、自分が数学の道に足を踏み入れた経緯について語る者、おのれの研究にとっての黒板の重要性について語る者、あるいは数学の愉しみをここぞとばかりに語る者など、個性豊かな100本あまりのエセーが写真の「キャプション」として並ぶ。
なかでも、これらのエセーには共通する一定の特徴がある。まず、本書に登場する数学者たちが総じて強調するのは、コミュニケーションの手段としての黒板の重要性である。ごく当たり前のことだが、PCやノートと比べてはるかに大きな面積を有する黒板は、その場に集まった複数の人間が即座に同じ情報を共有するのに適している。また、スクリーンに投影されたスライドなどとは異なり、その場で──原理的には──誰もが気軽に加筆・修正できるという点でも優れている。本書のもとになったプロジェクトが新型コロナウイルスの流行期に重なったという事情もあってか、本書に登場する複数の数学者が、オンラインでの議論では同じ成果が得られないとこぼしているのも印象的だ。
なかには、ウィルフリッド・ガンボやシミオン・フィリプのように、黒板がもたらす「遅さ」の重要性を強調する者もいる。講義や研究発表のさいに黒板を使用するとなれば、あらかじめ準備した資料にもとづいて内容を説明するよりも、ゆっくりとしたペースにならざるをえない。しかしそのことが結果的に、はじめてその内容にふれる他者の理解を促進する結果につながる、というのだ(20、82頁)。あるいはロネン・ムカメルが指摘するように、黒板を用いた講義や研究発表は「人間の思考の速さで行われる」がゆえに、「準備不足のパワーポイント」などよりもはるかにその優劣を浮き彫りにするだろう(78頁)。
かれら数学者のなかには、黒板のもつ物質性に大きな偏愛を抱く者が少なくない。例えば、本書のはじめに登場するフィリップ・ミシェルのエセーはこんなふうに始まる──「黒板は数学の研究をする生活の基本要素だ。10年前にローザンヌの職場に着いて私が最初にしたのは、悪臭のする赤いペンの置かれた醜いホワイトボードを、本物の黒板と交換するように手配したことだった」(12頁)。このような〈黒板≠ホワイトボード〉という考えかたは、アラン・コンヌ(54頁)、エスター・リフキン(152頁)、ジョン・モーガン(192頁)らも共有するところである。
他方、アミー・ウィルキンソンのように、黒板で数学の研究をすることが「触覚的な経験」(14頁)だと言う者もいる。かと思えば、フィリップ・オーディングのように、指導教員のオフィスにあったスレート製の黒板でチョークが奏でる、不思議なほど「一様な音」について語る者もいる(30頁)。黒板は視覚的なメディアであるにとどまらず、触覚的、聴覚的なメディアでもあるのだ。
本書にはまた、2015年に廃業した日本のメーカー・羽衣文具の栄光が書き留められていることも特筆しておきたい。前出のフィリップ・ミシェルは次のように言う──「滑らかに、途切れることなく書き込むには、上質のチョークも重要だ。特に感動したのは、ある年にクリスマス休暇から戻った博士研究員が、伝説的な日本の『ハゴロモ・フルタッチ・チョーク』を2箱持ってきてくれたときだった」(12頁)。羽衣文具のフルタッチ・チョークは数学者のあいだでは知られた逸品であったらしく、同社の廃業のさいには世界中の数学者による買い占めが起こったという。バッサム・ファヤドが言う「日本製の上質のチョーク」というのも、おそらくこの羽衣チョークのことだろう(156頁)。
昨今、大学の内外における講義や研究発表のほとんどは、Microsoftのパワーポイントをはじめとするデジタルツールによって行なわれている。本書はそうした世の趨勢に対し、実のある説明や議論をするには、黒板というオールドメディアが必要であることを高らかに唱える。それは、おそらく本書の主題である数学に限った話ではなく、新たなアイデアを生み出そうとするあらゆる分野の仕事に当てはまるだろう。本書に登場する数学者たちは、真に創造的な仕事のためには、黒板のような物質的抵抗をともなったメディアが必要であることを示唆しているように思われる。
2023/10/05(木)(星野太)
千葉奈穂子、アンティ・ユロネン、カイサ・ケラター「Dialogue With Land 土地との対話」

会期:2023/10/04~2023/10/15
工房親[東京都]
岩手県出身で、現在は山形県酒田市在住の千葉奈穂子は、2018年にフィンランドに滞在し、ラップランド地方を中心に撮影した。今回の工房親での展示では、そこで知り合った陶芸家、写真家のアンティ・ユロネン、アーティストで生物学者でもあるカイサ・ケラターとのコラボレーションを試みている。
千葉はこれまで、2019年に萬鉄五郎記念美術館八丁土蔵ギャラリーで開催した個展「父の家/Northern Lights」の出品作のように、古典技法のサイアノタイプ(青写真)を用いて、幼い頃の暮らしの記憶を甦らせ、封じ込めるような作品を発表してきた。それがフィンランド滞在を契機として、少しずつ変わり始めているように思う。被写体の細部までしっかりと描写したゼラチン・シルバープリントの黒白写真では、クローズアップや室内の情景を撮影した作品も含めて、より融通無碍なカメラワークを見ることができる。今回の展示には、東日本大震災後に継続して撮影している福島県南相馬市の写真が並んでいた。やはり南相馬市で撮影したアンティ・ユロネンの朽ち果てていく建築物の写真、ラップランドの神話的な記憶を再構築したテキストと写真とを合わせたカイサ・ケラターの作品とも相性がよく、東北とフィンランドという、似通ったところもある風土性が、互いに共振し合う時空間が形成されていた。
1990年代後半から続けてきた千葉の写真の仕事も、かなりの厚みを備えてきている。そろそろ写真集にまとめてほしいものだ。
工房親:https://www.kobochika.com/
2023/10/04(水)(飯沢耕太郎)
FUKI COMMITTEE / 東京風紀委員会 個展「Re:Real」

会期:2023/09/09~2023/09/24
Night Out Gallery[東京都]
桜丘町から代官山を進むJRの沿線は、時たま店の前に「ここでの撮影禁止」といった手製の看板があるほどに、人の作為を掻き立てる場所なのは間違いない★1。そして、グラフィティやステッカーが密集しているというわけではないが、すっと目を引くぐらいには楽しめる場所でもある。例えばステッカーは、フェンスの柱、電柱、標識の柱、看板の裏と、一度目につくと点々と貼られているのをつい眺めてしまう。サインのタイプが多く、同一のステッカーがリズムを伴って連続的に貼られているものが主だっているなかに、ナイトアウトギャラリーで個展が開かれた東京風紀委員会(Fuki Committee/以下、FC)のステッカーがとんと貼られていた。FC(その存在は匿名的であり、コレクティブだと思われる)にとってのステッカーは中心的な制作物であり、アートウォッチャーのはむぞう曰く、新宿、秋葉原にも点在しているという★2。FCのSNSを見ると、貼ってある場所の動画像がたまにシェアされていた★3。FCの個展で作品を見たとき、どこかで見た気がする……と思っていたのだけど、定期的に歩いている街中の急な階段にそのステッカーがあったのだった。
 渋谷区の路上 2023年11月の様子[筆者撮影]
渋谷区の路上 2023年11月の様子[筆者撮影]
ステッカーをはじめとして、FCのペインティングやオブジェの軸には「ウユ」がいる(いなければ、それは目下ウユの不在という意味になるだろう)。ステッカーでのウユは眉を吊り上げ、口元をきゅっとしばり、画面中央に向かって指を反り上げて指す。腰にある手は拳を握り、かなりの前傾姿勢。スカートははためき、ポニーテールの揺れからもこのポーズが瞬時の動作であることが強調されている。そしてその右側には「ダメよ。ゼッタイ。」と書かれている。
これは近野成美や松浦亜弥といった女性タレントが時に凛々しく、時に笑顔で呼びかけてきた麻薬・覚せい剤乱用防止センターによる薬物乱用未然防止活動のキャッチコピー「ダメ。ゼッタイ。」のパロディだ(2013年以降、タレントの起用はなくなった)。ポスター「ダメ。ゼッタイ。」の図像の多くは、爽やかにスポーツを行なう人物やそれに憧れる姿であり、「人のあるべき姿」を示した啓発的な偶像の生成だといえるだろう★4。それに対して「ダメよ。ゼッタイ。」は、もっと直にステッカーを見ているあなた自身にたったいま呼びかける。なにがダメかはわからないけれど。それゆえ、「ダメよ。ゼッタイ。」というフレーズは間違いなく薬物乱用未然防止活動に由来するものだが、どちらかといえば犯罪抑止のための「にらむ目」「見張りステッカー」の系譜にある。もっとも有名なもののひとつは隈取をした歌舞伎役者が見得を切っている図像で「見てるぞ」と添えられたものだ。イラストレーターのオギリサマホによる「見てるぞ」ステッカー探求の記事が指摘する通り★5、「目」をトリガーに他者の存在に思い至らせるという構造のポスターやステッカーは多岐にわたる。しかし、その本意は「ここは監視されている」「ケアされている」「侵犯してはいけない領域だ」と伝えることにある。ただ、こういったメッセージを伝えたいなら重要なのは、貼られている場所の適切さだろう。不法投棄や万引きが起こりそうな場所の入口やここぞという死角。なんらかの人や集団のステイトメントであるということによって、その目は誰かの生きた目を代理することができるようになるのだ。
ではウユの目は何を代理するのか。というのは、「ウユ」とはそもそも、詐欺や賭博といった犯罪を遂行するための見張りをする者(ダチ)という意味をもつ。いままでの話に犯罪の幇助者という意味を加味すると、FCのウユとは何なのか。
本展は複数のペインティングで構成されており、その中央には工事現場で見かけるレンジ色の「ガードフェンス(トラ)」が鎮座していて、そのトラストライプの部分はさまざまな人物によるステッカーで覆われていた。
ところで、@ssmj6543による記録写真のほとんどはそのフェンス越しに撮影されたものだった。ペインティング(キャンバスやスケートボード)は壁面や窓際に整然と並んでいたため、フェンス越しでしか見れないということはなかったのだが、このようにペインティングと鑑賞者の間に障害物が存在する距離に立つことによってさらに明確になるのは、いずれのペインティングも、ウユがこちらを見ていたということにこちらが気づいた瞬間であったり、こちらがウユを盗み見ていたという、視線の瞬間的な状況が描かれているということである。
 会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00007U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]
会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00007U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]
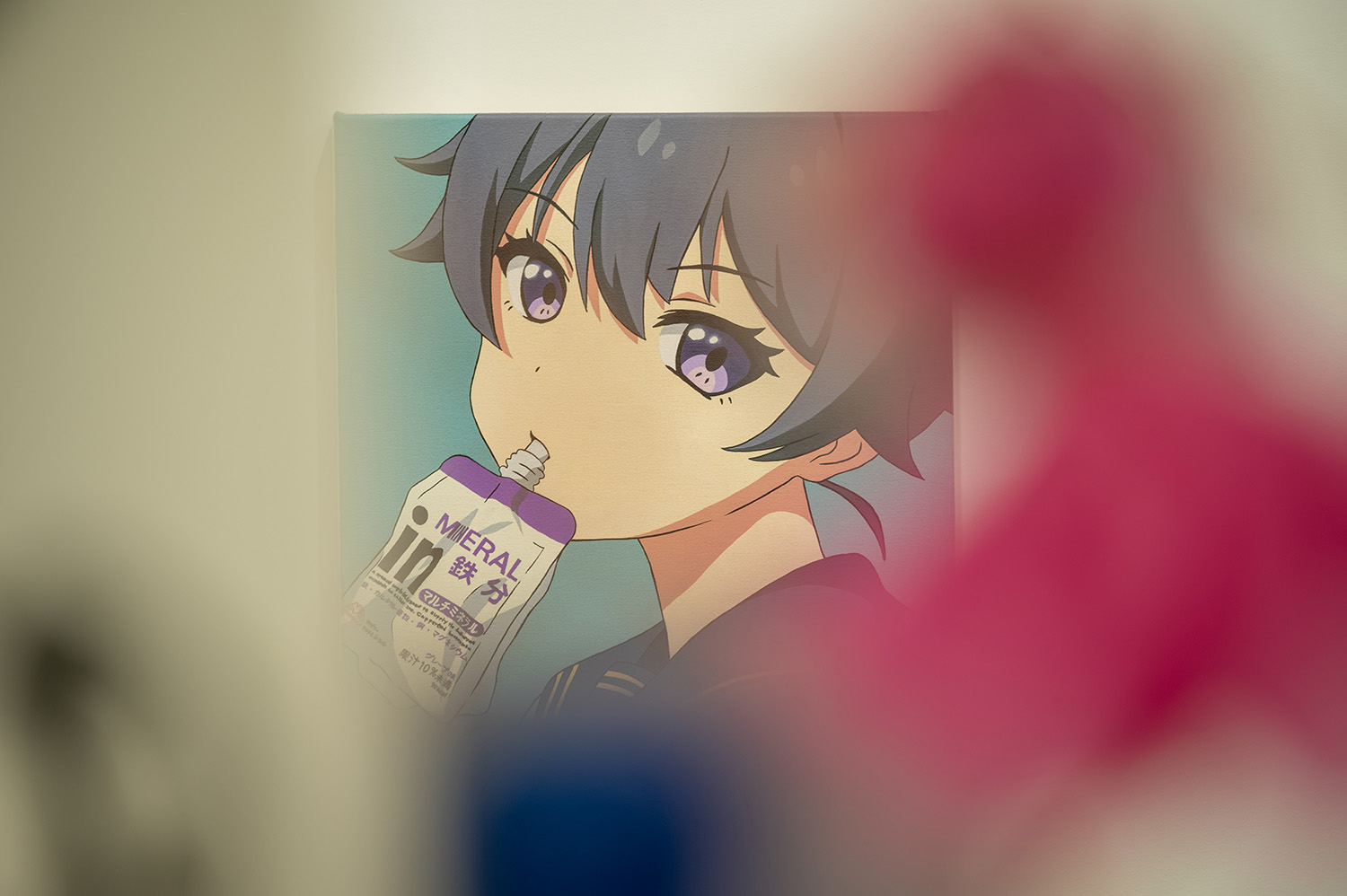 会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00008U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]
会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00008U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]
こういったキャンバスに描かれたウユのなかで、明らかに瞬間的な視線が描かれていない作品があった。それは《Re:REAL-00006U》という作品であり、ウユが机に向かって作業に没頭している様子が描かれたものだ。その構図はYoutubeの楽曲をストリーミングし続ける動画「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」のアニメーション、「lofi girl」を参照したものだ。「lofi girl」は2017年に『耳をすませば』を下敷きにファン・パブロ・マチャドによって描かれたもので、楽曲が配信され続けるように、ヘッドフォンをつけた彼女はひたすら勉学に勤しむというループアニメーションのなかに登場する。
ここで本展のウユに話を戻そう。本展の会場にもlofiが流れていたのだが、ウユが「lofi girl」の構図を取るとき、そこに他者の視線がどこに存在するかを考えることが可能になる。たとえば本作での他者の位置とは、日本語圏では少なくとも2015年頃から散見されるようになるような、タイムラプスでの録画や生配信といったもので他者による作業風景を見る視聴者であり、それを見返しうるウユ自身だ。
作業風景のスマートフォンでの動画記録というものは、「集中を阻害する存在としてのスマートフォン」を気軽に手に取ることができないようにするための方法であり、他者に自己を積極的に監視してもらい、律するための「勉強法」として一般的なものになっている★6。
ウユは「ダメよ。ゼッタイ。」と言いつつ、それが何に対してなのかは判然としないところがある。もちろん、時に手洗いレクチャーを行ない、マスクを着用したステッカーで現われたウユは、そういった社会的規律の順守を呼びかけるようでもある★7。しかし、時にそのステッカーが「落書き禁止を呼びかける看板」に貼られる★8といった状況にあるとき、ウユとは何者か。短く言ってみると、そこに何が犯罪かという判断はないのかもしれない。監視の監視、それが本展でのウユなのだろう。
本展は無料で観覧可能でした。
★1──2023年11月30日、渋谷区桜丘町に東急不動産が大規模複合施設「渋谷サクラステージ」を完成させる。桜丘町はいわゆる渋谷駅の裏側で、歩いていると駅のホームが至る角度から見えるにもかかわらず、JRをはじめとした駅への出入り口がほとんどないから、国道と線路で形取られた浮島のような場所だった。そこにJRの出口と直結する歩行者デッキが生まれることになる。ほとんどの窓にイラストレーションの大型出力シートが貼り付けられた巨大なビル群を見て、渋谷自体に興味はないが、桜丘町から渋谷駅が一気に身近になるのと同時に、人の流れも店も雰囲気も変わっていく予感がした。
★2──こちらのポストを参考にした(X[旧Twitter]:@hamuzou、2023.9.23)。
https://twitter.com/hamuzou/status/1705537257921548783
★3──FCのインスタグラム(Instagram:@fukicommittee)。
https://www.instagram.com/fukicommittee/
★4──「広報活動キャンペーンポスター一覧」(『公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター』)
https://dapc.or.jp/torikumi/62_poster.html
★5──オギリサマホ「街のあちこちで、にらまれる ……『にらむ目』ステッカーが我々に訴えかけるもの」(『散歩の達人』、2021.01.27)
https://san-tatsu.jp/articles/82742/
★6──「敵を最強の味方に!スマホで集中力爆伸び&映えもかなうタイムラプス勉強法」(『スタディサプリ 進路』、2020.11.27)
https://shingakunet.com/journal/exam/20201003000006/
★7──FCのインスタグラムより(Instagram:@fukicommittee、2020.4.13)。
https://www.instagram.com/p/B-6yp2ppt8G/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
★8──FCのインスタグラムより(Instagram:@fukicommittee、2019.10.16)。
https://www.instagram.com/p/B3rjJX6jqpk/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
FUKI COMMITTEE / 東京風紀委員会 個展「Re:Real」:https://nightoutgallery.com/fuki-committee-2nd-solo-show/
2023/09/24(日)(きりとりめでる)
片岡利恵「ディスタール」
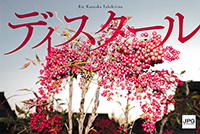
会期:2023/09/19~2023/10/01
Jam Photo Gallery[東京都]
片岡利恵がPlace Mで個展「あわせ鏡」を開催したのは2022年11月だから、まだ1年が経たないうちの展示ということになる。明らかに制作・発表のペースが上がっているだけでなく、今回の写真展を見ると、何をどのように追い求め、どんなかたちに落とし込んでいくかというターゲットがしっかりと見えてきていることがわかる。作品の点数(28点)、大小のカラープリントをアクリルに挟み込んで壁にアトランダムに並べていくやり方、その配列など、前回の展示よりも格段にインスタレーションのクオリティが上がっていた。
夜の場面を中心に、花や植物にカメラを向けるというテーマ自体に変わりはない。ただ、ここでも狙いが絞られてきていて、看護師という職業の実体験に根差した、生と死との境界領域の出来事が、花や植物に託されて説得力を持って語られていた。やや耳慣れないタイトルの「ディスタール」とは、「患者の心臓に一番近いところに向かって点滴を通す」カテーテルの一種なのだという。このタイトルの選び方にも、切実さと必然性を感じる。写真家としての歩みを着実に進めているといえるだろう。
ただ2回続けて同じテーマでの展示を見ると、次の展開を期待してしまう。花へのこだわりは保ち続けながらも、被写体の幅を少し広げてみることはできないだろうか。新たな領域に乗り出していく力は、充分についてきているのではないかと思う。
片岡利恵「ディスタール」:https://www.jamphotogallery.com/exhibitions#comp-llc1ho7y
関連レビュー
片岡利恵「あわせ鏡」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年12月15日号)
2023/09/23(土)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)