artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
山口聡一郎「デッサン」

会期:2023/09/07~2023/10/01
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
1959年、佐賀県生まれ、岡山市在住の山口聡一郎は、同市で写真専門ギャラリー722を主宰しながら作家活動を続けてきた。これまで主に都市風景や車窓からのスナップなど、どちらかといえばオーソドックスなモノクローム写真のシリーズを発表してきたのだが、2023年6月〜7月に奈義町現代美術館ギャラリーで開催した個展「ニュー・ネイチャー」の出品作は、これまでとは一味違っていた。120×90センチのダンボールを支持体として、A4サイズ16枚に分割した画像を感光乳剤に焼き付けた「月の光」「クリアーウォーター」「ビーチ」などの作品群には、彼の前に生起した自然現象が、さまざまな角度から定着されていたのだ。
今回、コミュニケーションギャラリーふげん社で展示した「デッサン」も、その「ニュー・ネイチャー」展で発表した作品である。1999年に、自分自身を被写体として開始したヌードの連作は、その後も続けられ、女性モデルの作品も加えてかなりの厚みに達している。そこにはエロティシズムを強調するよりも、むしろ「裸体という物体」の存在感を突き詰めようとする姿勢が一貫しており、撮影を通じて、写真という表現媒体の原点をあらためて確認しようとしているようにも見える。何かの下絵としての「デッサン」ではなく、むしろ撮り続けるという行為の積み重ねそのものに意味を見出しているのではないだろうか。ただ本作には、「ニュー・ネイチャー」という総体的な営みのひとつのパートという側面がある。その全体像を、東京でも見ることができる機会がほしいものだ。
山口聡一郎「デッサン」:https://fugensha.jp/events/230907yamaguchi/
2023/09/23(土)(飯沢耕太郎)
広川泰士「2023-2011 あれから」

会期:2023/09/22~2023/10/12
フジフイルムスクエア[東京都]
広川泰士は長くファッションや広告の世界で活動してきた写真家だが、同時に高度経済成長期以降の日本の変貌を緻密かつ粘り強く記録していく風景写真を、ライフワークとして撮影し続けている。2015年に赤々舎から刊行した写真集『BABEL ORDINARY LANDSCAPES』には、大地を引き裂き、大規模な工事によって環境そのものを変貌させていく人間の営みを、旧約聖書の、神をも恐れぬバベルの塔の建造と重ね合わせた写真シリーズがおさめられていた。その広川が2011年3月に発生した東日本大震災に強い関心を抱いたのは当然というべきだろう。震災直後に、救援物資を積んだ車で被災地に向かった。だが、その時に撮影した写真群を、すぐに発表する気にはなれなかった。そこには、あまりにも生々しく、凄惨な眺めが広がっていたからだ。
その後、同じ場所を同じアングルで時間を置いて撮影する定点観測写真という方法を見出すことで「撮り続ける」ことが可能となった。広川は、宮城県気仙沼に4ヶ所、岩手県陸前高田に2ヶ所、釜石に3ヶ所、定点観測写真のスポットを設け、2023年まで何度も足を運んで撮影を続けた。今回のフジフイルムスクエアの展覧会では、それらの風景写真に加えて、2011年6月から相馬(福島県)、気仙沼で撮影した被災者の家族たちのポートレートの連作もあわせて展示されていた。
広川の取り組みは、震災後10年以上を経た現時点におけるドキュメンタリー写真のあり方を、あらためて問い直すものと言えるだろう。定点観測という手法に終わりはない。むしろ今後も撮り続けていくことによって、その仕事の意味と重みはより増してくる。そのエンドレスな作業への覚悟が、展示から伝わってくるように感じた。
広川泰士「2023-2011 あれから」:https://fujifilmsquare.jp/exhibition/230922_01.html
関連レビュー
広川泰士「BABEL Ordinary Landscapes」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年03月15日号)
2023/09/22(金)(飯沢耕太郎)
サトウヒトミ「over the window」

会期:2023/09/19~2023/09/30
キヤノンギャラリー銀座[東京都]
コロナ禍の時期に活動を休止、あるいは制限しなければならなかった写真家たちも、ようやく自分のペースを取り戻しつつあるようだ。サトウヒトミもその一人で、キヤノンギャラリー銀座でのひさびさの新作展で、意欲的な作品を発表していた。
会場に並んでいるのは、さまざまな国の街頭、あるいは室内で撮影されたスナップ写真だが、それらを見ているうちに微妙な違和感が生じてくる。アメリカやヨーロッパの風景に日本人らしい姿が映っているものがあったりして、そのうちに画面の一部を合成しているのだと気づいた。つまり、撮り溜めていた旅のスナップ写真と、コロナの渦中の日本の眺めとをオーバーラップさせているのだ。どうやら、ステイ・ホームの時期に、パソコンのデスクトップで過去の写真を見ていて、「架空のスナップショット」というアイデアを思いついたようだが、時宜を得たいい作品になったのではないだろうか。
むずかしいのは、画面のどこに、どれくらいの割合で合成写真を入れ込んでいくかという匙加減だと思う。ものによっては、もう少し大胆な画像処理をしてもいいのではないかと思う作品もあったが、むしろこのさりげなく、押しつけがましくない見せ方が、サトウの持ち味と言えるのかもしれない。巧まずして、コロナが一段落したこの時期のやや緩んだ空気感を伝える世界像として成立していた。なお、展覧会にあわせて、京都の展示スペースPURPLEから、瀟洒なデザインの同名の写真集が刊行されている。本展は10月31日〜11月11日にはキヤノンギャラリー大阪に巡回する。
サトウヒトミ「over the window」:https://canon.jp/personal/experience/gallery/archive/overthewindow
2023/09/22(金)(飯沢耕太郎)
ERIC「東京超深度掘削坑」

会期:2023/09/12~2023/09/25
ニコンサロン[東京都]
1976年に香港で生まれ、1997年に来日して以来、東京で写真家として活動してきたERICは、7年前に生活の拠点を岡山に移した。その結果、農業や狩猟など、それまでは縁遠かった経験を積み重ねることになる。その「お金を介さない、本来的な食糧調達」のあり方に触れることで、彼のなかに「新たな目」が育ってきたのだという。その彼の新作では、そうやって獲得した視線のあり方を、コロナ禍以降の東京に向けている。
日中シンクロの手法を多用した路上のスナップショットという点においては、これまでの彼の写真のスタイルをそのまま踏襲しているように見えなくもない。だが、都市の表層を鋭利な刃物で剥ぎとるようなこれまでの写真と比べると、本作では視線の深度が深まっているように感じる。マスク姿が目立つ異形の人物たちや、むしろ人間以上の生命力を感じさせる植物たちの写真から見えてくるのは、むしろ都市の深層に伸び広がる「根」のようなものを探り当てようとする試みである。これまでのERICの作品と比較しても、本シリーズには、この時代のこの瞬間を写真に刻みつけておかなければならないという切迫感をより強く感じた。
この「超深度掘削坑」の試みは、もしかすると東京以外でも試みることができるかもしれない。次の展開が大いに期待できそうだ。
ERIC「東京超深度掘削坑」:https://www.nikon-image.com/activity/exhibition/thegallery/events/2023/20230912_ns.html
関連レビュー
ERIC「香港好運」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年02月01日号)
ERIC『LOOK AT THIS PEOPLE』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2012年02月15日号)
2023/09/14(木)(飯沢耕太郎)
川崎祐「未成の周辺」
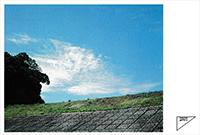
会期:2023/09/01~2023/09/24
Kanzan Gallery[東京都]
川崎祐は前作『光景』(赤々舎、2019)で、故郷の滋賀県長浜市の風景とそこに住む家族の姿を捉えたシリーズを発表した。その、否応なしに絡みついてくるような、かかわりの深さを感じてしまう写真群と比較すると、今回、Kanzan Galleryの個展に出品された新作「未成の周辺」からは、どこか淡く希薄な印象を受ける。被写体となった和歌山県新宮市の周辺は、川崎が学生時代からずっと関心を保ち続けてきた中上健次の小説の舞台になった場所である。だが前作と比較すると、そのような理由づけだけでは、どうしても必然性を欠いたものに見えてきてしまうのだ。
川崎はむしろ、「他者の風景」を撮ってみたかったのではないだろうか。『光景』に写し込まれた琵琶湖北岸の土地の呪縛から離れて、もっと自由に、のびやかに見渡すことのできる眺めを求めたともいえそうだ。その狙いはとてもうまくいっていて、意味づけの重力から逃れた「未成の」風景が、次々に目の前に生起してきた。だが展覧会に寄せたコメントには、「海にしろ山にしろ森にしろ、みあきることのない景色がいたるところにひろがる新宮とその周辺」にカメラを向けながら、結果的には「迂回に迂回を重ねたような道をぐるぐる歩きながら荒地や空き地や住宅が気になった」と書いている。その「荒地や空き地や住宅」は、『光景』にも頻繁に登場してくる。とすると、川崎が次にめざすべきなのは、「他者の風景」と「自分の風景」とが重なり合うところに出現してくる眺めなのかもしれない。その萌芽は、今回のシリーズにもすでにあらわれてきているように見える。
なお、展覧会にあわせて喫水線から同名の写真集が刊行されている。
川崎祐「未成の周辺」:http://www.kanzan-g.jp/yu_kawasaki.html
関連レビュー
川崎祐 写真展「光景」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年12月15日号)
2023/09/14(木)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)