artscapeレビュー
2017年02月01日号のレビュー/プレビュー
「身体をめぐる商品史」「百貨店と近世の染織」

会期:2016/10/18~2017/12/18
国立歴史民俗博物館[千葉県]
工業化の進展、流通網の発達につれて、私たちの身の回りの商品は変化してきた。商品の変化は、私たちの身体観、生活習慣、美意識に影響し、それらを少しずつ変えてきた。「身体をめぐる商品史」展は20世紀初頭から1980年前後までを対象に、さまざまな商品と身体との関係とその変化を見る企画。展示第1章「百貨店の誕生と身体の商品化」と第2章「流行の創出と『伝統』の発見」では三越を中心に、明治末から大正初めにかけて都市部を中心に台頭した中間層が消費を通じて自己を表現するようになった姿や、百貨店が流行を主導した様子が、引き札、広告、広報誌などの史料で語られる。田中本家博物館(長野県須坂)に残る百貨店の注文書や子供服からは、都市の流行が百貨店の通信販売を通じて地方にまで波及していたことがわかる。琳派のリバイバルに三越が果たした役割は知られているところだが、さらには百貨店の商品が現実の過去とは異なる江戸のイメージをつくりだしたという指摘は興味深い。第3章は「健康観の変遷」。明治初期からお雇い外国人たちが楽しんでいたレジャーやスポーツは、日本の上流層の若者たちへ波及し、学校教育にも取り入れられてゆく。海水浴やスキー、スケート、野球など、レジャーやスポーツのための道具は人々の健康観と一体となって売られていった。第4章は「衛生観の芽生え」。衛生観、清潔さのイメージは、国や地域、時代によって大きく異なっている。ここでは「日本人はきれい好きだった」という思い込みに対して疑問を呈すると同時に、石鹸、歯磨き粉、シャンプーなどの商品、パッケージ、広告によって人々の衛生観が形作られていった様が示されている。第5章は「美容観の変遷」。日に焼けた肌が健康的とされる時代、美白が良いとされる時代、しばしば矛盾する美のイメージ、身体のイメージが、商品とともに消費されていく。「身体をめぐる商品史」というタイトルはやや難解だが、戦後の化粧品メーカーの展開を見れば、商品と広告キャンペーンが人々の身体のイメージ──健康観、衛生観、肉体美──を作りあげ、それが時代によって変遷していったことは一目瞭然だろう。
5つの章のなかで、個人的にもっとも興味深かったのは第4章「衛生観の芽生え」で紹介されている歯磨きとシャンプーの事例だ。幕末開港後に日本を訪れた欧米人は、日本人には歯抜けが多い、味噌っ歯で汚いと述べていることから、歯磨きの習慣が定着していなかったことがうかがわれるという。
大正時代になってからも若年からの虫歯が多く、学校教育を通じて歯磨きの啓蒙運動が行なわれた。しかしながら現実に人々に歯磨きの習慣をつけさせ、歯を衛生的、健康的にしたのは、学校教育ではなく、ライオンや中山太陽堂などの歯磨き粉や歯ブラシ、そしてそれらの広告だった。シャンプーの習慣についても同様で、毎日の洗髪の習慣を可能にしたのは髪や肌を傷めないシャンプーや石鹸の開発であり、フケを不潔なものと人々に印象づけたのもフケを抑える効果を持つシャンプーの広告だった。人々は新しい商品と新しい広告によって従前の自分たちを不潔と定義し、新たな清潔さをこぞって求めたのだ。エイドリアン・フォーティーは、19世紀末から20世紀初頭の欧米において「清潔さの水準を高めるうえでは、商業のほうが衛生論者たち以上の成功をおさめた」★と述べているが、ここではまさに同様のことが日本の事例によって示されていることになる。商品史としても、広告史としても、デザイン史として見ても、たいへん興味深い。
企画展第2章「流行の創出と『伝統』の発見」と関連して、第3展示室では大正期に百貨店で開催された展覧会に出品された江戸時代の染織品が取り上げられていた。百貨店は新作を売り出すにあたり、参考品として歴史史料を展示することで製品に歴史的な裏付けがあること、それを身につけることが良い趣味を表すことなのだと顧客に訴えていたのである。[新川徳彦]

展示風景
★──エイドリアン・フォーティー(高島平吾訳)『欲望のオブジェ──デザインと社会 1750年以後』鹿島出版会、2010年8月、232頁。
2016/12/8(木)(SYNK)
わだばゴッホになる 世界の棟方志功

会期:2016/11/19~2017/01/15
あべのハルカス美術館[大阪府]
本展は昨年11月から行なわれていたが、記者発表日に別の仕事が入ったため取材が出来ず、そのまま年を越してしまった。本当のところをいうと、新年早々に出かけたのは正月ボケを直すため。つまりウォーミングアップであり、さほど思い入れはなかったのだ。しかし、棟方の作品を見た途端、筆者の心に火がついた。なんだ、この感情は。それは芸術鑑賞というより、祝祭の高揚に近い。理屈ではなく、身体の奥底から熱い塊がこみ上げてくるのだ。過去に何度も棟方の作品を見たことがあるのに、これほど盛り上がったことはなかった。きっと大作や連作が多かったからだろう。特に展覧会中盤の、《大世界の柵》(天地175.4×左右1284cmの2点組)や《鷲栖図》(天地275×左右803cm)などの超大作が並んだあたりは大迫力で、心のなかで何度も雄叫びを上げてしまった。年始から自分の根っこにあるジャパニーズ・ソウルをこれほど意識させられるとは。おかげで新年の良いスタートが切れたと思う。
2017/01/06(金)(小吹隆文)
新設常設展「Designer Maker User」
デザイン・ミュージアム[ロンドン(英国)]
テムズ河南岸にあったデザイン・ミュージアムが、昨年11月にケンジントンに移転し、再オープンした。ミュージアムの広さは以前に比べ3倍に増大、2つの特別展のスペースに加え、新しく無料の常設展とデザイナー・イン・レジデンスの場が設置された。そもそもこのミュージアムは、20世紀の近代デザインを展示することを目的に、1989年に創設された。今回できた常設スペースは「Designer Maker User」と銘打たれ、デザイナーと作り手と使い手の社会文化的諸関係を明示しながら、デザイン製品の生産から消費までの物語を紡ぎだそうとする。展示デザインにも意外性があってハイセンス。イタリアのVespa(スクーター)が頭上に展示されたり、液晶画面による説明パネル、さらに3面の大スクリーンには映像作品と言ってもよいほど凝った、デザイン関係者のインタビュー/ドキュメンタリー作品が投影されていたりする。来館者同士やミュージアムのスタッフも気さくに会話に加わって、会場は大いに盛り上がっていた。なお移転地はコモンウェルス・インスティチュート(英連邦協会)の跡地で、モダニズム建築としての歴史的価値も高い建物。今回の移転はテレンス・コンラン卿(ミュージアム設立者・デザイナー・実業家)の莫大な寄付によって可能になったそうだが、改装後の見事な内装はさすが。吹き抜けを活かしつつ階段などは木製の調度で仕上げ、非常にドラマチックな空間となっている。二つあるミュージアムショップも楽しいうえに、展示は大変充実、また立地も便利になったので、訪英の際はぜひ来訪をお薦めする。[竹内有子]

左:常設展「Designer Maker User」入口(筆者撮影) 右:会場風景
2017/01/08(日)(SYNK)
ゲーム・プラン展──ボードゲームの再発見
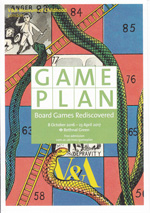
会期:2016/10/08~2017/04/23
V&A Museum of Childhood[ロンドン(英国)]
子供博物館は、ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館の分館。サウスケンジントン(同本館)初期の建築の一部をロンドン東部のべスナルグリーンに移築し、1872年に当時のプリンス・オブ・ウェールズ(ウェールズ公)によって開館された。文字通り子供のためのミュージアムで、展示されているのはノスタルジーを感じさせる多彩なヴィンテージのおもちゃと子供の生活を巡る日用品。なんといっても見事なのは、19世紀の上流階級が持っていたドールハウスのコレクション。細部まで忠実に作りこまれた大きなサイズのドールハウスは、当時の建築とインテリアを知るうえで大変参考になる。今回の企画展は、歴史的な「ボードゲーム」の変遷をテーマとしている。一口にボードゲームと言っても、歴史をさかのぼれば古代エジプトに遡る。以来、千年以上に及ぶ今日までのゲーム発展の歴史を、100点以上に及ぶ世界から集めた展示品で丁寧に跡付けている。デザインや美的観点にも着目しているので、子供から大人まで十分楽しめる内容だ。会場の最後では、いろいろな種類のボードゲームが置かれているので実際に遊ぶこともできる。ハイテクガジェットの全盛時代にあって、たくさんの親子連れが、和やかな雰囲気の中でボードゲームを楽しんでいる様子がとても印象的だった。[竹内有子]
2017/01/08(日)(SYNK)
茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術

会期:2016/12/17~2017/02/12
京都国立近代美術館[京都府]
樂家の樂焼のはじまりは今から450年前、千利休の指示のもと長次郎がつくった樂茶碗にまでさかのぼる。当代の吉左衛門で十五代を数えるという。本展では一子相伝という形態で途切れることなく脈々と受け継がれてきた、樂焼の技術と精神性を味わうことができる。2015年にロサンゼルス・カウンティ美術館ではじめて開催され、その後、エルミタージュ美術館、プーシキン美術館を巡回し、この度京都での開催となった。初代から当代までを余すことなく網羅した出品作には、重要文化財や茶の湯の名家に伝わる名品が含まれる。いずれも茶道の精神性、「侘び」に通じるといわれる樂茶碗で、色や模様のない、黒あるいは茶一色の手捏ね成形の茶碗である。当代吉左衛門の作品が出品の三分の一以上を占めており、ひとりの作家の30年間あまりの作風の変化を目の当たりにすることもできる。一つひとつの作品に刻まれた挑戦と葛藤の跡には歴史を受け継ぐ重責を跳ね返すかのようなエネルギーと気迫が感じられた。[平光睦子]
2017/01/08(日)(SYNK)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)