artscapeレビュー
2022年03月15日号のレビュー/プレビュー
Life in Art “TOKYO MODERNISM -2022-” Modernism Gallery

会期:2022/02/25~2022/04/10
ATELIER MUJI GINZA(無印良品 銀座 6F)[東京都]
もう20年以上も経つのか……。日本でミッドセンチュリー期のモダンデザイン家具が流行したのが、である。時は1990年代後半、私はまだ20代で、駆け出しのフリーライターとして大阪にいた。初めてチャールズ&レイ・イームズのシェルチェアを見たのも、大阪市内にオープンしたばかりのファッショナブルなカフェだった。そのときの衝撃たるや。その後、行きつけとなる別のカフェでもイームズのシェルチェアが使われていて、この椅子をきっかけに、私のなかでモダンデザイン家具への興味が俄然と湧き、世の中のブームも手伝ってこれらに関する記事を書く機会が増え、いまに至ったと言っても過言ではない。私自身もイームズのシェルチェア、ハリー・ベルトイアのサイドチェア、ジャンカルロ・ピレッティのプリアチェアなどを格安で手に入れ、当時、ひとり暮らしの部屋に置いて悦にいっていた。結婚後もさらに増え続けながら、暮らしのなかでこれらの椅子を愛でている。なぜならモダンデザイン家具は空間の中でオブジェとなるし、彩りをもたらすからだ。当時、多くの人々の心を捉えたのも、そんな魅力のせいだろう。
 展示風景 ATELIER MUJI GINZA
展示風景 ATELIER MUJI GINZA
本展はイベント「TOKYO MODERNISM -2022-」の一環として開催されているギャラリー展示で、同イベントではほかにオークションやショーが今後も予定されている。ミッドセンチュリー期のモダンデザイン家具というと、ハーマンミラー社に代表されるように米国が中心のイメージがあるが、本展ではほかに日本、北欧、フランス、ブラジルと5カ国・地域にコーナーを括り、全世界での現象として捉えていた点が面白い。確かにその後のブームとして日本や北欧のモダンデザイン家具に注目が集まったし、フランスにはル・コルビュジエを中心とする一派がいたし、ブラジルには建築家のオスカー・ニーマイヤーがいた。
 展示風景 ATELIER MUJI GINZA
展示風景 ATELIER MUJI GINZA
また出展者が、日本各地に点在するギャラリーやショップというのも興味深い。20年以上前からの日本での流行を支えたのはほかでもない、人から人へつなぐ役割を担ってきたギャラリーやショップであるからだ。オーナーら自身が影響を受けたという「逸品」がその思いとともに紹介されていた。そう、誰もがつい語りたくなってしまう愛着の深さも、モダンデザイン家具ならではの特徴と言える。
 展示風景 ATELIER MUJI GINZA
展示風景 ATELIER MUJI GINZA
公式サイト:https://www.idee-lifeinart.com/exhibition/tm2022/index.html
2022/02/26(土)(杉江あこ)
ホームビデオ・プロジェクト「テールズアウト」

会期:2022/02/02~2022/03/21
大阪中之島美術館[大阪府]
建設構想から約40年を経て、2022年2月に開館した大阪中之島美術館。開館プレイベント「みなさんの『ホームビデオ』を募集します!」で家庭に眠るホームビデオを一般市民から募集し、集まった300本超のビデオテープや映像データを用いて、現代美術作家3名が新たな作品を制作した。参加作家は、荒木悠、林勇気、柳瀬安里。展覧会タイトルの「テールズアウト」とはテープの巻き方を指す言葉に由来する。収録済みテープの最終部がテープの巻き終わりになっている状態を「テールアウト」と呼び、その続きから現代作家たちが新たな物語を紡ぎ出すことが企図されている。また、美術館建設構想が始まった1983年は、一般家庭向けのカムコーダ(ビデオカメラ)が登場した年でもあり、以降、小型化と長時間録音が可能となったビデオカメラの普及が進んでいく時代が、開館までの美術館の歩みと重ね合わされている。
主に家庭内で撮影され、子どもの成長や行事を記録し、家庭内でプライベートに鑑賞されるホームビデオ。8ミリビデオからデジタルデータに及ぶ記録媒体の変遷と、社会や家族のあり方の変化。普遍性や交換可能性と、個人性の強い刻印とのせめぎ合い。他人の私的な映像を見る行為の倫理性。記憶や時間についての省察。「ホームビデオ」から派生する問題に対し、荒木、林、柳瀬は三者三様のアプローチを見せた。
荒木悠の《HOME / AWAY》は、空港の出発ロビーをイメージした空間に、天井から3台のモニターが吊られている。モニターには、モノクロ、カラー、鮮明なデジタル映像と異なる時代のホームビデオが流れるが、映された光景は、旅行、動物園、運動会と共通し、「ホームビデオのお約束の主題」を指し示す。同様の試みとして想起されるのが、フィオナ・タンのファウンドフォト・インスタレーション「Vox Populi(人々の声)」だ。展覧会開催地の住民から収集した写真を、構図やポーズ、主題などでグルーピングし、「アマチュア写真の無意識的なコード」のマッピングを提示する。荒木も集合体から類型化を抽出し、3つの異なる時代や記憶媒体を並列化することで、普遍性と差異を浮かび上がらせる。

荒木悠《HOME / AWAY》[撮影:小牧寿里]
一方、ホームビデオが撮影・鑑賞される「家庭」という空間や、他人の私的な映像を見る行為の倫理性を問うのが柳瀬安里だ。《ホーム_01》《ホーム_02》では、黒い箱の中にミニチュアの家具を配置した「リビングルーム」が設えられ、被写体の顔にライトを当てて消した映像が投影されている。映像は(遠足や旅行、運動会や発表会、海やプールなど「家庭の外」を除外した)「家庭内の親密な光景」に限定され、画質の荒さから時代感がうかがえる。この「黒い箱」は、かつてホームビデオが鑑賞されたブラウン管モニターを指すと同時に、家庭という閉域の「のぞき箱」でもある。また、被写体の子どもの顔を匿名化する操作は、「それは私自身だったかもしれない」という交換可能性や既視感と同時に、SNS上でシェアされたプライベートな画像・動画を思わせる。時代感のあるホームビデオがSNS上にアップされているかのような奇妙なアナクロニズムは、逆説的に、時代を超えた普遍的な欲望を浮かび上がらせる。

柳瀬安里《ホーム_02》[撮影:小牧寿里]
上記の2作品はサイレントだが、「フィクショナルな語り」の上書きによって、記録媒体や時間の複数性、記憶のあり方についての多様なメタファーを示唆するのが、林勇気の《瞬きの間》である。真っ黒な画面中央には、円形の映像が映り、不安定に揺らぐ映像をよく見ると、さまざまなプラスチックのコップに満たされた水を通して映し出されていることがわかる。日常的なプラスチック製コップと、DVDやフィルム、磁気テープなどの記録媒体の原材料が同じ化石燃料であることに着目した仕掛けである。
また、のぞき穴、カメラのレンズ、トンネルの先に見える光景を思わせる「円形の窓」によって、私たちは、かつてレンズ越しに被写体に親密な眼差しを向けた撮影者、窃視者、時空のトンネルを超えた目撃者という複数の多重的な立場に立たされる。そしてコップは、形を持たず、儚くこぼれ落ちてしまう記憶を物質的にとどめたいという欲望や記録媒体の謂いでもある。キャラクターの絵柄付き、取っ手の有無、コップ自体の形の多様性は、それらが使用される家庭の個別性と同時に、記録媒体の多様性のメタファーでもある。

林勇気《瞬きの間》[撮影:小牧寿里]

林勇気《瞬きの間》[撮影:小牧寿里]
さまざまなホームビデオを断片的に繋ぎ合わせた映像にオーバーラップされるのは、20年前、実家の庭に兄とともに埋めたタイムカプセルを掘り出すため、車で故郷へ帰る男性のモノローグだ。タイムカプセルには、兄が撮ったHi8(ハイエイト)のビデオテープがあると語られる。かつて子ども時代に撮影され、家庭内のどこかに眠るホームビデオはまさに「タイムカプセル」であり、男性の車と平行に走る列車の線路は「異なる複数の時間の流れ」を示唆する。洞窟内で野宿し、焚き火の明かりで洞窟の壁に投影した影絵=映像の原理。回転する車輪=フィルムやビデオテープのリール。焚き火の火が燃え移り、溶けて燃えてしまうプラスチックのコップ=記録媒体の物質的な可燃性や損傷性。「画像や映像にオーバーラップさせたフィクショナルな語りのなかに、記憶や時間についての自己言及的なメタファーを散りばめる」という近年の林の手法が凝縮されていた。
関連レビュー
林勇気「15グラムの記憶」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年10月15日号)
2022/02/27(日)(高嶋慈)
鳥公園『昼の街を歩く』

会期:2022/02/27~2022/03/06
PARA[東京都]
2019年の『終わりにする、一人と一人が丘』を最後に西尾佳織が作・演出・主宰を兼ねる体制を終え、和田ながら(したため) 、蜂巣もも(グループ・野原)、三浦雨林(隣屋)の三人の演出家をアソシエイトアーティストとして迎えた鳥公園。体制変更の直後からワークショップや読書会など劇団としての活動は旺盛に展開していたものの、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、首都圏での公演は今回が初めてとなった。
鳥公園として初の蜂巣演出作品でもある本作は被差別部落問題に関するリサーチからスタートしたもの。当初は蜂巣の希望で「リサーチから戯曲を書く西尾の劇作のプロセスに、演出家として帯同」し「様々な土地でのフィールドワークから創作を始める予定」だったプロジェクトだが「新型コロナウイルスの蔓延により計画変更を余儀なくされ、今回は書籍やオンラインでのリサーチが主と」なり、2020年12月に森下スタジオで実施された10日間のワークインプログレス(非公開)を経て今回の公演が実現した。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
戯曲からひとまず物語のみを抽出するならば『昼の街を歩く』は次のような話である。同棲中の清太郎(松本一歩)と絹子(大道朋奈)。絹子からどうやら妊娠したらしいと聞いた清太郎は一晩のあいだ失踪してしまう。帰ってきた清太郎に絹子は「昨日、なにしてた?」と問うが、謝罪ばかりで答えは得られない。清太郎は「言ってないことがある」と絹子を大阪の実家に誘い、その週末、大学で東京に出て以来の実家へと戻る。そこには姉の初美(伊藤彩里)がひとりで暮らしている。初美には、子供を堕ろし、パートナーと別れた過去があるらしい。初美は絹子を喫茶店に誘い、家のことなどを話す。帰りの新幹線で今回の帰省を振り返る清太郎と絹子。絹子に生理が来て妊娠は勘違いだったことが明らかになる。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
筋としてはシンプルだが、戯曲は帰りの新幹線の場面からはじまり、複数の時間が行きつ戻りつしながら徐々に全体像が明らかになっていく構成となっている。これまでのほとんどの西尾戯曲に組み込まれていたような非現実的な場面はなく、基本的には(現実でもありそうなという意味で)リアルな設定でのリアルな会話のみで進行していくという点で、劇作家としての西尾の新たな(個人的には意外とも思える)展開を見た。
「被差別部落問題を扱った作品」として見るならば、この戯曲は社会的な問題を個人の問題へと矮小化してしまっているようにも思える。だがこの戯曲はむしろ、被差別部落問題について考えることからスタートして、個人対個人の関係が家族、地域、社会のなかでいかに(不)可能かということを描こうとしたのだと考えるべきなのだろう。それらは別々の問題でありながら互いに絡み合い、ときに身動きが取れないほどに個人を雁字搦めにしてしまう。西尾戯曲は食事、繁茂する多肉植物、隣人との関係などのディテールを通してそのさまを描き出し、描くことによって解きほぐそうともするのだが、それについては戯曲を読んでいただきたい。ここでは蜂巣演出が何をしていたかを見ていこう。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
会場のPARAは民家をそのまま使ったイベントスペース。受付を済ませた観客は玄関を入らず、縁側と塀との間のささやかな庭で開演を待つ。時間になると雨戸が開けられ、庭から縁側越しに見える和室には、体の正面をこちらに向けた状態で横たわり積み重なる清太郎と絹子の姿がある。隣あって立つ二人がそのまま横倒しになったようなかたちだ。奇妙な状況だが、二人はどうやら新幹線の座席に並んで座っているらしい。そういえば、奥のテレビの画面には車窓の風景が映っている。やがて絹子がトイレに立つと入れ違いに初美がやってきて「半端なことして」と清太郎に苦言を呈す。 時系列的には初美の苦言は前日の実家での出来事であり、ここではそれを清太郎が回想している(と戯曲では読める)のだが、蜂巣演出では清太郎が寝そべっているところに初美がごく普通に登場することで、あたかも初美の声で清太郎が目を覚ました、とでもいうように、ここまで非現実的な体勢で交わされてきた清太郎と絹子の会話の方に夢のような手触りが与えられることになる。戯曲上では新幹線の現在から実家での出来事を回想する場面が、蜂巣演出では同時に、実家での現在から未来を夢想する場面としても成立しているのだ。過去と同じように、未来もまた現在の裡にある。個人と家との関係を描いたこの作品において、このことはとりわけ重要であると思われる。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
ここまで観ると観客は家の中へと招き入れられ、清太郎が寝そべるまさにその和室で続く場面を鑑賞する。その場面の終わり、夜中に大きな地震が起き、しかし清太郎は同棲する絹子に声をかけることなく、離れて住む姉に電話をかけながら2階への階段を上がっていってしまう。その姿は絹子のいる家と初美のいる家とが交わることを忌避するかのようだ。絹子とともに取り残された観客は清太郎を追い、家のさらに内部、2階へと上がり込むことになる。だが、たどり着いた2階は窓が開け放たれ予想外に明るい。そうして踏み込むことでしか開けない未来もあるのだとでもいうように。
本作のクリエイションは今後も継続され、2023年度には八王子のいちょうホールでの再演が予告されている。今回の蜂巣演出は「家」という空間を巧みに使い観客にその磁場を体感させるものだったが、ホールでの上演はどのようなものになるのだろうか。今後の展開も楽しみに待ちたい。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
鳥公園:https://www.bird-park.com/
『昼の街を歩く』戯曲:https://birdpark.stores.jp/items/621034c01dca324ba5b2bae0
関連レビュー
鳥公園「鳥公園のアタマの中」展|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年04月01日号)
2022/03/06(日)(山﨑健太)
カタログ&ブックス | 2022年3月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
TOKYO POPから始まる 日本現代美術1996‐2021

著者:小松崎拓男
発行:平凡社
発行日:2022年2月18日
サイズ:四六判、304ページ
現代美術の現場を並走してきた著者が語る、日本のアート・シーンの四半世紀。村上隆から奈良美智まで、日本現代美術の貴重な記録。
建築から世界史を読む方法(KAWADE夢新書)

著者:祝田秀全
発行:河出書房新社
発行日:2022年2月21日
サイズ:新書判、240ページ
ギリシャ、ロマネスク、ゴシックなど建築様式の変遷と世界史は連動している。著名な建築物が「なぜそこに」「なぜその意匠で」造られたのかを追究すると、歴史の意外な事実が見えてくる!
日本文学大全集 1901-1925

著者:指田菜穂子
解説:ロバート キャンベル
発行:ART DIVER
発行日:2022年2月22日
サイズ:B5判、152ページ
「絵で百科事典をつくる」という発想のもと、言葉から連想されるあらゆる事象を一枚の画面に緻密に描き込む芸術家・指田菜穂子。その1冊目となる作品集です。
ゴッホを考えるヒント 小林秀雄『ゴッホの手紙』にならって

著者:佐藤公一
発行:アーツアンドクラフツ
発行日:2022年2月24日
サイズ:四六判、112ページ
印象派を超えようとした絵画制作と、いわば「文豪の手紙」とも見まがう書簡文学を表わしたゴッホ。その太陽のように輝く存在であるゴッホの真実を、一枚の《自画像》をからめつつ、ゴッホの全生涯の歩みをたどる。
アート&デザイン表現史 1800s-2000s
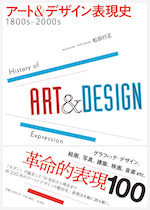
著者:松田行正
発行:左右社
発行日:2022年2月25日
サイズ:A5判、440ページ
グラフィック・デザイン、絵画、写真、建築、映画、音楽etc. 1807年〜2019年までに生まれた革新的な表現法。 その中心となる作品と、そこから派生、影響を受けた作品や似た作品をビジュアルとともに解説する。アートとデザインの歴史が概観できる「デザインの歴史探偵」松田行正による渾身の一冊!
春はまた巡る デイヴィッド・ホックニー 芸術と人生とこれからを語る

著者:デイヴィッド・ホックニー/マーティン・ゲイフォード
翻訳者:藤村奈緒美
発行:青幻舎
発行日:2022年2月25日
サイズ:B5判変型、280ページ
デイヴィッド・ホックニー×マーティン・ゲイフォード ロングセラー『絵画の歴史』コンビによる コロナ禍、ノルマンディーからの最新エッセイ!
中銀カプセルタワービル 最後の記録

編:中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト
発行:草思社
発行日:2022年3月1日
サイズ:A4判変型、204ページ
1972年の竣工から50年のときを経て解体される、日本屈指の名建築の最後の姿を記録する決定版。114カプセル、写真400以上に、実測図面と論考を収録。
和辻哲郎 建築と風土(ちくま新書)

著者:三嶋輝夫
発行:筑摩書房
発行日:2022年3月8日
サイズ:新書判、256ページ
唐招提寺、薬師寺、法隆寺から、世界の名建築を経めぐり、そして桂離宮へ――。知られざる和辻倫理学のもうひとつの思想的源泉!
新・今日の作家展2021 日常の輪郭

対談:田代一倫×百瀬文、百瀬文×清水知子、田代一倫×倉石信乃
編集:大塚真弓(横浜市民ギャラリー学芸員)
デザイン:川村格夫(ten pieces)
撮影:加藤健
発行:横浜市民ギャラリー
サイズ:B5判、34ページ
2021年9月18日(土) ~ 10月10日(日)に行われた「新・今日の作家展2021 日常の輪郭」の展示風景と、関連イベントの文字起こしを収めた記録集。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2022/03/14(月)(artscape編集部)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)