artscapeレビュー
高嶋慈のレビュー/プレビュー
椎原保+谷中佑輔「躱(かわ)す」

会期:2015/10/24~2015/11/07
CAS[大阪府]
粘土の塊を抱えて運ぶ、床に置く、抱きしめるように全身を押し付ける、出来た窪みに置いたトマトにかぶりつく、粘土をちぎって別の形をつくる。不定形の塊が新しくつくられては壊され、床にはトマトの果肉や汁が堆積していく。ギャラリー第1室では、会期中毎日、1時間の休憩以外は開場時間中ずっと、谷中佑輔が黙々とパフォーマンスを行なっている。いや、パフォーマンスを行なうというよりは、ギャラリーを一時的に占有してスタジオ兼寝泊りの場所にしてしまったような様相だ。扇風機のような彫刻やベッドが置かれ、「部屋」を模した空間。ベッドには粘土の塊が横たわり、食べかけのトマトやバナナの皮がはめ込まれ、ベッドの下に置かれた水槽は排泄場所を暗示する。労働、食事、排泄、休息。谷中は、制作の身体的行為そのものを前景化し、「つくること」はまずもって身体的行為すなわち労働であり、睡眠や食事といった生理的な行為と地続きであることを指し示す。
一方、椎原保は、丹平写真倶楽部のメンバーであった写真家の亡き父・椎原治(1905~74)の遺した写真や遺品に向き合い、詩的でセンスのよいインスタレーションとして再構成している。展示空間の真ん中には、木製で蛇腹式の古い写真機が置かれ、撮影用の椅子や照明も据え付けられ、父親の仕事場を擬似的に再現している。一見何もないように見える周囲の壁だが、目を凝らすと、極小のモノクロ写真が点々と、白い壁に溶け込むように配置されていることに気づく。それらの何枚かは、水の入ったガラス瓶やコップ、オブジェを組み合わせ、形態の反復や光の陰影で画面構成したシュルレアリスティックな作品であり、撮影に使用されたとおぼしき小道具やオブジェが展示台にひっそりと並べられている。
生身の身体の現前によって、日々つくり出される行為とその絶えざる更新を、「日常」を包摂した行為の総体として提示する谷中と、遺品の整理や再構成というかたちで父親の仕事に向き合った椎原。自分自身/肉親、生身の身体/故人、現在進行中/遺品の編集という違いはあれ、「アーティストの仕事・労働に向き合うこと」を基軸とした二人展だった。
2015/11/06(金)(高嶋慈)
伊藤高志映像個展

会期:2015/10/29~2015/11/01
LUMEN gallery[京都府]
日本の実験映像を代表する作家の一人、伊藤高志のほぼ全作品を一挙上映する個展。学生時代の8mm映画に始まり、《SPACY》《BOX》など、80年代~90年代半ばに制作された写真のコマ撮り撮影によるアニメーション(Aプログラム)、人物の実写によって不条理な心理的世界を描いた90年代後半~2000年代以降の中編作品(Bプログラム)、合わせて23作品計212分が上映された。
Aプログラムを貫くのは、「写真(静止画)と映画(イメージの運動)」の往還である。ゴダールは「映画は1秒間に24回の真実、あるいは死である」と言ったが、少しずつ距離やアングルを変えて撮影した写真をコマ撮り撮影し、1秒24コマのアニメーションとして再生することで、瞬間的に凝固させられ、「写真」のなかでいったん「死」を与えられたイメージが、擬似的な再生を迎えるのだ。ならば、そうした伊藤の映像作品のなかに、「ゴースト」的なイメージが繰り返し登場することは当然かもしれない。長時間露光(バルブ撮影)を用いることで、鬼火やエクトプラズマのような発光体の軌跡がスクリーン上を自在に駈け廻り、平凡なアパートの室内を異形の蠢く異界へと開いていくのだ。
このように、生と死の境界が曖昧になり、両者が重なり合って存在する幻視の世界は、Bプログラムへと受け継がれる。今回の個展で両プログラムを通覧して感じたのは、写真のコマ撮り/実写、映像の視覚的構造への自己言及/ストーリー性や心理的世界、8mmや16mmフィルム/ヴィデオ/DV/BDといったメディアの違い、などさまざまな相違はありつつも、両プログラムを架橋するそうした共通性である。Bプログラムの中編映像には、背後霊のように変質的なまでにつきまとう尾行者・窃視者がしばしば登場し、ストーリーの進行とともに、見る者と見られる者、自己と他者、死者と生者、現実世界と妄想の境界が不条理に溶解していく。あるいは《静かな一日・完全版》は、自分の「死」を演じた写真を撮り続けることで、自殺願望の成就を(繰り返し、だが擬似的に)味わう少女の物語である。
また、隣接したGalleryMainでは、撮影素材と機材の展示も行なわれた。写真を一枚ずつ台紙に貼り付けた撮影用スチールの実物は、パラパラ漫画のように手でめくって見ることができる。さらに、複数の写真を貼り合わせることで空間のパースが歪んで見えるスチールや、蝶番のように動く撮影用の台なども展示され、魔術的な映像が気の遠くなるような手作業によって生み出されていたことがよくわかった。
2015/10/31(土)(高嶋慈)
小野耕石展「版表現を切り開く者」
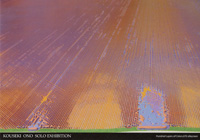
会期:2015/10/17~2015/11/15
ギャラリーあしやシューレ[兵庫県]
一見すると、モアレに覆われたような抽象的な色面が広がっているが、その前を横切ると、見えなかった色彩が次々と現われ、視点の移動とともに刻一刻と表情が変化する。オパールや玉虫色のように、光の反射や屈折によって複雑に千変万化する表面は、きらめく海面や暮れてゆく夕暮れ空、蝶の翅へと変貌していく。小野耕石の《Hundred Layers of Colors》は、その名の通り、100層以上もシルクスクリーンを刷り重ねることでつくられている。近寄って見ると、1cmほどの極小の突起が画面に規則正しく並んでいることがわかる。一つひとつの突起を横から見ると、インクの層を無数に刷り重ねた色の柱になっている。したがって、視点を移動させながら見ることで、真正面からは見えなかったさまざまな色が、角度によって現われては消え、幻惑的に色彩が移り変わる表面を生み出しているのだ。
「版画は、インクの物質的な層の堆積である」ことに自覚的に取り組みつつ、2次元と3次元の往還、視点の移動による表面の複数性に言及する小野の試みが、今後どう発展していくのか期待したい。
2015/10/30(金)(高嶋慈)
松谷武判の流れ MATSUTANI CURRENTS

会期:2015/10/10~2015/12/06
西宮市大谷記念美術館[兵庫県]
具体美術協会のメンバーであった松谷武判の、新作を加えた回顧展。初期の日本画、ボンドをレリーフ状に盛り上げた具体時代の絵画作品、版画、巨大なロール紙に鉛筆の線を描き重ねた黒一色の平面作品、ボンドの膨らみを鉛筆で黒く塗りつぶした作品、新作のインスタレーションに至るまで、約60年の軌跡を辿ることができる。
初期の幾何学的な造形構成の日本画においてすでに、「生命」というタイトルで染色体のような形が描かれていたが、松谷の関心は一貫して、細胞の分裂や増殖、生命の有機的エネルギーの表出にあることが窺える。具体時代のボンド絵画は、盛り上げたボンドの塊にできた裂け目が目や口、細胞分裂の過程、卵からの孵化、胎盤といった有機的なイメージを連想させる。さらに、一枚の紙を鉛筆の線で黒く塗りつぶした作品群を経て、近作では、ボンドの膨らみが鉛筆で黒く塗りつぶされている。そこでは、内部からの強い圧力で膨張し、表面張力ギリギリに膨らんだ緊張感や破裂の凄まじいエネルギーが、黒という色彩によって相乗効果を生んでいる。被膜を突き破って、どろりとした物質があふれ出す。あるいは、さざ波のように波打つ表面の起伏。光の当たる角度によって、光沢感と暗く沈む部分が交替する、豊穣な黒。それは、画家の身体的運動の痕跡でもある。ボンドと黒鉛という、無機的な素材、メタリックな質感、モノクロームの色彩にもかかわらず、硬質なエロスとでも言うべきものを開示していた。
2015/10/30(金)(高嶋慈)
チャンネル6 国谷隆志「Deep Projection」

会期:2015/10/29~2015/11/29
兵庫県立美術館[兵庫県]
正三角形に配置された数十本のネオン管が吊り下げられ、空間を赤い光で瞑想的に満たしている。近寄って見ると、ネオン管は丸い球が連なったようないびつな形をしており、鍾乳石や氷柱(つらら)といった自然の造形物を思わせる。そのなかを、炎のように、脈打つように揺らめく光。ネオン管の持つ都会的で人工的なクールなイメージは、柔らかで有機的なフォルムによって溶解していく。このいびつなフォルムは、熱したガラスに息を吹き込むことで成形されている。丸い球のような連なりは、作家の呼吸という身体的痕跡でもあるのだ。国谷の作品はライトアートの系譜に属するものだが、既製品ではなく、自らの息を吹き込んでつくったガラス管を用いることで、彫刻的要素とともに、生の痕跡をガラスという儚くも美しい素材で提示する装置ともなっている。
2015/10/30(金)(高嶋慈)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)