artscapeレビュー
福住廉のレビュー/プレビュー
六甲ミーツ・アート芸術散歩2014

会期:2014/09/13~2014/11/24
六甲ガーデンテラス他[兵庫県]
六甲山の観光地を舞台にした芸術祭。ケーブルカーや公園、植物園、ホテルなどに展示された作品をバスで周遊しながら鑑賞するという仕掛けだ。参加したのは淺井裕介、宇治野宗輝、太田三郎、加藤泉、金氏徹平、鴻池朋子、西山美なコ、三宅信太郎ら40組あまりのアーティスト。六甲山の観光地が手頃なサイズなので、ほぼ一日あれば、すべての作品を鑑賞して見て回ることができる。
昨今の芸術祭や国際展にとって、アート・ツーリズムは決して無視することのできない手法として、その構造の内側に深く組み込まれている。本展においても、美術作品を鑑賞する行為(アート)と観光地を周遊する行為(ツーリズム)を重ね合わせることで、全体を構成していた。それが、観客を動員する有効な手立てであることに疑いはない。事実、会場のいたるところで美術作品の鑑賞に誘導された観光客を数多く目にすることができた。アート・ツーリズムは「美術」にとっても「観光」にとっても有益というわけだ。
しかし、アート・ツーリズムに問題点がないわけではない。本展には、そのもっとも象徴的な2つの問題点が凝縮していたように思われる。ひとつは、アート・ツーリズムが歓迎する美術作品には、ある種の偏りがあるということだ。観光地という条件は、観光地にふさわしい美術作品を要請する。たとえば六甲山カンツリーハウスは家族で楽しむアウトドア施設だが、ここに展示された作品はおおむね遊具や空間演出装置のような作品で占められていた。その空間の特性に順接する作品が展示される一方、逆接する作品は省かれるという原則は、アート・ツーリズムに限らず公共空間や野外空間での展覧会に共通する一般原則であるとはいえ、本展ではきわめて明瞭にその原則が一貫していた。その目的が観光客の眼を楽しませることにあることは明らかである。
とはいえ、例外的な作品がないわけではなかった。鴻池朋子は六甲山ホテルのロビーの壁面に巨大な絵画を展示したが、その支持体は牛革。生々しい獣の皮を数枚つなぎ合わせた表面の上に、身体の臓器や血管、眼球などを鮮やかな色彩で描いている。元々壁に設置されている鹿の首の剥製を牛の皮が取り囲んでいるから、まるで鹿の肉体の内側がめくれ上がって露出しているかのようだ。肉の温度すら感じられるような絵と、格式高いホテルのロビーという静謐な空間との対比が目覚ましい。
その作品と空間の対比は、おそらくアート・ツーリズムを相対化する重要な契機にもなっている。すなわち、アート・ツーリズムのもうひとつの問題点とは、身体性が決定的に欠落しているという点である。ケーブルカーやロープウェイで一気に山を登り、周回バスで作品を見て回る。そうした鑑賞方法は、美術館におけるそれとほとんど大差ないか、あるいはそれ以上に身体を甘やかしている。せっかく窮屈な美術館の外の野外に出ているのに、身体を解放するのではなく温存させるような身体技法を、アート・ツーリズムは鑑賞者に強いるのだ。つまり鑑賞者は観光客として振る舞わなければならない。これがほんとうに鬱陶しい。
鴻池の作品が喚起しているのは、おそらく肉体の内側に隠されている原始的な感覚ではなかったか。それは、観光客としての身体技法を激しく揺さぶり、そうではない振る舞いに奮い立たせる。だからバスなんか乗ってはいけない。山道を歩いてみるがいい。裏道に一歩足を踏み入れれば、そこには「美術」にも「観光」にも望めない、新たな世界が待ち受けている。
2014/09/21(日)(福住廉)
ヨコハマトリエンナーレ2014「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」

会期:2014/08/01~2014/11/03
横浜美術館、新港ピア(新港ふ頭展示施設)[神奈川県]
昨今の地域型国際展や芸術祭に出品される作品の多くが、その土地の「記憶」を主題としがちなのに対し、本展のアーティスティック・デイレクターである森村泰昌は「忘却」をテーマとして掲げた。その超然とした態度には、そうした国際展や芸術祭がアートツーリズムに全面的に依拠していることへの批評性も、おそらく多分に含まれているのだろう。会場に漂っている静謐な雰囲気は、賑やかしを演出するアートを断固として拒否する明快な意志の表われのように見えたからだ。森村の野心的で潔い心意気は、ひとまず高く評価したい。
焚書について描いたレイ・ブラッドベリのSF小説『華氏四五一度』からテーマを引用しているように、本展は一冊の書物として構成されている。2つの序章と11の章によって、さまざまな入り口から読者=鑑賞者を忘却の海へと誘う仕掛けだ。語らないもの、語ってはならないもの、語りえぬもの。見たくないもの、見てはならないもの、見えにくいもの。とるにたらないもの、役に立たぬもの。そのような記憶されることのない忘却世界が、次から次へと眼前に現われるのだ。
もとより、大げさなスペクタクルとは端から無縁ではある。だが、本展の全体的な印象は、あまりにも禁欲的すぎるがゆえに、読者=来場者を自ら遠ざけてしまっているというものだった。ミニマリズムの傾向が強い作品が数多く出品されていることや、そのわりにはキャプションの解説文が不十分であり、森村自身による音声ガイドを聴いて初めて納得するという、複雑さがその例証である。私たちは、21世紀になってもなお、(あのクソツマラナイ)ミニマリズムを見なければならないのだろうか。不親切な解説文を読んで、現代アートは難解だというクリシェを、不愉快な苛立ちとともに、また上書きしなければならないのだろうか。
忘却の海への冒険は、「冒険」であるからには、もっと高揚感を感じてよいはずだし、驚きや不安、新たな発見に満ち溢れ、身体的な感覚を刺激するようなものであっていい。それらは、忘却というテーマとは無関係に、アートそのものなかに内在している、アートならではの特質だったはずだ。
とはいえ、個別的に見れば、そのような要素を含んだ作品がないわけではない。
たとえば福岡道雄の作品。巨大な平面に「何もすることがない」とか「何もしたくない」という文字が無数に描かれた作品だが、これは正確に言えば「描いた」のではなく「彫った」もの。そのことを知った瞬間、目前に広がる虚無的な文字の羅列が、一気に反転し、「何かをしたい」という表現への欲動が文字の向こうから強烈に押し寄せてくるのである。この鮮やかな経験こそ、アートの醍醐味にほかならない。
そして和田昌宏の作品は、まさしく「見てはならない」「見えにくい」ものを直視させる点で、忘れがたい印象を残す。ガンジーの置物にフィットする杖を自分の子どもとともに探し出す映像作品を見ると、子どもの眼がガンジーの置物をひとりの人格としてみなしていることがよくわかる。だが、私たち自身もまた、幼少時にはそのような視線を持って世界を見ていたはずなのだ。その視線をどこかで捨て去り、世界を客観的な現実として冷静な眼差しでとらえるようになってしまったことの退屈さを思い知るのである。もうひとつの映像作品は、妻の父親、すなわち義理の父に、その世界の真実について尋ねるもの。だが、自分が「あらゆるものが手に入る存在」であり、「まもなく世界を支配している組織の幹部になる」と力強く断言する義理の父の言葉を目の当たりにすると、「見てはならないもの」を見てしまったようなバツの悪さを覚える。とはいえ、これにしても、そもそも現代アートの真骨頂は、そのようにして図らずも出会ってしまったわけのわからぬ作品に伸るか反るかという問題にあるのであり、この和田の怪しげな作品を楽しむか退けるかも、とどのつまり鑑賞者の度量と判断によるのだ。伸る人は、ぜひ会場に用意された聖水を口にしてみるといい。
忘却の海を航海することと禁欲的な作品をマゾヒスティックに鑑賞することは、イコールではない。言い換えれば、忘却世界への入り口はもっと無数に、もっと豊かにあるはずだが、本展の入り口は数が多いわりには、あまりにも偏っていたように思う。たとえ表面的には賑やかしのアートに見えたとしても、その内側に忘却世界への入り口が隠されている例がないわけではなかろう。そこを切り開くのが、キュレーションの妙ではなかったか。さらに付け加えれば、「福岡アジア美術トリエンナーレ」や「札幌国際芸術祭」など、本展とは直接的に関係のない国際展や芸術祭についてのブースがあるなど、展示構成にも疑問が残る。
アートはもっと幅広いものだし、世界にはおもしろいアーティストがもっとたくさんいる。記憶せよ、本展が忘却の海に沈めたこの事実を。
2014/09/05(金)(福住廉)
浜田浄 個展 1982~1985の─鉛筆による大作「DRAWING」─
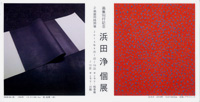
会期:2014/09/01~2014/09/13
ギャラリー川船[東京都]
浜田浄(1937-)が80年代に精力的に取り組んでいた鉛筆画を見せる個展。鉛筆の黒鉛を和紙の上に塗り込めた平面作品が20点弱、展示された。
それらはいずれも無機的で、何かの形象が描写されているわけでもなく、筆跡もまったく認めることができない。ただただ、黒い均質な画面が立ち現われているのだ。その黒い平面に、まず圧倒される。
とはいえ、その黒さは、漆の黒でもなく、墨の黒でもない、やはり鉛筆の黒なのだ。光をわずかに反射しているので硬質的に見えなくもないが、その反面、柔らかな温もりすら感じられることもある複雑な質感がおもしろい。とりわけ床置きにされた作品は、長大な2枚の和紙の両面を鉛筆で塗りつぶしたうえで、1枚の一端を丸めて重ねているため、その硬質と軟質の両極を同時に味わうことができる。
描くのではなく塗る、いや塗り込める。事実、この作品における浜田の手わざは、4Bの鉛筆で短いストロークを無限に反復させる作業をひたすら繰り返すものだった。シンプルではあるが強い身体性を伴う運動から生まれたからこそ、これほどまでに私たちの眼を奪うのだろう。絵画は、やはり身体運動の賜物なのだ。
展示のキャプションをよく見ると、近年の作品も含まれていることがわかる。つまり、浜田は70歳を超えた現在もなお、この過酷な身体運動を要求する作品に挑んでいるのだ。生きることと直結した絵画とは、まさにこのような作品を言うのではないか。
2014/09/01(月)(福住廉)
NIPPONパノラマ大紀行~吉田初三郎のえがいた大正・昭和~
会期:2014/07/26~2014/09/15
名古屋市博物館[愛知県]
吉田初三郎は鳥瞰図の絵師。大正から昭和にかけて全国の都市や景勝地の鳥瞰図を、およそ3,000点以上描き残した。本展は、初三郎についての研究者である小川文太郎のコレクションのなかから200点以上を厳選して展示したもの。会場には鳥瞰図のほか、観光旅行のポスターや時刻表、絵葉書など、関連する資料もあわせて発表された。鳥瞰図の鮮やかな色合いがじつに美しい。
初三郎の鳥瞰図は日本の近代化と併走していた。全国各地に鉄道が敷設され、鉄道による観光旅行が普及すると、各地で路線図と景勝地をあわせて描写した案内図の需要が高まった。初三郎の観光鳥瞰図を見ると、その対象が北は北海道から南は九州まで、文字どおり全国津々浦々に広がっていたことがわかる。初三郎の眼は、はるか上空から近代化していく日本列島を見下ろしていたのだ。
ただ、初三郎の鳥瞰図は近代絵画からは除外されてしまった。「絵画」ではなく「地図」として制度的に振り分けられたのだ。だが、よく見ると初三郎の鳥瞰図は必ずしも科学的な真正性によって描かれているわけではないことに気づく。景勝地の滝を極端に大きくデフォルメしたり、鉄道の路線をあえて一直線に単純化したり、初三郎はつねに彼の創意を工夫しながら絵に導入していたのだ。そもそも鳥瞰図という表現形式のなかにすら、必ずしも鳥の眼で見た光景を正しく反映しているわけではないという点で、想像的な次元が含まれていると言わねばなるまい。
吉田初三郎による観光鳥瞰図は単なる「地図」ではない。それらは、初三郎という類まれな絵師による、確かな表現なのだ。近代絵画が見失った、ありえたかもしれない、もうひとつの「絵画」が潜在しているのである。
2014/08/30(土)(福住廉)
デス・プルーフ in グラインドハウス
会期:2014/08/23~2014/08/31
新橋文化劇場[東京都]
名画座がまたひとつ消えた。JRの高架下に軒を連ねる新橋文化劇場・ロマン劇場が2014年8月31日をもって閉館した。終戦後の1950年代の開館以来、客席わずか81の小さな空間で上映される35ミリのフィルム映画を求めて、多くの来場者が訪れてきた。入れ替え制を採用するシネコンを尻目に、入場料900円で一日中過ごすことができるのも、人気のひとつだった。
最終週を飾ったのは、マーティン・スコセッシの『タクシードライバー』(1976)と、クエンティン・タランティーノの『デス・プルーフ in グラインドハウス』(2007)。いずれも、この映画館を自己言及的に暗示した、みごとなセレクションである。なぜなら、前者において不眠症に悩まされる主人公が夜な夜な通い詰めるのがポルノ映画館だからであり、後者の「グラインドハウス」とはB級映画館を意味しているからだ。それゆえ、来場者は映画の内と外をリンクさせながら、映画館で映画を鑑賞することの醍醐味を存分に味わうことができた。
とりわけ、すばらしかったのが『デス・プルーフ in グラインドハウス』。耐死仕様の車を使って次々と惨劇を繰り返すスタントマンの男と、その刃に襲われる女たちの物語だ。小気味よい音楽と冗長な会話劇という二面性は、これまでのタランティーノ映画と変わらない。けれども、映画の終盤からはじまる女たちの復讐劇は、フェミニズム映画とさえ言いたくなるほど、突出して痛快である。両手を突き上げて勝利を喜ぶラストシーンには、誰もが「どんなもんじゃい!」という熱い想いを重ねたにちがいない。
暗闇の中で見ず知らずの赤の他人と同じ映画を見るという経験。そして、たとえ一瞬だとしても、同じ気持を共有するという経験が、映画館で映画を見る最大の楽しみである。劇場がなくなった後も、この快楽は憶えておきたい。
2014/08/29(金)(福住廉)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)