artscapeレビュー
福住廉のレビュー/プレビュー
風間サチコ プチブル
会期:2014/01/09~2014/01/19
無人島プロダクション[東京都]
2002年にナンシー関が亡くなったとき、埋めがたいほどの喪失感を覚えた人は少なくなかった。彼女の批評的視線は視聴者のそれを鍛えあげる格好のモデルだったし、テレビのクリエイターにとっても鋭利な批評家の不在は良質の番組を制作するうえで大きな損失だったからだ。事実、テレビが退屈になり始めたのは、ナンシー関がテレビを見なくなった頃からだったと言ってよい。
本展は、版画家・風間サチコの初期作を一覧したもの。社会的政治的な主題をユーモアとアイロニーを込めながら巧みに構成する作風で知られているが、今回の展観でそれが初期から一貫していることがわかった。むろん、初期の作品はおおむね主題を二重三重に重層化していたので、現在の作品に見られる明快性は見受けられないという違いはある。けれども、風間が作品を制作するうえでの構えに、同時代的な批評性をつねに帯同していたことは一目瞭然であった。
なかでも注目したのは、新作の消しゴム版画である。「プチブル」「家畜」「レイシスト」「愚民」「下民」といった近年の社会を物語る言葉を消しゴムに彫り、それらで刷った風間の名刺が版とともに展示された。つまり以上のような言葉を自らの肩書きとして見せていたわけだ。風間の批評性には、言ってみれば自分の身体を貫通させながら、その切っ先で相手を一撃するような凄みがあるのだ。
ナンシー関は亡くなった。でも大丈夫。風間サチコがいるんだから。信じるに足る視線を持ったアーティストが同時代に生きていることの意味は、とてつもなく大きい。
2014/01/19(日)(福住廉)
ひろせなおき個展 東京ネットカフェ犯行記

会期:2014/01/17~2014/01/21
ナオナカムラ(素人の乱12号店)[東京都]
文化人類学でいう「フィールドワーク」とは、ここではないどこか遠い現場を調査する方法論を指すが、それに対していまここの現場をリサーチすることは「ホームワーク」と言われる。かつてハル・フォスターは80年代後半の欧米の美術界に生まれたパラダイム・チェンジを「民族誌的なアーティスト」の出現として解説したが、いま現在、日本の都市の只中で暮らしながら同時にそれを主題とする「ホームワーク・アーティスト」が出現しつつある。
ひろせなおきは、日常的に都内のネットカフェで生活しているアーティスト。初個展となる今回、会場にネットカフェの個室を再現しつつ、そこでひろせと同じようにネットカフェで暮らしている若者たちを取材した映像を発表した。それらを視聴すると、彼らの生態は決して「ネットカフェ難民」というネガティヴな言葉に収まらない拡がりをもっていることが伝わってくる。大学や会社に近いから、憧れの渋谷に住みたかったから、自宅より落ち着くからといった理由で、彼らは積極的に、いやむしろこう言ってよければ功利的に、ネットカフェを住処としているのだ。そこに見えない貧困が隠されている可能性は否定できないにせよ、これは来場者の多くにとって新たな知見だったのではなかろうか。
「ネットカフェ」という表象を正しく転覆すること。2007年に「ネットカフェ難民」という言葉を初めて使った日本テレビの早朝番組に、「難民じゃねぇし」と書いた垂れ幕をひろせ自身が掲げて勝手に出演したゲリラ・パフォーマンスも、かけ離れてしまったイメージを再びリアルなものとして取り返そうとしたに違いない。ひろせの「ホームワーク」は、自分のホームが偏って表象されることへの異議申立てでもあった。
むろん、ひろせにとってはホームワークだとしても、その展覧会を見る大半の鑑賞者にとってはある種のフィールドワークとして受容するほかないという根本的な矛盾は否定しえない。つまり誰もが「ネットカフェ」という現場を内部としてとらえるとは限らない。だが、興味深いのは、ひろせ自身が東京という街そのものをひとつの「家」として考えていることだ。とすれば、自宅と「ネットカフェ」は同じ家の中の別々の部屋に相当することになり、相互を往来するハードルは思っているほど高くはなくなる。かつて寺山修司は「街がひとつの図書館だ」と私たちを煽動したが、ひろせは寺山と同じような詩的想像力に近づきつつあるのではないか。それは現在のところ必ずしも十分に作品として結実しているわけではないにせよ、今後の展開と発展を大いに期待させるのである。
2014/01/18(土)(福住廉)
岩熊力也 weight
会期:2014/01/06~2014/01/18
コバヤシ画廊[東京都]
東日本大震災がアーティストに及ぼした影響は計り知れないほど大きい。にもかかわらず、それを作品に反映するアーティストが依然として少ないのは、おそらく美術が、他の表現文化に比べると、相対的に遅いメディアだからだろう。写真や映像、マンガ、あるいはデモであれば、直接的かつ瞬発的に表現することも可能である。だが、絵画や彫刻が思索と制作にそれなりの時間を要することはもちろん、アートプロジェクトですら、長期的な展望と持続的な過程を、その形式の内側に抱え込んでいる。同時代の事象に目を瞑る輩は論外だとしても、美術の同時代性が作品として現象するには、ある種の「タイムラグ」を避けることができないのである。
そうしたなか岩熊力也の新作展は、その同時代性を絵画として結晶させた、きわめて稀少な展観だった。展示されたのは、布に描いた絵画をもとにしたアニメーション映像と、その絵を水で洗い流した布など。いずれも「水」をキーワードにしながら3.11以後の絵画の可能性を自問自答した作品に見えた。
ウィリアム・ケントリッジのように描写と消去を繰り返しながら制作したアニメーション映像には、蛇口やバスタブから溢れ出る水、その水で浸かる街並み、そして水の底に引き込まれる男などが寓話的に描かれている。映像のなかに描写される赤いワンピースの女があまりにも陳腐に過ぎる感は否めないが、そうだとしてもここに立ち現われた詩情性が私たちの胸を打つことに変わりはない。
その詩情性は、しかし、必ずしも津波という主題が私たちの心情と共振したことに由来しているわけではない。それは、むしろ描写と消去を繰り返す岩熊の手作業に、まことに同時代的な絵画のありようを希求してやまない私たちの欲望が重なったということなのかもしれない。描いては消し、描いては消しを反復する作業は、アニメーション作品として成立させるために不可欠な工程というより、同時代の絵画をまさぐる身ぶりの現われだったのではなかろうか。
水で絵の具が洗い流された布には、辛うじて色彩の痕跡が認められるが、ほとんど染みと滲みといった程度で、もはや何が描写されていたのか確認することはできない。すなわち絵画ではなく、たんなる物体に近い。物体に残されているのは、だから文字どおり「白紙還元」を試みつつも、最後まで洗い落とすことのできなかった、絵画という原罪とも言えよう。だが、ちょうど産卵のために清流を遡行する鮭のように、それらを川の水のなかで漂わせた映像を見ると、岩熊の視線は絵画を物体に還元しながらも、同時にそれを再生することにまで及んでいるように思えてならない。そこに、岩熊は3.11以後の絵画の可能性を賭けているのではないか。
2014/01/16(木)(福住廉)
家庭遺産
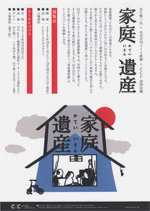
会期:2013/12/07~2013/12/28
静岡市クリエーター支援センター(CCC)2Fギャラリー[静岡県]
「家庭遺産」とは、どんな家庭にもある、家族の思い出が詰まった宝物のこと。捨てるに捨てられないまま、いつのまにか歴史的遺物のように保存してしまっているものと言えば、誰もが思い当たる節があるはずだ。そんな家庭遺産の数々を、漫画家の天久聖一の呼びかけによって全国から集め、一挙に展示したのが本展である。
限界ぎりぎりまで削り取られた鉛筆のコレクションや、ロゴを母が縫い合わせたナイキの(ような)手袋、オードリー・ヘップバーンの直筆サイン、ボーイ・ジョージの描き方などなど。一見するとどこにどんな価値があるのかわかりにくいが、作品と併せて掲示された応募者による解説文を読むと、一つひとつの作品にはそれぞれエピソードが随伴していることがわかる。
《サザエさんの新聞切り抜き》は、文字どおり切り抜いたサザエさんの4コマ漫画をホッチキスでまとめたもの。これらは、40年以上前に社宅の子どもたちのなかでボス的存在だった応募者の姉が、ある日突然朝のラジオ体操を始め、ラジオ体操が終わると子どもたちに配っていたものだという。ある種の「褒美」として与えられていたのか、それとも「貨幣」のように流通していたのか。家庭遺産の背後からそれぞれの物語が立ち上がってくるのだ。
なかでも傑出していたのが、《父の足跡》である。展示されたのは、ピカピカの床についた足跡を写しただけの、いかにも凡庸な写真。だが、これは4年前に亡くなった応募者の父親が生前にかけたワックスの上に残した足跡だという。決して見えるわけではないせにせよ、掃除に熱を入れる父親の姿が目に浮かぶ。応募者である娘の無精のおかげで、これが奇蹟的に現存しているという対比も面白い。
たしかに家庭遺産はおおむね個人的であり、普遍的な価値が認められにくいものも多い。けれども、それらが私たちの想像力を刺激しながら、それぞれの「家庭」というフレームを超えて私たちのもとに届いていることは事実である。個人的な表現に普遍的な価値を与えてきた近代芸術が隘路に陥ったとすれば、家庭遺産はその白紙還元から新たな芸術を探り出す画期的な試みとして評価できると思う。その萌芽は、美術館や画廊にではなく、あまつさえアーティストの手のなかにですらなく、私たち自身のそれぞれの家庭のなかに眠っているのかもしれない。
2013/12/27(金)(福住廉)
アイチのチカラ!

会期:2013/11/29~2014/02/02
愛知県美術館[愛知県]
戦後の愛知県おける美術史を振り返った展覧会。同館のコレクションから130点あまりが展示された。戸谷成雄や奈良美智、杉戸洋、安藤正子といった愛知県にゆかりのある美術家の作品をはじめ、片岡球子や中村正義の破天荒な日本画、舞妓を丹念に描いた鬼頭鍋三郎の油彩画など、見るべき作品は多い。
都市の美術史を編纂する重要な契機となるのは、公募団体と美術大学、そして美術館である。こうした諸制度は、美術家や鑑賞者、学生が集まる美術の現場になりうるからだ。事実、本展も1946年の中部日本美術協会の結成にはじまり、1955年の愛知県文化会館美術館の開館、そして1966年の愛知県立芸術大学開学などを歴史の動因としていた。
だが、本展には決して見過ごすことのできない重大な欠陥が2つあった。それは、展示された作品が「絵画」に偏重していることと、歴史を構築する美術館としての態度である。
本展のラインナップは、油彩画や日本画を含む絵画が大半で、立体や彫刻はきわめて少ない。ましてやパフォーマンスや映像は皆無だった。けれども、愛知には同地で結成され、その後全国的に活動を展開したゼロ次元をはじめ、1970年の「ゴミ裁判」や1973年の名古屋市長選挙に立候補した岩田信一など、重要な美術家がたくさんいる。言うまでもなく、赤瀬川原平や荒川修作といったネオ・ダダのメンバーも愛知とは関わりが深い。そうした側面をすべて欠落させたまま、あくまでも絵画を中心に提唱された愛知の美術史が著しく偏向していることは指摘しておかなければなるまい。
むろん、こうした偏りは美術館の収集方針に由来している。だが、本展で明らかにされていたそれを確認してみると、「絵画」を重視する明確な収集方針が打ち出されているわけでもないことに驚かされた。同館は、「愛知県としての位置をふまえた特色あるコレクションを形成する作品」を収集するというのだ。このひどくまわりくどい日本語がわかりにくいのは、コレクションを形成する主体が誰なのか明示されていないからだ。だが、これは明らかなトートロジーである。事実として美術館が収集した美術作品が美術史の主流を形成するのだから、このようにコレクションの主体を曖昧にするような言い方は、無責任というより不誠実と言わざるをえない。
今日、美術史が排除と選択の結果であることは誰もが知っている。だが、であればこそ、美術館に求められるのは美術の歴史を構築する明確な意志とフィロソフィー、すなわち「愛智」ではないのか。
2013/12/20(金)(福住廉)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)