artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
森栄喜『intimacy』
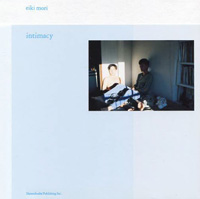
発行所:ナナロク社
発行日:2013年12月14日
だいぶ予定からは遅れたのだが、森栄喜の新作写真集『intimacy』がようやく刊行された。2013年1月~2月のZEN PHOTO GALLERYでの展示でも感じたのだが、日本ではこれまでゲイのカップルの日常を、ことさらにドラマティックな葛藤に逃げ込むことなく、こんなふうに淡々と描き切ったシリーズは、あるようでなかったのではないだろうか。
あるよく晴れた夏の日から、季節を経て、次の年の夏の日まで、森自身とパートナーの男性の日常が日記のように綴られていく。だがそれらの日々が、東日本大震災の直後からの一年であることに注目すべきだろう。多くのカップルが経験したことだと思うが、その時期には重苦しい不安に包み込まれることで、二人の関係にある種の切羽詰まった感情が影を落としていったことが想像できる。その翳りは写真には明確に表われてはいない。ただ、パートナーの髪の毛や皮膚や筋肉の微細な動き、表情の変化を細やかに追う森の眼差しに、緊張と弛緩とが交互にやってきたあの日々の、危うい気分が確実に投影されているように感じる。
おそらく森にとって次の課題となるのは、この親密なイメージの連鎖を、二人の関係の内側だけに留めることなく、よりのびやかに社会や現実に開いていくことだろう。日本社会に色濃くある、ゲイ・カルチャーへ向けられた差別や異化の視線は、むろんまだ完全に解消されたわけではない。「intimacy」のなかに潜むポリティックスを、より正確に抉り出していくことで、彼の写真の世界はさらなる広がりと深みを持つのではないだろうか。
2013/12/20(金)(飯沢耕太郎)
森山大道「モノクローム」

会期:2013/11/23~2014/12/27
武蔵野市立吉祥寺美術館[東京都]
森山大道はこのところずっと、デジタルカメラで街をスナップした写真を新作として発表し続けている。だが、カラー写真の「ペラペラとした」色味を追い求めていると、時折フラストレーションに襲われるようだ。個人的な作業を写真集として継続的に発表している『記録』(AKIO NAGASAWA PUBLISHING)でも、no.23はロンドンのカラー・スナップだったが、南仏やパリを撮影したno.24ではざらついた粒子を強調したモノクローム写真に回帰していた。2008~12年の作品を集成して月曜社から刊行した写真集も、一冊は『カラー』、もう一冊は『モノクローム』というタイトルである。つまり森山のなかには、カラーとモノクロームの両方に引き裂かれていく心性が共存しているのではないだろうか。
今回、武蔵野市吉祥寺美術館で開催された「モノクローム」展は、その写真集『モノクローム』からピックアップされた写真群と、「狩人」「光と影」「サン・ルゥへの旅」など1960~90年代の旧作を混在させた展示だった。それら59点のモノクローム作品を見ると、白と黒のコントラストに還元されたイメージに対する、森山の強いこだわりがはっきりと見えてくる。
では森山にとって、「モノクローム」とは何なのだろうか。それはカラー写真の表層的で、具体的な現実世界の見え方に対する、強烈な異議申し立てではないかと思える。むろんモノクロームでもカラーでも、目の前の現実に潜む微かなズレを鋭敏に感受する能力と、画面構成における正確無比なグラフィック的な処理能力に違いはない。だが、カラーよりはモノクロームの方が、被写体をより「エタイの知れない異界の破片」として再構築しやすいのではないだろうか。思えば、彼は写真家としてスタートした頃から、撮影を通じて、現実のなかに埋め込まれた異界、彼の言う「もう一つの国」を探求し続けてきた。その営みにおいて、やはりモノクローム写真が最強かつ不可欠の武器であることが、今回の展覧会でも明確に証明されていたと思う。
2013/12/19(木)(飯沢耕太郎)
「日本工房」が見た日本──1930年代

会期:2013/12/03~2013/12/25
JCIIフォトサロン[東京都]
1933年に日本工房を設立し、海外向け日本文化広報誌『NIPPON』を編集・出版して、日本の近代写真・デザインの展開に一時代を画した名取洋之助については、JCIIライブラリーの白山眞理の調査によって、新たな資料が明らかになりつつある。今回の展覧会では名取家からJCII(日本カメラ財団)に寄託された初期の日本工房のネガを再調査し、名取、土門拳、藤本四八らスタッフカメラマンが撮影した写真80点あまりを展示していた。
『NIPPON』をはじめとして、『写真週報』『Berliner Illustrierte Zeitung』など、日本工房の写真が掲載された雑誌のバックナンバーを丹念に当たることで、写真家の名前が特定できたものもある。だが、展示された作品の大部分は誰が何のために撮影した写真かよくわからないものだ。だが、逆にそれらの写真には1930年代の日本の空気感が生々しく写り込んでいるように感じてしまう。銀座の店のモダンなショーウィンドー、1940年の幻の東京オリンピックに向けてトレーニングに励む選手たちなどの、明るく輝かしい写真と隣り合って、日独伊防共協定記念国民大会、支那事変一周年記念大講演会など、戦時色の強いイベントの写真が並ぶ。胸を突かれるのは、芝浦製作所(現・東芝)の社員と思われる小平芳男という男性の「出征の日」の写真だ。いかにも東京・山の手のお坊ちゃんという風情の彼と、その家族が並んで写っている。彼らの満面の笑みが逆に痛々しい。
オリンピック、特定秘密保護法など、現在の日本の社会状況と無理して重ね合わせる必要はないかもしれないが、写真を見ていると、どうしてもいくつかの接点が浮かび上がってくる。特定の写真家の作品ではなく、日本工房という組織による、いわば集団制作の写真群だからこそ、よりくっきりと「あの時代」の手触りが見えてくるのではないだろうか。なお、日本橋高島屋8階催会場では、『NIPPON』や『週刊サンニュース』の実物展示を含む「名取洋之助展」(2013年12月18日~29日)が開催された。それに併せて、白山眞理編著の『名取洋之助 報道写真とグラフィック・デザインの開拓者』(平凡社[コロナ・ブックス])も刊行されている。
2013/12/14(土)(飯沢耕太郎)
日本の新進作家 vol.12 路上から世界を変えていく

会期:2013/12/07~2014/01/26
東京都写真美術館 2F展示室[東京都]
12回目を迎えた「新進作家展」。日本の若手~中堅の写真家たちにとって、この選抜展の存在は大きな意味を持ちつつある。実際に「I and I」で第38回木村伊兵衛写真賞を受賞した前回の出品者の菊池智子のように、この展覧会をひとつのきっかけとして次のステップに進む者も出てきているのは、とてもいいことだと思う。
今回は「世界と向き合う行為を象徴する『路上』という場所」に焦点を合わせることで、大森克巳、糸崎公朗、鍛冶谷直紀、林ナツミ、津田隆志の5人の作品を紹介している。大森は、ピンク色のアメリカン・クラッカー越しに震災後の東京や福島の桜を撮影して「すべては初めて起こる」をまとめた。糸崎は「組み立てフォトモ」や「ツギラマ」といった特異な手法を駆使して街の光景を再構築する。歓楽街の看板、ポスター、チラシなどに徹底してこだわる鍛冶谷、浮遊セルフポートレートで風景の意味を軽やかに変換していく林、「あなたがテントを張れそうだと思う場所」に実際に宿泊してその場所を記録した津田の仕事も、それぞれの切り口で2010年代の「路上」のあり方を開示していた。
だが全体的に見て、今回は展覧会としてはあまり成功していなかったのではないだろうか。5人の写真家の方向性がバラバラなのは仕方がないが、それらが絡み合うことで、何か新たな「路上」へのアプローチが育っていくようには見えなかったのだ。会場のプラニングも、各作家の特性がうまく活かされているようには見えなかった。津田のパートは、もっとゆったりとしたスペースで見せてほしかったし、糸崎の展示は盛りだくさんすぎた。この種の展示では、バランスをとりながら、はみ出していく部分も大事にするという、難しい舵取りが必要になってくるということだろう。
2013/12/12(木)(飯沢耕太郎)
植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ 写真で遊ぶ

会期:2013/11/23~2014/01/26
東京都写真美術館 3F展示室[東京都]
植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグといえば、世代的には1894年生まれのラルティーグの方が20歳ほど上だが、どこか似通ったところがありそうに感じる。何よりも、彼らの写真を見る時に伝わってくる手放しの幸福感、被写体に対する肯定的な眼差しが共通性しているのではないだろうか。とはいえ今回のように、それぞれ85点の作品を「1実験精神」「2インティメイト:親しい人たち」「3インスタント:瞬間」「自然と空間」の4部構成で、互いに比較するように並べた展示を見ると、共通性だけではなくその違いもまた目についてくる。
植田はずっと自分は「地方の一アマチュア写真家」であると言い続けてきた。単なる謙遜というだけではなく、そこには自由に、好きなように写真を撮って発表することができるという、アマチュアならではの特権を、誇り高く主張するという側面があったのではないのだろうか。植田にとって最大の目標は、言うまでもなく「写真する」ことであった。その生涯を、ありとあらゆるテクニックと持ち前の実験精神を総動員して、優れた写真を残すことに捧げたと言ってもよい。
一方、フランスのブルジョワ家庭で何ひとつ不自由なく育ったラルティーグにとって、写真は人生を心ゆくまで愉しみ、享受するためのスパイス以上のものではなかったのではないか。彼の写真には、むしろ「余技」であることの純粋な歓びが表われ出ている。見る者を感動させるような一瞬が、見事な構図で切り取られていたとしても、それはあくまでも結果であり、彼がそれを求めていたわけではなかっただろう。
だが、この二人の写真がブレンドされた相乗効果により、それぞれの仕事がそれまでとは違った角度から見えてくることも確かだ。二人ともごく身近な出来事や人物を被写体にしていても、それらがまるで魔法をかけられたような輝きを発していることを確認することができた。
2013/12/12(木)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)