artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
堀田真悠『新月』
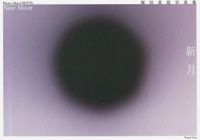
発行所:東京ビジュアルアーツ/名古屋ビジュアルアーツ/ビジュアルアーツ専門学校・大阪/九州ビジュアルアーツ
発行日:2013年11月20日
2013年度の第11回ビジュアルアーツアワードを「新月」で受賞した堀田真悠は1992年、京都生まれの20歳(受賞当時)。同賞の最年少受賞者ということになる。だが、その作品世界の完成度の高さは恐るべきもので、写真を取りまく現在のハード及びソフトの環境を的確に使いこなせば、高度な表現力を年齢にはまったく関係なく発揮できることがよくわかる。
「新月」というタイトルが示すように、彼女が引き寄せられていくのは「見えない闇」の世界である。そこには普通の視力では「見えない」けれども、確実に何かがうごめいていて、時には魅惑的な、時には禍々しく不吉な世界を垣間見させる。堀田はそれらを的確にカメラで捕獲していくのだが、プリントして作品化する時にさらに操作を加えることが多い。彼女をビジュアルアーツ専門学校・大阪で指導した百々俊二によれば、「マットブラックインクを光沢紙で使用することで暗部のテクスチャーは浮きあがり反転したミスマッチで出来たプリント」なのだと言う。撮影・プリントの機材のデジタル化によって、これまでとは違った多様な表現の可能性が生じてきているわけで、堀田のような世代は、それらをごくナチュラルなプロセスとして身につけることができるのではないだろうか。
もうひとつ興味深いのは、彼女の作品全体に貫かれている、琳派を思わせる華麗で装飾的な画面構成である。この奇妙にクラシックな美学は、やはり彼女が「京都と奈良の県境の田園地帯に育った」という風土性に由来するのだろうか。
2013/12/04(水)(飯沢耕太郎)
茂木綾子『travelling tree』

発行所:赤々舎
発行日:2013年10月1日
茂木綾子は東京藝術大学美術学部デザイン科を中退後、1997年に渡独し、映画作家、アーティストのヴェルナー・ペンツェルというパートナーと、二人の子どもを得た。スイスのラ・コルビエールでアーティスト・イン・レジデンスなどの活動をした後、2009年に帰国し、淡路島の廃校になった小学校に住みついて「ノマド村」の活動を展開している。本作はその茂木がヨーロッパ滞在中に撮影した写真をまとめた写真集である。
写っているのは、夫との日々の暮らしの断片、二人の子どもの成長の記録、旅と移動の合間に出会った風景など、文字通りの「個人的な写真」である。にもかかわらず、写真集のページを繰っていると、そこにはまぎれもなく優れた写真家の眼差しが介在していると思えてくる。茂木は「あとがき」にあたる文章で、「なぜ私はこのような写真を撮り続けてきたのか」と自問自答し、その答えとしてそれが「不可解さ」に促されて成立していたのではないかと思い至る。「不可解さ」というのは「自分と自分が含まれるこの世界を満たす有形無形の数限りない出来事のなかで、ふと気になる象徴的で謎めいた物事」のことだと言う。
確かに彼女の写真には、そんな「象徴的で謎めいた出来事」が写り込んでいるものが多い。写真集の表紙にも使われている、窓際の壁にピン止めされた「燃える靴下」の写真もその1枚である。だがそれらのなかには、わかりやすいドラマチックな出来事ではなく、ごく些細な身じろぎ。微かな気配としてしか感じられないものもある。むしろそちらの方が圧倒的に多いだろう。茂木が世界に向けて差し出すアンテナの精度は、12年にわたるヨーロッパでの生活のなかで、少しずつ、だが着実に上がっていったのではないだろうか。その成果が、「不可解さ」の写真の連鎖として目に飛び込んでくるのだ。
2013/12/02(月)(飯沢耕太郎)
上本ひとし「海域」

会期:2013/11/20~2013/12/03
銀座ニコンサロン[東京都]
上本ひとしは1953年、山口県下松生まれの写真家。靴の販売店を営みながら、1970年代から写真撮影を続けてきたが、2001年にニッコールフォトコンテストでニッコール大賞、長岡賞を受賞したのをひとつのきっかけとして、本格的に写真作家としての活動を開始した。以後、写真集『峠越え』(2005年、翌年さがみはら写真新人奨励賞を受賞)、『OIL 2006』(2007)を刊行するなど、旺盛な創作意欲で力作を発表し続けている。
今回発表された「海域」は山口県徳山湾の沖合にある大津島の周辺を撮影したシリーズである。大津島、及びその近くの光、平生には、太平洋戦争末期に「人間魚雷」回天の基地があり、若い兵士たちが訓練にいそしんでいた。回天は操作が難しく、訓練中に死亡する兵士も多かったという。上本はそのような史実を踏まえながらも、あくまでも現在の瀬戸内海の「海域」の眺めを、しっかりと写しとろうと努めた。その結果として、回天の乗組員たちも日々目にしていたであろう「海の色、島影」は、静かな緊張感をたたえた「風景写真」として、きちんと成立していると思う。薄暮の時間に撮影された写真が多いこともあって、会場全体に、遥か彼方へと連れ去られてしまうような寄る辺のなさ、茫漠とした雰囲気が漂っていた。写真を見ながら、「海くれて鴨の声ほのかに白し」という芭蕉の句を思い起こしていた。
なお、本展は2013年12月19日~28日に大阪ニコンサロンに巡回する。また、展覧会にあわせて蒼穹舍から同名の写真集も刊行されている。
2013/11/27(水)(飯沢耕太郎)
鷹野隆大「香港・深圳 1988」

会期:2013/11/21~2013/12/21
ツァイト・フォト・サロン[東京都]
小説や詩でも「若書き」の作品というのは独特の存在感を発しているものだ。その作者の後年の作品世界の芽生えが見られることが多いが、逆にまったく異質な手触りを備えている場合もある。鷹野隆大が今回発表した「香港・深圳 1988」も、やはり「若書き」としての面白さが感じられる作品だった。
鷹野は撮影時には25歳。「もはや若いとは言えないものの、当たり前に写真を撮ることを信じていた無邪気な若造」だったという。香港ではまず取り壊しが迫っていた“魔窟”九龍城塞を目指した。首尾よく、かつてその一角に住んでいたという日本語ができる女性と知り合いになり、彼女の案内で“魔窟”の内部も撮影することができた。さらに、当時経済特区として急速に発展していた中国本土の深圳に出向き、市内の縫製工場、アパートなどを撮影した。
今回はそのなかから45点のプリントが展示されている。それらを見ると、鷹野の眼差しがフォト・ジャーナリスト的な物欲しげなものではなく、かといって単なる観光客とも違って、ニュートラルな透明性を保っているのが印象に残った。ことさらな感情移入はないのだが、それでも九龍城塞や深圳の住人たちに寄り添って、彼らの生活の襞々を丁寧に押し広げるようにして撮影しているのだ。このような撮影の経験が、後に彼の代名詞となる男性ヌードを撮影する場面などでも、細やかな気配りとして活かされていったのではないだろうか。彼が、なぜ今頃になってこれらの写真を発表する気になったのかはわからないが、時を経ることで、写真そのものが味わい深く醗酵してきているようにも思える。
2013/11/27(水)(飯沢耕太郎)
ユートピアを求めて ポスターに見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズム

会期:2013/10/26~2013/01/26
神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]
ファッション・ブランド、BA-TSUのデザイナーの松本瑠樹が蒐集した、1917年のロシア革命から、ソヴィエト連邦が形をとる1930年代に至るポスターよる展覧会である。全体は「I.帝政ロシアの黄昏から十月革命まで」「II.ネップ(新経済政策)とロシア・アヴァンギャルドの映画ポスター」「III.第一次五カ年計画と政治ポスター」の3部に分かれ、約180点の大判ポスターが展示されている。
ワシーリー・カンディンスキー、カジミール・マレーヴィチ、ウラジーミル・マヤコフスキー、アレクサンドル・ロトチェンコなど、綺羅星のように並ぶロシア・アヴァンギャルドの巨人たちの作品は見応えがあるが、なんといっても圧巻なのは「II.ネップ(新経済政策)とロシア・アヴァンギャルドの映画ポスター」のパートに展示されたウラジーミルとゲオールギーのステンベルク兄弟の映画ポスター群だろう。この時期、ソヴィエト政府は大衆宣伝・娯楽としての映画上映に力を入れ、国内で製作された映画だけでなくアメリカ、ヨーロッパの映画も積極的に公開していた。ステンベルク兄弟は、ロシアの民衆芸術に起源を持つ、原色を駆使した独特の色彩感覚と、モンタージュや構成主義的な画面構成のようなアヴァンギャルドの手法を融合させ、生命力あふれる力強い映画ポスターを次々に発表していった。さらに1930年代以降のグスタフ・クルーツィスらの政治ポスターになると、写真を使用する比重がより大きくなり、フォト・モンタージュの可能性が極限近くまで追求されることになる。美と政治との軋轢のなかから花開いていったソヴィエト連邦のグラフィック・デザインと写真を、もう一度新鮮な眼で見直すいい機会となる展示だった。
2013/11/23(土)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)