artscapeレビュー
SYNKのレビュー/プレビュー
勝正光が作品を携えて、別府から神戸に船でやって来た。──神戸での制作と展示とまち歩き
会期:2012/05/10~2012/05/15
GALLERY 301[兵庫県]
鉛筆によるドローイングを手がける勝正光の個展。1981年生まれの勝は大学卒業後、東京で活動していたが、2009年に別府で開催された「わくわく混浴アパートメント」への参加を機に同地に移り住んだ。今回の神戸での個展は、別府で勝に出会った神戸大学大学院国際文化学研究科の学生が企画したもの。出品作からはアートで結ばれた心と心の交流が伝わってきた。
それをもっとも象徴するのは、天井から無造作につり下げられた単語帳だろう。めくってみるとカードの一枚一枚に街角のスケッチ。さらには、側の机の上にも多数の単語帳──これは、展覧会に先立って行なわれた神戸の「まち歩き」の成果だ。勝と参加者たちは、2日間にわたり単語帳と6Bの鉛筆を手に長田や元町の路地を歩いてスケッチした。ぶら下がっているのは勝の単語帳、机の上にあるのは参加者たちの単語帳だ。描きなれない絵を描くことに最初は躊躇した参加者も、まち歩きが進むにつれ、スケッチに熱中し始めたという。勝は自らの制作スタイルを「自分の体を通して向き合えた姿勢そのものを鉛筆と紙で落とし込む」と述べるが、机の上の単語帳はまさに、言語ではなく黒鉛の線で街のイメージを表わす行為が、戸惑いから喜びへと変わる瞬間をとらえている。
実際、鉛筆と紙は、勝の身体そのものというべきかもしれない。本展には旧作も展示されたが、四角い紙の表面を筆触の跡形もなく鉛筆で丹念に塗りつぶした初期の作品は、紙という支持体によって、やっとのこと黒鉛がその薄氷のような身体を持ちこたえるかのようだ。鈍色の平面はやがて、スカーフの柄の輪郭線などを内部に刻み込むことになるが、これもまた、黒鉛でできたレースを想わせる。
対照的なのは、写真をもとに人物を描いた近作であるが、これは、別府で出会った人々に思い出の写真を見せられたことがきっかけで始められたという。「写真を描くことでその人の思いに寄り添えることに気づいた」と勝は語る。ここでも、写真のイメージをかたどる鉛筆の線は、たんなる輪郭線ではなく、黒鉛という彼の身体の断片であるかにみえる。おそらくは、黒鉛が織りなす物質性こそが、彼の感情そのものなのだ。この特質は、やはり既存のイメージを描いたドローイングではあるが、実物を見ずに、勝が幼い頃、神戸を訪れた記憶を頼りに描かれた甲子園球場などの新作ドローイングに一層あらわである。それゆえ、「尖った鉛筆を紙に押し当てること」に向き合う勝の姿勢には、人間が絵を描くことの根源的な意味をみる思いがする。[橋本啓子]


会場風景
2012/05/10(木)(SYNK)
佐藤卓「光で歩く人」
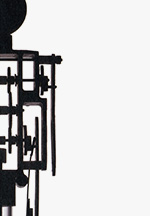
会期:2012/04/23~2012/05/05
巷房[東京都]
「光で歩く人」とは、ソーラーパネルから得られるわずかなエネルギーで歩き続ける小さなロボット。デザイナー・佐藤卓がタカラトミーの依頼で試作したが、諸事情でお蔵入りになってしまっていたものを、震災後に完成させた作品だという。ロボットたちは、古代の埋もれ木や石でできた台の上に立ち、歩き続ける。3階ギャラリーでは窓から入る自然の光で、地階では人工的な光のエネルギーを得て、歩き続ける。私が訪れた日は生憎の天気で空は暗く、3階のロボットたちは脚を休めていたが、それでも地階のロボットたちはガラスのドームや金属のカゴの中で、電灯に照らされながら歩いていた。自然のリズムとは関わりなく歩き続けるためには、人工的なエネルギーを絶えることなく供給し続けなければならなない。ふたつのフロアのロボットには、私たちの文明の過去と現在が重ねられていると同時に、未来への選択肢が示されているのではないだろうか。[新川徳彦]
2012/05/03(木)(SYNK)
佐伯祐三とパリ──ポスターのある街角

会期:2012/04/28~2012/07/16
大阪市立近代美術館(仮称)心斎橋展示室[大阪府]
佐伯祐三(1898-1928)は近代日本洋画を代表する画家の一人。彼はパリの街角を題材に多くの傑作を残した。本展は、佐伯の代表作に、1920年代前後のパリの街角を飾った実際のポスターをあわせて紹介するもの。画家としての佐伯祐三の生涯は、通常、渡欧までの初期(1898-1923)、第一次滞欧時代(1924-26)、一時帰国時代(1926-27)、第二滞欧時代(1927-28)の四期に分けられる。とくにパリは遠い異国からやってきた若い画家の創造の源泉となり、画家はパリの街角を凝視し続けたのである。彼が滞在していた、20世紀初頭のパリといえば、ポスターが日常生活に密着した身近なものであった。いわゆるヨーロッパ・ポスター芸術の黄金時代。アール・ヌーヴォーやアール・デコといった芸術運動のなかで、芸術性の高いポスターが数多く制作され、トゥールーズ=ロートレックやミュシャ、シェレなど、たんなる職人ではない、人気ポスター作家も現われた。ポスターは、当時、佐伯祐三が魅せられた芸術の都パリの街角の息吹を伝えてくれる。[金相美]
2012/05/01(火)(SYNK)
開館25周年記念特別展「柿右衛門展」

会期:2012/04/28~2012/05/31
戸栗美術館[東京都]
実業家戸栗亨(1926~2007)が蒐集した東洋陶磁を展示する美術館の、開館25周年を記念する特別展。ふだんの戸栗美術館は充実した蒐集品をさまざまな切り口で紹介するコレクション展が中心であるが、本展は、柿右衛門家所蔵の史料・現代の作品と、戸栗美術館のコレクションの核のひとつである17世紀後半の柿右衛門様式の磁器とを対比するする試みである。
初代酒井田柿右衛門が創始したといわれる色絵(赤絵)は、17世紀後半にオランダ東インド会社がヨーロッパに輸出したことによって有田の磁器産業とともに大きく発展し、濁手(にごしで)と呼ばれる暖かみのある白い素地とともに、「柿右衛門様式」を完成させた。しかし、17世紀末以降、輸出向けには中国・景徳鎮との国際競争が激しくなったこと、国内では流行の中心が金襴手(きんらんで)に移行したことなどにより、濁手の技術は18世紀(江戸中期)に途絶えてしまった。その技術を1953(昭和28)年に復活させたのが、12代(1878~1963)と13代(1906~1982)の柿右衛門である。そして、当代14代酒井田柿右衛門(1934~)は伝統的な技術を受け継ぐばかりではなく、山野の草花などに取材した新たなモチーフをデザインに積極的に取り入れていることでも知られている。
このように、近代以降の柿右衛門の取り組みは、失われた技術を復興させたり、新たな意匠に取り組むなど、ただ引き継がれてきた伝統を守るばかりではなく、むしろ常に革新を繰り返してきたように思われる。そもそも初代柿右衛門が達成したのは、それまで日本では創り出すことができなかった美しい色絵磁器の製造であった。そして17世紀末からヨーロッパに渡った柿右衛門様式の器は、それまでの染付に代わって人気を呼び、マイセンをはじめ各地で模倣品がつくられた。すなわち当時の人々にとって、日本の色絵磁器は最新のデザインだったのだ。
伝統を守るということはただ同じものを作り続けることではないし、革新とはただいままでと異なる製品を作ることでもない。守るべきものと新しくすべきことは正しく峻別されなければならない。17世紀後半の柿右衛門様式の作品と現代の柿右衛門の作品とをそれぞれの時代の文脈に置いた本展覧会が明らかにするのは、時代を超えて継承される優れた革新の精神なのだと思う。[新川徳彦]
2012/04/27(木)(SYNK)
塩川コレクション──魅惑の北欧アール・ヌーヴォー「ロイヤル・コペンハーゲン ビング・オー・グレンタール」

会期:2012/04/07~2012/05/20
松濤美術館[東京都]
塩川博義氏(日本大学教授・陶磁器コレクター)のコレクションを中心に、デンマークのふたつの名窯ロイヤル・コペンハーゲンとビング・オー・グレンタールにおけるアール・ヌーボー磁器の展開を探る展覧会である。
地階会場では釉下彩(絵付け後に透明釉をかける下絵付けの技法)作品により、両窯の技術の発展と様式の確立とを跡づける。1775年に設立されたロイヤル・コペンハーゲンは、1868年に民間企業となり、1882年に陶器を製造していたアルミニア(1863年設立)に買収されたことで、近代化がはじまった。1885年、経営者フィリップ・ショウ(1818-1912)は、建築家・画家であったアーノルド・クロー(1856-1931)を工場のディレクターに任命。クローの下で、技術としては釉下彩、装飾としてはアール・ヌーボー様式を展開した。昆虫や爬虫類、魚類のモチーフは、アール・ヌーボー様式に共通したものであるが、淡い色彩とグラデーションによる絵付と優美で滑らかな器形は、フランスのアール・ヌーボーとはまた異なった独特の美を生み出している。他方、ビング・オー・グレンタールは、1853年にロイヤル・コペンハーゲンの彫刻師F・グレンダールと、商人であったビング兄弟によって設立された。絵画的表現を特徴とするロイヤル・コペンハーゲンに対して、ビング・オー・グレンタールの製品は彫刻的要素が強く、前者に対する製品差別化としてセンターピースやフィギュアなど立体的な作品が多く作られたという★1。
2階会場では、とくに日本磁器に与えた影響の指摘が興味深い。アール・ヌーボー様式の形成には海外に渡った日本美術の影響がある。ロイヤル・コペンハーゲンもジャポニスムの発信地であったパリのビング商会から日本の浮世絵や工芸品を購入していたという。そうした影響の下につくられた釉下彩の作品は、1889年と1900年のパリ万国博覧会でグランプリを獲得した。これらの博覧会でヨーロッパの陶磁器に触れた日本の関係者は、自国の陶磁器に革新が必要であることを訴える。その結果、日本でも釉下彩という技法が探求されたが、そればかりではなくモチーフの模倣も行なわれたのである。ヨーロッパにとって装飾の源泉であった日本において、ヨーロッパ人が創り出した「ジャポニスム様式」の磁器がつくられ、海外に輸出されていたのはなんとも奇妙なことである。
両窯ともに「ユニカ」(=ユニーク)と呼ばれる一点ものの作品もあるが、多くは量産品であった。そもそも釉下彩は上絵付けよりも焼成回数が少なくて済むため、生産コストを削減する技術でもある。ロイヤル・コペンハーゲンの経営者フィリップ・ショウは技術者であり、機械を導入するなど工場の近代化に努めた。高火度に耐える釉薬を開発したのは化学者アドルフ・クレメントであった。また、ショウはアーノルド・クローをはじめとする多くのアーティストを迎えた。いまだ近代デザインの揺籃期であった19世紀末に、彼らが科学、技術、芸術を融合し、質の高い優れた作品を市場に送り出していたという事実には驚きを禁じ得ない。
本展はこのあと京都・細見美術館に巡回する(2012年7月14日~9月30日)。[新川徳彦]
★1──ビング・オー・グレンタールは1987年にロイヤル・コペンハーゲンに買収された。
2012/04/20(金)(SYNK)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)