artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
ハンマーヘッド オープンスタジオ
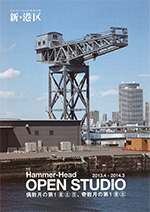
会期:2013/04/05~2013/04/07
新・港区[神奈川県]
横浜トリエンナーレの会場として2008年に建てられた新港ピア。同年のトリエンナーレには使われたものの、次の11年には使われず、代わりにBankARTが「新・港村」として入居した。その縁でBankARTのプロデュースにより、「ハンマーヘッドスタジオ 新・港区」と称して今年度いっぱいアーティストの共同スタジオとして使用されている。若干の出入りはあるものの現在ここで活動しているのは約50組。開発好明、タカノ綾、曽谷朝絵、さとうりさといったアーティストから、青山|目黒、ダンスアーカイヴ構想、メビウスの卵といった団体まで多種多様。残りあと1年たらず、ここからなにか(なにが)生まれてくるだろうか? しかし空間がだだっ広いせいか、それともみんな遠慮深いのか、あまり熱気や活気は伝わってこないなあ。
2013/04/05(金)(村田真)
桂ゆき展──ある寓話
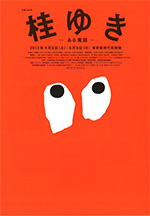
会期:2013/04/06~2013/06/09
東京都現代美術館[東京都]
大正末の女学生時代のスケッチから、平成初期の遺作まで、60余年におよぶ彼女の画業はすっぽり昭和という時代を包み込む。スッゲ。もっとスッゲーのは、彼女の作品からは昭和美術史の香りがあまり感じられず、彼女の3本柱ともいうべき「細密描写」「コラージュ」「戯画的表現」がひたすら繰り返されていることだ。とくに感心するのは細密描写とコラージュの関係で、戦前にはコルクのコラージュと、それを克明に描いたトロンプ・ルイユ(騙し絵)のような細密描写もある。ほかにも布地や新聞紙などがコラージュと見まがうような細密描写で描かれていて、両者は補完的な関係にあったようだ。わからないのは童画チックな戯画的表現で、細密描写の絵に突然ポコンと人の顔や目玉が現われたりするのでズッコケてしまう。これがなければもっと高く評価されただろうに。と思うのはモダニズムに毒されてる証か。
2013/04/05(金)(村田真)
フランシス・アリス展(第一期:メキシコ編)
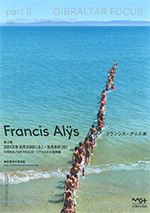
会期:2013/04/06~2013/06/09
東京都現代美術館[東京都]
アリスちゃん、ぜんぜん知りませんでした。カワイイ名前だけど、50すぎのベルギー野郎で、ヴェネツィアで建築を学び、兵役でメキシコに飛ばされて気に入り、そのままメキシコシティに住みついたコスモポリタンだ。昨年のドクメンタ13にも参加したそうだけど、サテライトのカブール会場で映像を見せたらしい。最初は建築家として活動していたが、30歳ごろからアーティストとして作品を発表。記者会見で本人が語ったところによれば、メキシコシティは飽和状態を超えた大都市だが、この都市に直接的な関わりをもちたかったので建築よりアートを選んだのだという。どんなことやってるかといえば、路上で巨大な氷の固まりを溶けるまで押していったり、拳銃を手に繁華街をさまよい歩いたりする映像だ。これって、美大生ならだれもがやった(またはやろうとした)おバカなストリートパフォーマンスと変わりないじゃん。いったいどこが違うのかというと、彼がおふざけでも冷やかしでもなく、最初からアートワールドを目指して戦略的にやってること。そのためにメキシコの歴史や社会問題を読み解き、アート表現として構築していることだ。つまりプロの仕事ってことですかね。いやーほんと、アートってわけがわかりませんな。
2013/04/05(金)(村田真)
平野正樹「MONEY」

会期:2013/04/04~2013/04/16
PROMO-ARTE[東京都]
平野正樹は1991~93年に社会主義政権崩壊後のロシア、東ベルリン、カンボジアを撮影した「祭りの後(AFTER THE FESTIVAL)」を皮切りに、「人間の行方(DOWN THE ROAD)」と題する連作を発表し始めた。今回、表参道のギャラリーPROMO-ARTEで展示された新作「MONEY」も、その一環として制作されたものだが、これまでの彼の作品とは一線を画するものになっていると思う。平野の作品は、代表作と言える内戦後のサラエボの壁に残る弾痕を撮影した「HOLES」のように、自然環境や政治体制崩壊後の人間たちの生の痕跡を捉えたものが多かった。ところが今回「人間の行方シリーズ 沈黙の価値」という副題を添えて発表された「MONEY」では、いよいよ社会システムそのものがテーマになってきている。
会場にはお札、株券、証券、債券証書の類をスキャナーにかけて画像データをとり、大きく引き伸ばしたプリントが並ぶ。紙の皺や折り目や破れ目もそのまま複写されているので、生々しい物質感がそのまま写り込んでいる。背景となる画像のパターンも、スキャニングしたデータを加工してつくっているのだという。2008年の「リーマン・ショック」の引き金となったリーマン・ブラザーズの証券、1917年のロシア革命で紙屑になった「ロシア帝国債券」、内戦や財政赤字によるハイパー・インフレで数字のゼロの数が増えてしまった「百万トルコリラ」や「百万ザイール」の紙幣──平野が題材にしているのは、われわれの経済活動の信頼性の根拠となっている「MONEY」のシステムが、いかに脆弱なものであるのかをまざまざとさし示すサンプルばかりだ。
ストレートな複写であるにもかかわらず、そこには「MONEY」の背後にうごめくグロテスクな欲望や情念が幻影のように浮かび上がってくる気がして、心底ぞっとしてしまう。ドキュメンタリー写真の新たな切り口、方法論を提示する意欲作と言えるだろう。
2013/04/04(木)(飯沢耕太郎)
トーキョー・ストーリー2013 第1章「今、此処」

会期:2013/03/09~2013/04/29
トーキョーワンダーサイト本郷[東京都]
2012年度のTWSのクリエーター・イン・レジデンスに参加したオル太、二藤建人、潘逸舟という3組のアーティストによる成果発表展。オル太は相変わらずプリミティヴでダイナミックなパワーにあふれている。《大地の消化不良》というインスタレーションは、「歯並び」で囲った領域に塩を敷きつめ、水を噴き出す便器や、真っ二つに切った牛(ハリボテ)や、フジツボにおおわれた「貝爺」などを配したもの。便器はデュシャン、真っ二つの牛はデミアン・ハーストを連想させる。第1次産業的労働から一歩アートに近づいたけど、妙に洗練されることもなくワケのわからないパワーが健在でなによりだ。潘は2本の映像作品。ひとつは、岩山のような大きな石がわずかに動くという映像で、これは自分と同じ重さの石を身体の上にのせて撮ったという。もうひとつはその石を船にのせて撮ったもので、これは石は動かず、背景の海がゆっくり動く。思索的なモノクローム映像だが、こういうのは70年代にさんざん見た。二藤は直径5メートルほどの巨大な器を出品。その内側には手足の凸型が浮き上がってちょっとグロだが、凸型ということは砂か泥の山に手足を突っ込んでその上から石膏をかぶせて型どったものだろう。こいつもオル太に劣らずダイナミックだが、二藤のほうがより彫刻原理に肉薄している点でアート濃度が高い。
"大地の消化不良" オル太 [at TWS本郷]
2013/04/03(水)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)