artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
東川哲也「New Moon」
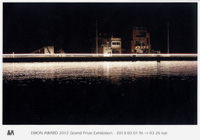
会期:2013/03/01~2013/03/26
EMON PHOTO GALLERY[東京都]
東川哲也は1982年愛知県瀬戸市生まれ。2005年に日本大学芸術学部写真学科を卒業し、現在朝日新聞出版写真部に所属しながら作品を発表している。昨年開催された「EMON AWARD 2012」でグランプリを受賞した本作は、東日本大震災直後の2011年4月から、新月の夜に被災地に残された家屋を撮影し続けたシリーズだ。闇の中にヘッドライトで照らし出された建物が浮かび上がる様子をやや距離を置いて撮影し、728×485ミリの大判プリントに引き伸ばして展示している。プリントをおさめたフレームの内側にLEDのライトを仕込み、画像を透過光で浮かび上がらせるという仕掛けがとても効果的で、建物に残る震災の傷跡が、静かな、だが説得力のある眺めとして定着されている。
だが、これはほぼ同世代の川島崇志の作品とまったく同じ感想なのだが、その巧みなインスタレーションによって、展示全体が均質に見えてくることは否定できない。東川が報道写真的なアプローチを避け、スタイリッシュで美学的なフレーミングや展示方法に固執した気持ちもわからないではない。だが、このところ発表が続いている写真家たちによる、「震災後の写真」への取組みには、志賀理江子のような例外を除けば、どこか共通した弱点があるように思えてならない。ノイズを削ぎ落とし、一定の枠組みの中に作品を落とし込んでしまうことで、彼らが現場で受けとめていたはずのリアリティが、どんどん希薄になってしまっているのだ。もう少し皮膚感覚を鋭敏に研ぎ澄ませ、全身で抗い続けないと、震災後2年を経て風化していく状況に押し流されるままになるのではないだろうか。
2013/03/18(月)(飯沢耕太郎)
CARNIVAL カーニヴァル
会期:2013/03/01~2013/03/31
旧横田医院[鳥取県]
鳥取市の中心部にある病院の廃墟で催された展覧会。悪魔のしるしとフジタマの2組が病院内の随所にそれぞれ作品を展示した。主催はホスピテイル・プロジェクト、キュレーションは赤井あずみ。
何より圧倒的なのが、病院の建築だ。地上3階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で、円筒形のフォルムがひときわ異彩を放っている。中心から放射状に広がるかたちで病室やレントゲン室、手術室などが設えられ、内部の空間はいずれも小ぶりで、中心部は外光が届かないせいか、やたらに暗く、そして寒い。けれども、円環状の廊下を歩いていると、方向感覚を喪失するような感覚が生まれるのが、おもしろい。
そこで不意に出会うのが、フジタマの映像作品である。TVモニターやプロジェクターで見せられているのは、人形や民芸品を使った謎めいた物語をはじめ、中高年のバスツアーの記録映像を再編集したもの、ハワイ人に似ている男性など、いずれも不可解な魅力があふれているものばかり。それらを時空がねじれたような空間で鑑賞するから、頭のなかの混乱によりいっそう拍車がかかり、映像から引き起こされる笑いと恐怖が倍増するのである。
搬入プロジェクトで知られている悪魔のしるしは、「蛇籠め」という土着的な祭りをでっちあげ、藁を身にまとわせた参加者とともに力を合わせながら巨大な蛇を会場である旧横田医院に運び入れるイベントを催した。会場には、その記録映像と写真、この病院の模型、搬入した蛇などが展示されていたが、土着的な祭事を人為的に演出するコンセプトには共感できるものの、イベントにも造形化された作品にもさほど魅力を感じなかった。それは、おそらくそれらの作品がおおむね私たちの理解の範疇に収まってしまうからであり、フジタマのように理解の範疇を超越するのりしろが欠落していたからではないだろうか。建物自体がひとつの芸術作品のような奇妙な場なのだから、もっと突拍子もない祭事を想像しなければ、私たちの視線は廃墟の空間をいつまでも彷徨うことになるだろう。
2013/03/17(日)(福住廉)
竹内麻 展「大体、アラスカマニラ」
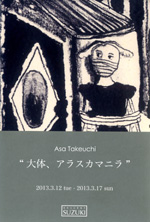
会期:2013/03/012~2013/03/017
ギャラリーすずき[京都府]
名古屋芸術大学で版画を学ぶ竹内麻の個展。繊細な線と、企みを隠しているような人物や動物のモチーフ、毒のあるユーモアが興味をそそるものばかりで、一点一点がとにかく気になる。作家自身は見る人がそれぞれに想像と解釈を楽しんでもらえたらと話していたが、引っかかる謎の要素が多く、つい、これは?あれは?と根掘り葉掘り尋ねてしまった。作品のすべてに呆れるほど詳細なストーリーがあるのが面白い。竹内は、日頃、何気なく頭に浮かんだ言葉や耳にした音の響きからイメージを広げ、物語を想像し描いているのだというが、想像というよりも、それはもはや妄想にも達しているイメージの飛躍とリアルな感覚。なんて豊かな感受性と自由な想像力なのだろうと感動するほどだった。夢と現実が入り混じるような荒唐無稽な場面にも、それぞれに悲しみ、喜び、美しさと醜さなど玉石混淆の人間ドラマがあり、それらが交錯するリズミカルな構図にも惹きつけられる。今後の作品発表も楽しみだ。
2013/03/16(土)(酒井千穂)
KOBE ART LOOP 2013
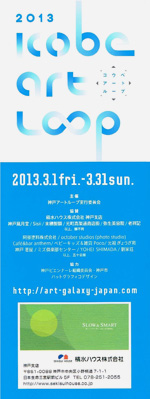
会期:2013/03/01~2013/03/31
ギャラリーほりかわ、GALLERY & SPACE DELLA-PACE、Pocket美術函モトコー、OLD BOOKS & GALLERY SHIRASA、南京町ギャラリー蝶屋、GALLERY 301、ギャラリーTANTO TEMPO、Gallery Vie、ギャラリー開、Kobe 819 Gallery[兵庫県]
神戸の元町・栄町通近辺に居を構える10画廊が、周遊型のアートイベントを企画。内容は画廊の通常活動である個展の集合体だが、マップやスケジュール表付きのパンフレットを作成し、それぞれの存在をアピールしていた。神戸は大阪や京都に比べて画廊の数が少なく、過去に同種の試みが行なわれたことはなかった。しかし、ここ5、6年の間に栄町通を中心に新規の画廊が増え、ようやく面的な展開が可能になった。今回はシンプルな仕掛けだったが、今後も継続しつつ企画性を増して行けば、徐々に効果が現われるだろう。参加画廊に無理のない範囲で、息の長いイベントに成長することを願う。
2013/03/16(土)(小吹隆文)
川島崇志「新しい岸、女を巡る断片」
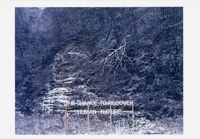
会期:2013/03/08~2013/04/07
G/P GALLERY[東京都]
川島崇志は1985年宮城県白石市生まれ。2011年に東京工芸大学大学院芸術学研究科を修了し、12年にTOKYO FRONTLINE PHOTO AWARDでグランプリを受賞するなど将来を嘱望されている若手写真家だ。今回G/P GALLERYで開催された初個展「新しい岸、女を巡る断片」でも、その才能のひらめきのよさと作品構築の能力の高さを充分に感じとることができた。
出身地を見てもわかるように、東日本大震災とその余波は彼にも大きく作用したようだ。今回展示されたシリーズは、震災直後に被災地の海岸でたまたま見つけて撮影したという、2人の女性が写っている写真が基点となっている。彼女たちとのその後の交友を縦軸にして、川島自身の震災へのメッセージを絡ませながら、巧みに作品群をインスタレーションしていく。その手際は高度に洗練されており、彼がこの若さで現代美術と現代写真の文法をきちんと身につけていることに、正直驚かされた。欧米のスタイリッシュなギャラリーの空間に作品が配置されていたとしても、まったく違和感なく馴染んでしまうのではないだろうか。
だが、この洗練は諸刃の剣でもある。作品を見ていて、手法の多様性にもかかわらず、どことなく均質な印象を受けることが気になった。彼が震災の衝撃を受けとめ、咀嚼して作品化する過程で、行きつ戻りつしたはずの思考や行動の軌跡が、もう少し作品にストレートに表われていてもいいのではないのではないかとも思った。混沌を鷲掴みにするような野蛮さ、野放図さがほしい。それが持ち前の高度な作品構築力と結びつくことを期待したいものだ。
2013/03/15(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)