artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
黒田辰秋・田中信行│漆という力
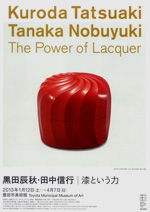
会期:2013/01/12~2013/04/07
豊田市美術館[愛知県]
とてつもなくすばらしい展覧会を見ると、しばらく言葉を失って茫然自失とすることが、ままある。黒田辰秋と田中信行による二人展は、ほとんどマスメディアの注目を集めることはなかったが、両者によって表現された漆という力とそれらを巧みに構成する展覧会の力が絶妙に調和した、近年稀に見る優れた企画展だった。
黒田辰秋(1904-1982)は木工芸で初めて重要無形文化財に認定された漆芸家。木工の指物をはじめ、乾漆や螺鈿による漆芸を数多く手がけた。本展の前半は、同館が所蔵する黒田の作品をはじめ、黒田が直接的に影響を受けたという柳宗悦が私蔵していた朝鮮木工や、親交のあった河井寛次郎による焼物や木彫も併せて、展示された。
一見して心に刻み込まれるのは、黒田の作品から立ち上がるアクの強さ。木工芸にしろ漆芸にしろ、大胆な文様と造形を特徴とする黒田の作品には、一度見たら決して忘れられないほどの強烈な存在感がある。それは、表面上の装飾や技巧に終始しがちな伝統工芸とは対照的な、まさしく「肉厚の造形感覚」(天野一夫)に由来しているのだろう。《赤漆捻紋蓋物》や《赤漆彫花文文庫》などを見ると、まるで内側の肉が反転して露出してしまったような、えぐ味すら感じられる。それを「縄文的」と言ったら言い過ぎなのかもしれないが、岡本太郎が好んだ「いやったらしい」という言葉は必ずしも的外れではあるまい。
そして、会場の後半に進むと、一転して田中信行による抽象的な漆芸世界が広がる。鋭角的な造形の黒田に対し、田中の漆芸を構成しているのは、柔らかな曲線。しかも従来の漆芸のように支持体としての木工に依存せず、表皮としての漆だけを造形化しているところに、田中の真骨頂がある。だから広い会場に点在する漆黒の造形物は、造形としては薄く、儚い。にもかかわらず、その黒光りする表面を覗きこむと、どこまでも深く、吸い込まれるように錯覚するのだ。とりわけ《Inner side-Outer side》は、それが湾曲しながら自立しているからだろうか、自分の正面に屹立する漆黒の表面の奥深くに全身で飛び込みたくなるほど、魅惑的である。
黒田辰秋の作品が外向的・遠心的だとすれば、田中信行のそれは内向的・求心的だと言える。双方が立ち並んだ会場には強力な磁場が発生していた。いや、むしろこう言ってよければ、芸術の魔術性が立ち現われていたと言うべきだろう。それは、近代芸術が押し殺してきた、しかし、かねてから私たち自身が心の奥底で芸術に求めてやまない、物質的なエロスである。本展は、物質より概念を重視するポスト・プロダクトへと流れつつある現代アートに対する批判的かつ根源的な一撃として評価できる。
2013/03/30(土)(福住廉)
ウラサキミキオ展
会期:2013/03/25~2013/03/30
Gallery K[東京都]
銀座の画廊をていねいに見て歩くと、美術館やコマーシャル・ギャラリーでは決して出会えない作品を目にすることができる。これらを端から度外視するから、総じて言えば、今日の美術評論はかつてとは比べ物にならないほど浅薄で脆弱なものになり下がったのである。美術評論の基礎体力を蓄えるには、美術館や画廊の外部、すなわちストリートにおける表現活動を視野に収める必要があるし、同時に、それらの内部におけるさまざまなアートをいかなる偏りもなく均等に鑑賞しなければならない。これは最低条件である。
ウラサキミキオは、ここ数年、同ギャラリーで定期的に新作の絵画を発表しているが、今回の個展はこれまでの作風を持続させながらも、それらがある一定の高みに到達したことを証明した。日常的な風景を主題とした具象性の高い画面に、しかしその主題とはまったく無関係な紙片を貼りつける。その紙片にはデカルコマニーで色彩が施される場合もあるし、白い無色のまま貼付される場合もある。そうして構成された絵画は、これまでは具象性に重心が置かれることが多く、紙片はあくまでも従属的な立場にあった。ところが、今回の個展で発表された新作では、その紙片が具象性の画面を縦横無尽に暴れまわったり、あるいは紙片の上にさらなる色彩と形態が塗り重ねられたり、主題と紙片の関係性がよりいっそう複雑に錯綜していたのである。しかも一点一点の作品が、相互の類似性を見出すことが難しいほど、それぞれ自立している点もすばらしい。ウラサキは、絵画の成熟を手に入れたのではないか。
「VOCA」にしろ「シェル美術賞」にしろ、現行の美術制度は実年齢の若さと新人を同一視しているが、ウラサキのような中堅層にも有望で実力のあるアーティストは確かに存在している。ウラサキ以外で類例を挙げるとすれば、コバヤシ画廊で発表している永原トミヒロの仕事も、いま以上に注目されるべきである。それらをみすみす見逃すのは、大いなる損失というほかない。
2013/03/29(金)(福住廉)
石ノ森萬画館

石巻に1泊し、翌朝自転車を借りて海寄りの南浜町や旧北上川の対岸へ行ってみる。瓦礫はずいぶん少なくなったが、ポツンポツンと半壊の家が残るだけであとは土台だけの殺風景な元住宅地は、ほとんどそのまま変わってない。遠目には新築そのままでビクともしてないように見える市立病院と文化センターも、近づいてみると解体工事が始まろうとしていて心が痛む。そんななか、旧北上川の中州に建つ卵形の屋根の石ノ森萬画館が先週リニューアルオープンしたというので、のぞいてみることに。さっそく入口のスロープに「龍神沼」の原画コピーが貼り出されている。忘れもしない『マンガ家入門』に「作例」として載っていた作品だ。当時マンガ家志望で石森章太郎の大ファンだったぼくは、この本をむさぼるように繰り返し読んだものだ。しかし2階の展示室は案の定「仮面ライダー」に支配されていて楽しめなかった(3階は「サイボーグ009」で、こちらは懐しかった)。たどってみると、ぼくが石森章太郎に耽溺したのは60年代までで(「ボンボン」「となりのたまげ太くん」「ミュータントサブ」「サイボーグ009」「ファンタジーワールドジュン」……)、70年になるまでに終わっていたということがわかった。もう40年以上も前だよおおお。
2013/03/29(金)(村田真)
若冲が来てくれました──プライスコレクション 江戸絵画の美と生命
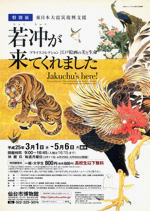
会期:2013/03/01~2013/05/06
仙台市博物館[宮城県]
石巻に用事があり、仙台市博物館に寄る。「若冲が来てくれました」とは奇妙なタイトルだが、これは日本美術コレクターとして知られるアメリカのエツコ&ジョー・プライス夫妻の発案により、東日本大震災復興支援のために若冲をはじめとするコレクションを東北の被災3県に巡回するもの。プライス夫妻のコレクションは2006~07年にも「最後の里帰り展」として全国を巡回したが、今回は震災復興のためもういちど特別公開することに。だから若冲が来てくれたのは東京からでも京都からでもなく、カリフォルニアからなのだ(一部国内コレクションも出ている)。展示は画家別でも時代順でもなく、長沢芦雪の《白いゾウと黒いウシ》などの大きな屏風絵にはじまり、「目がものをいう」「数がものをいう」「プライス動物園」「美人大好き」と、美術的価値とは異なる観点から子どもでも親しめるように構成されている。作品名も《野をかけまわるウマたち》《のめやうたえや、おおさわぎ》《〈かんざん〉さんと〈じっとく〉さん》など、仮名表記でわかりやすく砕いて表わしている。これは肩ひじ張らずにだれでも楽しんで見てもらおうという主催者側の配慮だろう。実際、前に見たときよりずっと作品のおもしろさがダイレクトに伝わってきた。ひとつだけ不満をいえば、芦雪や曽我蕭白や鈴木其一や河鍋暁斎らの作品だって十分見ごたえがあるのに、タイトルが「若冲が来てくれました」になっていること。たしかに「若冲」のブランド効果は抜群かもしれないが、これではほかの絵師たちの立場がないし、プライスコレクションの過小評価にもつながりかねないではないか。
2013/03/28(木)(村田真)
円山応挙 展─江戸時代絵画 真の実力者─
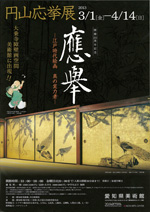
会期:2013/03/01~2013/04/14
愛知県美術館[愛知県]
愛知県立美術館にて、円山応挙展を見る。好き嫌いが分かれる作家だ。まとめて全体の作品を見ると、同一の人物と思えないほど、さまざまなスタイルを駆使し、器用な人だと思う。建築系からは、特に西洋からの眼鏡絵の手法の導入(その事例として、細長く、透視図法を強調できる三十三間堂を選ぶのもうなずける)、ジグザグに置かれることを意識した屏風絵の立体的な表現、そして会場に再現された障壁画と空間の関係が興味深い。
2013/03/27(水)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)