artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
六本木アートナイト2013
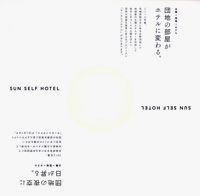
会期:2013/03/23~2013/03/24
六本木界隈[東京都]
国立新美術館から東京ミッドタウン、六本木ヒルズと回ったが、とくに収穫もないので家に帰ろうと交差点に向かったら、アマンドのビルの4階でもなにかやってるというので寄ってみた。北沢潤の《サンセルフホテル──六本木ショールーム》だった。「サンセルフホテル」というのは取手市の団地を舞台に、太陽光エネルギーを利用して団地の空き部屋を客室に変えていこうというプロジェクト。ここはそのプレゼン用のショールームというわけだ。部屋の中央に天井いっぱいの照明バルーンが置かれているが、その明かりは昼に貯めた太陽光エネルギーで賄われているそうだ。目の前の首都高から見たら(地上からは見えない)六本木のど真ん中でなにやってんだと思うだろう。アマンドの入ったビルの一室というミスマッチなロケーションも含め、今夜はこれがいちばん納得できる作品(?)だった。
2013/03/23(土)(村田真)
カリフォルニア・デザイン1930-1965──モダン・リヴィングの起源
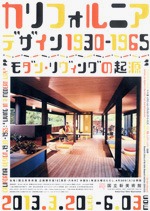
会期:2013/03/20~2013/06/03
国立新美術館[東京都]
今日は無料だからつい入っちゃったけど、デザインに興味はないんで足早にグルッと一周する。あ、おもしろいじゃん。作品はほとんど見なかったんでなにもいえませんが、会場構成がおもしろい。観客はまず展示室の壁に沿って大きく一周し、次いで内側にしつらえた仮設壁に沿ってもう一周するという動線。肝腎の作品は仮設壁にのみ展示され、部屋の内壁には1点も飾られていない。おまけに中央部分が広場のように空き、そこから全体が見渡せるという会場構成なのだ。これは展覧会場(エキジビション)というより展示場(エクスポジション)に近い。
2013/03/23(土)(村田真)
第66回日本アンデパンダン展

会期:2013/03/20~2013/04/01
国立新美術館[東京都]
うちの庭が騒がしいと思ったら、下界では「六本木アートナイト」が始まったらしい。ちょっとのぞいてみるかと足を向けたのは、本日に限り入場無料の国立新美術館。セコ! まずは敗戦直後から続く日本アンデパンダン展。アンデパンダンだからある程度ヘタな作品が並んでいるのは想定内だったが、ものすごくヘタな作品もあったのは想定外の喜びだった。どんなヘタな絵でも国立美術館に飾れることを証明してくれたんだから、絵描きに勇気を与える展覧会だ。ハッとするような作品もあった。しんぶん赤旗に掲載された風景のスケッチ数点を拡大コピーして額に入れたり、川越の古い蔵やカメルーンの人たちの顔のスケッチをボードに貼ったり、こんな「作品」があっていいんだろうかとハッとした。また今回はネット世代も採り込もうってわけか、入口で黄色い「いいね!」シールを配り、いいねと思った作品の脇に貼ってもらうことも試みていた。もちろん作品によって多い少ないはあるものの、ざっと見たところシールゼロというのはなかったな。ついでに「ヘタね!」シールもやってみればよかったのに。
2013/03/23(土)(村田真)
維新の洋画家──川村清雄
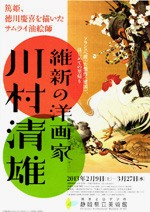
会期:2013/02/09~2013/03/27
静岡県立美術館[静岡県]
旗本の子であった川村清雄(1852~1934)は、明治維新に際して徳川家達に従って静岡に移った静岡ゆかりの画家である。明治4年には徳川家の援助を受けてアメリカ、後にヴェネツィアで絵を学び、明治14年に帰国。もっとも早い時期に海外で油彩画の技法を学んだ画家のひとりである。その作品の特徴は、油彩画の技術を極めながらもモチーフや構図、描線が日本画的である点にあろう。絵の支持体もカンバスばかりではなく、絹地、漆器、板、黒繻子の帯にまで及んでいる。和洋折衷、あるいは和魂洋才と呼ばれる所以である。明治40年の東京博覧会における審査官辞任以降は画壇と距離を置き、その没後はなかば忘れられた画家とされてきた。しかし、ご子息の清衛氏(2002年没)の努力と、明治美術学会の活動により、近年になって作品・資料の調査が進み、1994年には静岡県立美術館で最初の回顧展が開催されている(1994/8/13~9/25)。今回の展覧会は、清衛氏の没後に寄贈された川村家資料を所蔵する江戸東京博物館との共催による文献資料の渉猟と作品研究の両面からの最新の研究成果である(本展図録は美術館連絡協議会2012年の「優秀カタログ賞」を受賞した)。東京展では歴史に重点をおいた展覧会という印象があったが、静岡展では絵画作品の展示に重点がおかれ、オルセー美術館から里帰りした《建国》(1929)を含め、広い展示室でゆったりと鑑賞することができた。
日本絵画史では長らく忘れられた画家とされてきた川村清雄は、存命中は貧しく暮らし、遅筆ゆえに一部に悪評はあったものの、作品が残り、再評価が可能になった背景には同時代の支援者たちの存在がある。勝海舟や徳川家達、小笠原長生など徳川家ゆかりの人々のほか、経済学者の和田垣謙三や、出版社至誠堂の加島虎吉などの支援があってこそ、清雄は独自の絵画を追求することができた。春陽堂や至誠堂との仕事は経済的な支えとなったばかりではなく、文学者たちとの繋がりをもたらした。彼らが清雄の作品に魅了されていたのはもちろんのことであるが、その人物にも大いに惚れ込んでいたようである。明治32年の個展開催に尽力したのは橋本雅邦であった。昭和2年の展覧会発起人には和田英作、岡田三郎助、藤島武二らが名を連ね、最終日には東伏見宮妃が観覧に訪れている。聖徳記念絵画館の80枚の壁画の制作を委嘱するにあたって、川村清雄は最初に名前を挙げられた画家であり、彼は10年近い歳月をかけて大作《振天府》(1931)を完成させている。清雄を推挙したのは明治神宮奉賛会会長でもあった徳川家達であった。こうした川村清雄の作品づくり、人間的魅力を知ることができる第一の文献は木村駿吉の『川村清雄 作品と其人物』(私家版、大正15年)であろう。稀覯書ではあるが、近代デジタルライブラリーで閲覧可能である。[新川徳彦]
関連レビュー
維新の洋画家──川村清雄|村田真
もうひとつの川村清雄 展|SYNK
2013/03/23(土)(SYNK)
喜多村みか「Einmal ist Keinmal|my small fib」

会期:2013/03/20~2013/03/31
THERME GALLERY[東京都]
喜多村みかは渡邊有紀と互いにポートレートを撮影し合った「TWO SIGHT PAST」で2006年に写真新世紀優秀賞を受賞した。その後、自分の写真の世界を構築する作業を、じわじわと水が地表に沁み出してくるように続けて、今回写真集『Einmal ist Keinmal』(THERME Books)の刊行につなげた。本展はそれを契機として開催されたもので、1階スペースに大小のカラー・プリントをちりばめた「Einmal ist Keinmal」が、2階スペースにモノクロームの「my small fib」のシリーズが展示されていた。
写真集の表題となっている「Einmal ist Keinmal」というのはドイツのことわざで「一度は数のうちに入らない。ただ一度なら全然ないのと同じこと」という意味だ。つまり「些細なもの、取るに足らない事柄」ということなのだが、たしかに彼女の写真の中に写っているものには、壁の傷とか、光のプールとか、ぼんやりした影とか、鉢植えの植物とか、たまたま出会った人物とか、日常のなかで見出される「取るに足らない事柄」が多い。だがそれらの小さな「しるし」が、不思議な輝きを帯びて目に飛び込んでくる所に、彼女の写真術の秘密があるのではないかと思う。「数のうちに入らない」ことが、「たった一度しか起らなかった」稀有な出来事に転化していく。それを見届けたということの歓びが、どちらかと言えば地味な写真が並ぶ展示からも確実に伝わってきた。
写真集も写真の構成、レイアウト、デザインのレベルが高く、素晴らしい出来栄えだ(装丁は熊谷篤史)。カラー作品→モノクローム作品→カラー作品という転調がうまく効いていて、読者の気持ちをそらすことなく、最後まで運んでいってくれる。
2013/03/22(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)