artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
樋口明宏「Margaret─少女マンガ彫刻」
会期:2022/01/07~2022/02/03
MA2 Gallery[東京都]
少女マンガに登場する典型的なキャラクターを木彫にした作品が15点ほど。少女マンガのキャラクターといえば、大きなおめめにキラキラの瞳、尖った鼻に長い髪が特徴だが、それを荒削りに彫っている。マンガというのは平面の世界だから、現実にはありえない表現もしばしばある。だいたい顔は斜めの角度からカッコよく見えるように描かれるので、目や鼻や口の位置関係が矛盾している場合が多く、立体化しようとするとそのツケが回ってくる。おそらくフィギュアの原型師の苦労もそこにあるが、それを強引に立体化するからおもしろい。
樋口はこれまで昆虫の標本に繊細な装飾を施したり、仏像をポップなフィギュアに修復したり、卓越した技術によって古典とポップ、ハイとロー、西洋と日本、平面と立体のあいだを往還し、攪拌し、組み合わせてきた。この「少女マンガ彫刻」も、卑俗でチープな少女マンガを、仏像や神像といった聖なるイメージが強い木彫に接続した手腕が鮮やかだ。なかには「ピキッ」といった擬音が彫ってあったり、背景に放射線が刻まれたりして笑えるが、彩色は控えめで、近代彫刻のような風格さえ漂う。器用だなあ。
角材から彫っているので、大半は側面や天地が平面で断ち切られている。そのため、まるで彫刻が立体的な1コマに収まっているようにも見える。3次元コマ割りというか。これを積み重ねていけば、4次元の立体少女マンガができるかもしれない。

「Margaret─少女マンガ彫刻」展 展示作品[筆者撮影]
2022/01/22(土)(村田真)
喜井豊治展「壁画から天使まで」
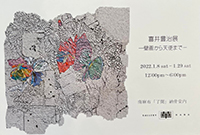
会期:2022/01/8~2022/01/29
ギャラリー華[東京都]
ぼくがモザイクに興味を持つようになったのは喜井豊治のおかげだ。数年前、彼が所属するモザイク会議の定期展にぼくを審査員として採用してくれたからだ。本来モザイクは床や壁に石のかけらを貼りつけて完成させるので、フレスコ画などと同じく「不動産美術」といえる。不動産美術は基本的に注文がなければ制作できないので、依頼主の要求に沿った職人仕事になり、表現内容はある程度制約されざるをえない。そこで多くのモザイク作家は展覧会に出したり売ったりするため、タブローとしてのモザイク画を制作している。モザイク会議の展覧会も、今回の個展も、そうした発表の場のひとつだ。
ついでにいうと、モザイク展の審査でぼくが重視したのは、いま述べたようなモザイクの成り立ちをどれだけ作品に反映しているか、そして、油絵でもフレスコ画でもないモザイクならではの新しい表現がされているか、という点だった。つまり、不動産美術の記憶を止めつつ現代を表現すること、それがタブローとしてのモザイク制作のモチベーションでなければならない、と勝手に考えていた。モザイクの素人がいうのもおこがましいが、今回の喜井の作品はまさにそれを実現しているように思えた。
その作品の多くは、灰白色の石の小片を部分的に規則正しく、部分的にランダムに並べ、ところどころ草花や火や水を表わす緑、赤、青などの石をはめ込んだもの。しかも外縁が矩形ではなく不定形なので、パッと見、瓦礫と化した廃墟の床を真上から俯瞰したような印象がある。彼がテーマにするのは「人のいない景色の物語」。自然破壊が進んで無人になった世界を表わしているらしい。例えば、青い石をうねるように並べた《クレージー水ドラゴン》は川の氾濫や大津波を、白い石から赤い石を炎のように立ち上らせた《山は燃え川は暴れる》は、大火事か火山の噴火を思わせる。不動産美術の記憶を蘇らせると同時に、現代または近未来の日本を暗示するような表現といえるだろう。だが、いちばん共感したのはその作品より、会場に掲げられた彼の言葉だ(以下、ステートメントから抜粋)。
「話すのも気恥ずかしい陳腐な自然破壊のテーマです。それでもこのテーマを選ぶのは、石のかけらを組み合わせた画面にドリルで穴を開け、ハンマーでたたいて壊し、また組み合わせる。そういう破壊衝動に意味を持たせるためです」
ここから読み取れるのは、モザイク作家としての恥じらいと矜恃だ。「破壊衝動に意味を持たせる」というのは、形而上的な表現内容と形而下の創作行為との埋めがたい距離を縮めようとする努力にほかならない。もうひとつ指摘しておきたいのは、「話すのも気恥ずかしい陳腐な自然破壊のテーマ」は、売れ筋ではないということ。彼の主な仕事は壁画制作であり、その一部は会場に写真パネルで紹介されている。東京を中心に各地の公民館や図書館、地下鉄駅などに壁画を設置しているが、見たところ「自然破壊」をテーマにした作品はないようだ。先述のようにモザイクは依頼主の希望に沿って制作されるので、自然破壊のようなネガティブなテーマは好まれない。そうした壁画では需要のないテーマを、彼はタブローとしてのモザイク画で実現させようとしているのだ。ここに彼の恥じらいと矜恃の理由がある。
2022/01/22(土)(村田真)
Museum of Mom's Art ニッポン国おかんアート村

会期:2022/01/22~2022/04/10
東京都渋谷公園通りギャラリー[東京都]
叔母が昔、いらなくなったネクタイを使って器用に人形をつくってくれた。どこかにそんな教室かサークルみたいなのがあって、そこで覚えたのだろう。早くに連れ合いを亡くした叔母は、時間だけはあり余っていたから。でもその人形も、見慣れた柄とはいえ別に愛着が湧くわけでもなく、かといって捨てるのも忍びなく、結局どこかに仕舞い込んだまま忘れ去られている。これなどは典型的な「おかんアート」だろう。
展覧会をのぞくと、あるわあるわ、PPバンドを編んでつくった犬、軍手をリサイクルしたウサギ、緑色の紐を巻いてできたカエル、半透明のリボンを組み合わせた金魚、毛糸で編んだキューピーの服や帽子、マツボックリの笠のあいだに縮緬を詰めた置き物などなど。動物系が多く、カワイイけどなんの役にも立たない、けど邪魔になるほど場所をとらない、と油断しているうちに増殖して始末に負えなくなるオブジェたち。
同展をキュレーションした都築響一氏によれば、「メインストリームのファインアートから離れた『極北』で息づくのがアール・ブリュット/アウトサイダー・アートだとすれば、正反対の『極南』で優しく育まれているアートフォーム、それがおかんアートだ」。確かに、あり余るヒマと日用品にあかせてつくるおかんアートは、やむにやまれぬ衝動に突き動かされるアウトサイダー・アートの対極にあるが、しかし芸術性や経済的価値を追求するファインアートからの距離はアウトサイダー・アートに近いかもしれない。カッコよくいえば「ブリコラージュ」ということになるが、むしろ「ポップ民藝」といったほうがわかりやすい。民藝と同じく一つひとつは下手物だけど、それが何百何千と集まると体系が見えてきて、芸術的オーラまで帯びてくるから不思議だ。
会場に並ぶのは数千点。数が多ければ多いほど見る者は楽しめるけど、集め出せばキリがないし、なにより美術品と違ってすぐ飽きるので何度も見たいものではない。それでも、素材やモチーフに時代や地域性が感じられ、おかんのセンスの移り変わりもわかるという点で、歴史的・資料的価値は大いにある。これはやはりMoMA(Museum of Mom’s Art=おかん美術館)を設立すべきだろう。下手物といわれた民藝が100年後に東京国立近代美術館で回顧されたように、おかんアートもひょっとしたら本物のMoMAからお声がかかるかもしれない。

「Museum of Mom’s Art ニッポン国おかんアート村」展 会場風景[筆者撮影]
2022/01/22(土)(村田真)
滋賀県立美術館

滋賀県立美術館[滋賀]
本当は昨年のリニューアル・オープン後、すぐに行くつもりだったのだが、コロナ禍もあって予定が変更なり、ようやく《滋賀県立美術館》を初訪問することができた。最寄りの駅からのアクセスはやや面倒だが、茶室や池を眺めながらアプローチする庭園の奥という環境は楽しめる。建築はコンペで選ばれた日建設計が手がけ、1984年に竣工したものだが、grafやUMA/design farmらが参加し、内装デザインがアップデートされている。受付でAICA(美術評論家連盟)のプレスカードを提示すると、ていねいに報道の腕章まで渡され、感心させられた。欧米では、プレスを確認すると、すぐに入館できるのだが、日本の地方美術館では、たとえカード有効館になっていても、何それ? という反応がよくあって、説明が面倒なのである。

滋賀県立美術館の外観、UMA/design farmによるロゴマーク

滋賀県立美術館の庭園

NOTA & UMA/design farmによるサイン

grafによるオリジナルの可動什器
まず常設の「野口謙蔵生誕120年展」が、思いのほか良かった。1924年に東京藝大を卒業した後、洋行せず、地元の近江に戻って絵画を探求し、高いオリジナリティをもつ表現に到達していることに驚かされた。例えば、《五月の風景》や《霜の朝》(いずれも1934)など、表現主義と抽象がまじったような独特の風景画である。その後も、さらに独自の画法を展開したが、早すぎる死が悔やまれる作家だ。また同じく常設の「昔の滋賀のくらし」展は、博物館的なまなざしによってコレクションを読み解き、過去の風俗、道具、生活、風景などを紹介している。続く、小倉遊亀のコーナーは、西洋画の手法を導入しつつ、日本画の枠組を刷新してきた試みを説明していたが、全体を通して、わかりやすいキャプションも印象に残った。
企画展の「人間の才能 生みだすことと生きること」は、新館長の保坂健二朗が自ら企画を主導し、美術館のテーマのひとつであるアール・ブリュットを打ちだしつつ、現代美術やつくるという行為の普遍性に迫ろうとするものだった。冒頭では、「アール・ブリュット」の概念をめぐる議論や批判を振り返り、続いて、古久保憲満の巨大な空想都市のドローイングや鵜飼結一朗による百鬼夜行のような絵巻など、日本の表現者を紹介する。そしてみずのき絵画教室や海外の実践など、教育のプロジェクト、また中原浩大の幼少時からの膨大な作品群アーカイブが示される。後者は以前、京都芸術センターでも見たことはあったが、ここでは美術教育とアール・ブリュットの境界を揺るがす事例という文脈になっている。なお、企画展は全体として展示デザインもユニークなものだった。最後に会場を出ると、鑑賞者に「生みだすことと生きること」を問いかける壁が用意されていた。

「人間の才能 生みだすことと生きること」展 古久保憲満の作品展示風景

「人間の才能 生みだすことと生きること」展 みずのき絵画教室の作品展示風景

「人間の才能 生みだすことと生きること」展 中原浩大の作品展示風景
野口謙蔵生誕120年展
会期:2021年12月7日(火)〜2022年2月20日(日)
会場:滋賀県立美術館
(滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1)
昔の滋賀のくらし
会期:2021年12月7日(火)〜2022年2月20日(日)
会場:滋賀県立美術館
人間の才能 生みだすことと生きること
会期:2022年1月22日(土)〜2022年3月27日(日)
会場:滋賀県立美術館
2022/01/22(土)(五十嵐太郎)
オルタナティブ! 小池一子展 アートとデザインのやわらかな運動

会期:2022/01/22~2022/03/21
アーツ千代田 3331[東京都]
小池一子さんてだれ? と聞かれたとき、どのように紹介すればいいのだろう。そもそも彼女を「さん」づけすべきか迷ってしまう。ぼくは記事を書くとき、慣例的にアーティストの名前は敬称抜きだが、学芸員や評論家などその他の人たちには「氏」や「さん」など敬称をつける。小池さんはいわゆるアーティストではないけれど、ある意味アーティスト以上にアーティスティックなクリエイターだし、なにより今回は展覧会の主役でもあるので、小池一子と敬称抜きで記すべきかもしれない。とはいっても、40年近くおつきあいさせていただいている大先輩、やはり呼び捨てにするのははばかられるので、ここでは敬意を込めて「小池さん」と呼ばせていただきます。
で、小池さんを紹介すると、コピーライター、編集者、クリエイティブ・ディレクター、翻訳者、無印良品の企画・監修者、武蔵野美術大学名誉教授、東京ビエンナーレ共同代表、フェミニスト……。過去の肩書も含めると、元西武・セゾン美術館アソシエイト・キュレーター、元佐賀町エキジビット・スペース主宰者、元十和田市現代美術館館長……まだまだあるかもしれない。実に多彩な活動をされているので、ひとことで言い表わすことはできないが、共通しているのはいずれも名前や顔が表に出ることの少ない裏方仕事であることだ。そんな人物の展覧会とはいったいどんなものなのか。
展示は大きく、前半の「中間子」と後半の「佐賀町」の2部に分かれている。前半は、パルコや西武美術館、イッセイミヤケ、無印良品などのポスターが壁面を埋め、編集者やコピーライターとして関わった『週刊平凡』『森英恵流行通信』などの雑誌、デザイナー田中一光と制作した『JAPANESE COLORING』(リブロポート、1982)、『三宅一生の発想と展開ISSEY MIYAKE East Meets West』(平凡社、1978)などの書籍も公開。特にポスターは華やかで、広告デザイン全盛期の1970-80年代に見覚えのあるものがずらりと並ぶ。昨年開かれた石岡瑛子の回顧展を思い出したが、それもそのはず、石岡と共作したポスターもある。石岡もアートディレクターとして、写真家やデザイナー、イラストレーターらをつなぐ仕事をしていたが、みずから「ものづくり」をするデザイナーでもあった。でも小池さんはあくまで人と人、人と企業や美術館をつなげて新しい価値を生み出すことに徹した。いわば才能と才能との触媒。それが「中間子」の意味であり、役割でもあるだろう。
後半の「佐賀町」とはいうまでもなく、日本では稀なオルタナティブ・スペースとして1983年に誕生した佐賀町エキジビット・スペースのこと。小池さんが主宰したこの特徴あるスペースで、2000年までの17年間に106の展覧会やパフォーマンスを実現させた。今回はそのうち、吉澤美香、大竹伸朗、横尾忠則、シュウゾウ・アヅチ・ガリバー、杉本博司、森村泰昌ら約20人による当時の作品を展示している。しかし考えてみれば、小池一子の名を冠した展覧会なのに、本人の「作品」はなく、20人ものアーティストの作品が並ぶのは、変といえば変。だが、ここに小池さんの「中間子」たるゆえんがある。彼らアーティストは小池さんがいなければ(佐賀町がなければ)現在の地位を築けなかったかもしれないし、これらの作品も日の目を見なかったかもしれないのだ。裏返せば、これらの作品もアーティストも小池さんの「作品」なのだ。といってみたい欲望に駆られるが、そこまではいわないでおこう(もういっちゃったけど)。
ちなみに後半の「佐賀町」の展示スペースは、前半の「中間子」の倍くらいある。現代美術だからポスターより幅をとるのは当然だし、また、小池さんの興味が広告デザインから徐々にアートへと重心を移しているように感じられるので納得だが、そうでなくても「佐賀町」が同展のメインディッシュであることは間違いない。それはタイトルの「オルタナティブ!」からも明らかなように、企画したのが美術館でもギャラリーでもない、佐賀町のオルタナティブ精神を受け継ぐ3331であるからだ。
2022/01/21(金)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)