artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
松本健宏「正直な人 honesty」
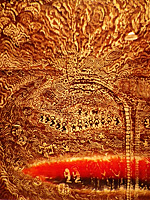
会期:2012/03/06~2012/03/11
ぱるあーと[京都府]
柿渋や墨を用いたロウ染めの作品と、素朴な風合いの人形を出品。ロウ染めは柿渋を厚く塗り重ねることで絵具のような光沢の色面をつくり出しているのが特徴。模様ではなく絵を描いており、主題は彼のアトリエがある京都府綾部市の限界集落や山陰地方の流し雛など、日本の原風景である。また、人形は石塑粘土や藁と土で動物や神、神獣などを表現しており、ひなびた民芸品的な味わいがある。どちらも日本の土着的な美意識を濃密に宿しており、自身の深奥に潜む古層がよみがえるような感覚を味わった。
2012/03/06(火)(小吹隆文)
莫毅「因獣」

会期:2012/09/28~2012/10/28
MEM[東京都]
1958年生まれの莫毅(モイ)は中国現代写真を代現する作家のひとりだが、これまでほとんど日本では紹介されてこなかった。榮榮(ロンロン)や劉錚(リウジョン)が、北京で手づくりのコピー写真誌『NEW PHOTO(新攝影)』を刊行して、先鋭的な写真表現の狼煙を上げるのは1990年代後半だが、莫毅は1980年代から、彼らから距離をとりつつ独自の作風を育て上げていった。チベット出身の彼にとって、北京や天津などの都市の生活は、大きな刺激を与えられるとともに違和感を覚えるものであったはずだ。主に都市の路上で撮影されてきた彼のスナップショットには、彼の心身に刻み込まれたその軋轢や軋みが、色濃く滲み出ているように見える。
今回展示されたのは、毛沢東の銅像とそこに写っている自分の影を撮影した1986年の作品から撮り続けられているセルフポートレート、路上を行き交う人々の脚や自転車のスポークなどを野良犬の目の高さから撮影した「舞踏的街道」、首の後ろに据え付けたカメラで1メートル後ろの人物たち(公安警察官を含む)を撮影した「1米─我身后的風景」、多重露光やピンぼけの画像で揺れ動く都市の光景を捉えた「我虚幻的城市」などのシリーズである。いずれも自分の身体とカメラを都市の路上にさらし、文字通り体を張って撮影を続けつつ、哲学的とも言える深い思考にまで達した写真群と言えるだろう。それらはまた結果的に、1989年の天安門事件を経て、激しく流動してきた中国社会を、あくまでも個人的な視点から読み解いたユニークな報告でもある。今回はまだ「紹介」といった趣の個展だったが、もう一回り大きなスケールの展示をぜひ見てみたいと思う。
2012/03/05(月)(飯沢耕太郎)
フェリーチェ・ベアトの東洋

会期:2012/03/06~2012/05/06
東京都写真美術館 2階展示室[東京都]
イタリアに生まれ、クリミア半島、インド、中国、日本、スーダン、そして最期の活動の地となったビルマ。フェリーチェ・ベアト(1832~1909)のドラマチックな生涯と、彼が足跡を残した場所の広がりは、当時としては驚くべきものだ。それを可能としたのが、これまた驚くべき勢いで表現領域を拡大しようとしていた写真術だった。ポール・ゲティ美術館のコレクションに、東京都写真美術館の所蔵作品も加えた130点を超える展示を見ると、この「19世紀の戦場カメラマン」の仕事の質の高さがまざまざと見えてくる。
ベアトが求めていたのは芸術的な評価などではなく、出来事をその細部まで精確に写しとることができる写真の能力を最大限に発揮して、あわよくば高額の報酬を得ようという野望だったはずだ。時には危険を冒しても、血なまぐさい戦場に足を運んで撮影したのは、その商品的価値がきわめて高かったからだろう。1863年から20年以上も滞在した日本を去るきっかけになったのが、銀相場の投機の失敗だったということをみても、ベアトは相当に山師的な人物だった。また彼が日本の絵師たちとともにつくり上げた「横浜写真」(手彩色の風景・風俗写真)は、写真の事業化の走りだった。ベアトのようなややいかがわしいところのある人物が跳梁していたということも、ある意味で19世紀の写真の面白さだと思う。
それに加えて、これは堀野正雄にも通じることだが、写真家としてのベアトのプロフェッショナリズムは特筆に値する。ガラスネガを使用する湿板写真の精密な描写力、丁寧にプリントされた鶏卵紙印画の美しさ、印画紙を横につなぐパノラマ写真の精度の高さは、ベアトが自らの写真のクオリティを保つことに、職人的な誇りを持ち続けていたことをよく示している。結果的に彼の仕事は、19世紀後半の世界の姿を現在までいきいきと伝える、貴重な視覚的資料となった。
2012/03/05(月)(飯沢耕太郎)
幻のモダニスト──写真家 堀野正雄の世界

会期:2012/03/06~2012/05/06
東京都写真美術館 3階展示室[東京都]
堀野正雄(1907~98)という名前を聞いて、すぐにその仕事を思い浮かべることができる人はそれほど多くないだろう。1930年代の「新興写真」の金字塔というべき写真集『カメラ・眼×鉄・構成』(1932)の作者としては常に取りあげられてきたが、彼の写真家としての全体像は1990年代までおぼろげにしか見えてこなかった。最晩年になって、「おそらく千枚近い数百枚」の写真印画が残っていることが判明し、東京都写真美術館専門調査員の金子隆一を中心として調査・研究が開始された。今回の展覧会は以後10年以上の研究の成果を一堂に会するものであり、日本写真史において画期的な意味を持つものといえる。
堀野はひと言でいえば、日本で最初にプロフェッショナルな「職業写真家」としての意識を持った写真家のひとりといえるだろう。6部構成200点余りの展示を見ていると、被写体を的確に把握し、完璧な技術でプリントし、さらに印刷原稿として仕上げていく能力が抜群に高いことがわかる。初期の前衛舞踊家や築地小劇場の舞台から、街頭スナップ、「機械的建造物」の構造研究、女優のポートレート、戦時中の報道写真まで、読者に最善の形で視覚的な情報を伝えようという意識が明確に貫かれているのだ。堀野はよく自分のことを「技術家」と書いているが、これは決して卑下しているのではなく、むしろ誇りを持ってそう位置づけていたのではないだろうか。
今回の展示で最も興味深かったのは、1931~32年にかけて『中央公論』や『犯罪科学』といった雑誌に掲載された「グラフ・モンタージュ」作品の実物展示のパートだった。堀野はこの頃、板垣鷹穂、村山知義、大宅壮一、北川冬彦、武田麟太郎といった書き手と組んで、言葉と写真とでまとまったメッセージを伝えようとするグラフ・ページをさかんに発表していた。《大東京の性格》《首都貫流──隅田川アルバム》《終点》《玉川ベリ》といった作品をあらためて見直すと、コラージュ的な写真構成と短いキャプションとの組み合わせによって、視覚伝達の枠組みを解体/構築していく意欲的な実験が試みられていたことがわかる。その試みは、残念なことに短い期間で終わってしまうのだが、それは1960年代以降のヴィジュアル誌で展開される編集・レイアウトの先取りだったともいえるだろう。
「グラフ・モンタージュ」に限らず、堀野の写真家としての位置づけは、この展覧会によって大きく変わっていくのではないだろうか。あれほど情熱を傾けていた写真の仕事を、なぜ戦後すぐに断念してしまったのか。この最大の謎を含めて、まだ考えなければならないことが多く出てきそうだ。
2012/03/05(月)(飯沢耕太郎)
2011年度京都造形芸術大学卒業制作関連イベント シンポジウム「万博へ、万博から」

会期:2012/03/04
京都造形芸術大学 京都芸術劇場 春秋座[京都府]
京都造形芸術大学の卒業制作展を訪れた。美術、建築、デザインだけではなく、テキスタイル、日本画など、いろいろなジャンルがある。1円玉を集めて103万円をかたどる作品、クリムト的な絵画がある和風の空間インスタレーション、壁が絵になった作品などが印象に残る。旅館の増築のように、傾斜に沿って、奥まで複雑に建物が続いていたことを初めて知った。坂茂による構築物も建設中だった。今回の卒制展のテーマ、万博にあわせて、浅田彰、五十嵐、ヤノベケンジ、岡崎乾二郎のトークイベントが開催された(当初、磯崎新も来る予定だったが、欠席)。五十嵐は建築、ヤノベは自作から大阪万博を中心に語り、岡崎は大阪万博と対極的な構造をもつ1967年のモントリオール万博を論じた。すなわち、丹下健三が全体計画を担当した大阪万博の未来都市がツリー構造だとすれば、モントリオールは逆に一枚一枚の葉がそれぞれの幹をもつ思想だという。
2012/03/04(日)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)