artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
相模友士郎『ナビゲーションズ』

会期:2015/09/25~2015/09/27
STスポット[神奈川県]
舞台と客席がある。踊る人が居て、それを演出する人が居て、それを見つめる人が居る。演出する人は見つめる人に話しかけ、スマホと持ち物を預かる。スマホはバッグに集められて舞台に吊るされる。持ち物たちはすでに置かれたいくつかのものたちと床に散りばめられた。そして、はじまる。踊る人が現われる。演出する人(相模友士郎)は客席の脇で、身を隠さぬまま照明をコントロールしている。冒頭から明らかなのは、ここには、隠されているものがなにもない、ということ。はじめ(1)、踊る人(佐藤健大郎)はゆっくりと歩き、初めて見る持ち物たちの名前を読み上げる。次に(2)、持ち物たちの前に立ち、それを用いる身振りを行なう。それが終わると(3)、持ち物を身につけてみたり、水筒ならば中身を飲んでみたりする。その次には(4)、持ち物を誰かが身につけ用いるのを手助けするようにして、その誰かと踊ってみる。シンプルな佐藤への四つのインストラクション(「ナビゲーション」)が、時間を構成し、空間を構成する。ここにあるのは、それだけ。相模の「ナビ」に促され、佐藤は動作をとる。それを、見つめる人は追いかける。見つめる人の持ち物が、踊る人の動作を動機づけていく。持ち物が見えない糸を生み、見つめる人と踊る人とを結ぶ。この見えぬ「糸」が、微弱な緊張を作り出す。ゆっくりとした動作を続ける踊る人から、見つめる人はなにを受けとるのだろう。自分の持ち物と踊る人に、見つめる人は割って入ることはできず、ただ「見つめること」をもって応えるしかない。まるで現世に降りた幽霊の如く、傍観するほかない。(4)で踊る人は誰かと踊った。しかしその「誰か」は目に見えない。不在ではない。しかし、見えない。ここにも幽霊がいる。踊る人も例外ではない。佐藤健大郎もまた、持ち物に触れはするものの、その場に「踊る人」として居るだけで、佐藤健大郎個人の実体は見えない。「隠されているものがない」と先に述べた。「ナビ」にとなるわずかなルールが構造をなし、スケルトン状態でむき出しになっている。そのなかを幽霊たちは徘徊し、彼らを別の幽霊たちが見つめている。それが本作での出来事なのだ。パフォーマンスの基本的関係をあらわにしたところで面白い?と問われるかもしれない。では本作は「空っぽ」(中身なし)なのかというと、それが違うのだ。佐藤の動きは丁寧で動作が正確になされた。「正確」とは、余計なものがない、ということ。ゆえに見応えがあった。最終場は、それまでの丁寧な動作を濃縮したダンスで締めくくられた。ダンスとはどこに宿る? 踊る人のなかに、輪郭に、それとも外側に? わからないが、その「ダンスなるもの」を舞台空間に降臨させるようとする繊細な手つきが、本作をあまねく満たしていた。
2015/09/25(金)(木村覚)
PACIFIKMELTINGPOT
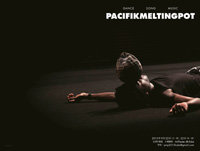
会期:2015/09/22~2015/09/23
Art Theater dB KOBE[兵庫県]
フランス人振付家、レジーヌ・ショピノのカンパニーをハブに、日本、ニューカレドニア、ニュージーランドという3つの太平洋諸地域のアーティストが参加し、各地域でのリサーチワークを積み上げてきた《PACIFIKMELTINGPOT》。2013年に大阪で行なわれたリサーチワークの成果発表「PACIFIKMELTINGPOT / In Situ Osaka」は基本的に3地域のグループに分かれてのショーイングという形式で、それぞれの文化圏ごとに身体性の差異が提示され、多文化主義的な性格が強かった。しかし、新たに3週間の滞在制作を経て作品化された本公演は、確実に深化を見せていた。
冒頭、上手と下手に分かれて対面したダンサーたちは、その隔たりを架橋するように、ひとりずつボールを床に転がして向こう側の相手に渡し、ボールは手から手へと渡っていく。静かな幕開けの後、ボールはあるときは祝祭的な花火のように空間を飛び交い、あるときは床に打ち付けられて力強いリズムを刻む。ボールの描く軌跡と弾む音が、ダンサーたちの身体の動きや声と呼応し、響き合う。ソロやデュオとして、個々人の身体性が強く浮かび上がる時間と、共同作業のように全員が混ざり合う時間。ふたつの時間のあいだをダンサーたちは行き来する。そこでは、一糸乱れぬ群舞のように全員が全体の目的に奉仕するのではなく、異なる身体性を持った個々人をつなぐ要素として、音や声といった音楽的要素が重要な役割を果たしていた。とりわけ、四股を踏むように、足で床=大地を強く踏む動作は何度も繰り返され、ダンサーたち全員に共有された身体言語として強い存在感を放っていた。また、それぞれの言語で歌われる歌に加えて、ひとりが声を発すると、口々に異なる音程やリズム、手拍子が加えられていき、多層的だが調和したひとつの音楽が即興的に生成されていく。豊穣な声が織りなす時間と、ボールの乱打や打楽器、掛け声が飛び交う喧騒の時間と、深い森のなかのざわめきを思わせる時間。ダンサーたちは動物や鳥の鳴き声を囁き交わし、ある者は動物へと擬態する。侵犯されていく境界。水平的に始まった上演の時空間は、さまざまな厚みと固有の響きを持って自在に拡張し、旅するように多様な風景を出現させ、それぞれのダンサーの身体から発せられる熱量が蓄積されていく。
そのエネルギーは終盤、輪になって集団で刻む足踏みのリズムと、ボールを床に打ち付けるリズムによって体現され、狭まる輪とともに内側へ収縮し、圧力を増していく。最後に一斉に虚空へ解き放たれるボールは、闇に火柱が立ち上がるようで、まさにエネルギーの噴出を思わせた。そう、「PACIFIKMELTINGPOT」の島々は、環太平洋造山帯として地下深くで繋がっているのだ。本作は、目下、経済的欲望に支配された巨大貿易圏に包摂され、他者の排除と多様性の否定が進行する現在に対して、身体的な対話と想像力を持つことの意義を提示していた。
2015/09/22(火)(高嶋慈)
山城知佳子+砂川敦志(水上の人プロダクション)「PACIFIKMELTINGPOT / In Situ Osaka 2013」映画上映

会期:2015/09/22~2015/09/23
神戸映画資料館[兵庫県]
フランス人振付家、レジーヌ・ショピノのカンパニーをハブにして、太平洋諸地域のアーティストや研究者が展開する《PACIFIKMELTINGPOT》。これまで、ニューカレドニアやニュージーランドの先住民であるカナックやマオリなど、口承文化をまだ受け継ぐ地域の人々とワークショップを行ない、リサーチを積み上げてきた。2013年には大阪で「PACIFIKMELTINGPOT / In Situ Osaka」ライブパフォーマンス&ディスカッションが開催され、日本、ニューカレドニア、ニュージーランドという3つの地域のアーティストが参加した。この映画は、大阪でのリサーチワークとその成果発表の上演を記録したドキュメンタリーである。監督は、沖縄を拠点に活躍する映像作家・山城知佳子と映画監督・砂川敦志。《PACIFIKMELTINGPOT》の完結編となる神戸での公演に合わせて上映された。
このドキュメンタリー映画の特徴は、振付家やダンサーたちが交わす言葉に対して、字幕が一切付けられていない点にある。フランス語、英語、日本語。3つの地域の3つの言語が入り乱れてやり取りされるリサーチワークの現場。ダンスは身体言語の芸術だが、創作現場ではたくさんの言葉が発せられ、身体への探究が言語化を通してフィードバックされる。加えて、《PACIFIKMELTINGPOT》の場合、身体から発せられる音や声、つまり口承文化の豊かな語りや歌唱も作品を構成する素材となる。映画では、観客が「字幕を読む」ことを封じることで、身体の動きへの注視に加え、聴こえてくるさまざまな歌や音そのものが際立っていた。アカペラ歌唱、その力強さやハーモニックな調和、手拍子や足踏みで集団的に刻むリズム……。さらに木琴の即興演奏が加わる。ここでは常に絶えず声と音が流れ、多声的な場を醸成している。その意味で、これはダンス映画であると同時に、音楽映画と言えるだろう。
字幕がないことで、(日本の観客にとって)もうひとつ際立つ部分が、通訳を兼ねた日本人ダンサーと振付家とのやり取りだ。3地域それぞれのグループ毎に、動きや声を通して身体の共同体的質を探っていくのだが、日本の子守唄やわらべ唄を歌いながら踊ってみせたダンサーたちに対して、ショピノは「私にはそれは何のバイブレーションも起こさなかった」と厳しい判断を下す。共同体的身体や「起源」の捏造や再生産は、とりわけそれが「国家」という仮構されたシステムと結びつくとき、同化と排除の論理の強化につながる危険性を大いに孕んでいる。あるいは、グローバリゼーションと消費資本主義が覆っていくなか、多文化主義への回収や観光資源化されていくだろう。しかし、口承文化が生活のなかにまだ残っているカナックやマオリの出演者たちとは異なり、われわれの身体にはそうした共同体的質がどの程度まで宿っているのだろうか。筆者のインタビューにおいて、ショピノは「2年前の大阪でのクリエーションは互いの差異を知る段階として必要だった」と語っていたが、ここでの「差異」とは所作やリズム感、体格の違いといった表面的なもの以前に、歌や踊りとして身体化された共同体のルーツの有無という、より根源的な差異ではなかったか。
2015/09/22(火)(高嶋慈)
フェスティバルFUKUSHIMA! presents 納涼!盆踊り in TodaysArt.JP 2015 TOKYO
会期:2015/09/12
東京海洋大学 グラウンド特設会場[東京都]
大友良英のPROJECT FUKUSHIMA!が、「オランダ発の最先端アートの祭典『TodaysArt.JP 2015』」の関連企画として、東京海洋大学で行なわれた。「3.11以後のアート・プロジェクト」と「最先端アートの祭典」と「東京海洋大学」との関連は希薄で、夕方にまだまばらな観客たちとプロジェクトFUKUSHIMA!盆バンドをしゃがんで聞いているころは、その「とってつけた」感じに馴染めずにいた。次第に音頭の演奏となり、観客は踊り手となって櫓を囲み踊りだす。すると、温泉に浸かっているような、じわじわと心と体がほぐれるような感触が訪れた。それが島根の盆踊りだとしても、自分の体の中にあるなにかが触発されて「腑に落ちた」気持ちになってくる。盆踊りによって自分の眠っていた「日本的身体」を目覚めさせられた、とまでいってよいのかわからないが、そんな錯覚に陥る。珍しいキノコ舞踊団が踊りをサポート。彼女たちらしい振りのコミカルさかわいさには、自分は「腑に落ちた」気持ちになれず。だが、伝統的な踊りばかりでは「ただの盆踊り」になってしまう。土地のものと最新の感性とが混じり合って、その土地の魅力を消さずに洗練されたものを生み出す、そんな大地の芸術祭に感じた「年季」みたいなものが、いつかこの「盆踊り」からも滲んでくるとよいのでは、と思わされる。その後、DJフクタケが、歌謡曲やアニソンのなかの隠れた音頭ソングを1時間超、かけ続けた。その楽曲の多いこと! 100年前、50年前ではなく、多くは20~30年前のものだ。今日の日本人も、ことあれば音頭を聴きたがってきた、そんなことがわかるプレイだった。いよいよ、大友良英のバンドによる音頭に編曲した『あまちゃん』関連曲が演奏されると、『あまちゃん』へのなつかしさに「ふるさと」を感じて、踊りが勢いづく。そんな仕掛けも巧みだが、ふるさとを奪われ傷つけられた「福島」が、誰もが自分の「ふるさと」であるかのように思いをはせる場「FUKUSHIMA」へと変貌していくとしたら、この「盆踊り」は土地に根ざさずとも永続する祭りとなるかもしれない。
2015/09/12(土)(木村覚)
アロリー・ゴエルジェ&アントワンヌ・ドゥフォール「GERMINAL─ジェルミナル」
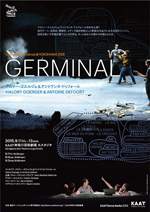
会期:2015/09/11~2015/09/13
KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ[神奈川県]
思想、情報、メディア論を横断するフランス/ベルギーのユニットによる舞台である。最初は暗闇だけだ。そして、呼吸するような照明。創世記のように世界が始まり、続いて四名の男女がモノリスに触れた猿のように、コミュニケーションの手段をゼロからつくり出す。彼らは試行錯誤しながら、それを発達させ、世界をカテゴリー化していく。通常はあまり活用されない床の使い方がとても斬新な演出だった。
2015/09/11(金)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)