artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
公開制作vol.2 佐藤朋子「狐・鶴・馬」

会期:2022/05/28~2022/09/11
長野県立美術館[長野県]
本企画は、佐藤朋子による長野県立美術館での公開制作と、そのあとの成果発表としての展覧会で構成されている。公開制作時には、佐藤によるパフォーマンスはもとより、アーティストトーク、応募者とのオープンエンドな哲学対話と幾度とないイベントが開催された。そして展覧会は、(1)佐藤によるレクチャーパフォーマンスの記録映像と劇中歌のレコードを含む《Song of the Fox, August 2022 Version》(2022)、(2)「アーティストインタビュー」、(3)本展がインストールされるまでに繰り返された佐藤の収集したものや公開制作での対話の記録、異類婚姻譚を軸とした鶴についての自筆テキスト、明治天皇と馬を巡る自筆テキストといった「制作の資料」(鑑賞者は自由に手に取り閲覧できる)で構成されている。
 公開制作vol.2 佐藤朋子「狐・鶴・馬」成果発表展の様子
公開制作vol.2 佐藤朋子「狐・鶴・馬」成果発表展の様子
[撮影:蓮沼昌弘/提供:長野県立美術館]
本展の軸となる(1)《Song of the Fox, August 2022 Version》は、大学の講義の記録のような映像作品で、暗い部屋のなかでプロジェクターに映し出される図像や文章について佐藤が説明を加えていく。本作で取り上げられているのは、人間の男と人間の女に化けた狐とその二人の間に生まれた子について、岡倉天心が英語で書いたオペラ「白狐」(The White Fox)の解釈の可能性だ。ただし、作中に出てくる資料や図像ひとつとっても、何が事実で、どの程度が翻訳の範疇であり、飛躍なのかが鑑賞者に明示されるわけではないがゆえに、作品を通して、鑑賞者は自身が与えられた情報を元に「何を思ったか」という自分の信条を手繰り寄せることになる。本展の場合は、それを(2)と(3)によって各人が検証することも可能になっているが、そもそも、佐藤のレクチャーパフォーマンスは「何が事実で、何がフィクションなのか」ということに、なぜここまで意識が向くのか考えてみたい。ヒト・スタヤルやハルン・ファロッキをはじめとして、数多くあるレクチャー形式の映像作品を見ていても、ここまで「虚実」に気を遣ったことがわたしはなかったと思い至ったからだ。
(1)と(2)での佐藤の現われ方についての差分で考えてみてもよいが、以下がわたしを佐藤作品での「虚実の見極め」へと駆り立てる。暗い壇上でのスポットライトや佐藤の表情を捉えようとするショットの切り替わりといった、「ここは劇場である」と示す演出の存在。レクチャーをしている人物(=佐藤)がどのような立場によってレクチャーを担うのかが映像上宙づりとなりながらも、主体的に喋り続けるという点が、一般的な講義記録からはほど遠いものだとわかる。これが、当たり前である「この映像はつくられたものだ」という事実を繰り返し鑑賞者に明示する。世界中に溢れるファクトチェックなしの動画が誰かに何かを信じこませ再生数を稼ごうと知略を駆使する一方で、あるいは、その手法を美術に援用するレクチャー作品とは似て非なるものとして、佐藤のレクチャーパフォーマンスはつねに「この情報はどう飲み込んだらいいのか」と鑑賞者を揺さぶり続ける。本展における「アーティストインタビュー」と「制作の資料」の設置は、ただのワークインプログレスを超えて、佐藤作品における「鑑賞者へ情報を与える文法」を何重にも増幅させる仕掛けとして機能していたといえるだろう。
なお、展覧会や公開制作は無料で観覧可能でした。
 公開制作vol.2 佐藤朋子「狐・鶴・馬」成果発表展の様子
公開制作vol.2 佐藤朋子「狐・鶴・馬」成果発表展の様子
[撮影:蓮沼昌弘/提供:長野県立美術館]
 公開制作vol.2 佐藤朋子「狐・鶴・馬」成果発表展の様子
公開制作vol.2 佐藤朋子「狐・鶴・馬」成果発表展の様子
[撮影:蓮沼昌弘/提供:長野県立美術館]
公式サイト:https://nagano.art.museum/exhibition/publicproduction02
2022/09/11(日)(きりとりめでる)
中野成樹+フランケンズ『EP1(ゆめみたい)』

会期:2022/09/11, 23
個人的なことは政治的なことである。演劇の実践もまたその渦中にある。中野成樹+フランケンズ(以下ナカフラ)が「20年かけて『ハムレット』を最初から最後までゆっくりたどっていく企画」の第一弾『EP1(ゆめみたい)』(原作:シェイクスピア『ハムレット』より、作・演出:中野成樹)はそのことを正面から引き受けようとする試みだ。
前作『Part of it all』でナカフラは「現状のメンバー全員が、 ①日常生活を維持しながら無理なく参加できる ②あるいは、積極的に不参加できる」という二つの指針に基づき準備を行ない、結果として上演の場にメンバーの子供たちの姿があるような公演が実現することになった。20年かけて『ハムレット』を上演するという今回の企画はその延長線上にあり、より長いスパンで生活と演劇とを撚り合わせる試みだと言えるだろう。中野は今回の試みをEP=extended play(ing)と呼んでいる。演劇の時間が限りなく、とまでは言わずとも20年という長さにまで拡張されたとき、それと生活の時間との、あるいは人生との関係はどのようなものになるだろうか。
『EP1(ゆめみたい)』として上演されるのは原作『ハムレット』の1幕5場にあたるシーンまで。以下では各シーンの内容に触れていくが、今作は9月23日(金・祝)に2回目の上演が、10・11月にも同内容での上演が予定されているので注意されたい。気になる方はホームページで作品の冒頭部にあたるシーン1「今 半透明」の戯曲も公開されているのでそちらをチェックするのもいいだろう。今作では原作において重要なモチーフとなる亡霊を軸に、見えない(ことにされてきた)ものの存在や陰謀論など、『ハムレット』の今日性が引き出されていくことになる。

会場に入ると舞台(となるであろう空間)では公演関係者とその子供たち(と思われる人々)がおもちゃを広げて遊んでいる(ということは拡張されるのは演劇ではなく子供の遊びの方なのかもしれない)。やがておもちゃが一旦片づけられると前説(斎藤淳子、出演者と配役は回によって異なりここでは9月11日の回の配役を記す、以下同様)がはじまり、今回の公演では子供たちがいてその行動は予測不能であること、諸々の事情で公演に参加していないメンバーがいることなどが告げられる。「いなくてもいい人の出席」と「いなくちゃいけない人の欠席」という表現からしてすでにすこぶるハムレット的である。なにせ、いるかいないか(To be, or not to be)、それが問題(?)なのだから。

シーン1および1.5「だから半透明」は原作の1幕1場を踏襲し見張り同士の会話の場面。「例の亡霊」が出たか否かという会話も交わされるものの、バナードー(野島真里)はいまいち要領を得ない様子でフランシスコー(佐々木愛)との会話も噛み合わない。「オカルトは、政治と連んでろって」と言うホレイショー(石橋志保)に対し、マーセラス(森唯人)は陰謀論は「それほど嘘じゃない気がする」と亡霊=陰謀論説を持ち出したりもする。しかしようやく亡霊が登場するに至り、世界は反転する。亡霊と思われた人物が、あたかもバナードーたちこそが亡霊であるかのように「誰だ! 何のため、姿を見せた?」と誰何するのだ。「俺たちが、亡霊にされている……?」「不具合の原因にされている……!」と彼(女)たちは言うが、さて、見えていないものは、不具合の原因は真実のところ果たしてどちらにあるのだろうか。ここには再び生活と演劇の関係も重ねて見ておくべきだろう。そこでは何が見えておらず、不具合の原因は果たしてどちらにあるのか(それは本当に不具合か)。「見え(てい)ないもの」は『Part of it all』から引き継がれたテーマでもある。

シーン2はクローディアス(洪雄大)とガートルード(小泉まき)による記者会見の設え。官僚の不倫騒動など現実の出来事を下敷きにしたと思しき場面はコミカルにアイロニカルだが、ここは「個人的なことは政治的なことである」という言葉がその本来意味するところとは異なる、悪しきかたちで体現された場面でもある。かつて物語の主人公は王侯貴族であり、そこでは個人的なことはつねにすでに政治的なことであった。だが、現代の権力者たちは政治を私物化することによって「個人的なことは政治的なことである」を実現してしまっている。

続くシーン3「お正月」で描かれるボローニアス(中野)、レアティーズ(新藤みなみ)、オフィーリア(端田新菜)のやりとりもまた、家族の会話でありながら政治的なものであることからは逃れられない。そしてこの場面では子供たちが舞台に戻り、正月の親戚の集まりさながら舞台上でわいわいと遊んでもいる。切っても切れない政治と家との、そして演劇と生活との関係がそこで絡まり合っている。
再び見張りの場面を挟んで先代ハムレット王の亡霊(福田毅)とハムレット(竹田英司)の対話(だがそこに滲むのはごくごく個人的な感情のようだ)で『EP1(ゆめみたい)』は一旦終わる。しかし物語は閉じず、生活も続く。決してオールオッケーではない、ひとまずのplayの区切り。
中野成樹+フランケンズ:http://frankens.net/
関連レビュー
中野成樹+フランケンズ『Part of it all』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年09月15日号)
2022/09/11(日)(山﨑健太)
Transfield Studio『Lines and Around Lines』
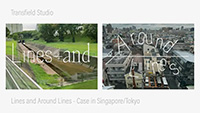
会期:2022/09/01~2022/09/04
元映画館[東京都]
私の足下にあるこの土地を規定しているものは何か。建築家の山川陸とパフォーミングアーツマネージャーの武田侑子によるユニットTransfield Studioの『Lines and Around Lines』(企画・構成:Transfield Studio[山川陸+武田侑子])は、「水の流れ」をキーワードに観客の土地への視線と想像力を更新する試みだ。パフォーマンスはレクチャーパフォーマンスとツアーパフォーマンスの二部構成。観客は会場となった元映画館でシンガポールの水の流れに取材したレクチャーパフォーマンスを鑑賞した後、簡易な地図とそこに付されたQRコードからアクセスできるオーディオガイドを頼りに隅田川へと向かうツアーパフォーマンスに旅立つことになる。
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
ところで、なぜシンガポールなのだろうか。実はTransfield Studioはシンガポールの劇場Esplanadeが主催するレジデンスプログラムContemporary Performing Arts Research Residencyの参加アーティストとして2022年の4月から6月までシンガポールに滞在しており、『Lines and Around Lines』はそのときのリサーチをもとにした作品となっている。公演期間中には関連イベントとしてシンガポールでの滞在制作の報告会も実施され、滞在制作の様子とシンガポールのパフォーミング・アーツ事情を知ることのできる貴重な機会となった。なぜシンガポールなのか、という問いに対するひとまずの答えは、たまたまTransfield Studioがそこに滞在する機会があったから、という身も蓋もないものになるだろう。
Transfield Studioはこれまでもフェスティバル/トーキョー19公式プログラムの『Sand (a)isles(サンド・アイル)』では池袋を、豊岡演劇祭2020フリンジに参加した『三度、参る』では豊岡を舞台に、その場所に関するリサーチからツアーパフォーマンスを立ち上げることを試みてきた(いずれも発表時は別名義)。そもそも特定の場所を歩くことが作品の根幹をなすツアーパフォーマンスにおいて、その場所に関するリサーチから創作が出発することはあまりにも当然のことであるようにも思えるが、しかしここにはある種の二重性がある。ツアーパフォーマンスはまず創り手がそこを歩き、次に観客が歩くことで成立するものだからだ。ならばそこにはズレを導入することもできるはずだ。未知の土地を訪れた者は、無意識のうちに自分の知る土地とその場所とを比較し、そこにある共通点と差異からその土地のありようを測るだろう。『Lines and Around Lines』は日暮里/荒川エリアを歩く観客に、シンガポールを歩いたTransfield Studioの視点をインストールする。
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
前半のレクチャーパフォーマンスではスクリーンに映し出される画像や映像に山川の声が重なり、シンガポールにおける水の流れを追っていく。やがて明らかになってくるのは、水資源の貴重なシンガポールにおいては、その流れのあり方こそがある面において国を「定義」しているということだ。山川の語りのなかに繰り返し登場する「定義」という言葉。シンガポールでは湾の出口は水門で塞がれ、そこはreservoir=貯水池として定義される。湾を堰き止めた水門はそのまま、国の輪郭を定める線の一部となるだろう。山川はスクリーンの手前に置かれたポールにロープを巻きつけていくことでその輪郭線を示す。線の内側、国土の9割はcatchment、雨水を集める場所と定義されているのだという。そして水が流れるための傾きの存在。 レクチャーパフォーマンスを聴き終えた観客は会場を出て、方位磁針を手に隅田川を目指す。地図には目的地である隅田川へと真っ直ぐに伸びるラインと、それと交差するJR常磐線、明治通り、都電荒川線、そして隅田川の4つのライン。その交差地点につく度に再生を促されるオーディオガイドは、ときおりシンガポールについての語りとも響き合いながら、東京という土地の来し方とそこに流れる水へと観客の意識を向かわせる。
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
ところで、今回のツアーパフォーマンスに詳細なルートの設定はない。あるのは隅田川という目的地と北北東という大まかな方向だけ。レクチャーパフォーマンスを終え、おおよそ同時に街へと出た観客は、最初のうちこそ同じようなルートを辿るものの、住宅地の入り組んだ路地を進むうち、徐々に異なるルートへとバラけていく。それでも時おり、曲がり角を曲がった先にほかの観客の背中が見え、同じ方向へと向かっていることが確認されるのだった。複数の流れはときに合流し、ときに分かれ、そしていずれにせよ川へと至る。観客の歩みは水の流れと重なり合う。自らの身体をもって、目には見えぬ東京の水の流れを体感すること──。
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
Transfield Studio:https://www.transfieldstudio.com/
関連レビュー
JK・アニコチェ×山川 陸『Sand (a)isles(サンド・アイル)』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月15日号)
2022/09/02(金)(山﨑健太)
プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022

会期:2022/10/01~2022/10/23
ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO、京都市京セラ美術館、京都中央信用金庫 旧厚生センター ほか[京都府]
13年目を迎えるKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭(以下KEX)。やっとKEXが戻ってきた! という実感だ。コロナ禍を受け、ここ2年間のフェスティバルでは、海外アーティストの作品は映像上映・オンライン配信などへの変更や公演中止を余儀なくされていたが、2年ぶりに海外アーティストを招聘し、新作や日本初演が並ぶ期待に満ちたプログラムだ。
今回は、「ニューてくてく」をキーワードに、上演プログラムのShowsには11演目がラインナップ。舞台芸術の創作環境や国際交流はもちろん、日常生活に大きな影響を与えた社会的変動の後、「歩くこと」を新たに捉え直すことを目指す。前回のキーワード「もしもし? !」に続き、肩肘の張らない柔軟な姿勢を示しつつ、深い思考の広がりを促すような言葉だ。「てくてく」には、身体的な移動に加え、異なる時間の移動、意識や感情の動き、思考を整理するための散歩、政治的行為としての行進やデモなど多様な含意が込められている。さらに、都市を遊戯的に歩くことで、消費資本主義の空間化や、近代的合理性や有用性に訓育された身体を批評的に脱しようとするドゥボールらシチュアシオニストの「漂流」の実践も位置づけられるだろう。
「歩くこと」を直接的に扱うのは、メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子によるビジュアルコンサートと、ミーシャ・ラインカウフ。前者では、東日本大震災後に建設された巨大な防波堤を歩き続ける人物を映す志賀の新作映像に、国際コラボレーションによる大音量のノイズ・ミュージックが重ねられる。ミーシャ・ラインカウフは、陸路では越境困難な「国境」を海底を歩くことで横断する行為と、都市空間の地下の巨大インフラに潜って歩く行為を記録した映像作品を展示する。

ミーシャ・ラインカウフ《Fiction of a Non-Entry(入国禁止のフィクション)》
[© Mischa Leinkauf - alexander levy - VG Bild/Kunst]
観客が自ら歩くことで発見や出会いをもたらす参加型の作品が、梅田哲也とティノ・セーガル。梅田のツアー型パフォーマンス作品では、元銀行の建物の構造を活かしたインスタレーションの中で、ガイド役に案内されさまざまな出来事に遭遇する。ティノ・セーガルの作品では、京都市京セラ美術館の日本庭園を舞台に、観客自身について即興的に1対1で歌ってくれる歌い手との出会いが作品体験となる。

ティノ・セーガル 京都市京セラ美術館 日本庭園
[Photo by Koroda Takeru]
イギリス現代演劇のパイオニア、フォースド・エンタテインメントによる2作品は、「タイムトラベル」「クイズショー」の形式を借りて、場に起こるパワーバランス、経済や組織の構造について問いを投げかける。
個人の声や視点から大きな歴史と未来の物語を見つめ直すのが、ジャールナン・パンタチャートとアーザーデ・シャーミーリー。タイの演出家、パンタチャートは、隣国ミャンマーのアーティストや俳優との協働により、大きな物語として共有される歴史と個人的出来事の関係を問い直す。イランの演出家、シャーミーリーは、言論統制されたディストピアとなった2070年を舞台に、個人的な記憶が記録媒体を通してどう再構築されるのかを問う。

アーザーデ・シャーミーリー[© Roberta Cacciagla]
また、ジェンダーの視点から注目したいのが、フロレンティナ・ホルツィンガー、サマラ・ハーシュ、松本奈々子、西本健吾/チーム・チープロの3作品。KEX 2021 SPRINGでの『Apollon』映像上映で大きな衝撃を与えたホルツィンガーは、三部作の最後を飾る『TANZ』においても、全裸の女性パフォーマーが演じる血みどろのバレエのレッスンをスプラッターやポルノと接続させることで、「美」の元に搾取・消費されてきた女性の身体について過激かつポップに問う。サマラ・ハーシュの参加型演劇では、受話器の向こうのティーンエイジャーから投げかけられるセクシュアリティ、老い、死についての疑問に観客が応えることで、大人/子ども、教師/生徒、パフォーマー/観客といったヒエラルキーの解体とともに、世代間の対話を促す。リサーチを元に身体とテクストの関係を探るチーム・チープロは、「接触禁止の下で想像の他者と踊るワルツ」をテーマとした前作からリサーチを発展させ、「月経の再魔術化」をテーマに、女性の身体と相撲の四股を参照した新たな「儀式」を開発する。

フロレンティナ・ホルツィンガー[© Urska Boljkovac]
身体とテクストの拮抗性の探求は、小野彩加・中澤陽のユニット「スペースノットブランク」と気鋭の劇作家・松原俊太郎による、4度目のコラボレーションにも期待できる。舞台上では、松原による戯曲の上演と、リアルタイムでの映画の撮影・上映が同時進行するという。
プログラムの3本柱のひとつで、関西地域をアーティストの視点からリサーチするKansai Studiesでは、建築家ユニット dot architectsと演出家・和田ながらが3年間の集大成を演劇作品として発表する。また、エクスチェンジプログラムSuper Knowledge for the Future [SKF]は、上演作品に関連したワークショップやトークに加え、山歩きツアー、LGBTQ勉強会、沖縄・タイ・ロシアのアートとポリティクスについてのトークシリーズなど多彩なラインナップで構成される。
期待がふくらむ一方、フェスティバルの存続をとりまく経済状況は厳しい。コロナ禍による経済への打撃、京都市の財政難による負担金減額、渡航費の高騰、円安の影響を受け、予算補填のためのクラウドファンディングを初めて実施した。もちろん観劇も支援であるという気持ちで劇場に足を運びたい。
KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 公式サイト :https://kyoto-ex.jp/
2022/08/30(高嶋慈)
新人Hソケリッサ! 横浜市役所パフォーマンス

会期:2022/08/29
横浜市役所アトリウム[神奈川県]
ホームレスによるダンスグループ「新人Hソケリッサ!」のドキュメンタリー映画「ダンシングホームレス」の上映と、ダンスパフォーマンスの公演。新人Hソケリッサ!は、振付家のアオキ裕キが路上生活者のメンバーを募って結成したダンス集団。洗練されたモダンダンスの動きに対して、日本人の土着的な身振りを強調した土方巽の暗黒舞踏のように、都市の狩猟採集民ともいうべき路上生活者の動きや身振りを踊りに反映させようということらしい。「ソケリッサ!」とは「それいけ!」といったニュアンスで、「H」は「ホームレス」「ヒューマン」「ホープ」などを意味する。映画のなかでも語られるとおり、メンバーは精神疾患があったり子どものころ親に暴力を振るわれたり、なにかしらワケありの人生を歩んできた人たちばかり。その多くが歯が欠けており、彼らの過酷な人生を物語っている。
都市の狩猟採集民と呼んだが、彼らの動きはハンターのように素早いわけではなく、逆におどおどしてどんくさい。むしろその不自由でのろまな肉体表現が、無駄のないテキパキ至上主義の現代では新鮮に映る。だが、それを見て喜ぶ人がどれだけいるだろうか。映画では、関西に遠征して釜ヶ崎で野外公演を行なったとき、観客から「いつまでやってんだ」みたいなヤジが飛ぶ。その後に出演したロックバンドはウケがよかったので、なおさら落ち込む。東京とは違って大阪人は反応がストレートなのだ。そりゃあ薄汚い中年オヤジがのそのそ動くだけの踊りより、ノリのいいロックに惹かれるのは当たり前、対抗するもんではない。
上映後、アオキ裕キのトークを挟んで、サウンドアーティストの西原尚をゲストに迎えてのパフォーマンスが行なわれた。西原は自作のキテレツな音具を鳴らしながら練り歩き、それに合わせるともなくダンサーは独自の踊りを始めるのだが、どうも映画で見た動きとは違っておもしろくない。市役所の巨大なアトリウムで、大勢の観客を前にアガってしまったんだろうか。無理しているというか、いつもよりうまく踊ろうと背伸びしているようにも見受けられ、見ていて辛かった。うまく踊ろうとすればするほど、単なる素人のヘタな踊りに近づいてしまうのだ。しかも西原の音とオブジェが圧倒的に場を支配したため、彼らの存在がますます霞んでしまったようにも感じられた。やはり音には敵わないのか。
だが、ハーメルンの笛吹きのように西原の先導でダンサーが屋外に出て行ったあと、最後に残ったメンバーのひとり平川収一郎が披露したソロが、すばらしいの一言に尽きた。背伸びも気負いも感じられず、路上生活者たる自分の動きをまっとうしたのだ。いやー、いいものを見せてもらった。こんな素敵な企画に真新しいアトリウムを提供した横浜市役所もエライ。ていうか、こういうイベントに使うほかに有効な使い道はあるか?
新人Hソケリッサ! 公式サイト:https://sokerissa.net
2022/08/29(月)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)